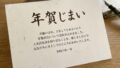布団を送りたいけれど、どの方法が一番安くて安心なのか分からない。引っ越しや実家への仕送り、季節の入れ替えなどで布団を運ぶ機会は意外と多いのに、料金やサイズの基準が複雑で迷ってしまう方は少なくありません。特に布団配送のゆうパック料金は、重さやサイズで変わるため、事前にきちんと理解しておかないと予想以上の出費になることもあります。
そんな悩みを解決するのがこの記事です。布団配送のゆうパック料金の基本から、サイズや重量による違い、最新の料金改定情報、さらに持ち込み割引や梱包の工夫によって安く送る方法までを詳しく解説します。初めての方でも迷わず布団を発送できるように、送り方の手順や袋の選び方まで実践的にまとめています。
この記事を最後まで読めば、自分に合った最適な料金プランや送り方が分かり、安心して布団を届けることができるでしょう。
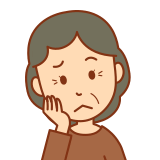
💡記事のポイント
- 布団配送とゆうパック料金の仕組みや決まり方を理解できる
- サイズ別の考え方や持ち込み割引など節約の道筋が分かる
- 値上げ動向への備え方と重量ゆうパックの適用場面を把握できる
- 送り方のステップと布団配送用の袋選びまで一通り学べる
布団配送のゆうパック料金の基本と料金体系について

- 布団を郵送するにはどうしたらいいのか?
- 布団セットをゆうパックで送ることは出来るのか?
- 布団配送のゆうパック料金の相場と目安について
- 布団の配送料金を安くする方法とは?
- ゆうパックのサイズ料金の仕組みについて
- ゆうパックの料金は何で決まるのか?
布団を郵送するにはどうしたらいいのか?
布団を郵送する際に最も重要なのは「衛生状態の管理」と「適切な梱包」の2点です。まず出荷前の準備として、布団を必ず清潔な状態に整えましょう。クリーニングに出してから発送すれば受け取る側も安心して使用できますが、自宅で対応する場合でも天日干しや布団乾燥機を使って十分に乾燥させることが大切です。湿気が残ったまま発送すると、輸送中の気温や湿度の変化によってカビや臭いが発生する恐れがあるため注意が必要です。
次に行うべきなのは梱包作業です。布団はかさばる荷物の代表格ですが、布団専用の圧縮袋を使えば体積を半分以下に抑えることが可能です。圧縮後は破れにくい厚手の布団袋、または専用ダンボールに入れて強度を確保し、配送中の衝撃から中身を守ります。さらに、伝票には「布団」と明記し、「天地無用」や「水濡れ注意」といった取り扱い上の注意を記載しておくと、配送業者側の取り扱いも丁寧になり、トラブルのリスクを減らせます。
郵送手段としては日本郵便の「ゆうパック」が最も一般的です。全国一律のサイズ区分に基づいて料金が決まるため、布団のサイズや重量を把握しておくことがコスト管理の第一歩になります。また、自宅まで集荷に来てもらえるサービスを利用すれば、大きな荷物を持ち出す手間を省けますし、郵便局や一部のコンビニに持ち込めば割引を受けられる場合もあります。利便性を取るか、コスト削減を優先するかは発送者の状況によって選択が分かれる部分ですが、いずれにせよ事前に料金体系を確認しておくことが重要です。
布団セットをゆうパックで送ることは出来るのか?
掛け布団、敷き布団、枕などをまとめた「布団セット」も、ゆうパックを利用すれば送ることが可能です。ただし、複数の布団を一つにまとめると荷物のサイズや重量が大きくなり、結果的に送料が高くなることがあります。そのため、まとめて送るか、それとも分けて複数口にするかは事前に検討すべき重要なポイントです。
例えば掛け布団と敷き布団を同じ圧縮袋に入れた場合、160サイズやそれ以上になることも珍しくありません。この場合、送料は一気に高額になります。一方で、それぞれを個別に圧縮して120サイズや140サイズに収めれば、結果的に合計料金が安く済むケースもあります。実際に発送する前に、各アイテムを圧縮した際のおおよそのサイズを計測し、料金シミュレーションを行って比較してみることが推奨されます。
また、圧縮袋の使用はほぼ必須といえます。布団は空気を含むことでかさばりますが、圧縮袋を利用すれば1/3程度まで小さくできることもあります。ただし、羽毛布団や特殊素材の敷き布団などは、過度な圧縮によって保温性や反発性といった機能が損なわれる恐れがあるため注意が必要です。メーカーが発行している取り扱い説明や注意事項を事前に確認し、素材に応じて圧縮の強弱を調整することが大切です。
さらに、配送時の利便性という観点も見逃せません。まとめて発送すれば受取人が一度に受け取れるため便利ですが、荷物が重くなり運びづらいというデメリットも生じます。逆に分割発送をすれば持ち運びや保管は容易になりますが、受け取る側が複数回の受け取りをする必要が出てきます。状況に応じて「まとめるか分けるか」を選択するのが効率的な布団セット配送のポイントです。
布団配送のゆうパック料金の相場と目安について
布団配送の料金は「サイズ」「重量」「発送元と宛先の距離」の3要素で決まります。ゆうパックでは縦・横・高さの合計サイズと重量のどちらか大きい方が適用されるため、布団を発送する際は圧縮後のサイズ測定と重量確認が不可欠です。
目安として、シングルサイズの掛け布団1枚を圧縮した場合、100サイズまたは120サイズに収まることが多く、送料は2,000円前後になるケースが一般的です。一方で、敷き布団や複数の布団をまとめた場合は140サイズ~160サイズとなることが多く、その場合は3,000円以上かかる可能性もあります。さらに、地域によって料金が変動します。例えば同一県内や隣県であれば安価に収まりますが、北海道から九州のような長距離輸送では料金が大幅に上がる点を理解しておきましょう。
また、ゆうパックの料金は燃料費や人件費の上昇を背景に定期的に見直されており、近年は値上げ傾向が続いています。発送前には必ず日本郵便の公式サイトにある最新の料金表を確認し、想定外の出費を避ける準備をしておくことが大切です。特に布団のように大きな荷物は、数百円の差が積み重なることで全体の負担が大きくなる可能性があるため注意が必要です。
さらに節約を考えるのであれば、持ち込み割引や複数口割引といった制度を活用すると良いでしょう。郵便局や一部のコンビニに直接持ち込めば割引が適用され、まとめて発送する場合は1個あたりの料金が抑えられる場合があります。こうした制度を知っておくだけでも、布団配送のコストを効果的に削減できます。
(参考:日本郵便公式サイト ゆうパック料金表 https://www.post.japanpost.jp/cgi-simulator/youpack_choice.php )
布団の配送料金を安くする方法とは?

布団の配送料金をできるだけ抑えるためには、発送前のちょっとした工夫が大きな差を生みます。特にゆうパックではサイズと重量が料金に直結するため、まずは「いかにコンパクトにするか」が最重要ポイントです。布団専用の圧縮袋を活用し、空気をしっかり抜いて体積を減らせば、同じ布団でもワンランク下のサイズに収まることがあり、これだけで数百円から千円単位の節約が可能です。また、段ボールよりも専用の布団袋や配送用ビニールを選ぶと梱包資材そのものが薄く軽くなり、サイズオーバーを防ぐ効果もあります。
割引制度を賢く使うことも大切です。例えば、郵便局やローソンなどの取扱店に荷物を持ち込めば「持込割引」で1個あたり120円安くなります。さらに、同じ宛先に複数の荷物を同時発送すると「同一あて先割引」が適用され、1個につき60円引きになります。布団セットを分けて送る場合などは特に効果が大きく、合計すると数百円から千円以上お得になるケースもあります。
加えて、オンラインサービスを活用すればさらに安くなります。日本郵便が提供する「Webゆうプリ」や「ゆうプリタッチ」でラベルを事前に作成しておけば、1個につき100円割引が適用されます。持込割引と組み合わせれば1個あたり220円もの節約が可能になり、複数口発送では総額でかなりの違いが出ます。
ただし、割引の適用には条件があるため、日本郵便の公式サイトで事前に確認しておくのが安心です。これらの方法を組み合わせれば、布団を安全に送りながらもコストを最小限に抑えられるため、引越しや季節の入れ替えなど大量の布団を送るシーンでも大きな効果を発揮します。
(出典:日本郵便公式サイト 割引サービス
https://www.post.japanpost.jp/service/you_pack/advantage/toku.html
ゆうパックのサイズ料金の仕組みについて
ゆうパックの料金は、荷物の「縦・横・高さの合計」によって決まるサイズ区分を基本としています。サイズは60から170まで7段階に分けられており、数字はそのまま縦横高さを足した合計センチ数を意味します。例えば、縦60cm・横40cm・高さ20cmで合計120cmなら「120サイズ」に分類されます。布団のように柔らかく、梱包方法によって大きさが変わる荷物は、この仕組みの影響を特に受けやすいため、圧縮や袋選びの工夫が料金を大きく左右するのです。
サイズに加え、重量制限も料金に関わります。ゆうパックは最大25kgまで対応していますが、布団の場合は体積が大きい割に重量は軽いことが多いため、ほとんどの場合は「サイズ」が料金を決める決定的要素になります。ただし、厚みのある敷布団やマットレス一体型布団などは重量が20kg近くになることもあり、その場合はサイズと重量の両方を意識する必要があります。
また、ゆうパックの料金表は発送元と宛先の「距離区分」によっても変動します。県内・近隣・中距離・遠距離などで区分されており、同じ120サイズでも関東から関西に送る場合と、関東から北海道に送る場合では大きな差が生じます。このため、発送前には自宅で縦横高さを測り、距離を踏まえて料金表を確認しておくことが不可欠です。
布団を送るときは「どのサイズに収まるか」「どの距離区分で送るか」を理解しておくと、費用感を正確に把握でき、無駄な出費を避けることができます。特に引っ越しやまとめて布団を送る場面では、ちょっとしたサイズの違いで総額が数千円変わることもあるため、事前のシミュレーションが安心です。
(出典:日本郵便 ゆうパックサイズと料金
https://www.post.japanpost.jp/service/you_pack/charge.html
ゆうパックの料金は何で決まるのか?
ゆうパックの料金を決める要素は大きく分けて「サイズ」「重量」「距離」の3つです。まずサイズは、縦・横・高さの合計で区分され、料金の基本となる指標です。次に重量は、25kg以内かどうかで確認されます。布団の場合はサイズが先に基準になることが多いですが、厚みのある布団や重い寝具では重量制限も無視できません。最後に距離は、発送元と宛先の地域によって区分され、近場なら安く、遠方ほど高くなります。
これに加え、発送方法やオプションも料金を変動させる要因です。例えば、自分で持ち込めば持込割引が適用されますが、集荷を依頼すると便利な反面、割引が使えません。また、配達日や時間帯の指定、速達やチルド便といったオプションを利用すると料金が加算されます。布団は湿気を嫌うため「水濡れ注意」を指定する人も多いですが、これ自体は無料で記載できるため積極的に活用すべきポイントです。
特に注意したいのはサイズの境界線です。例えば、120サイズと140サイズの境目をわずかに超えるだけで料金が一気に数百円から千円近く跳ね上がることがあります。布団は柔らかい分、梱包によってサイズを小さく抑えられる可能性があるため、袋の選び方や角の詰め方など工夫次第で料金を抑えることができます。
料金の仕組みを理解すれば「なぜこの料金になるのか」を納得しやすくなり、適切な工夫や割引サービスの組み合わせによって、より合理的に布団を送れるようになります。単に料金表を見るだけではなく、その裏にある仕組みを知っておくことが、無駄のない配送につながるのです。
(出典:日本郵便 ゆうパック料金表
https://www.post.japanpost.jp/cgi-simulator/youpack_choice.php
布団配送のゆうパック料金を節約する方法と送り方のコツ

- ゆうパックの60サイズの送料と布団配送の関係について
- ゆうパックの料金一覧と持ち込み割引を活用する方法
- ゆうパックの料金値上げの最新情報とその影響について
- 重量ゆうパックの料金と布団の重さの考え方
- ゆうパックで布団を送る際の送り方のステップ解説
- 布団配送用の袋の選び方と梱包のコツ
ゆうパックの60サイズの送料と布団配送の関係について
ゆうパックの料金体系の中で最も小さい区分である60サイズは、縦・横・高さの合計が60cm以内、かつ重量が25kg以下の荷物に適用されます。このサイズ帯は主に小型の雑貨や衣類、食品などを対象としているため、布団のようにかさばる荷物が入るケースはほとんどありません。一般的な掛け布団や敷布団をそのまま送ると、100サイズ以上になるのが一般的です。しかし、薄手の掛け布団を専用の圧縮袋でしっかりと真空状態にすれば、例外的に60サイズに収まる可能性もゼロではありません。
ただし、ここには注意すべき落とし穴があります。圧縮袋は種類によって空気の漏れやすさに差があり、品質の低い製品を選ぶと配送中に膨張してしまうことがあります。日本郵便の窓口では荷物のサイズを実際に計測して料金区分を判定するため、膨張してしまった場合は想定より大きなサイズ扱いとなり、追加料金が発生します。結果的に節約どころか余計なコストがかかる可能性すらあります。
このようなリスクを考えると、布団を無理に60サイズに収めようとするのは現実的ではありません。むしろ100サイズや120サイズを前提とした計画を立てるほうが安定しており、費用対効果の面でも合理的です。布団を圧縮しても60サイズに収まるのはごく限られたケースであり、基本的には「うまくいけば掛け布団1枚程度が収まるかもしれない」という程度の目安にとどめるのが賢明です。最終的には、布団の品質保持や配送時の安全性を優先して、適正なサイズ選びをすることが最も確実な方法といえます。
ゆうパックの料金一覧と持ち込み割引を活用する方法
ゆうパックの料金体系は全国一律ではなく、発送元と届け先の距離、そして荷物のサイズに応じて細かく設定されています。そのため、布団配送を計画する際には公式サイトに掲載されている料金一覧表や料金シミュレーターを活用することが欠かせません。シミュレーターを使えば、発送地と宛先を入力し、サイズを指定するだけで、具体的な送料を即座に確認できます。これにより、配送前に正確なコストを把握でき、予算オーバーを防ぐことができます。特に布団のようにサイズが大きく変動する荷物では、事前確認が大きな意味を持ちます。
(出典:日本郵便公式 ゆうパック料金シミュレーター https://www.post.japanpost.jp/cgi-simulator/youpack_choice.php )
さらに注目したいのが、持ち込み割引です。郵便局やローソンなどの取扱店に直接荷物を持参すると、1個あたり120円の割引が受けられます。布団セットのように複数口で発送する場合は割引額が積み重なり、例えば3個口であれば合計360円の節約につながります。これに加えて、同一宛先に複数個を同時に送る場合に適用される複数口割引を利用すれば、さらに1個あたり60円が割り引かれます。両方を組み合わせれば、布団配送1回で数百円から千円近くの節約が可能になるのです。
ただし、布団はサイズも重量も大きいため、持ち運びの負担が少なくありません。自家用車で郵便局に運べる場合は割引の恩恵が大きい一方、公共交通機関を利用する場合や徒歩で持ち込む場合は、時間や労力の負担が割引額を上回ってしまう可能性もあります。そのため、「コスト削減」と「手間や利便性」のバランスを考え、自分の環境に合わせて割引制度を活用することがポイントとなります。賢く計画を立てれば、布団配送のコストを着実に下げることができます。
ゆうパックの料金値上げの最新情報とその影響について
ここ数年、物流業界全体で人件費の上昇や燃料価格の高騰が続いており、その影響は日本郵便が提供するゆうパックの料金にも反映されています。2023年以降、日本郵便は複数回にわたって料金改定を行っており、特に布団のような大型荷物を送る際の負担は以前よりも大きくなっています。これまで「手頃な料金で全国どこへでも送れる」というイメージがあったゆうパックですが、最新の料金体系を確認すると、従来よりも確実に高くなっていることに気づく利用者も多いでしょう。
(出典:日本郵便公式ニュースリリース https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/ )
値上げの影響を軽減するには、まず常に最新の料金表をチェックすることが第一歩です。さらに、持ち込み割引やWeb割引などの公式割引制度を積極的に利用することで、実質的な負担を抑えることができます。配送の頻度を下げてまとめて発送する工夫や、代替サービスを比較することも有効です。実際に、布団配送の利用者の中には、ヤマト運輸の「らくらく家財宅急便」や佐川急便の「飛脚ラージサイズ宅配便」を候補に加え、料金やサービス内容を比較検討するケースが増えています。各社が提供するオプションや集荷サービスを含めて総合的に判断すれば、最適な配送手段を見つけやすくなります。
ゆうパックの料金改定は、個人の家計に直結する問題でもあります。布団配送は決して安くはない支出のため、出費を抑えるためには「最新情報を常に把握する」「割引を効果的に利用する」「必要に応じて他社サービスと比較する」という3つの工夫が不可欠です。料金の動向に敏感であることは、安心して布団を配送できることにつながり、結果として賢い生活コスト管理にも直結します。
重量ゆうパックの料金と布団の重さの考え方

布団配送を検討する際、まず意識すべきは「サイズ」ですが、場合によっては「重量」も料金に関わってきます。ゆうパックは縦・横・高さの合計で区分されるサイズ制と、最大25kgまでの重量制が基本です。これを超えない限り通常のゆうパックで送ることができますが、重さに特化した「重量ゆうパック」という料金区分も存在します。特に重量がかさむ荷物では、知っておくと役立つ知識です。
布団そのものは比較的軽量ですが、種類によって差があります。例えばシングル掛け布団であれば2kg程度、敷き布団なら4〜6kg前後が標準です。ダブルやクイーンサイズになるとさらに重量が増し、冬用の厚手布団や羽毛布団セットでは10kgを超えるケースもあります。さらに、複数枚をまとめて梱包する場合や、ダウン布団と敷布団を同時に送るようなケースでは重量が合計15kg近くになることも珍しくありません。
重量ゆうパックは25kgまで対応しているため、布団単体では上限を超えることはほぼありません。しかし、注意すべきなのは外装や資材です。段ボールや緩衝材を多用すると意外と重量が増加し、思わぬ料金加算につながることがあります。こうしたリスクを避けるには、家庭用体重計で梱包後の荷物を必ず測定し、郵便局での計測と差が出ないように準備することが重要です。
重量管理をしっかり行えば、予想外の追加料金を防げるだけでなく、効率的に布団を配送することができます。つまり、布団配送ではサイズだけでなく重量にも注意を払い、両面からのコスト管理を行うことが失敗しない秘訣です。
ゆうパックで布団を送る際の送り方のステップ解説
布団をゆうパックで配送する場合、適切な準備を踏むことで安全性とコストの両方を確保できます。特に布団はかさばり、湿気や汚れが残っていると輸送中のトラブルの原因になるため、段階を踏んだ送り方が必要です。
まず最初に行うべきは、布団を清潔に整えることです。使用後すぐの布団は汗や湿気を含んでいることが多く、そのまま梱包するとカビや異臭が発生するリスクがあります。必ず天日干しや布団乾燥機を活用し、しっかり乾燥させてから作業に入ることが理想です。
次に行うのが圧縮作業です。市販の真空式圧縮袋を使い、掃除機や専用ポンプで空気を抜いてサイズを小さくします。布団を60サイズや80サイズに収めたい場合、この工程が大きなポイントとなります。袋を選ぶ際には、逆止弁付きや厚手素材のものを選ぶことで、輸送中の膨張を防ぐことができます。
圧縮後は、配送専用の布団袋または段ボールに梱包します。段ボールを使う場合は、角を補強して緩衝材を入れ、布団が動かないように固定することが大切です。袋を利用する場合でも、防水性の高い素材を選ぶと雨天時の配送でも安心です。
送り状は正しく記入し、宛先・電話番号などに誤りがないかを二重チェックしましょう。天地無用や水濡れ注意などのラベルを貼っておくと、配送スタッフに配慮してもらえる可能性が高まります。最後に、郵便局やコンビニへの持ち込み、または集荷サービスを利用して発送します。発送後は追跡番号を必ず控えておき、受取人に伝えると受け取りがスムーズです。
このように順序立てて準備を進めることで、布団を安全に、そして確実に相手に届けることができます。
布団配送用の袋の選び方と梱包のコツ
布団をゆうパックで送る際には、どの袋や資材を使うかが料金と安全性の両面に大きく影響します。布団は大きくかさばるため、まずは圧縮袋を使うのが一般的です。圧縮袋は厚手で破れにくいものを選び、ジッパー部分が二重構造のタイプや、バルブ付きで空気漏れしにくいものが望ましいです。圧縮後は、配送専用の布団袋に収納することで、強度と防水性を確保できます。
布団配送用の袋には、ナイロン製やポリエステル製のものが多く、市販の簡易的な布団袋に比べて破れにくい構造になっています。インターネット通販では「布団専用配送バッグ」として販売されているものもあり、持ち手やジッパー部分が補強されているため、持ち運びの際にも安心です。袋が用意できない場合は段ボールでも代用可能ですが、その場合はサイズが大きくなりやすく、結果的に料金が高くなるリスクも考慮する必要があります。
梱包の際には、角を補強し、余分な空間を作らないことが重要です。隙間があると布団が動き、輸送中の衝撃で袋が破れたり、段ボールが潰れる原因になります。新聞紙や緩衝材を使って隙間を埋めると安定感が増し、輸送時の破損リスクを大幅に減らせます。また、梱包テープは布製やクラフト製など、粘着力の強いものを使用し、十字に貼ることで強度を高めるのがコツです。
布団は重量よりも「大きさ」と「かさばりやすさ」に課題がありますが、正しい袋選びと梱包の工夫を取り入れることで、安全性とコストの両立が可能です。これらを押さえておけば、安心して布団をゆうパックで送ることができるでしょう。
布団配送のゆうパック料金を徹底解説まとめ

- 布団配送は、圧縮の仕方と外装資材の選び方によってサイズが大きく変わり、送料に直結します。
- ゆうパック料金は、荷物のサイズ・重量・配送距離、さらに受付方法によって最終的に決まります。
- 送料の目安は、必ず梱包後に実際に測定し、料金表のサイズ区分を確認して判断することが大切です。
- 60サイズは薄手の布団や小物に向いており、無理な圧縮は生地や復元性を損なうため避けるべきです。
- 持ち込み割引や事前ラベル作成サービスを利用すれば、ちょっとした工夫で送料を節約できます。
- 値上げ局面では、圧縮・分割・持ち込みの三点を意識して対策を講じることが賢明です。
- 重量ゆうパックを利用する場合は、対象条件を確認し、梱包後の重さを正しく管理する必要があります。
- 外装はできるだけ軽量かつ強度のある素材を選び、余分な重量増を抑えることが重要です。
- 梱包の際は角あてや防水層を追加し、「天地無用」などの表示で輸送時のダメージを減らします。
- 家庭用体重計とメジャーを使い、梱包後のサイズと重量を事前に把握しておくと安心です。
- 同一宛先への配送は、複数口とサイズの組み合わせを工夫することで総額を最適化できます。
- 配達希望日時は受取人の都合を優先し、再配達の発生を防ぐことがスムーズな受け渡しにつながります。
- 圧縮は布団の復元性を損なわない範囲で行い、品質や快適性を守ることを心掛けます。
- 集荷と持ち込みは、移動時間や割引額を比較し、総合的に便利で経済的な方法を選びましょう。
- 到着予定日の共有と控えの保管を徹底することで、受け取り時のトラブルを未然に防げます。
関連記事