「84円切手を2枚貼っても大丈夫?」「複数枚貼るときの位置はどうすればいいの?」と悩んだことはありませんか。手紙や書類を郵送するとき、切手を2枚貼る場面は意外と多いものです。しかし、貼る位置や組み合わせを間違えると、見た目が不格好になったり、場合によっては配達が遅れる原因にもなります。
そんな不安を解消するために、この記事では切手2枚の貼り方について、正しい位置やマナー、知っておきたい注意点をわかりやすく解説します。郵便局での実際のルールや、複数枚を貼るときのきれいな配置のコツも紹介します。
初めての方でも安心して郵送できるよう、失敗しない切手2枚の貼り方を一緒に確認していきましょう。
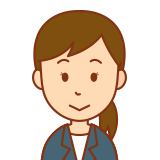
💡記事のポイント
- 切手を複数枚を使うときの基本ルールと配置の考え方
- 封筒サイズ別の切手を貼る位置とレイアウトのコツ
- 切手の水やのりの使い分けと仕上がりを整える手順
- 複数切手のマナー面で失礼にあたらないための判断基準
切手2枚貼り方の基本|正しい位置と複数枚を貼るときのルール

- 切手を2枚貼るときの基本マナーと注意点
- 切手を複数枚貼る場合の正しい貼り方とは?日本郵便の公式ルールを解説
- 切手を複数枚貼るときの正しい位置と配置バランス
- 切手を貼る場所がないときの対処法と封筒サイズごとの工夫
- 84円切手を2枚貼ってもいいの?料金の考え方と組み合わせのルール
- 切手を横に貼るのはOK?縦貼り・横貼りのマナーと見た目の違い
切手を2枚貼るときの基本マナーと注意点
切手を2枚使用する目的は、郵便料金を正確に満たすことにあります。郵便料金は重さや封筒のサイズ、郵送方法(定形・定形外・速達など)によって細かく決まっており、必要額をちょうど満たすように切手を組み合わせるのが理想です。
まず、封筒の右上隅に主切手を貼り、その左隣または下に2枚目を配置します。このとき、封筒の端から約5〜10ミリ程度の余白を残すことで、全体のバランスが整い、宛名や郵便番号欄との干渉を避けられます。
貼る際には、気泡やシワが入らないように注意します。切手の中央から外側に向かって軽く押さえながら空気を抜くと、美しく仕上がります。また、濡れた手で触れると印面がにじむことがあるため、清潔で乾いた手で作業することが望ましいです。特に記念切手や特殊印刷のものは、指紋や汚れが目立つためピンセットの使用も効果的です。
封緘や宛名に切手が重ならないようにし、図案の上下を揃えることで、受け取る側に対しても丁寧な印象を与えられます。日本郵便では、消印機械がスムーズに読み取れるよう右上部分への貼付を推奨しています(出典:日本郵便「郵便の差し出しに関する基本ルール」https://www.post.japanpost.jp/service/standard/one_price.html)。この位置を守ることで、誤配や遅延のリスクも低減できます。
切手を複数枚貼る場合の正しい貼り方とは?日本郵便の公式ルールを解説
複数枚の切手を使うことは、料金を調整するための一般的な方法です。日本郵便では、複数の切手を貼ることを明確に認めており、合計金額が郵便料金を上回っていれば差し出し可能とされています。たとえば、84円切手を2枚貼って168円にする場合や、100円と10円の切手を組み合わせて110円にする場合など、目的に応じて柔軟に対応できます。
切手は、郵便局の消印機が処理しやすいよう、封筒の右上部分にまとめて貼るのが基本です。上下や左右に分散させて貼ると、消印が押されない切手が発生し、再利用防止の観点から再処理が必要になる場合があります。そのため、切手はできるだけ近接して整然と並べるようにしましょう。
封筒の折り目や角の部分は、はがれやすくなるため避けるのが無難です。貼り付け前に軽く封筒を撫でて凹凸がないか確認すると、密着性を高められます。また、封筒表面のコーティングや光沢が強い場合、のりや水分が浸透しにくいため、郵便用スティックのりを使用するのが安全です。
料金不足があると、受取人に「不足料金請求」の形で届く可能性があるため、発送前に日本郵便の料金表で金額を確認する習慣をつけると安心です(出典:日本郵便「郵便料金・運賃を調べる」https://www.post.japanpost.jp/send/fee/index.html)。貼る位置と金額を正確に管理することで、信頼性の高い郵送が実現します。
切手を複数枚貼るときの正しい位置と配置バランス
切手を2枚以上貼る場合、最も重要なのは見た目の整え方と機能性の両立です。一般的には、封筒の右上の角から下へ縦に2枚並べるか、左へ横に並べる形が好まれます。封筒の上端および右端から5〜10ミリの余白を確保し、バランスの取れた配置にすることで、消印のスペースを確保しながら美しい印象になります。
縦に並べる場合は、上から下へ向かって金額の大きい切手を先に貼ると視覚的に安定します。横に並べる場合は、左から右へ金額の大きい順に貼ると読みやすくなります。この順序は郵便局の消印処理にも配慮した配置といえます。隣接する切手の間隔は1〜2ミリを目安にし、密着させないことで湿気や温度変化による反り返りを防げます。
封筒のサイズによっても適した並べ方が異なります。長形3号などの一般的な定形封筒では、縦並びが最も自然で整然とした印象を与えます。洋形封筒のように横幅が広いタイプでは、横並びのほうが見た目に安定感があります。角形2号などの大きな封筒では、右上に縦方向で並べると間延びせずバランスが取れます。
また、切手の図柄が上下逆にならないよう注意し、図案を揃えることで清潔感のある仕上がりになります。特にビジネスシーンでは、見た目の整然さが信頼を左右することもあるため、細部まで丁寧な配置を心がけましょう。
封筒サイズと並べ方の目安
| 封筒サイズの例 | おすすめ配置 | 余白の目安 |
|---|---|---|
| 長形3号(定形) | 縦2枚または横2枚 | 上右5〜10ミリ |
| 洋形2号(定形) | 横2枚 | 上右5〜8ミリ |
| 角形2号(定形外) | 縦2枚 | 上右8〜12ミリ |
このように、封筒の形状と使用目的に応じて切手の位置を工夫することで、視覚的にも実務的にも最適な貼り方が実現します。封筒全体の印象を左右するポイントであるため、日常的な郵送でも一手間を惜しまない姿勢が大切です。
切手を貼る場所がないときの対処法と封筒サイズごとの工夫

封筒の右上には本来、切手を貼るためのスペースを確保しておくことが理想ですが、デザイン性の高い封筒やロゴ入りのビジネス封筒、宛名のレイアウトによっては十分な余白が取れないことがあります。このような場合、見た目のデザインよりも郵便としての可読性と実務的な正確さを優先することが大切です。
まず検討すべきは、宛名ブロックの位置調整です。宛名を左寄せに少しずらすことで、右上に3センチ四方程度の余白を確保できます。郵便局の自動仕分け機は封筒右上を読み取って消印処理を行うため、このスペースを確保することで機械処理の不具合を防げます。もし封筒デザイン上どうしても調整できない場合は、封筒のサイズそのものを変更することも選択肢です。長形3号から角形2号など、わずかに大きめの封筒へ変更することで作業効率が向上し、レイアウトにも余裕が生まれます。
また、切手のサイズや額面の選び方を工夫する方法もあります。例えば、84円切手を1枚貼るよりも、50円や20円、10円などの小型の切手を組み合わせることで、貼る面積を小さく抑えることができます。視覚的にもすっきりした印象になり、限られたスペースでも整然と配置できます。さらに、ラベルや切手貼付用の透明シールを別途用意し、その上に切手を整列させてから封筒に貼ると、位置調整が容易になります。これにより、複数枚の切手をまっすぐ貼る精度が高まり、貼り直しによる紙の傷みを防ぐことができます。
それでも右上に貼る余地がない場合は、封筒の上端に近い右寄りの位置にまとめて貼付します。このとき、すべての切手が消印範囲に収まるよう、なるべく近接して配置するのが望ましいです。郵便局では、消印が切手全体にかからないと再処理が必要になるため、重ならずにまとめて貼る工夫が求められます(出典:日本郵便「郵便の差し出しに関するルール」https://www.post.japanpost.jp/service/standard/one_price.html)。
ビジネス封筒の場合、企業ロゴを避けるために切手位置を微調整するケースもありますが、機械処理上の認識エリア(右上約40mm×40mm)を優先することで、郵便事故のリスクを最小限に抑えることができます。つまり、見た目のデザインよりも郵便物としての機能性を重視する判断が、結果的に最もスマートな対応と言えるでしょう。
84円切手を2枚貼ってもいいの?料金の考え方と組み合わせのルール
84円切手を2枚貼ると合計168円となり、これは定形外郵便の軽量区分(50g以内)や速達、書留などの加算料金に対応するケースで使用されます。郵便料金は「重さ」「サイズ」「オプション(速達・簡易書留など)」の3要素で決まるため、事前に封入物の重量を確認し、必要な料金を正確に把握することが欠かせません。
たとえば、定形郵便の25g以内は84円ですが、50gを超えると料金は94円になります。これを知らずに84円切手を2枚貼ると、必要額よりも74円多く支払うことになり、結果的に無駄が生じます。逆に不足している場合、受取人に不足料金を請求されることになり、相手に手間をかけてしまいます。したがって、料金の正確な確認は郵送マナーの第一歩です。
郵便物の重さは家庭用のデジタルスケールで測ることができますが、誤差を避けたい場合は郵便局の窓口で計量してもらうのが確実です。必要料金がわからない場合は、日本郵便公式サイトの「料金を調べる」ページを利用するのも便利です(出典:日本郵便「郵便料金・運賃を調べる」https://www.post.japanpost.jp/send/fee/index.html)。
また、余分な料金を避けたい場合は、小額面切手を組み合わせて調整する方法がおすすめです。以下の表を参考に、封入物の重さやサービスに合わせて最適な組み合わせを選びましょう。
額面の組み合わせ例
| 必要額の例 | 組み合わせの一例 |
|---|---|
| 120円 | 84円+36円 |
| 140円 | 84円+56円 |
| 168円 | 84円×2 |
| 210円 | 84円+84円+42円 |
もし168円より多い額面を貼った場合でも郵便物は差し出せますが、差額の返金は行われません。そのため、封筒の重量を事前に把握し、必要な料金に近い組み合わせを選ぶことが経済的です。ビジネス用途では、郵便料金表を常に手元に置き、複数の額面を効率的に使い分けることが信頼感のある発送につながります。
切手を横に貼るのはOK?縦貼り・横貼りのマナーと見た目の違い
切手を2枚貼る場合、縦並びでも横並びでも基本的に問題はありません。ただし、封筒の種類や目的によって、どちらがより適しているかが変わります。
縦並びは日本の郵便文化において最も一般的で、正式で落ち着いた印象を与えます。宛名の縦書き封筒では特に縦並びが自然で、視線の流れもスムーズです。消印も上から下へ連続して押されるため、機械処理上も適しています。
一方で、横並びは洋形封筒やカジュアルなカード郵送などに向いており、横書きの宛名レイアウトとの相性が良い貼り方です。封筒の横幅が広い場合、2枚を横に並べても十分な余白を確保できるため、全体のデザインに統一感が生まれます。特に記念切手や絵柄を活かしたい場合、横並びにすると美しく見えることが多いです。
貼る際のポイントとしては、上下左右の余白を均等に保ち、切手の縁が封筒の角に平行になるよう配置することです。余白が5ミリ前後あると整然と見え、宛名や郵便番号欄とのバランスも取れます。複数枚を貼る際は1〜2ミリの間隔を空け、密着させないことで湿気による浮き上がりを防げます。
ビジネス文書の場合は、縦貼りがよりフォーマルな印象を与える傾向にあります。特に役所や企業宛ての封筒では、縦並びのほうが礼節を重んじた印象を与えます。一方で、友人や家族への手紙、イベントの招待状などでは、横貼りにしても失礼にはあたりません。送る相手や目的に応じて、縦横を選び分ける柔軟さが望ましいでしょう。
封筒全体のレイアウトと一体感を持たせることが、美しい切手貼付の鍵です。どちらの配置を選んでも、整然と揃えられた切手は相手への丁寧な心遣いの証となります。
切手2枚貼り方で失礼にならないコツ|のり・水の使い方とマナー

- 切手は水で貼っていいの?のりとの違いと正しい使い方
- 切手をのりで貼るときの注意点ときれいに仕上げるコツ
- 切手を複数枚貼るのは失礼?ビジネスシーンでのマナーを解説
- 切手の金額をオーバーするのは失礼?正しい金額設定と考え方
- 切手を3枚・5枚貼る場合の配置例と見た目を整えるポイント
- 封筒を美しく仕上げるための切手2枚の貼り方
切手は水で貼っていいの?のりとの違いと正しい使い方
現在流通している多くの日本の切手は、裏面に「水溶性のり」が塗布された湿式タイプです。これは、裏面を軽く湿らせることで糊が溶け、紙に密着する仕組みになっています。そのため、水を使って貼ること自体はまったく問題ありません。ただし、適切な水分量を守ることが重要です。
水を使う場合、直接切手を水に浸すのではなく、綿棒やスポンジにごく少量の水を含ませるのが最も安全です。水分量の目安は、綿棒を軽く押さえたときに水滴が出ない程度です。裏面全体を均一に湿らせ、端までムラなく塗るよう意識しましょう。水分が多すぎると、紙の繊維が膨張して波打ちが起こり、乾燥後に剥がれやすくなります。特に、封筒のコート紙や光沢のある素材では、のりが浸透しにくいため、水量の加減が仕上がりに直結します。
一方で、のりを使用する方法も非常に安定した貼付が可能です。スティックのりや郵便用のりなど、紙質に適した接着剤を薄く均一に塗布します。液体のりは手軽ですが、水分が多くにじみやすい点に注意が必要です。特に速乾タイプのスティックのりは作業効率が高いものの、位置調整の猶予が短いため、貼る位置を事前に確認しておくことが大切です。
貼り付け後は、柔らかい布やティッシュで軽く押さえながら中央から外側へ空気を逃がすようにすると、気泡を防ぎながら密着度が高まります。完全に乾燥するまで数分置くことで、切手の角が浮き上がるのを防げます。
なお、2019年以降に発行された一部の特殊切手(例:グリーティング切手など)は、裏面に「シール式」が採用されています。これらは水を使わずに貼るタイプであり、水をつけると接着剤が劣化するおそれがあります。封筒の材質や切手の発行年によって最適な方法を選ぶことが大切です(出典:日本郵便「郵便切手の種類と仕様」https://www.post.japanpost.jp/kitte/)。
切手をのりで貼るときの注意点ときれいに仕上げるコツ
切手をのりで貼る場合、仕上がりの美しさと粘着力のバランスを取ることが重要です。のりの厚塗りは、紙が波打ったり、気泡ができたりする原因となります。最もきれいに貼るコツは、薄く均一にのりを塗り、中央から外側に押さえながら密着させることです。
スティックのりは、紙全体に薄く塗布しやすく、にじみにくい点で最も扱いやすいタイプです。郵便局でも推奨されることが多く、速乾タイプを選べば作業効率が向上します。一方で、液体のりは水分が多く、紙質によってはしわやヨレを起こしやすいため、慎重に使う必要があります。特に薄手の封筒やクラフト紙では、のりが浸透しすぎて見た目を損なう場合があります。
角や縁の浮きを防ぐためには、四隅までのりを行き渡らせることがポイントです。綿棒や指先で角を押さえながら塗ると、自然な密着が得られます。さらに、冬場や乾燥した環境では静電気の影響で紙が反発し、貼り付きにくくなることがあります。その場合、作業前に軽く手を保湿したり、部屋の湿度を40〜50%程度に保つと安定します。
また、位置合わせも美しい仕上がりには欠かせません。貼る位置を間違えて貼り直すと、切手や封筒の紙が傷む恐れがあります。仮置き(位置確認)→接着の二段階で作業することで、失敗を防げます。仮置き時に軽く角を押さえ、全体のバランスを見てから本貼りに移ると、正確で整った見た目に仕上がります。
このように、のりの種類と塗布量を丁寧に管理することで、切手の浮きや波打ちを防ぎ、長期間剥がれない美しい郵送物を作ることができます。ビジネス書類などでは、細部まで丁寧に仕上げることで信頼感を高められます。
切手を複数枚貼るのは失礼?ビジネスシーンでのマナーを解説
複数の切手を貼ること自体は、郵便局のルール上もまったく問題ありません。金額の合計が正しいことと、見た目が整っていることが満たされていれば、正式な郵送物として受け付けられます。実際に、84円切手を2枚貼る、または100円+10円+10円のように組み合わせることは日常的に行われています。
ただし、ビジネスシーンにおいては「見た目の印象」も大切です。額面の異なる切手を使用する場合は、金額の大きい切手を上側または左側に配置することで、視覚的に安定感を持たせることができます。また、派手な記念切手やキャラクター切手などは、カジュアルな印象を与えるため、フォーマルな書類や弔事では避けた方が無難です。代わりに、落ち着いた色合いの通常切手(桜や鳥シリーズなど)を選ぶと、相手に対して礼儀正しい印象を与えます。
特に官公庁や企業への提出書類では、整然と貼られているかどうかが信頼性を左右することがあります。切手の縁が揃っていなかったり、斜めに貼られていたりすると、細部への配慮が足りない印象を与えかねません。逆に、複数枚でも丁寧に並べて貼られていれば、むしろ几帳面で誠実な印象を与えることができます。
一方で、受け取る相手が友人や個人の場合は、多少カジュアルな切手を使っても問題ありません。記念切手を組み合わせて個性を表現することも、温かみのあるコミュニケーションの一環といえます。要は、「誰に送るか」「どんな目的で送るか」を意識して選ぶことがマナーに直結します。
また、金額の過不足にも注意が必要です。料金が足りないと受取人に追加料金が請求され、逆に多すぎても返金はされません。発送前に日本郵便の料金表を確認し、正確な額を計算することが、最も確実な信頼の証です(出典:日本郵便「郵便料金・運賃を調べる」https://www.post.japanpost.jp/send/fee/index.html)。
丁寧な配置と相手への配慮があれば、切手を複数枚貼ることは決して失礼ではなく、むしろマナーをわきまえた送付の形として評価されます。
切手の金額をオーバーするのは失礼?正しい金額設定と考え方
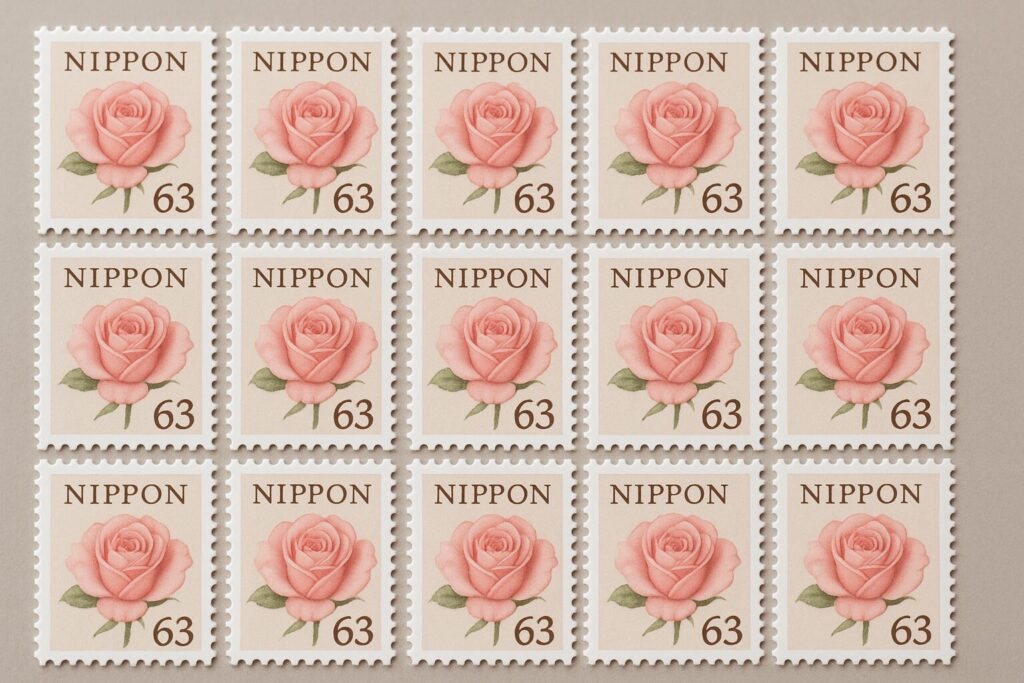
郵便を送る際に、必要な料金よりも多くの金額分の切手を貼ることは法律上も実務上も問題ありません。郵便局では、料金が不足していなければ受理されます。しかし、マナーや資源の観点から見ると、過剰な上乗せは好ましくない行為とされています。これは、切手が本来「必要な郵便料金を支払うための手段」であり、使い過ぎはコストや資源の無駄につながるためです。
少額の端数を合わせるために1円〜2円分ほど多めに貼るのは、一般的な実務対応として許容範囲です。たとえば、実際に必要な料金が94円で84円切手しか手元にない場合、84円+10円=94円が理想ですが、84円切手を2枚貼って168円とするのは過剰です。どうしても金額が合わない場合は、郵便局の窓口で不足分を補ってもらうか、計量・確認サービスを利用するのが確実です。
万一料金が不足していると、郵便物が差出人に返送されたり、受取人が不足分を支払う「料金受取人払い」扱いになる場合があります。これにより、到着が遅れる・受取人に負担をかけるといったトラブルにつながる可能性もあります。したがって、「不足よりは少しの超過のほうが安全」というのは実務的な判断です。
一方で、フォーマルな書状や贈答品の郵送など、印象を重視すべき場面では必要額を正確に合わせることが礼儀とされます。切手の金額を丁寧に調整することは、相手に対する配慮や誠実さの表れでもあります。
なお、郵便料金の正式な区分や重量ごとの設定は日本郵便が公開しています(出典:日本郵便「郵便料金・運賃を調べる」https://www.post.japanpost.jp/send/fee/index.html)。送付前に一度確認しておくと、安心して発送できます。
切手を3枚・5枚貼る場合の配置例と見た目を整えるポイント
複数の切手を貼る際は、見た目の整然さと郵便処理のしやすさの両立がポイントです。郵便局の消印は通常、右上から左下方向に押されるため、複数枚を貼る際もこのエリアにまとめて配置することが基本となります。
三枚の場合は、縦に二枚、その右側に一枚を配置するL字型レイアウトが最も実用的です。封筒の右上コーナーに自然に収まり、消印も一度で押しやすい構成になります。封筒が小型の場合やスペースが限られる場合でも、無理なく整えることができます。
五枚を使用する場合は、上段三枚・下段二枚の「将棋盤型」の配置がバランスよく見えます。縦横の間隔はおよそ1〜2ミリを保ち、隣の切手と密着させないことが重要です。これにより、湿気や接着剤の影響による剥がれを防ぎ、全体がすっきりとした印象になります。
さらに美観を高めるコツとして、額面が大きいものを左上から右下へ向かって配置する方法があります。これにより、視線の流れが自然になり、整った印象を与えます。また、記念切手や図柄の方向がある場合は、天地を必ず揃えるようにします。封筒のデザインに対して切手が斜めになっていると、全体の印象を損なうため注意が必要です。
作業前に、切手を封筒に「仮置き」して配置バランスを確認し、スマートフォンで撮影して客観的に角度をチェックする方法も有効です。貼る前に一度確認することで、微妙なズレや傾きを修正しやすくなり、完成度の高い仕上がりになります。
複数枚の代表的な配置パターン
| 枚数 | 配置の例 | コメント |
|---|---|---|
| 3枚 | 縦2枚+右に1枚 | L字で省スペース・消印が押しやすい |
| 4枚 | 2×2の格子 | バランスが取りやすく美観も安定 |
| 5枚 | 上3枚+下2枚 | 面積の大きい封筒や角形封筒向け |
こうした配置ルールを守ることで、郵便物としての実用性を確保しながら、見た目にも美しい封筒デザインを実現できます。特にビジネス文書や贈答品の郵送時には、こうした細部への配慮が、相手に対する誠実さやプロ意識を印象づけます。
封筒を美しく仕上げるための切手2枚の貼り方
切手を2枚貼る際の基本は、「右上エリアに整然と配置する」ことに尽きます。縦並びでも横並びでも問題はありませんが、封筒の形状や宛名のレイアウトに応じて選ぶのが最適です。縦型封筒(和封筒)では縦貼りが自然で落ち着いた印象を与え、横型封筒(洋封筒)では横貼りが全体に調和します。
貼る位置の目安は、封筒右上から約10ミリ内側・上端から約5ミリ下の位置です。上下の余白を均一に保ち、切手間の隙間を1〜2ミリ程度確保すると、消印が綺麗に押されます。また、封筒のデザインや宛名ブロックにかからないよう、バランスを見ながら微調整することが大切です。
複数の額面を組み合わせる場合は、高額の切手を上側または左側に配置し、金額の小さい切手を下側や右側に添えると安定感のある印象になります。さらに、封筒全体を俯瞰で確認して、切手と宛名、郵便番号欄のバランスを整えると、機能性と美観を両立できます。
切手の貼り方一つで、封筒全体の印象が変わります。特に、ビジネス文書や公式な案内状では、細部まで整った郵送物が「信頼」「誠実さ」「丁寧な仕事ぶり」を象徴します。
郵便局が示す**基本ルール(右上配置・額面合計の適正・天地の統一)**を守りつつ、デザインの調和を意識すれば、機能性と美しさを兼ね備えた仕上がりが実現できます。
切手2枚の貼り方|正しい位置・マナーまとめ

- 切手は封筒の右上に貼るのが基本ルール
日本郵便の規定では、切手は封筒の「右上隅」に貼るのが原則。機械による消印処理をスムーズに行うため、この位置を守ることが大切です。 - 切手2枚を貼るときは重ねず整列させる
2枚貼る際は、縦または横に1〜2ミリの隙間を空けて並べると美しく見えます。消印もきれいに押されやすくなります。 - 縦貼り・横貼りは封筒の向きに合わせて選ぶ
縦長の和封筒では縦貼り、横型の洋封筒では横貼りが自然。宛名との視線の流れを意識すると全体が整います。 - 額面の大きい切手を上または左に配置する
複数の金額を組み合わせる際は、高額のものを上または左に配置。視覚的にも安定し、金額の確認もしやすくなります。 - 切手の間隔は1〜2ミリが最も美しい
隙間を保つことで、切手同士ののりの影響による剥がれやヨレを防げます。見た目の統一感も生まれます。 - 貼る前に仮置きで配置をチェックする
スマートフォンで撮影して角度やバランスを確認すると、ズレや傾きを事前に防げます。 - 水で貼る場合は綿棒やスポンジで少量を使う
切手の裏面は水溶性のりが使われているため、水分を均一に少量つけるのがコツ。濡らしすぎると波打ちや剥がれの原因になります。 - のりを使う場合はスティックのりを薄く均一に
液体のりは水分が多く紙を傷める恐れがあるため、スティックタイプの郵便用のりが最適です。四隅まで薄く塗布しましょう。 - 切手が貼れないデザイン封筒では宛名をずらす
ロゴやデザインで右上に余白がない場合は、宛名を左寄せにするか封筒サイズを変更。または小さい額面切手を組み合わせて対応します。 - 84円切手を2枚貼るときは合計168円の扱いになる
重量や追加サービス(速達・書留など)で168円が必要な場合に有効。ただし、不要な超過は避けるのがマナーです。 - 切手代をオーバーしても郵送は可能だが控えめに
少額の超過(数円)は実務上問題ありませんが、大幅な上乗せは無駄になります。特にフォーマルな場では必要額に合わせるのが礼儀です。
(出典:日本郵便「郵便料金・運賃を調べる」) - 切手を3枚・5枚貼る場合は配置を意識する
三枚はL字型、五枚は上3枚+下2枚の整列が推奨。宛名や郵便番号枠にかからないよう、右上にまとめて貼ります。 - 封筒サイズに合わせた余白設定を守る
長形3号では上・右5〜10ミリ、洋形2号では5〜8ミリ、角形2号では8〜12ミリ程度の余白を取ると整います。 - ビジネスシーンでは落ち着いた通常切手を選ぶ
派手な記念切手よりも、シンプルで上品なデザインの通常切手を選ぶと、信頼感を損なわず好印象を与えます。 - 美しい貼り方は「礼儀と信頼」を伝える
切手の位置や角度を丁寧に整えることで、送り手の誠意と細やかさが相手に伝わります。ビジネス・プライベートを問わず、基本を押さえた貼り方が大切です。
関連記事







