郵便物を送ったのに、思いがけず「差出人に返送されました」という通知が届くと、戸惑ってしまう人も多いでしょう。宛先は合っていたはずなのに、なぜ返送されてしまったのか。さらに、もう一度届けたいときにはどう手続きをすればいいのか。郵便差出人に返送再配達に関する疑問は、実は多くの人が抱えているトラブルのひとつです。
この記事では、郵便が差出人に返送される原因から、再配達や再発送の具体的なやり方、そして今後同じことを繰り返さないためのチェックポイントまでをわかりやすく解説します。ちょっとした住所の書き方や保管期限の違いを知っておくだけで、再送トラブルを防ぐことができます。
「返送されたけれど、もう一度確実に届けたい」「郵便局でどう対応してもらえるのかを知りたい」という方は、ぜひ最後まで読んでみてください。あなたの郵便トラブルをスムーズに解決するヒントがきっと見つかります。
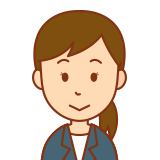
💡記事のポイント
- 郵便物が返送に至る代表的な理由と最初に取るべき対応
- 郵便物の再配達と再発送の違いと費用の考え方
- 郵便物の追跡と問い合わせで状況を把握する具体的手順
- 郵便が差出人に返送再発防止のチェックポイントと実務のコツ
郵便が差出人に返送される理由と対処法(再配達)

- 郵便物が差出人に返送される主な理由とは?
- 「差出人に返送」とはどういう意味?郵便局での扱いを解説
- 郵便が差出人に返送された場合にやるべき3つのステップ
- 郵便局の保管期限が切れたときの返送ルールと確認方法
- 郵便が差出人に返送されるまでの日数の目安と追跡のコツ
- 返送時に再配達を依頼した場合の料金はかかるのか?
郵便物が差出人に返送される主な理由とは?
郵便物が返送される背景には、単純なミスから制度的な取り扱いまで、いくつもの要因が重なっています。最も多いのはあて所不明や転居先不明で、これは宛先の住所情報が古い、または記載が不完全な場合に発生します。例えば、番地の抜けや部屋番号の記入漏れ、郵便番号の誤記、または建物名の省略があると、配達員が現地で宛先を特定できず、結果的に返送対象となります。
次に多いのが、受取人不在による保管期間の経過です。通常、郵便局では書留やゆうパックなどの不在郵便物を7日間程度保管しますが、その間に再配達の依頼がなければ差出人に返送されます(出典:日本郵便「郵便物等の保管期間」https://www.post.japanpost.jp/question/620.html)。この期間はサービスの種類によって異なり、一般郵便では即時返送される場合もあります。
そのほか、受取拒否による返送も少なくありません。企業宛てのダイレクトメールや督促状など、受取人が受け取りを拒否した場合も差出人へ戻されます。また、料金不足や危険物の疑いなど、郵便法や内国郵便約款に基づく取り扱い制限によって返送されるケースもあります。
差出人がまず行うべきは、封筒やラベルの宛先情報を丁寧に見直すことです。住所表記の順序、番地・号・部屋番号の抜け、郵便番号と住所の整合性、建物名の正式名称を確認します。特に集合住宅では、表札と宛名が一致していないことが原因になることもあるため注意が必要です。
さらに、受取人が長期不在や転居届未提出などの事情を抱えている場合もあります。連絡が可能であれば、相手の現在の住所や受け取り可能なタイミングを確認することで、再送時のトラブルを防ぐことができます。これらを一つずつ検証していくことで、次の発送に向けた正確な改善が可能となります。
「差出人に返送」とはどういう意味?郵便局での扱いを解説
差出人に返送とは、配達が成立しなかった郵便物を、発送者の元へ戻す取り扱いを意味します。この返送処理は、配達経路上での確認作業を経て行われ、あて所不明や受取拒否、保管期限切れなど、郵便法上の配達不能事由に該当した場合に適用されます。返送物には赤いスタンプで「差出人に返送」と明示され、理由を示すチェック欄(例:あて所に尋ねあたりません、受取拒否など)が記載されます。
郵便局でのステータスは、通常「持ち戻り中」→「保管中」→「差出人へ返送」の順で更新されます。追跡サービスでこれらの表示を確認することで、配達のどの段階で返送処理が始まったのかを把握することができます。特に「差出人へ返送」の表示が出た時点で、配達局から発送元の郵便局へ戻る輸送工程に入っているため、途中で受取人側の再配達依頼は原則できません。
再配達という言葉は、受取人側が同一の配達郵便局に対して再度配達を依頼する手続きを指します。これに対して返送は、配達不能を前提とした「差出人への戻し処理」であり、目的地そのものが異なります。この違いを理解しておくことは、今後の対応を決めるうえで非常に大切です。
また、返送物の扱いには種類ごとの取り決めがあります。普通郵便の場合は封筒の表面にスタンプを押したうえで返送されますが、書留やゆうパックなどの記録扱い郵便では、伝票番号や記録が残り、返送履歴をオンラインで確認することが可能です。公式情報に基づき確認することで、誤解を防ぎ、スムーズに再発送の手続きを進められます。
郵便が差出人に返送された場合にやるべき3つのステップ
郵便が差出人に返送された場合、焦って再投函する前に、段階的に確認と修正を行うことが再発防止につながります。ここでは実際の流れに沿った3つのステップを詳しく解説します。
ステップ1:追跡番号で状況と返送理由を特定する
返送通知や追跡番号を確認し、郵便物の現在位置と返送理由を特定します。日本郵便の追跡サービスでは、持ち戻り中・保管中・差出人へ返送などの詳細な履歴を時系列で確認できます。ステータスが「保管中」の段階であれば、受取人側が再配達を依頼することで返送を回避できる可能性もあります。差出人が早期に動くためにも、追跡確認は最初に必ず行いましょう。
ステップ2:返送理由に応じて修正方針を決める
返送理由によって取るべき対応が変わります。あて所不明であれば宛先の再確認、転居先不明であれば受取人への連絡、料金不足なら重量や規格の見直しが必要です。受取拒否の表示がある場合は、相手に意向を確認し、再送しても良いのか、内容変更が必要なのかを判断します。封筒や送り状に返送理由のスタンプが押されているため、必ず内容を確認してから修正に取り掛かるのが安全です。
ステップ3:再送の準備を整え、確実に届ける
修正が完了したら、新しい封筒や送り状を用意し、訂正した情報を記入します。返送された封筒をそのまま再利用すると、旧宛名が読み取られて誤配されるリスクがあるため、基本的には新しい資材を使用するのが望ましいです。また、書留・速達・配達日指定などのオプションを追加すると、到達確認や再送保証の点で安心です。
再送前には、受取人が確実に受け取れる時間帯や在宅状況を確認しておくと、再び返送されるリスクを大幅に減らせます。これら3つのステップを丁寧に行うことで、再発送をスムーズに進めるとともに、次回以降のトラブル防止にもつながります。
郵便局の保管期限が切れたときの返送ルールと確認方法

受取人が不在で配達できなかった郵便物は、配達を担当する郵便局で一時的に保管されます。この保管期間を過ぎると、自動的に差出人への返送手続きへと移行します。
郵便局では郵便物の種類によって保管期限が異なり、たとえば普通郵便では保管制度がない一方で、書留やゆうパックなどの追跡サービス付き郵便は一定期間の保管後に返送が行われます。
通常、書留やレターパック、ゆうパックの保管期間は7日間が標準です。7日以内に受取人が再配達の依頼を行わなければ、郵便物は差出人の住所へ返送されます。これらの取り扱いは郵便法第40条および日本郵便の「郵便物の保管期間等に関する取扱基準」に基づいています(出典:日本郵便「郵便物等の保管期間」https://www.post.japanpost.jp/question/620.html)。
受取人が旅行や出張で一時的に不在となるケースでは、保管期限が過ぎて返送処理に入る前に再配達を申し込むことで、返送を防ぐことが可能です。再配達はインターネットや電話、自動音声サービスからも申し込みできるため、期限が迫っている場合は早めに行動することが重要です。
差出人として返送通知を受け取った場合でも、郵便物がまだ配達郵便局の保管庫に残っていることがあります。この段階で受取人に連絡し、速やかに再配達を依頼してもらえば、返送を食い止められる可能性があります。郵便物の動きはリアルタイムで変化するため、追跡サービスの確認と電話による直接の問い合わせを併用することが最も確実です。
不在通知(不在連絡票)に記載されている問い合わせ番号を利用すれば、配達を担当した郵便局に直接つながり、現状の保管状況を確認できます。特に年末年始や大型連休の時期は、通常よりも返送処理が遅延する場合があるため、期限内でも余裕を持った確認が安心です。
種別ごとの取り扱い比較(概要)
| 種別 | 代表的な保管の扱い | 返送に至る主な契機 | 再送時の留意点 |
|---|---|---|---|
| 通常郵便 | 保管扱いにならない場合がある | あて所不明や受取拒否 | 宛先修正と料金見直し |
| 書留類 | 一定期間の保管後に返送 | 不在連絡票で期間満了 | 記録扱いの再封入に注意 |
| ゆうパック | 保管期間経過後に返送 | 受取人への連絡未達 | 送り状の再発行と補償条件 |
通常郵便の場合は不在時に保管されず、そのまま返送処理に移ることもあります。一方、書留やゆうパックは受取人に通知が届くため、再配達を依頼する機会があります。再送時には、新しい送り状を発行し直し、宛先の表記を最新の情報に更新しておくと安全です。
特にゆうパックは補償金額の上限や再発行時のルールがあるため、詳細は郵便局窓口や公式サイトで確認しておくことをおすすめします。
郵便が差出人に返送されるまでの日数の目安と追跡のコツ
返送にかかる日数は、保管期間・再配達の試行回数・地域間距離・天候・交通事情など、さまざまな要因によって変動します。平均的な目安としては、配達不能から差出人への返送完了までおおよそ7〜14日程度が一般的です。
ただし、返送処理の流れは次のように段階を踏んで進行します。
- 配達局による保管期間の経過
- 差出人への返送決定
- 返送ルートの確定と輸送(通常配送より優先度が低い)
- 差出人最寄り郵便局での到着・仕分け・配達
特に地方や離島間の郵送では、交通便数の制限によりさらに数日かかる場合があります。また、年末年始や祝日を挟むと配送が集中し、返送完了まで2週間以上要することもあります。
追跡サービスを活用することで、郵便物がどの段階にあるかを把握できます。ステータスが「持ち戻り中」から「保管中」に変わった場合は、受取人の再配達依頼を待っている状態です。「差出人へ返送」と表示された時点で、郵便物は返送ルートに入っており、受取人側の操作では停止できません。
一方、「あて所に尋ねあたりませんでした」という表示のあと、すぐに返送されるとは限りません。このステータスは現場確認中を意味しており、誤配防止のために再確認を行っていることがあります。そのため、数日経過しても動きがない場合は、配達郵便局または集配センターへ電話で直接問い合わせ、状況を説明してもらうのが確実です。
追跡情報と電話確認を組み合わせて管理することで、返送ルートの把握と次の再送準備が円滑に進みます。差出人に戻るまでの流れを理解しておけば、必要に応じて再発送や宛先修正をタイムリーに行うことが可能になります。
返送時に再配達を依頼した場合の料金はかかるのか?
再配達と再発送は似ているようで異なる制度であり、費用の扱いにも明確な差があります。受取人が同じ配達郵便局に対して再配達を依頼する場合は、追加料金はかかりません。ただし、返送処理が進行して差出人に戻ってしまった場合、再度発送する際には新たな郵便料金が必要になります。
再発送時には、通常郵便・定形外・書留・ゆうパックといったサービスごとに料金体系が異なります。たとえば、
- 定形郵便(50g以内):110円
- 定形外郵便(100g以内):180円
- ゆうパック(60サイズ・関東→関西):約880円前後
また、速達・書留・配達日時指定などのオプションを付ける場合は、その分が加算されます。再発送では封筒の再利用を避け、新しいラベルや送り状を作成するのが基本です。古いバーコードや宛名が残っていると誤配の原因になるため、完全に剥がすか、新しい封筒を使うことを推奨します。
料金不足によって返送された場合は、差額分だけでなく再発送の全額を支払う必要があります。再送時には封筒のサイズ・厚さ・重量を計測し、料金表をもとに正確な切手を貼付してください。郵便局窓口で料金を再確認してから投函すれば、再び戻ってくるリスクを防げます。
コストの見通しを立てるためには、郵便局の公式料金計算ツールを活用すると便利です(出典:日本郵便「料金を計算する」https://www.post.japanpost.jp/cgi-charge/)。あらかじめ料金とオプションの組み合わせを把握しておくことで、再発送時の手間を減らし、確実な再配達を実現できます。
郵便が戻ってきた後の再配達・再送手続きと防止策

- 郵便が返送されたときの再送のやり方|再発送の正しい手順
- 郵便局への問い合わせで返送状況を確認する方法
- 差出人に返送された場合の正しい対処法と注意点
- 「あて所が不明のため差出人に返送された」ときの原因と対策
- ゆうパックが返送になった場合の流れと再配達の依頼方法
- 郵便物が差出人に戻ってしまった場合はどうすればいい?実例と専門家のアドバイス
郵便が返送されたときの再送のやり方|再発送の正しい手順
郵便物が返送されてしまった場合、焦らずに一つひとつの手順を確認することが大切です。まず最初に行うべきは、封筒や送り状の表面を丁寧に確認し、返送理由に直結する修正箇所を特定することです。返送理由は封筒や伝票にスタンプやシールで表示されています。「あて所に尋ねあたりません」「受取拒否」「料金不足」などの表示内容を読み取り、それぞれの原因に応じて対応します。
住所の記載では、都道府県名から番地、建物名、部屋番号までを省略せずに正確に記す必要があります。特にマンション名や部屋番号の記載漏れは非常に多く、配達不能の大きな原因となります。郵便番号は日本郵便の公式サイトにある郵便番号検索ツール(出典:日本郵便「郵便番号検索」https://www.post.japanpost.jp/zipcode/)で照合し、最新の表記を使用してください。
封筒の再利用は可能ですが、返送理由の訂正や修正が目立つ場合、またはラベルが重なって機械で読み取りにくい状態のときは、新しい封筒や送り状を使用する方が安全です。返送済み封筒のバーコードや宛名が残っていると、誤配のリスクが高まります。
さらに、再送前に内容物の重量を計量し、定形・定形外・ゆうパックなどの適切な区分を判断します。重さが1g違うだけでも料金区分が変わることがあるため、窓口での確認が確実です。急ぎの場合は速達や書留、特定記録などのオプションを追加すると安全性と追跡性が向上します。
再送時には、相手が受け取りやすい時間帯を確認しておくと到達率が格段に上がります。配達希望時間帯を指定できるサービスを活用すれば、相手の生活リズムに合わせた受け取りが可能です。最後に、宛名と郵便番号を声に出して確認する「音読チェック」を行うと、見落としを防ぐ効果があります。再送時は慌てず、丁寧な確認が確実な配送の鍵となります。
郵便局への問い合わせで返送状況を確認する方法

返送の進行状況を正確に把握するには、郵便局への問い合わせが有効です。まずは手元に追跡番号(お問い合わせ番号)を用意しましょう。この番号は送り状や控え伝票に記載されており、日本郵便の追跡サービスページまたは公式アプリで配送履歴を確認できます。ここで「持ち戻り中」「保管中」「差出人へ返送」などのステータスを確認でき、現在の郵便物の状態を把握することが可能です。
オンラインで情報が更新されていない場合や詳細を知りたい場合は、配達を担当する郵便局または集配センターへ直接電話します。その際、以下の情報を整理して伝えるとスムーズです。
- 差出人の氏名と連絡先
- 差出日(発送日)
- 宛先の地域名または住所概要
- 返送理由(封筒の記載内容)
問い合わせ時に「保管中」と案内された場合は、まだ返送処理が完了していない可能性があります。この段階で受取人側に連絡し、再配達依頼を行ってもらうことで、返送を未然に防げることもあります。一方、「差出人へ返送済み」と案内された場合には、返送経路や到着見込み日を確認しておきましょう。地域や配送量によっては返送までに7〜14日ほどかかるケースがあります。
急ぎの案件や重要書類の場合は、相手方にも現状を共有し、再送時に受け取り体制を整えてもらうとスムーズです。また、今後の再送計画を立てる際には、同様の返送トラブルを避けるために、住所データベースや取引先管理リストを最新化しておくとよいでしょう。問い合わせを怠らず、リアルタイムで状況を把握する姿勢が、トラブル防止と再発送準備の両面で有効に働きます。
差出人に返送された場合の正しい対処法と注意点
郵便物が差出人に返送されたときは、返送理由に応じて対処の優先順位を決めることが再送成功への近道です。最も多い原因は「あて所不明」「受取拒否」「料金不足」の3つであり、それぞれに対応方法が異なります。
まず、あて所不明の場合は、住所情報を正確に再取得することが必要です。相手に直接確認できる場合は最新の住所を聞き、できない場合は名刺や契約書などの記録を参照して情報を更新します。また、建物の表札やポストの表記が宛名と一致していないと配達できないため、受取人に表記確認を依頼することも効果的です。
受取拒否の場合は、相手の意向を確認することが第一です。内容に誤解があった場合や再送を希望される場合には、再発送前に相互理解を得ておきましょう。なお、法律上は受取拒否が成立すると郵便局はその郵便物を差出人に返送する義務を負うため、無理に再送しても再び拒否される恐れがあります。
料金不足で返送された場合は、封筒のサイズ・厚さ・重量を再計測し、正しい料金を算出します。再利用封筒の切手をそのまま使用せず、新しい封筒に正しい金額を貼り直すのが基本です。窓口で料金を確認すれば、次回の返送を防げます。
また、再送時には封筒のバーコードや宛名シールを完全に剥がすことが不可欠です。旧ラベルが残っていると機械で誤認され、再び返送されるリスクがあります。特にラベルプリンタで印字されたバーコードは、透明フィルムを剥がしても跡が残るため、新しい封筒を使う方が確実です。
重要書類や高額商品を送る際は、配達状況を記録できる書留や特定記録郵便を選ぶことで、トラブル時の追跡が容易になります。受け取り方法も相手と事前に調整し、確実に受領できる日時や場所を設定しておくことが大切です。
発送前に、以下のようなチェックリストを用意しておくとミス防止に役立ちます。
- 住所・郵便番号の整合性を確認したか
- 部屋番号や建物名の記載に抜けがないか
- 宛先と差出人の表記が明確か
- 封筒やラベルの古い情報を削除したか
- 内容物の重量・サイズを再確認したか
急ぎの案件ほど焦りが生じやすく、基本的な確認を省略してしまう傾向があります。再送を確実に成功させるためには、手順を冷静に整理し、正確な情報をもとに準備を進めることが最も重要です。
「あて所が不明のため差出人に返送された」ときの原因と対策

郵便物に「あて所が不明のため差出人に返送された」と表示される場合、それは記載された住所情報と実際の居住情報が一致していないことを意味します。郵便局では、住所の番地・号の順序、丁目の有無、建物名の省略、部屋番号の欠落など、ほんのわずかな記載ミスでも配達が不可能と判断されることがあります。
まず最初に行うべきは、記載した住所を公式の住所検索サービスで照合することです。郵便番号から正確な住所を逆引きできる日本郵便の公式ツールを利用すると、町名の表記揺れ(例:「○○町」と「○○丁目」など)や地名変更後の住所を正しく把握できます(出典:日本郵便「郵便番号検索」https://www.post.japanpost.jp/zipcode/)。
また、マンションやオフィスビルなど集合建物宛ての場合、建物名と部屋番号は必ず記載する必要があります。建物名の省略や旧名称の使用、または「101」などの部屋番号の記載漏れが、あて所不明の原因になるケースが多く見られます。さらに、受取人側の表札が旧姓や会社名のままになっている場合、配達員が一致確認できずに返送されることもあります。
こうしたリスクを避けるためには、再送前に次の3つの手順を踏むのが有効です。
- 公式住所検索で郵便番号と住所を照合する
- 地図アプリで建物の位置を確認し、類似名称の建物がないかチェックする
- 受取人に表札表記や郵便受けの名称を確認してもらう
特に近隣に同名の建物や似た番地の住所が存在する場合、配達ミスのリスクが上がります。住所表記を一字一句正確に整え、再送前に音読確認を行うことで、再度の返送を防ぎやすくなります。
ゆうパックが返送になった場合の流れと再配達の依頼方法
ゆうパックが返送になる主な流れは、「配達時不在」→「持ち戻り(郵便局での保管)」→「保管期間満了による返送」という三段階です。郵便法に基づき、ゆうパックの保管期間は原則7日間と定められています。この期間内に受取人が再配達を申し込まない場合、自動的に差出人への返送処理が行われます。
再配達の依頼を行うには、まず追跡番号(お問い合わせ番号)を確認します。この番号は、送り状右上のバーコード下に記載されており、日本郵便の「郵便追跡サービス」で最新の配送状況を確認できます。「保管中」と表示されていれば、受取人側からインターネット・電話・LINE公式アカウントなどを通じて再配達依頼が可能です。
一方、すでに差出人への返送が始まっている場合は、郵便局に連絡しても停止できません。この場合、返送完了後に新しい送り状を作成して再発送する必要があります。再発送時には、補償金額(ゆうパックは最大30万円まで指定可能)や配達希望時間帯(午前中・12〜14時など)を設定すると良いでしょう。
また、ゆうパックは「サイズ(縦・横・高さの合計)」と「重量」に応じて料金が変わる仕組みのため、返送時に箱のサイズや重さが変化した場合は再計測が必要です。サイズ違いによる料金不足で再び返送されるトラブルも少なくありません。
壊れやすい荷物や精密機器を再送する際は、緩衝材(プチプチ・発泡材など)を追加し、「こわれもの」や「天地無用」などの指定シールを貼付すると安心です。これにより輸送中の破損リスクが低減し、補償申請がスムーズになります。
ゆうパック再送時の確認ポイント
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 伝票番号 | 返送の履歴と到着見込みの把握。追跡システムで最新状況を確認する。 |
| サイズと重量 | 区分ごとに料金が変わるため再計測。変更がある場合は新料金を適用。 |
| 受取希望 | 受取人の在宅時間帯や置き配可否を確認して指定。 |
| 追加オプション | 補償金額設定、時間帯指定、チルド・クール便などの必要性を検討。 |
この表を参考に、再送準備を進めると効率的です。伝票番号の管理を怠ると、返送・再発送のタイミングを逃すことがあるため、発送控えは保管しておくようにしましょう。
また、ゆうパックの配達に関する公式ルールは日本郵便のウェブサイトでも確認できます。再配達や補償制度などの詳細は、利用前に一度チェックしておくと安心です(出典:日本郵便「ゆうパックサービスガイド」https://www.post.japanpost.jp/service/you_pack/)。
郵便物が差出人に戻ってしまった場合はどうすればいい?実例と専門家のアドバイス

郵便物が差出人に返送されたときの対応は、返送理由によって異なります。日本郵便では主に以下の4つの理由が多く見られます。
- あて所不明(住所誤記・不備)
- 受取拒否(受取人が拒否を明示)
- 保管期間満了(不在再配達なし)
- 料金不足(切手不足や区分誤り)
専門家である郵便物流管理士によれば、最も多い返送原因は住所誤記であり、全体の約6割を占めるとされています。郵便番号・丁目・番地の順序を誤るだけで、システム上の自動仕分けで弾かれることもあるため、正確な住所入力は基本中の基本です。
返送物が届いた場合、まずは封筒の返送理由スタンプを確認し、原因に即した対処を行いましょう。誤記の場合は正しい住所を再確認し、受取拒否の場合は相手への意向確認が必須です。料金不足なら郵便局窓口で再計測を行い、正しい切手額を貼り直す必要があります。
さらに、返送物をそのまま再利用する際には、古いバーコードや宛名ラベルを完全に剥がすことが重要です。残したまま再送すると、機械で誤って旧宛先に仕分けされるリスクがあります。再封入時には、封筒の破れや汚れをチェックし、新しい資材を使用するのが安全です。
最後に、再送の前に相手方へ連絡を取り、受け取り可能な日時や住所の変更有無を確認しておくことで、二重返送を防げます。郵便物の返送は必ずしも失敗ではなく、改善のきっかけにもなります。焦らず原因を突き止め、確実な再送計画を立てることが、最終的な解決への近道です。
郵便が差出人に返送された原因・対処法・再発送のやり方まとめ

- 住所は郵便番号から日本郵便公式サイトで照合する
町名・丁目・番地の表記揺れや旧住所を正確に修正することが、返送防止の第一歩。
(出典:日本郵便「郵便番号検索」) - 建物名・部屋番号を必ず明記する
集合住宅やオフィス宛てでは、建物名や部屋番号の欠落だけで「あて所不明」となることが多い。 - 表札・ポストの表記を確認してもらう
受取人の表札が旧姓や旧社名のままだと、配達員が照合できず返送されるリスクがある。 - 封筒・ラベルの再利用は避ける
古い宛名やバーコードが残ると、機械仕分けで誤配・誤返送されやすい。再送時は新封筒を使用。 - 返送理由を必ず確認してから対応を決める
「あて所不明」「受取拒否」「料金不足」「保管期間満了」など、理由に応じた対処が必要。 - 郵便局での保管期間は郵便種別で異なる
ゆうパックは7日、書留は10日など、種別ごとに返送までの猶予が異なる。早めの確認が重要。 - 追跡番号を常に管理し、配送状況を定期確認する
「保管中」「持ち戻り」「返送中」などのステータスを見逃さないよう、追跡サービスを活用。 - 再配達の依頼は受取人側が行うのが原則
差出人ではなく、受取人が指定することで返送を回避できる場合がある。 - 再発送は新しい送り状を作成し、料金を再計算する
返送後の再発送には新料金が必要。サイズや重量を再計測して正しい区分を適用する。 - 緩衝材・封入材・ラベルの再点検を行う
精密機器や壊れ物は「こわれもの」「天地無用」表示を追加し、輸送事故を防止する。 - 受取人の在宅時間や置き配可否を確認しておく
時間帯指定や再配達の依頼時に活用し、保管期限切れによる返送を防ぐ。 - 返送通知を受けたらすぐに配達局へ連絡する
まだ局で保管中なら、受取人側の手続きで再配達に切り替えできるケースもある。 - 料金不足で返送された場合は窓口で正しい金額を再確認する
重量や厚さ区分の誤りが多く、再度の返送を防ぐには正確な計測が必要。 - 再送時は封筒・送り状の清潔さや明瞭さを重視する
にじみやラベルの重ね貼りはバーコード読み取りエラーを招くため、新しいラベルを推奨。 - 返送・再送の記録を残しておく
発送日、返送理由、追跡番号、局名などを記録しておくと、トラブル時の問い合わせがスムーズ。
関連記事







