「切手 長形4号」と検索したあなたは、おそらく「この封筒にいくらの切手を貼ればいいのか」「重さやサイズにルールはあるのか」といった疑問をお持ちではないでしょうか。郵便物を送る機会はそう多くはないかもしれませんが、いざというときに正しい知識がないと、料金不足で返送されたり、相手に追加料金の負担をかけてしまったりするリスクがあります。
この記事では、長形4号封筒に関する切手の料金や郵送ルールを中心に、定形郵便・定形外郵便の違いや、サイズ・重さによってどう料金が変わるのかをわかりやすく解説していきます。さらに、84円切手はもう使えないのか、コンビニで切手を買う際の注意点、長形3号や2号との使い分けまで、実際に送る場面を想定して網羅的に紹介します。
「ただ封筒に切手を貼るだけ」と思っていた方にも役立つ内容を盛り込んでいますので、読み終えるころには不安なく郵便を出せるようになるはずです。間違えやすいポイントや最新の料金改定にも触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。
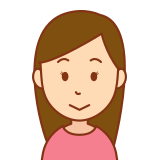
💡記事のポイント
- 長形4号封筒に必要な切手の金額とその理由
- 封筒のサイズや重さによって変わる郵便料金の仕組み
- 84円切手の現在の使い方と注意点
- 定形郵便と定形外郵便の違いと見分け方
切手 長形4号の料金とサイズ|定形郵便で送れる条件とは

- 長形4号の郵便はいくらですか?
- 長形4号の切手代はいくらですか?
- 長形4号の84円はいつまで送れますか?
- 封筒の切手 110円で送れる重さとサイズ
- 定形郵便のサイズと料金の早見表
- 切手はオーバーしてもいいですか?
長形4号の郵便はいくらですか?
長形4号封筒で郵便を送る場合、その料金は中に入れる用紙の重さや封筒の厚みによって変わります。現在の郵便制度では、長形4号封筒は「定形郵便物」として取り扱われ、重さが50g以内であれば全国一律110円の料金で送ることができます。
この料金は2024年10月に改定され、それ以前は25gまで84円、50gまで94円という2段階制でした。新制度では、よりわかりやすくするために50gまでの定形郵便物がすべて110円となり、利用者にとっての計算が簡素化されました。
例えば、長形4号にA4サイズのコピー用紙を三つ折りにして2〜3枚入れると、重さはおおむね10〜15g程度です。この場合は110円で問題なく送付できます。ただし、チラシやパンフレット、写真などを同封して合計重量が50gを超えると、定形郵便としては扱えなくなります。
さらに注意したいのは、サイズや厚みです。長形4号封筒は通常、縦23.5cm×横12cm程度で、これは定形郵便のサイズ制限内に収まっていますが、封筒が膨らんで厚みが1cmを超える場合は、定形外郵便としての扱いに変わり、料金も140円以上に跳ね上がります。したがって、長形4号に書類を入れて送る際は、重量と厚みの両方を意識しておくと安心です。
長形4号の切手代はいくらですか?
長形4号封筒を使用して郵便を出す場合、基本的な切手代は110円です。これは、2024年の料金改定以降の価格で、重量が50g以内の定形郵便物に適用される料金です。つまり、長形4号封筒で通常の文書や請求書などを送るとき、切手は原則として110円分を用意すれば問題ありません。
以前は、封筒の中身が25g以内であれば84円で送ることができました。そのため、古い情報をもとにして84円の切手だけを貼ってしまうと、料金不足になるおそれがあります。特に、企業などで大量に切手をストックしていた場合、旧料金のまま使ってしまうこともあるため、注意が必要です。
このような場合には、旧料金の切手を無駄にするのではなく、差額分の切手を組み合わせて使用することが推奨されます。たとえば、84円切手に26円切手を追加で貼れば、新しい基準に対応できます。もちろん、110円切手が市販されているため、それを一枚貼っても構いません。
一方で、封筒の中に同封するものによっては、切手代が変わるケースもあります。たとえば厚みがある冊子や試供品を入れた場合、重さが50gを超える、あるいは1cm以上の厚さになれば「定形外郵便物」としての料金が必要になります。その場合、料金は140円以上になるため、投函前に郵便局の窓口や計量器などで確認するのが無難です。
長形4号の84円はいつまで送れますか?
現在、84円切手だけで長形4号封筒を送ることはできません。かつては、封筒の中身が25g以下であれば84円で送れた時期がありましたが、2024年10月1日に郵便料金が改定され、定形郵便の最低料金は110円に引き上げられました。そのため、84円切手のみでの郵送は料金不足として扱われます。
もしも2024年9月30日までに差し出していれば、84円で送れた可能性はありますが、それ以降に出す郵便物には新料金が適用されるため、追加の切手を貼る必要があります。郵便局では、このような場合に差額分の切手を貼って対応するよう案内しています。たとえば、84円切手と26円切手を組み合わせれば、現在の110円に対応できます。
実際のところ、料金改定直後は旧料金のまま投函してしまう人も多く見られます。これには、長年の習慣や在庫の切手を消化したいという心理が関係しています。しかし、料金不足の郵便物は、受取人が追加料金を払わされるか、場合によっては返送されてしまう可能性があるため、結果としてトラブルの原因になりかねません。
そのため、84円切手を活用するのであれば、必ず追加分を合わせて110円相当になるよう注意しましょう。今後も切手料金の変更が行われる可能性があるため、郵送前に最新の情報を確認することが、スムーズなやり取りのために重要です。特に定形郵便を多く利用する企業やフリーランスの方は、郵便局の公式情報に常に目を通しておくと安心です。
封筒の切手 110円で送れる重さとサイズ

110円切手で送ることができる封筒には、明確な条件があります。郵便局が定める「定形郵便物」としての基準を満たしていなければ、110円では送れず、追加料金や別種の郵便物としての扱いが必要になるためです。
具体的に言えば、110円で送るためには、封筒の重さが50g以内、サイズが長辺14〜23.5cm以内、短辺9〜12cm以内、厚さ1cm以内である必要があります。この範囲を1つでも超えてしまうと、定形郵便ではなくなり「定形外郵便物」として扱われ、料金は140円以上に跳ね上がります。
例えば、長形4号封筒はこのサイズの範囲に収まっており、非常に一般的な定形郵便用の封筒です。ここにA4のコピー用紙を三つ折りで2〜3枚入れた場合、重量はおおむね10〜15g程度となり、十分に110円で送ることができます。ただし、厚手の用紙やカラー印刷のパンフレット、小冊子などを入れると、重さがすぐに増えてしまい、気づかないうちに50gを超えるケースもあります。
また、封筒の素材や構造にも注意が必要です。たとえば中にエアクッションが入っている「クッション封筒」などは厚みが1cmを超えることがあり、たとえ軽くても定形外となってしまいます。つまり、重さだけではなく「サイズと厚み」も110円で送るための大きな判断材料になるということです。
こうした郵送の条件を知らずに封筒を出してしまうと、「料金不足」として返送されたり、受取人が追加料金を支払わされたりする事態も起こり得ます。特にビジネスで郵便物を扱う場合、郵送先に迷惑をかけないよう、重さとサイズのチェックは必ず行うべき作業です。小さなコストと時間で防げるトラブルを未然に防ぐためにも、正確な情報を把握しておくことが大切です。
定形郵便のサイズと料金の早見表
定形郵便のサイズと料金は、日本郵便が定めた明確なルールに基づいています。これを把握しておくことで、日常的な郵送の際に余計なトラブルや追加料金を避けることができます。特に料金の改定が行われた2024年10月以降は、従来の認識のままだと対応できないこともあるため、改めて確認することが重要です。
まず、定形郵便に該当するサイズは以下の通りです。長辺14cm〜23.5cm、短辺9cm〜12cm、厚さ1cm以内、重さ50g以内。この範囲に収まっていれば、内容物が書類であろうと写真であろうと、「定形郵便物」として全国一律の料金で送ることが可能です。
料金については、2024年10月の改定により統一され、50g以内であればすべて110円となりました。これは以前のような25gまで84円、50gまで94円という段階制が廃止され、簡素化された結果です。したがって、現在では「定形郵便=110円」という理解で問題ありません。
具体的な封筒サイズとしては、長形4号や洋形2号などがよく使われます。特に長形4号はA4書類を三つ折りにして収めることができるため、ビジネス用途での請求書や通知書の送付などに重宝されています。
ただし、厚さや重量のギリギリを狙う場合には注意が必要です。例えば、用紙が5枚以上になったり、紙質が厚手のものだったりすると、知らず知らずのうちに50gを超えてしまうことがあります。また、パンフレットのように折りたたみにくいものを封入すると、厚さ1cmの制限に引っかかる可能性もあります。
このようなリスクを避けるためには、投函前に家庭用のはかりや定規を使って確認することをおすすめします。郵便局では、料金不足の郵便物は返送されるか、受取人に不足分の支払いを求めるため、信頼関係にも関わってくる問題です。サイズと料金を正しく把握し、的確に送ることが郵便マナーの第一歩といえるでしょう。
切手はオーバーしてもいいですか?
切手を貼る際に「必要な金額より多めに貼ってしまっても大丈夫なのか」と疑問に思う方は少なくありません。この点については結論から言えば、「オーバーしても問題ない」が正解です。ただし、それによって特別なサービスが追加されることはなく、単に多めに支払っただけ、という扱いになります。
例えば、110円の郵便物に120円分の切手を貼ったとしても、差額の10円が返金されることはなく、そのまま通常の郵便物として取り扱われます。つまり、払いすぎた分は自己負担となるのです。この点で言えば、切手の貼りすぎは経済的には損をすることになります。
しかしながら、オーバーしてしまうことにも一定の意味はあります。というのも、料金不足で郵便物が差し戻されたり、相手に追加料金を請求されたりするよりは、過剰に貼っておいた方が確実に届くという安心感があるためです。特に重量がギリギリのときや、自宅での計量が不安な場合などには、数円のオーバーで済むなら保険として余分に貼る人もいます。
一方で、毎回の郵送で無駄な切手を貼っていると、積もり積もって大きな損失になります。企業などが大量に郵便物を扱うケースでは、数円のオーバーが繰り返されれば、年間で何千円、何万円単位の余計なコストになりかねません。
このため、正確に切手代を把握して、必要最低限の金額だけを貼ることが基本です。家庭でも、1円~10円の補助切手を複数そろえておくと、正確な貼付がしやすくなります。また、郵便局の窓口では重さとサイズを測ったうえで適正料金を案内してくれるため、不安があるときは迷わず相談するとよいでしょう。
いずれにしても、切手のオーバーは「ダメではないけれど、なるべく避けるべき」という立ち位置にあると考えるのが現実的です。郵便物をきちんと届けるために、正確な料金を理解し、無駄なく効率よく送ることが、結果としてお互いにとって気持ちのよいやり取りにつながります。
切手 長形4号と他封筒サイズの比較|最新料金(2024〜2025年)対応

- 長形3号 切手代 2024・2025年の変更点
- 長形3号のサイズとA4書類の折り方
- a4 長形3号の切手は何円必要?
- 長形2号・3号と長形4号の使い分け
- 茶封筒の切手の値段と定形外になる条件
- 切手 コンビニで買える種類と注意点
長形3号 切手代 2024・2025年の変更点
長形3号封筒を使用して郵便を送る場合、2024年10月に実施された郵便料金改定の影響を受けることになります。これまでは、25g以内が84円、50g以内が94円といった段階的な料金体系でしたが、現在では、50gまでの定形郵便物が一律110円という形に変更されています。つまり、長形3号封筒を使った郵送にも、この110円という新料金が適用されます。
この背景には、郵便事業全体の見直しがあります。人件費や配送コストの上昇、そして配送物の減少に伴って、収益構造の維持が難しくなったことが影響しています。これにより、日本郵便は制度の簡素化を目指し、段階料金から一律料金への変更を選択しました。郵便を頻繁に使わない方にとっては、計算がしやすくなるというメリットもありますが、軽量の郵便物を送っていた人にとっては値上げと感じるケースもあるでしょう。
例えば、A4用紙1枚を三つ折りにして送る場合、以前であれば84円で送れたのが、現在では110円が必要になります。このように、「少ない書類なのに料金が上がった」と感じる方も少なくないと思われます。ただし、この料金変更は、2024年10月の段階で実施されたもので、2025年時点ではまだ新たな変更の発表はありません。したがって、2025年においても引き続き、50g以内の定形郵便には110円の切手が必要になります。
企業で長形3号封筒を日常的に使用している場合は、旧料金の切手を使用していた在庫がそのままでは使えなくなることもあるため、差額分の切手を一緒に貼って対応するなど、実務上の注意が求められます。また、料金の変更時には、差額用の切手や新料金に対応した切手が発行されるため、必要に応じて郵便局での確認が重要です。
長形3号のサイズとA4書類の折り方
長形3号封筒は、ビジネスや個人の郵送において非常に汎用性が高く、特にA4サイズの書類を封入するのに最適なサイズとされています。この封筒の寸法は、縦23.5cm、横12cmとなっており、これは「定形郵便物」として郵便局が定める基準を満たしています。
この封筒にA4用紙を収めるには、「三つ折り」が最も一般的な方法です。A4サイズの用紙(縦29.7cm、横21.0cm)を三つ折りにすると、おおよそ9.9cmの高さに収まるため、長形3号の短辺である12cmに余裕をもって封入できます。この折り方には一定のコツがあり、見た目の美しさと取り出しやすさを両立させるためには、定規などを使って折り目をしっかり付けるとよいでしょう。
ビジネス用途では、請求書や見積書などのフォーマルな書類を折りたたんで送る場面が多いため、長形3号は定番の封筒となっています。また、封筒自体も薄手で扱いやすく、重さも軽量なため、郵便料金が安く済むという利点もあります。
ただし、A4書類をそのまま折らずに送る必要がある場合には、長形3号ではなく「角形2号」などの大きめの封筒を使用する必要があります。角形封筒は定形外郵便として扱われるため、料金も高くなることを覚えておきましょう。
一方で、長形3号封筒のデメリットとして、三つ折りにすることで一部の書類が読みづらくなる、または折り目が目立ってしまうこともあります。特に証明書類や再利用予定の文書では、折りたたみを避けたいというニーズもあるため、用途に応じた封筒選びが重要です。
a4 長形3号の切手は何円必要?
A4サイズの書類を長形3号封筒に入れて郵送する場合、貼付する切手は内容物の重さによって変わります。ただし、2024年10月以降の料金改定により、50gまでの定形郵便物はすべて一律110円で送れるようになったため、通常の使用であれば110円の切手1枚で対応できます。
A4のコピー用紙は1枚あたりおおよそ4〜5g前後です。したがって、用紙が5〜6枚程度までであれば、封筒と合わせても50g以内に収まりやすく、110円切手で問題ありません。また、封筒そのものも、一般的な長形3号封筒は約4〜6gと非常に軽量に作られているため、多少の封入物を増やしても重量制限に引っかかる可能性は低いといえます。
ただし、注意が必要なのは、紙の質や封入物の種類によっては50gを簡単に超えてしまう場合があるという点です。例えば、厚手のパンフレット、写真用紙、またはホチキス留めされた複数ページの資料などは、少量でも意外と重さが増します。特に封筒の中に書類だけでなく、名刺、返信用封筒、小冊子などを同封する場合は、重さと厚みの両方を確認する必要があります。
また、厚みが1cmを超えた場合は、たとえ重さが50g以内であっても定形外郵便物として扱われ、140円以上の料金が発生します。そのため、郵送前には家庭用のキッチンスケールや定規を活用して、サイズと重量のチェックをすることをおすすめします。
企業の事務作業や請求書郵送など、頻繁に長形3号封筒を使用する場合は、110円切手のほかにも、10円や20円といった補助用の切手を備えておくと、万が一の重量オーバーにも柔軟に対応できて便利です。郵便料金は細かいようでいて、積み重なればコストに影響するため、切手の選び方と貼り方にも注意を払うことが大切です。
長形2号・3号と長形4号の使い分け

長形2号・3号・4号はすべて日本郵便で規格化された封筒サイズであり、それぞれの封筒には用途に応じた最適な使い分けがあります。見た目は似ているものの、サイズが異なるため、封入できる書類の大きさや、郵便料金の区分に影響を与える点で重要な違いがあります。
まず、長形4号は縦23.5cm・横9cmというサイズで、A4サイズの書類を「三つ折り」にして入れることができます。もっとも一般的に使われている封筒で、個人の手紙、請求書の郵送、通知書などに幅広く使われています。サイズと厚さが定形郵便の規格内に収まりやすく、特別な配慮をせずとも110円で送れる点が魅力です。
一方、長形3号は長形4号よりもやや大きめで、サイズは縦23.5cm・横12cmです。こちらもA4の三つ折りに対応していますが、横幅に余裕があるため、中身が厚手だったり複数枚あったりしても封入しやすく、封筒がパンパンにならずに済むという利点があります。そのため、より丁寧な印象を与えたい場合や、資料を多めに入れる場合に向いています。見た目がすっきりとし、受取人に対しても配慮が感じられる封筒です。
そして、長形2号になるとサイズはさらに大きくなり、縦33.2cm・横24cmとなります。この封筒はA4サイズの書類を「折らずにそのまま」入れることができる点が特徴です。契約書や証明書など、折り目をつけずに送付する必要がある場合に最適ですが、そのぶん定形郵便の規格を超えてしまうため、定形外郵便として扱われ、140円以上の料金がかかります。
このように、封筒のサイズ選びは、ただ封入物が入るかどうかだけでなく、郵便料金、受取人への印象、文書の取り扱いといった複数の要素を考慮することが大切です。送るものの重要度や厚み、読みやすさを踏まえた上で、長形2号・3号・4号のいずれがふさわしいかを判断しましょう。
茶封筒の切手の値段と定形外になる条件
茶封筒と聞くと、多くの方が事務書類や履歴書の送付など、ややフォーマルな用途を思い浮かべるのではないでしょうか。茶封筒は一般的に「角形2号」や「角形A4号」といった大型封筒のことを指す場合が多く、これらの封筒はA4用紙を折らずにそのまま封入できる大きさを持っています。
このタイプの封筒はサイズが大きいため、定形郵便の規格外とされ、自動的に「定形外郵便物」として扱われます。具体的には、長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内かつ重量1kg以内であれば「定形外・規格内」となり、それを超えると「定形外・規格外」としてさらに高い料金が必要です。
例えば、茶封筒にA4サイズの書類を数枚入れた状態で、重量が50g以内であれば140円、100g以内なら180円、150g以内なら270円と段階的に料金が上がっていきます。重量の上限が厳格に決まっているため、封入する枚数や紙質に注意しなければ、思わぬ料金オーバーが発生することもあります。
さらに注意が必要なのは厚みです。見た目では1cm以内に収まっていても、封筒が膨らんでしまったり、角がめくれたりして郵便局の機械に通らなかった場合、自動的に「規格外」と判断され、260円以上の料金が適用されるケースもあります。
このように、茶封筒を使用する際には、サイズ・重量・厚さの3要素を事前にチェックすることが重要です。郵便局の窓口では、実際に測定してくれるので、不安な場合は投函前に確認すると安心です。自宅に郵便用の計量器や厚さ測定スロットがあると、より確実に料金を把握できます。
また、切手を貼る場合には、140円・180円・210円といった金額の切手を組み合わせる必要があります。すぐに正しい額の切手を貼れるように、10円や20円単位の補助切手を複数ストックしておくと便利です。
切手 コンビニで買える種類と注意点
郵便局と異なり、コンビニで切手を購入するときにはいくつかの特徴と注意点があります。大きな利点は、24時間営業でいつでも手軽に利用できることですが、それ以外には覚えておくべき点もあります。
一般的なコンビニ(セブン-イレブン、ローソン、ファミマなど)では、85円(はがき用)、110円(定形郵便用)、140円(定形外50g以内用)切手が常備されていることが多いです。ただし、300円以上の高額切手や慶弔用、特殊デザイン切手はほとんど取り扱いがありません。
また、購入時には以下の点に注意が必要です:
- 店舗によって在庫が異なるため、事前に電話確認が推奨
- 重さを測る手段がないため、料金が分からず必要分を貼れない可能性
- ポスト設置店(ローソン・ミニストップなど)であればその場で投函可能ですが、ポストのない店舗もある
このように、コンビニは「時間」と「利便性」において優位ですが、切手の種類の少なさ、重量未計量、在庫不安定といったデメリットもあります。そのため、重要な郵便のときは、郵便局窓口での購入と計量を併用するのがおすすめです。
切手 長形4号の料金と郵送ルールのまとめ
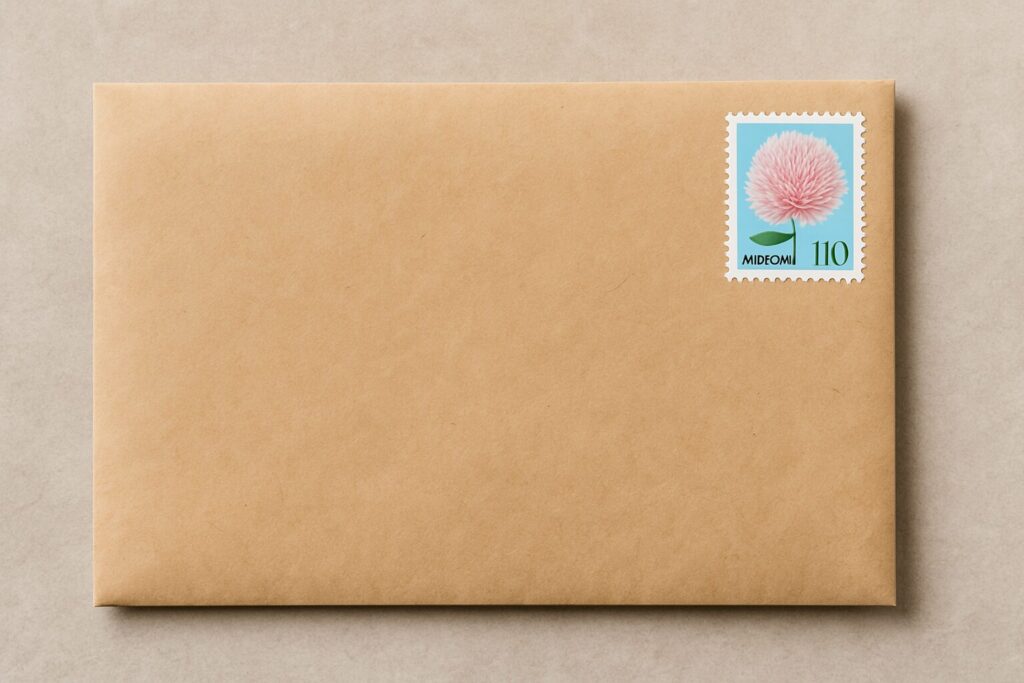
- 長形4号封筒は定形郵便で扱われ、50g以内なら切手代は110円
- 2024年10月から定形郵便の料金が一律110円に変更された
- 長形4号のサイズはおおよそ23.5cm×12cmで定形の範囲内
- 厚さが1cmを超えると定形外扱いとなり追加料金が必要
- 旧84円切手は現在そのままでは使えず、差額切手が必要
- A4書類を三つ折りにすれば長形4号に問題なく収まる
- 110円切手で送れる条件はサイズ・厚さ・重さすべてが規定内であること
- 封筒の内容物が多くなると50gを超えて料金が高くなることがある
- 切手の金額をオーバーして貼っても問題はないが差額は返金されない
- 定形郵便は50g以内で全国一律110円のシンプルな料金設定となった
- 長形4号は家庭用・業務用どちらでも使いやすく汎用性が高い
- 郵便料金の改定は2024年10月であり、それ以前の情報には注意が必要
- 定形外になると140円以上の料金が発生しコストが増える
- コンビニで110円などの基本的な切手は購入できるが種類に限りがある
- 投函前に封筒の厚さと重さを確認することで料金不足を防げる
関連記事


