レターパック食べ物と検索している人は、きっと「本当に食品を送って大丈夫なのか」「どこまでが送れる範囲なのか」をはっきり知りたいはずです。お菓子やレトルト食品はOKなのか、チョコレートや生菓子はどうなのか、そして季節や気温による影響まで気になるでしょう。
さらに、レターパックライトとレターパックプラスのどちらを選べば良いのか、料金やサイズ、梱包方法、書き方などの細かい疑問も浮かんでいるかもしれません。
この記事では、公式の発送ルールや注意点を押さえながら、食品を安全に届けるための具体的なポイントを丁寧に解説します。最後まで読めば、レターパックで食べ物を送る際の判断基準が明確になり、自信を持って発送準備ができるようになります。
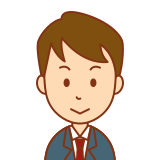
💡記事のポイント
- レターパックで食べ物を送れる条件と送れない基準
- ライトとプラスの違いと、食品に向く使い分け
- 品名の書き方や梱包のコツ、トラブル回避の実践知
- 料金・コンビニ購入・ゆうパックの代替まで一気通貫で把握
レターパックで食べ物を送る際の発送ルールと注意点

- レターパックで食べ物を送れる?基本ルールと制限
- レターパックで食品を送る際の書き方と正しい記載方法
- レターパックで食品を送るときの梱包ポイント
- レターパックで送ってはいけないものと食品の例
- レターパックでチョコレートは送れる?温度変化の影響
- レターパックでレトルト食品を常温発送できる?
- レターパックでお菓子や焼き菓子を送る際の注意事項
- レターパックに入るお菓子とサイズ制限の確認方法
レターパックで食べ物を送れる?基本ルールと制限
レターパックは全国一律料金で利用でき、追跡機能が付いているため、食品やお菓子など軽量の品物を送る手段として人気があります。しかし、日本郵便株式会社が公式に定める条件や制限を理解していないと、発送後にトラブルになる可能性があります。
レターパックには「レターパックライト」と「レターパックプラス」の2種類があり、いずれも重量は4kgまで、専用封筒に収まるサイズであることが必要です。ライトは厚さ3cm以内で郵便受けに配達、プラスは厚さ制限はなく対面で配達されます(出典:日本郵便「レターパック」https://www.post.japanpost.jp/service/letterpack/
食品については、常温で保存でき、輸送中に腐敗や変質の恐れがないものであれば送ることが可能です。具体的には、市販の未開封の焼き菓子や乾物、レトルト食品などが該当します。一方、冷蔵・冷凍が必要な生鮮食品、カットフルーツや生ケーキなどは温度管理ができないため送付できません。日本郵便は公式案内で「なまもの」や「変質しやすいもの」を禁止品として明記しています。
また、輸送中は車両や倉庫での一時保管などにより、外気温以上の高温にさらされることがあります。特に夏季や温暖地域では、品質が落ちやすい食品は避けることが望ましいです。こうした条件を事前に把握し、食品の種類と季節を考慮して利用することが、安全な発送につながります。
レターパックで食品を送る際の書き方と正しい記載方法
発送ラベルの品名欄の記入方法は、食品を送る際の重要なポイントです。内容物が不明瞭なままだと、郵便局から中身の確認や差し戻しを求められる可能性があります。公式ガイドでも、具体的かつ正確な品名記載を推奨しています(出典:日本郵便「レターパックご利用上の注意」https://www.post.japanpost.jp/service/letterpack
例えば、「食品」とだけ記載するのではなく、「焼き菓子(クッキー)」「レトルトカレー」「キャンディ(個包装)」のように、品目を特定できる書き方を心がけます。さらに、品名の後に「常温保存可」と追記すると、輸送時の判断がスムーズになります。
また、発送先が法人や施設の場合、食品であることを明示することで、受け取り時の対応も円滑になります。特に病院や学校などは受け取りに制限がある場合があるため、事前に確認を取った上で品名を記載するとトラブル防止になります。
封入物は信書や現金など禁止品と混在させないよう注意が必要です。禁止品を同封すると、規約違反となり返送や廃棄の対象になることがあります。食品以外の同梱物がある場合は、それぞれの品名を分けて記載すると安全です。
レターパックで食品を送るときの梱包ポイント
食品をレターパックで安全に届けるためには、輸送中の破損や漏れを防ぐ梱包が欠かせません。封筒は紙製で防水性がないため、液漏れや油染みが発生すると他の郵便物にも影響を与える恐れがあります。
まず、食品は必ず未開封で、外装がしっかりしているものを選びます。そのうえで、個別包装の上から透明のOPP袋やジッパー付き保存袋に入れて、においや粉が外に漏れないようにします。割れやすいお菓子やスナック類は、エアパッキン(プチプチ)や薄手の緩衝材で包み、封筒内で動かないよう固定します。
レターパックライトの場合、厚さ3cmの制限があるため、緩衝材の厚みを調整する必要があります。封筒の口が自然に閉じる状態でなければ、郵便窓口で受け付けてもらえない場合があります。レターパックプラスは厚さ制限がない分、緩衝材を多く入れられますが、封筒が膨らみすぎると破れやすくなるため注意が必要です。
さらに、夏場の高温や冬場の低温により、食品の品質が変化する可能性があるため、発送日は週の前半を選び、週末に配達がかからないよう調整するとより安全です。到着までの時間を短縮することが、品質保持の鍵になります。
レターパックで送ってはいけないものと食品の例
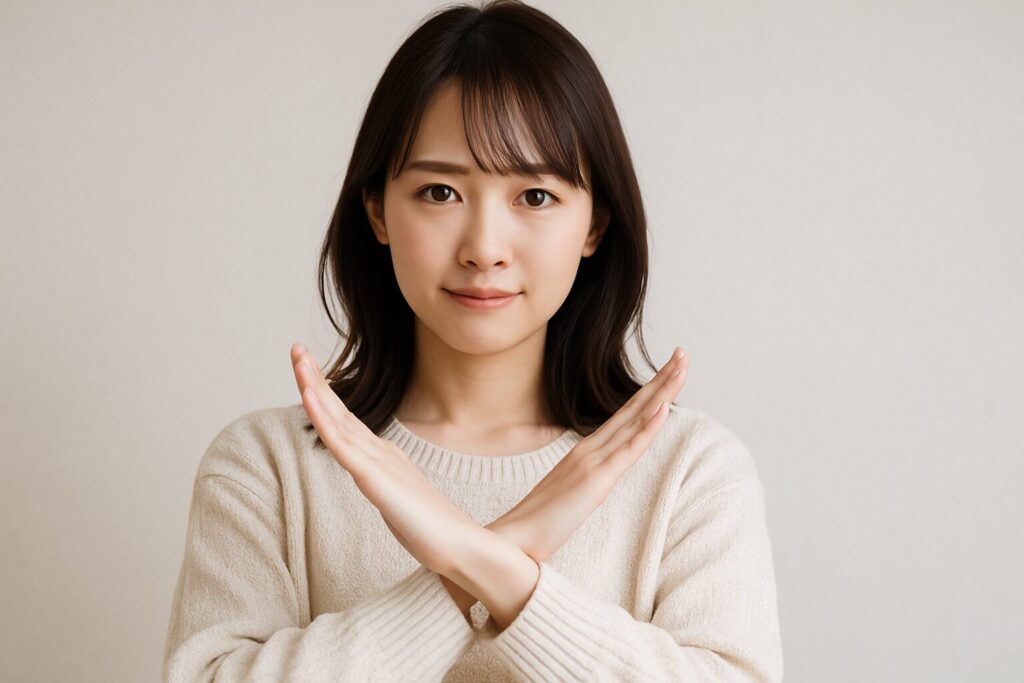
日本郵便はレターパックで送付できない品目を明確に定めています(出典:日本郵便「信書便物等の送達に関する規定」https://www.post.japanpost.jp/service/letterpack/
禁止品には、以下のようなカテゴリーがあります。
- 現金、貴金属、宝石類、株券や小切手などの有価証券
- 爆発物や可燃性液体などの危険物
- 毒劇物や腐食性物質
- 生きた動物や植物
- 腐敗しやすい食品や温度管理が必要な生鮮食品
- 割れやすいガラス製品や精密機器
食品については、未開封で常温保存が可能なものに限られます。例えば、缶詰や真空パックの乾物、個包装された焼き菓子などは適していますが、生鮮肉、魚介類、要冷蔵のスイーツ、カットフルーツなどは対象外です。
こうした制限は、輸送中の品質保持と他の郵便物への安全配慮のために設けられています。
発送前には、公式サイトや郵便窓口で最新の禁止品リストを確認し、食品の保存方法や消費期限も併せてチェックすることが推奨されます。
レターパックでチョコレートは送れる?温度変化の影響
チョコレートは常温保存が可能な食品であるため、規約上はレターパックで送ることが可能です。しかし、実際には温度変化の影響が大きく、特に夏季や高温環境での輸送には注意が必要です。
チョコレートは28℃前後を超えると脂肪分が溶け出し、ブルームと呼ばれる白い粉状の変色が発生します。この現象は風味や食感を損ない、見た目にも影響します(出典:一般社団法人日本チョコレート・ココア協会「チョコレートの保存と取り扱い」
レターパックライトは郵便受け投函のため、真夏の昼間はポスト内の温度が50℃以上になることもあり、品質劣化のリスクが極めて高くなります。プラスであっても、配達車両や中継拠点での一時保管中に高温環境にさらされる可能性は避けられません。
気温が高い時期にチョコレートを送る場合は、保冷剤を併用する、発送日を天候や気温の低い日に設定する、あるいはチルドゆうパックを利用するなど、温度管理を重視した方法が望まれます。
レターパックでレトルト食品を常温発送できる?
レトルト食品は高温高圧で殺菌された密封包装食品であり、未開封であれば常温で長期間保存できます。そのため、レターパックでの発送に適した食品のひとつです。
日本農林規格(JAS規格)では、レトルト食品は120℃以上で4分以上の加熱殺菌を行い、常温で保存可能であることが定められています(出典:農林水産省「レトルト食品の基準」
発送時は、袋が破損しないよう厚紙で補強し、さらにビニール袋で二重包装して液漏れ対策を行います。重量やサイズの条件として、ライトは厚さ3cm以内・4kgまで、プラスは厚さ制限なし・4kgまでという制限があるため、まとめて送る場合は特に注意が必要です。
また、製造から長期間経過したレトルト食品は、常温保存可能であっても風味が劣化している場合があるため、賞味期限を確認してから発送することが推奨されます。
レターパックでお菓子や焼き菓子を送る際の注意事項
お菓子や焼き菓子は、レターパックで送られる食品の中でも特に需要が多いカテゴリーです。しかし、その種類や形状によっては、輸送中に割れやすかったり、油分がにじみ出たりするリスクがあります。
特にクッキーやラングドシャなど薄くて脆い焼き菓子は、封筒内での衝撃で割れやすくなります。これを防ぐためには、まず外箱に入った商品を選び、その外箱を緩衝材で包みます。封筒内の空間を新聞紙などの重量のある素材ではなく、軽量のエアパッキンや発泡シートで埋め、輸送時の振動を吸収させることが効果的です。
油分が多いバターケーキやパウンドケーキは、時間経過で油染みが発生する可能性があるため、必ず油分が外に染み出さない包装資材(グラシン紙や耐油袋)を使用します。さらに全体を防水性の高い袋に入れ、におい移りや湿気の影響を抑えます。
また、製品によっては賞味期限が短く、輸送中に期限切れとなる場合があります。発送日と到着予定日を逆算し、受取人がすぐに受け取れるスケジュールを組むことが望まれます。日本郵便ではレターパックの配送日数は通常1〜2日ですが、地域や天候によって遅延することもあるため、余裕を持った日程調整が必要です(出典:日本郵便「お届け日数を調べる」https://www.post.japanpost.jp/deli_days/index.html
レターパックに入るお菓子とサイズ制限の確認方法
レターパックは専用封筒を使用するため、入れられるお菓子のサイズや形状には制限があります。レターパックライトはA4サイズ(340mm×248mm)、厚さ3cm以内、重量4kgまでという条件があり、プラスは同じサイズで厚さ制限なし、重量4kgまでです(出典:日本郵便「レターパック」https://www.post.japanpost.jp/service/letterpack/
厚さ3cm以内で収まるお菓子には、板チョコレート、スティックパイ、個包装の薄型クッキーなどがあります。箱菓子を送る場合は、外箱の厚みを事前に測り、規定内に収まるかを確認します。プラスを使えば厚さを気にせず梱包できますが、封筒の口が自然に閉じる状態でなければ受け付けてもらえません。
また、封筒がパンパンに膨らむと、輸送中に破れやすくなるため、内容物の高さや角の形状にも配慮が必要です。形状の確認には、定規や厚みゲージを使い、事前にポストの投函口サイズとも照らし合わせると、受け取りやすさや安全性が高まります。
レターパックで食べ物を送る具体的な方法と代替サービス

- レターパックライトとレターパックプラスの違い(食べ物発送の視点から)
- レターパックプラスで食べ物を送るメリットとデメリット
- レターパックの料金とコストを抑える発送の工夫
- レターパックをコンビニから発送する手順
- レターパックでお菓子を送れる?実際の発送事例
- ゆうパックで食品を常温発送できる条件
- ゆうパックで食べ物を送れる?冷蔵・冷凍便との比較
- レターパックで送れるもの・送れないものの一覧と最終チェック
レターパックライトとレターパックプラスの違い(食べ物発送の視点から)
食べ物発送の視点で見た場合、レターパックライトとプラスの違いは主に以下の点に集約されます。
- 配達方法:ライトは郵便受け配達、プラスは対面配達で受領印または署名が必要
- 厚さ制限:ライトは3cmまで、プラスは制限なし(封が閉じる範囲)
- 料金:2024年10月時点でライトは430円、プラスは600円
- 安全性:プラスは手渡しのため盗難や雨濡れのリスクが軽減される
ライトは厚さ制限があるため、クッキーやキャンディなどの軽量・薄型食品に向きます。一方、プラスは厚みのある箱菓子や緩衝材を多く使いたい場合に適しています。温度管理が不要な食品であっても、夏場の高温や冬場の極端な低温を避けるには、受取時間を調整できるプラスの方が有利です。
ただし、どちらも補償制度はありません。高額または希少な食品を送る場合は、損害賠償制度のあるゆうパックや宅配便の利用が推奨されます(出典:日本郵便「損害賠償制度」
レターパックプラスで食べ物を送るメリットとデメリット
レターパックプラスは、厚さ制限がなく、全国一律料金で対面配達される点が特徴です。食品発送における最大の利点は、緩衝材を十分に使用できるため、割れやすい箱菓子や瓶入り食品を安全に送れることです。また、対面で手渡しされるため、郵便受け投函のライトに比べて盗難や雨濡れのリスクが低くなります。
さらに、受取人の署名や押印が必要なため、配送時の受け取り確認が確実に行われます。特に、ギフト用の食品や贈答品では、受け取りの確実性が信頼性を高めます。
一方でデメリットとして、料金がライトより170円高く、封筒の重量や厚みが増えると持ち運びがやや不便になることがあります。また、補償は付かないため、高額品や生鮮食品には不向きです。対面配達であるため、受取人が不在の場合は再配達が必要となり、受け取りまでに時間がかかる可能性もあります。
レターパックの料金とコストを抑える発送の工夫
レターパックは、2024年10月の改定時点でライトが430円、プラスが600円です(出典:日本郵便「郵便料金・運賃改定」
全国一律料金のため、近距離でも遠距離でも同一価格となりますが、重量やサイズによっては他の配送サービスの方が安くなる場合もあります。
コストを抑えるには、まず内容物の厚さと重量を確認し、3cm以内かつ4kg以内であればライトを選択します。重量が軽いのにプラスを選ぶと割高になるため、商品の形状や保護材の量を工夫してライトに収めることが節約につながります。
また、複数の軽量食品をまとめて送る場合は、サイズと重量のバランスを見て、ゆうパックの60サイズ料金と比較することが有効です。近距離で軽量の場合、定形外郵便の方が安くなるケースもあるため、発送前に日本郵便の料金計算ページでシミュレーションを行うと確実です(出典:日本郵便「料金計算」https://www.post.japanpost.jp/send/fee/index.html
レターパックをコンビニから発送する手順
レターパック専用封筒は、郵便局だけでなく、取り扱いのあるコンビニエンスストアでも購入できます。主な取扱店舗はローソン、ミニストップ、セイコーマートなどですが、店舗によっては在庫がない場合があるため、事前に確認することが望まれます。
購入後は、宛先と差出人の住所・氏名、品名を正確に記入します。食品を送る場合は、先述の通り具体的な品目名を書くことで、受取人や郵便局員が中身を判断しやすくなります。
差し出し方法は、ポスト投函または郵便窓口への持ち込みが可能です。コンビニで購入した場合でも、その場で差し出せるかどうかは店舗によって異なります。ポスト投函する場合、ライトはポストに入りますが、プラスはサイズ的に入らないこともあるため、郵便窓口からの差し出しが安心です。
なお、差し出し後はレターパックの追跡番号を利用して、配送状況をオンラインで確認できます(出典:日本郵便「個別番号検索」https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv/search/
レターパックでお菓子を送れる?実際の発送事例

レターパックでは、多くの利用者が常温保存可能なお菓子を送っています。代表的な例としては、個包装されたクッキーやキャンディ、板チョコレート、パウンドケーキ、焼きドーナツなどがあります。いずれも未開封で常温保存が可能であり、厚みや重量の条件を満たす場合に適しています。
例えば、厚さ3cm以内の焼き菓子詰め合わせをレターパックライトで送る場合、適切な緩衝材を用いても重量は1kg未満に収まり、全国一律430円で発送可能です。対して、箱入りの高級チョコレートや割れやすい菓子は、厚みが増すためレターパックプラスでの発送が安全です。
発送事例からも分かるように、形状と重量の条件に合う食品であればレターパックは便利ですが、季節や配送日数にも注意が必要です。夏場の高温や梅雨時期の湿気は品質に影響を与えるため、受け取り可能な日時を事前に確認することが推奨されます。
ゆうパックで食品を常温発送できる条件
ゆうパックは、日本郵便が提供する宅配サービスで、サイズと重量によって料金が決まります。常温発送の対象となる食品は、未開封で常温保存が可能なものに限られます。例えば、缶詰、瓶詰、乾麺、レトルト食品、真空パックされた乾物などが該当します(出典:日本郵便「ゆうパック」https://www.post.japanpost.jp/service/you_pack/
サイズは、縦・横・高さの合計が170cmまで、重量は25kgまでの範囲で対応可能です。温度管理が不要な食品でも、破損防止のため緩衝材を使用し、外装には食品である旨を記載すると安心です。
さらに、ゆうパックでは配達日や時間帯の指定ができるため、受け取りの確実性を高められます。レターパックでは不可能な大型サイズや重量物の発送も可能なため、ケース単位の飲料やまとめ買い食品などにはゆうパックが適しています。
ゆうパックで食べ物を送れる?冷蔵・冷凍便との比較
ゆうパックは常温便だけでなく、チルドゆうパック(冷蔵)や冷凍ゆうパックも利用できます。これにより、要冷蔵や要冷凍の食品も安全に送ることができます。
チルドゆうパックは2〜10℃の温度帯で輸送され、生菓子や精肉、乳製品などに向いています。冷凍ゆうパックは-15℃以下での輸送が可能で、アイスクリームや冷凍食品に適しています(出典:日本郵便「チルドゆうパック」https://www.post.japanpost.jp/service/you_pack/chilled/index.html
常温便との比較では、冷蔵・冷凍便は温度管理のための追加料金が発生しますが、品質保持の面では圧倒的に有利です。一方で、梱包時には保冷箱や保冷剤の使用が推奨され、総重量やサイズが増えるため送料が上がる傾向にあります。
食品の種類や賞味期限、受け取りスケジュールを総合的に判断し、最適な温度帯のサービスを選ぶことが重要です。
レターパックで送れるもの・送れないものの一覧と最終チェック
レターパックは全国一律料金で利用できる便利な発送方法ですが、送れるものと送れないものが明確に区別されています。発送前に最終チェックを行うことで、差し戻しやトラブルを防ぐことができます(出典:日本郵便「レターパックご利用上の注意」
送れるものの主な例
- 常温で保存できる未開封の食品(焼き菓子、キャンディ、板チョコレート、乾麺、レトルト食品、缶詰など)
- 書籍、書類、カタログなどの紙製品
- 小型の日用品や雑貨(アクセサリー、衣類小物など)
- プラスチック製品や軽量の工芸品
送れないものの主な例
- 現金、有価証券、貴金属などの貴重品
- 危険物(ガス、火薬、揮発性液体など)
- 毒物、劇物、放射性物質
- 生きた動植物
- 腐敗や変質しやすい食品(生鮮肉、魚介類、生ケーキ、カットフルーツなど)
- 割れやすいガラス製品や精密機器
- 信書以外の書簡に該当するものを混載した場合
発送時の最終チェックポイント
- 封筒のサイズと重量(ライトは厚さ3cm以内・4kgまで、プラスは厚さ制限なし・4kgまで)
- 内容物が禁止品に該当しないか
- 食品は未開封で常温保存が可能か
- 緩衝材や防水対策が十分か
- 宛先と差出人の住所氏名、品名を正確に記載しているか
- 配送時期や天候を考慮して品質が保持できるか
これらの項目を発送前に確認することで、規約違反による返送や品質トラブルを防ぎ、スムーズに食品やその他の品物を届けることができます。
レターパックで食べ物は送れる?送れるもの・送れないものまとめ

- レターパックは常温輸送で、要冷蔵や生鮮は避ける理解が基本
- ライトは厚さ3cm以内、プラスは厚さ制限なしで重量は共通で4kgまで
- 割れ物や貴重品、危険物などはレターパックの対象外
- チョコは夏場の品質劣化が起きやすく季節配慮が必要
- レトルトは未開封で常温安定なら候補だが漏れ対策が前提
- 品名は食品の具体名を記載し中身が分かるようにする
- ライトは郵便受け配達で温度や直射の影響を受けやすい
- プラスは対面配達で厚みが確保でき緩衝材を入れやすい
- 料金は全国一律でライト430円、プラス600円
- コンビニは店舗により取り扱いが異なるため事前確認が無難
- 迷ったらサイズと温度帯でレターパックとゆうパックを比較
- 補償は付かないため高価・希少・壊れやすい物は避ける
- 封が自然に閉じる範囲で梱包し過剰な圧迫を避ける
- 投函後は追跡番号で到着目安を確認し受取人に共有
- 季節と相手の受取環境を考え、最適な手段を選択
関連記事







