海外にいる家族や友人に贈り物を送りたい、またはビジネスで書類や商品を海外に発送したい。そんなとき、多くの人がまず思い浮かべるのが「郵便局を使った海外発送」ではないでしょうか。特に「海外に荷物を送る方法郵便局」と検索している方の多くは、どんなサービスがあるのか、料金はどれくらいかかるのか、送り方に特別なルールがあるのかなど、初めてのことで不安を感じているかもしれません。
このページでは、郵便局を使って海外に荷物を送る際に知っておくべき基本的な方法や手順、サービスごとの特徴、梱包時の注意点、料金の目安まで、初心者でもわかりやすく丁寧に解説しています。さらに、ヤマト運輸との比較や、便利なオンラインサービスの活用方法についても触れながら、あなたが最適な発送方法を選べるようサポートします。
知識ゼロの状態からでも、自信を持って国際発送ができるようになるための情報をぎゅっと詰め込みました。迷っている方も、ぜひ最後まで読み進めてみてください。きっと、あなたにとってベストな発送方法が見つかるはずです。
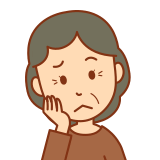
💡記事のポイント
- 郵便局で利用できる国際発送サービスの種類と特徴
- EMSと国際小包の違いや使い分けのポイント
- 国際郵便を送る際の手順と梱包の注意点
- 配送費用を抑える方法や集荷サービスの活用方法
郵便局で海外に荷物を送る方法と手続きの流れ

- 郵便局で海外に荷物を送る際に利用できるサービスとは
- 郵便局の国際小包とEMSの違いは何ですか?
- 国際郵便を送る方法と手順をわかりやすく解説
- 国際郵便の箱には何を使えばいい?梱包のルールと注意点
- 郵便局の国際郵便は何時まで対応している?窓口の営業時間
- 国際郵便はどこの郵便局でも送れる?対応窓口の確認方法
郵便局で海外に荷物を送る際に利用できるサービスとは
現在の日本国内において、郵便局から海外に荷物を送る手段はいくつか用意されています。それぞれのサービスには特徴や制限があり、目的や送りたいものに応じて選択することが大切です。
まず基本となるのが「EMS(国際スピード郵便)」です。これは、スピード重視の国際配送サービスであり、手紙・書類・小包などを最速で届けたいときに向いています。追跡機能が標準で付いており、配達日数も比較的安定しています。ただし、料金はやや高めに設定されており、大量に送る場合やコストを抑えたいときには不向きです。
一方、「国際小包郵便」はEMSよりも料金が抑えめで、航空便・SAL便(エコノミー航空便)・船便の3種類から配送方法を選ぶことができます。航空便は早めの到着を希望する人に、船便は時間に余裕があり料金を抑えたい人に向いています。重量が重い荷物や大きな段ボールを送りたいときにも便利です。
さらに、比較的小さな荷物を送る場合には「国際eパケット」や「小形包装物」が適しています。国際eパケットは2kgまでの軽量な荷物に対応しており、追跡も可能です。小形包装物はもっと簡易的で、書類やちょっとした雑貨などを安価に送る際に重宝されます。
その他にも、「書留」や「保険付き郵便」など、送る荷物の内容や重要度に応じた追加サービスも用意されています。
このように、郵便局では目的に応じて複数の海外発送手段を利用できます。どのサービスを選ぶかは、送りたい物の種類・重さ・急ぎかどうか・送り先の国などによって変わるため、あらかじめ比較検討しておくことが大切です。
郵便局の国際小包とEMSの違いは何ですか?
言ってしまえば、郵便局が提供する「国際小包」と「EMS」はどちらも海外に荷物を送る手段であるものの、利用目的やサービス内容に明確な違いがあります。それを理解して使い分けることで、無駄なコストやトラブルを防ぐことができます。
まず大きな違いとして挙げられるのが、「スピード」と「優先度」です。EMSは「国際スピード郵便」という名称のとおり、最も早く荷物を届けることを前提としたサービスです。多くの国において、配達までの日数が2〜4営業日と非常に短く、さらに追跡機能や損害賠償制度が標準装備されています。ビジネス文書や壊れやすい商品、または受取日が明確に決まっている場合などには、安心感があります。
一方で、国際小包はEMSよりもやや時間がかかるものの、配送方法(航空便・SAL便・船便)を自分で選択でき、料金の幅も広く設定されています。たとえば、送料を抑えたい場合には船便を選ぶことでコストを大幅に削減できますが、その代わりに配達までに1か月以上かかることもあります。逆に、少し高くなっても早く届けたい場合は航空便を選べばよいのです。
また、取り扱う荷物の重さやサイズにも違いがあります。EMSでは最大30kgまで、国際小包でも同様に30kgまで対応していますが、送り先によって上限が異なる場合があるため、事前に確認が必要です。
このように考えると、EMSはスピードと安全性を重視する人向け、国際小包は料金や配送スタイルを柔軟に選びたい人向けということになります。どちらが「良い」というよりも、用途や目的に応じて適切なサービスを選ぶことが求められます。
国際郵便を送る方法と手順をわかりやすく解説
ここでは、郵便局から国際郵便を送る際の基本的な手順について説明します。初めての方でも迷わないよう、順を追って具体的に見ていきましょう。
最初にすべきことは、「送る荷物の内容と重さを確認すること」です。なぜなら、国際郵便には国によって送れない品目や、重さ・大きさの制限があるからです。たとえば、アルコール類やスプレー缶、バッテリーなどは多くの国で禁止されていることがあります。そのため、内容物の安全性と送付可能性を郵便局の公式サイトなどで事前にチェックしておくと安心です。
次に行うのが「梱包」です。箱や封筒は基本的に自分で用意する必要がありますが、郵便局で購入できる専用箱もあります。破損を防ぐため、緩衝材などを使ってしっかりと固定しましょう。特にガラス製品や電子機器など、壊れやすいものを送る場合は注意が必要です。
その後、送り状(ラベル)の記入に移ります。最近では、国際郵便マイページサービスを使えば、オンラインで送り状を作成・印刷できるため、手書きの手間が省けて便利です。宛先や差出人、内容物の詳細、価格などを正確に記入しましょう。英語での記載が必要になるため、不安な方は郵便局の窓口でサポートを受けるのもおすすめです。
準備ができたら、郵便局に荷物を持ち込み、発送手続きを行います。一部のサービスでは自宅まで集荷してもらうことも可能です。手続き後には追跡番号が渡されるため、大切に保管しておきましょう。
このように、国際郵便の発送は一見複雑に見えるかもしれませんが、手順をひとつずつ確認しながら進めれば、初心者でもスムーズに対応できます。慌てず、事前準備をしっかり行うことが成功のポイントです。
国際郵便の箱には何を使えばいい?梱包のルールと注意点

郵便局で海外に荷物を送る際、梱包に使用する箱や封筒は非常に重要です。送りたいものの破損を防ぎ、相手に安全に届くように準備する必要があります。まず、購入できる箱には「郵便局指定の国際小包箱」があります。これは厚みや耐久性が一定基準を満たしており、安全性に優れています。また、市販の段ボール箱や丈夫な宅配用の箱を使うことも可能ですが、サイズ・重量制限に注意が必要です。
次に梱包のルールです。ガラス製品や電子機器など壊れやすいものは、新聞紙や発泡スチロールなどの緩衝材でしっかり包み、なるべく隙間がないように固定します。動くと破損につながるため、テープや紐で内部を固定しておくと安心です。封筒で送る書類や薄手の物品についても、折れや湿気対策としてクリアケースや防水袋を併用するのがおすすめです。
注意点としては、梱包材や箱に「穴が空いていないか」「破れていないか」を必ず確認してください。穴や破れがあると、航空便などで中身が飛び出す可能性があり、配達が滞る原因になります。加えて、料金を抑えようとして不適切な梱包をすると、損害賠償制度の対象外になったり、国際ルール違反で差出人が責任を問われる場合があります。
このように考えると、信頼できる梱包資材を用意し、荷物の種類に応じて緩衝材と密閉性を意識して準備することが、国際郵便発送の成功の要となります。
郵便局の国際郵便は何時まで対応している?窓口の営業時間
郵便局で海外発送を行う場合、窓口の営業時間を把握しておくとスムーズに手続きできます。一般的な郵便局では、平日の営業時間は午前9時から午後5時または5時30分までとなっています。私であれば、余裕をもって午前中や午後早めの時間帯に訪れることをおすすめします。理由は、窓口での待ち時間や書類記入、梱包確認などを余裕をもって行えるからです。
ただ、すべての郵便局が同じ時間帯に対応しているわけではありません。大きな郵便局では土曜日も午前中のみ海外発送業務を受付している場合があります。さらに、年末年始や祝日、特殊な国際便の受付停止日など、例外的な営業時間の変更もあるため、出かける前に公式サイトや最寄りの郵便局に確認することが賢明です。
一方で、高速道路サービスエリアやターミナル近くの大規模局では、他の窓口より早く閉まることもあります。実際、窓口業務は午後5時に終了でも、国際郵便カウンターは多少早めに締まることがあります。そのため、送付予定日の前日までに到着条件を確認し、余裕をもった訪問スケジュールを立てると安心です。
結局、時間的なトラブルを避けたいなら、前もって郵便局の営業時間と国際受付業務の時間帯を把握し、午前や昼過ぎまでに窓口を訪れることが最も安全な方法です。
国際郵便はどこの郵便局でも送れる?対応窓口の確認方法
多くの人が、「地方の小さな郵便局でも海外に荷物を送れるのか」と疑問に思うかもしれません。確かに、一部の窓口では国内郵便のみを扱い、国際配送業務を行っていない場合があります。そこで、一連の手順を確認することで、確実に対応できる窓口を探す方法をご紹介します。
まず、本来は郵便局の公式ウェブサイトや「ゆうびんマップ」で、最寄りの郵便局が国際郵便に対応しているかどうかを確認するのが一般的な方法です。検索結果には「国際小包」「EMS」「書留付き」など対応サービスがアイコンで表示されるため、一目で判断できます。
その中で、初心者にもわかりやすいのは「国際郵便対応窓口」の表記がある局を選ぶことです。一方で、小規模な郵便局では対応がないことが多く、そうした場合は少し距離があっても近くの中~大型郵便局を利用するほうが効率的です。
また、私が以前経験した例では、急ぎの荷物を出そうとしたとき、近隣の小さな局では国際便の受付ができず、結局大きな局まで足を運ぶ必要がありました。その経験から言うと、事前にオンラインで対応可否を調べておくことが、余分な移動や時間のロスを避けるうえで重要です。
いずれにしても、国際郵便を確実に利用したいなら、公式サイトや郵便局サポートなどで「国際郵便対応局」を事前に確認し、可能なら電話で最終確認してから向かうのが安心の方法になります。
郵便局で海外に荷物を送る方法と料金を安く抑えるコツ

- 郵便局で海外に荷物を送る際の料金はいくらかかる?
- 国際郵便の集荷料金はいくら?コストを抑えるポイント
- 海外に荷物を送るのに安いのはどこ?郵便局とヤマトを比較
- 郵便局とヤマト、海外配送で便利なのはどっち?
- 国際郵便マイページサービスを使うメリットと登録手順
- 海外に書類を送るときの封筒の選び方と正しい書き方
郵便局で海外に荷物を送る際の料金はいくらかかる?
郵便局を利用して海外に荷物を送る際、最も気になるのは送料です。発送先の国や地域、荷物のサイズや重量、配送方法によって料金は大きく異なるため、事前に確認しておかないと想定以上の出費になることがあります。
例えば、日本からアメリカへ2kgの荷物を送るケースを考えてみましょう。EMS(国際スピード郵便)を選択した場合、2025年時点の目安で約4,400円程度かかります。一方、同じ荷物を国際小包の航空便で送ると、おおよそ3,700円前後。さらに、SAL便(エコノミー航空)であれば3,000円弱、船便を選べば2,500円前後にまで抑えることが可能です。ただし、安価な配送方法には時間がかかるというデメリットもあるため、単純に「安さ」だけで選ばないことが重要です。
また、荷物の内容によって関税が発生する場合もあるため、料金は「郵便局で支払う金額」だけに留まらない可能性があります。特に高額商品や商用目的の品物を送る際には、受取人側で追加費用が発生するケースも想定しておくべきです。
さらに、国や地域によっては送ることができない品目やサイズ制限があり、それらに抵触すると発送できなかったり、返送・破棄になることもあります。送付前に郵便局の公式サイトや「国際郵便料金表」「料金計算ツール」を使って、最新の金額や発送条件を確認しておくと安心です。
こうして見ると、郵便局を利用した国際発送は非常に便利で制度も整っている一方で、料金に関しては多くの要因が関係してくるため、荷物の中身・重さ・送り先の3つの要素をもとに、最適な配送方法と料金帯を事前に把握することが重要です。
国際郵便の集荷料金はいくら?コストを抑えるポイント
現在の郵便局では、国際郵便でも集荷サービスを利用することができます。特に大型の荷物や複数個を同時に発送する場合、自宅や職場まで取りに来てもらえるこのサービスは非常に便利です。では、その便利な集荷にどの程度の料金がかかるのかを見ていきましょう。
まず、通常の個人利用において、1回の集荷にかかる基本料金は無料です。これは、郵便局が提供する「ゆうパック」「EMS」「国際小包」「国際eパケット」などに対応しているからです。ただし、一部の地域では対応していない場合や、法人契約が必要なケースもあるため、必ず事前に「集荷申し込みページ」や電話で確認しておくのが賢明です。
一方で、追加料金がかかる条件もあります。例えば、再集荷を依頼した場合や、定期的に大量の荷物を出す法人で特別便を希望する場合などです。これらは1件あたり数百円の料金がかかることがあります。また、集荷の時間指定を厳密に行う場合にも、柔軟に対応できないケースがあるため、時間に余裕をもって申し込むようにしましょう。
費用を抑えるためのポイントは、できるだけ荷物をまとめて出すことです。1件ずつ依頼するよりも、複数の荷物をまとめて集荷してもらうほうが、時間効率もコスト面でも有利になります。また、郵便局の「国際郵便マイページサービス」を利用すれば、送り状の作成から集荷依頼まで一括管理できるため、印刷や記載ミスによる再提出を防げるだけでなく、割引が適用される場合もあります。
こうして考えると、郵便局の国際郵便集荷サービスはコストパフォーマンスに優れた仕組みであり、正しく活用すれば配送業務が効率化され、余計な支出を減らすことが可能です。単に送るだけでなく、サービス全体の最適化を意識することが、賢く安く国際発送するコツと言えるでしょう。
海外に荷物を送るのに安いのはどこ?郵便局とヤマトを比較
海外への荷物発送を考える際、「郵便局とヤマト(ヤマト運輸)のどちらが安いのか」は非常に気になるポイントです。両者ともに日本国内では信頼性の高い配送サービスを提供しており、国際発送にも対応していますが、料金・スピード・利便性の面で違いがあります。
郵便局では、国際小包やEMS、eパケットなど複数の配送手段があり、発送先や荷物の内容に応じて細かく選択できる点が特徴です。特に、船便を使えば非常に安く送ることができ、たとえば2kgの荷物をアメリカに送る場合、約2,500円程度で対応可能です。時間はかかりますが、コスト重視であれば魅力的です。
一方、ヤマト運輸が提供する「国際宅急便」は、料金体系が比較的シンプルで、梱包資材・送り状なども一括で手配できる利便性があります。ただし、最安値では郵便局にやや劣るケースが多く、例えば先ほどの2kgの荷物であれば、アメリカ向けの発送に約4,000円〜5,000円かかることもあります。配送スピードは非常に優秀で、日数に余裕がない方には適していると言えます。
また、ヤマトは集荷に強みがあり、自宅までドライバーが来てくれるため、荷物を持っていく手間が省けます。郵便局も集荷に対応していますが、対応地域や時間に限りがある場合があるため、その点ではヤマトの柔軟性が高いと感じる人も多いようです。
ここから言えることは、「できるだけ安く送りたい」のであれば郵便局の国際小包や船便が優位です。しかし「利便性や速さ」を求めるのであれば、ヤマト国際宅急便も十分に検討の余地があります。どちらを選ぶかは、荷物の内容や緊急性、送り先の国、そしてあなた自身のライフスタイルに応じて判断すべきです。
郵便局とヤマト、海外配送で便利なのはどっち?

海外に荷物を送る際、多くの方が悩むのが「郵便局とヤマトのどちらを使うべきか」という選択です。どちらも信頼できる配送事業者ですが、サービスの特徴や利便性においては異なる点があります。そこで、それぞれの違いを比較しながら、どのようなケースでどちらを選べばよいのかを解説します。
まず、郵便局は「国際郵便」という形で、EMS(国際スピード郵便)・国際小包・eパケット・小形包装物など、目的に応じた複数の配送手段が用意されています。特に料金体系の幅が広く、急ぎの荷物はEMS、コスト重視なら船便といった選択が可能です。また、世界的な郵便ネットワークに基づいて配送されるため、多くの国や地域へ送る際の信頼性にも優れています。さらに、比較的細かいサイズや重さに対応している点も魅力のひとつです。
一方で、ヤマト運輸が提供する「国際宅急便」は、手軽さとスピードに強みがあります。特に自宅への集荷対応が柔軟で、専用資材の提供、送り状の記入サポートなど、初心者でも迷わず使える設計になっています。さらに、通関手続きが簡略化されており、関税の計算も一括管理してくれるため、ビジネスでの利用や継続的な発送にも適しています。ただし、発送可能な地域は郵便局に比べて限定される傾向があり、料金もやや高めになる場合が多いです。
こう考えると、「利便性」「対面でのサポート」「スピード重視」であればヤマト、「コスト」「送達エリア」「柔軟な配送方法」であれば郵便局のほうが向いています。特に海外在住の家族に定期的に荷物を送りたい人や、配送先がマイナーな国の場合は郵便局の選択肢が広がります。
このように、それぞれの特徴を理解した上で、自分の荷物の内容・送り先・予算・緊急性などに応じて使い分けるのが賢い選択です。
国際郵便マイページサービスを使うメリットと登録手順
現在の国際発送では、手続きのデジタル化が進んでおり、郵便局が提供する「国際郵便マイページサービス」は、そうした流れの中でも特に便利なオンラインサービスの一つです。このサービスを活用することで、従来の手書きの送り状作成や窓口での時間のかかる手続きが、大幅に簡素化されます。
まず、このサービスを利用することで得られるメリットは多岐にわたります。たとえば、送り状をWeb上で作成・印刷できるため、手書きによる記載ミスが減り、英語での記入に不安がある人でも安心です。さらに、宛先の情報は一度登録しておけば再利用できるため、複数回にわたる発送がスムーズに行えます。また、発送する内容品の記録も残るため、以前送ったものを振り返る際にも便利です。
加えて、このマイページからは集荷依頼も可能で、重い荷物を持ち込む手間が省けます。ポイント制度もあり、利用状況に応じて特典を受けられる点も、日常的に海外発送を行う人にとってはうれしいポイントです。
登録手順も難しくはありません。まず、郵便局の公式サイトにアクセスし、国際郵便マイページの登録フォームに進みます。名前・住所・電話番号・メールアドレスなどを入力し、利用規約に同意すれば、登録用の確認メールが届きます。メール内のリンクをクリックすることでアカウントが有効化され、すぐにサービスの利用を開始できます。
なお、送り状を印刷するためにはプリンターが必要になるため、事前に準備しておくことをおすすめします。スマートフォンからもアクセス可能ですが、住所や内容品を入力する際にはPCの方が操作しやすいかもしれません。
このように、国際郵便マイページサービスは、煩雑だった国際発送の手続きを大幅に効率化してくれるツールであり、特に繰り返し発送する人にとっては不可欠なサービスと言えるでしょう。
海外に書類を送るときの封筒の選び方と正しい書き方
海外に重要な書類を送る際は、封筒の選び方や宛名の書き方に細心の注意を払う必要があります。誤った記載や不適切な封筒の使用は、配達遅延や紛失、最悪の場合には返送されるリスクすらあるため、丁寧に準備を進めることが欠かせません。
まず、封筒選びの基本ですが、送る書類の大きさや枚数に応じてサイズを選ぶ必要があります。A4用紙が折らずに入る「角形2号」や、少量の文書なら「長形3号」などが適しています。封筒はできる限り厚手で、耐水性や耐久性のあるものを選ぶと安心です。特にビジネス文書や契約書など、絶対に破損できない内容物を送る場合は、クッション封筒や厚紙を挟んだ保護封筒を使うとよいでしょう。
次に、宛名の書き方です。海外に送る場合、宛先は英語またはローマ字で記載し、書式は「宛名 → 番地・通り名 → 都市名 → 州・県名 → 郵便番号 → 国名」の順に並べます。国名は必ず大文字で最後に記載し、郵便局のルールに従って目立つ位置に書きます。差出人の情報も裏面または左上に明記し、必要があれば電話番号やEメールアドレスを添えておくと、万一の際にも連絡がつきやすくなります。
また、封筒の表面には「BY AIR MAIL」または「PAR AVION(航空便)」と青いラベルを貼付するか、手書きで記載する必要があります。ラベルは郵便局で無料配布されており、窓口で申し出れば入手可能です。
いくら中身が重要でも、封筒が破れていたり、宛名が不明瞭であれば、配達時にトラブルになることもあります。ですので、書類は中で動かないようしっかり固定し、封はテープで完全に閉じるようにしてください。
こうして準備を整えることで、大切な書類を確実に安全に届けることができ、送り手としても安心して発送を完了できます。少しの工夫と丁寧な作業が、確実な海外配送につながります。
海外に荷物を送る方法郵便局で送るなら知っておきたいポイントまとめ

- EMSは最も速く届く国際配送サービスで、追跡機能や損害補償が標準で付帯している
- 国際小包は航空便・SAL便・船便から配送方法を選べ、予算や配送スピードに応じて調整できる
- 小形包装物や国際eパケットは2kg以内の軽量な荷物に適しており、比較的安価に送ることができる
- 書留や保険付き郵便など、荷物の重要度に応じて補償や確認機能を追加できるオプションがある
- 海外発送では送る荷物の中身や重量・サイズを事前に正確に把握しておくことが必要である
- アルコール類・スプレー缶・リチウム電池など、多くの国で禁制品に指定されているものには注意が必要
- 梱包には中身をしっかり保護するための緩衝材を使用し、配送中の破損リスクを最小限にする工夫が重要
- 梱包用の箱や封筒は郵便局指定のもの以外でも利用可能だが、サイズや強度などの条件を満たす必要がある
- 送り状は郵便局のマイページサービスで作成・印刷すれば、手書きの手間が省けミスも減らせる
- 国際郵便の取り扱いはすべての郵便局で行っているわけではなく、対応局を事前に調べておく必要がある
- 郵便局の窓口は局ごとに営業時間が異なり、特に国際郵便は受付終了時間が早まることもあるので注意する
- 集荷サービスは基本的に無料で利用できるが、地域や契約形態によっては対象外の場合もある
- 複数の荷物をまとめて出すことで、集荷の効率を高められ、対応コストも抑えることができる
- 郵便局は幅広い国・地域への配送に対応しており、料金を抑えやすい手段が豊富である
- ヤマトは集荷の柔軟性やスピードに優れているが、配送地域や料金面では郵便局に劣ることもある
関連記事







