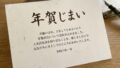重要な書類や個人情報を安全に送りたいときに頼りになるのが「簡易書留」です。しかし、忙しくて郵便局の営業時間に間に合わない方や、近くに郵便局がないという方の中には、「簡易書留をコンビニから送ることはできるの?」と気になって検索している人も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな「簡易書留コンビニ」で検索している方に向けて、ローソンなど一部のコンビニで簡易書留が出せる仕組みや対応店舗の探し方、注意点、封筒や切手の準備方法まで、初めての方でも迷わず実践できるよう丁寧に解説します。
また、郵便局との違いや、速達・配達証明といったオプションサービスとの組み合わせ方も紹介しますので、「自分にとってベストな送り方」が見えてくるはずです。
この記事を読み終えるころには、あなたも簡易書留の出し方に自信を持てるようになっているでしょう。ぜひ最後までご覧ください。
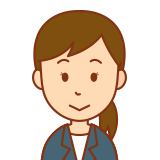
💡記事のポイント
- コンビニで簡易書留を送る方法と対応店舗の確認方法
- 簡易書留の仕組みと郵便局との違い
- 封筒や切手の選び方と購入のポイント
- 利用できるオプションサービスと注意点
簡易書留をコンビニで送るには?送り方や手続き方法を徹底解説

- 簡易書留はどうやって送るのですか?基本的な仕組みを解説
- コンビニから簡易書留は送れるの?対応店舗や注意点を紹介
- コンビニと郵便局での簡易書留の送り方の違いとは?
- 簡易書留用の封筒はコンビニで購入できる?サイズや選び方も解説
- 簡易書留用の切手はコンビニで買える?料金と購入方法について
- ローソンで簡易書留を出す方法とは?受付時間や注意点も紹介
簡易書留はどうやって送るのですか?基本的な仕組みを解説
簡易書留とは、差出人が郵便物の配達状況を確認でき、さらに万が一の事故に備えて損害要償額がついている郵送方法の一つです。特に、重要な書類や契約書、個人情報を含む文書などを郵送する際に利用されることが多く、信頼性と安全性を重視する人にとっては心強い手段です。
まず、簡易書留は「書留郵便」の一種であり、通常郵便に追加料金を支払うことで利用できます。郵便局の窓口で手続きを行うのが一般的で、郵便物の内容物が金銭などでない限り、封筒や荷物の形に特別な制限はありません。ただし、内容物が貴重品や現金である場合は、「一般書留」や「現金書留」など他の手段が適しています。
発送時には、郵便局の窓口で「簡易書留でお願いします」と伝えると、差出人の情報を記入する控え用の伝票が渡されます。郵便物にはこの伝票と対応するバーコードが貼り付けられ、追跡番号が発行されます。この番号を使えば、配達状況をインターネットや電話で確認することができます。
なお、簡易書留には補償がありますが、その金額は上限が5万円までと定められています。そのため、高額なものを送るには不十分であり、その際はより補償の厚い「一般書留」を選ぶべきでしょう。
このように、簡易書留は「いつ・誰に・どこで届いたか」が記録されるため、ビジネスや役所とのやり取りなど、証拠が必要な場面で重宝されています。普通郵便よりもやや手間がかかりますが、安全性と証明性を確保できる点において、その価値は十分にあるといえます。
コンビニから簡易書留は送れるの?対応店舗や注意点を紹介
現在のところ、全国すべてのコンビニから簡易書留を送れるわけではありません。実際には、郵便ポストが設置されているだけの店舗も多く、簡易書留のような「窓口対応が必要な郵送サービス」は取り扱っていないことが一般的です。では、どのコンビニであれば簡易書留を出せるのでしょうか。
実際に簡易書留の取り扱いがあるのは、ローソンの一部店舗に限られます。これらの店舗では「ゆうパック取扱店」や「郵便ポスト併設型のローソン」であることが条件です。具体的には、郵便局と提携している店舗に専用の窓口が設置されており、郵便局が休みの時間帯でも郵送サービスが一部利用できるようになっています。
ただし、ここで注意しておきたいのは、ローソンで簡易書留を出すには店内に「ゆうゆう窓口機能」があることが前提だという点です。すべてのローソンでこの機能が備わっているわけではありません。そのため、事前に日本郵便の公式サイトや店舗検索で「ゆうゆう窓口対応店舗」を調べておく必要があります。
さらに、コンビニから出す場合は、郵便局で受け付けるときのようにその場で相談したり、不明点を聞いたりすることが難しい場合もあります。店員が郵便に詳しくないこともあるため、自分であらかじめ封筒や切手の準備、宛先の記載などを完了させておくことが望ましいです。
このように、ローソンなど一部のコンビニでは簡易書留の発送が可能ですが、対応店舗が限られていること、スタッフ対応が郵便局ほど丁寧でないことなど、いくつかの制約がある点には留意しましょう。安心して簡易書留を出すためには、可能であれば郵便局の窓口を利用する方が確実です。
コンビニと郵便局での簡易書留の送り方の違いとは?
コンビニと郵便局では、簡易書留の送り方や手続きの流れに明確な違いがあります。それぞれの特徴を理解しておくことで、状況に応じた適切な選択ができるようになります。
まず、郵便局の場合は、通常の窓口業務として簡易書留を取り扱っており、専用の伝票を使って受付を行います。手続きはスタッフが丁寧に案内してくれるため、初めての人でも安心して利用できます。料金や補償内容についての質問にも即時対応してもらえるため、イレギュラーな対応が必要な場合にも柔軟に対応できるというメリットがあります。
一方で、コンビニから簡易書留を送る場合は、前述の通り取り扱いのある一部のローソンに限られること、また受付対応が郵便局のように専門ではない点が大きな違いです。受付可能な時間帯も店舗によって異なり、深夜や早朝に対応していない場合もあります。
もう一つの違いは、その場での相談・サポートの有無です。郵便局であれば、封筒のサイズ、切手代、追跡番号の説明なども受けられますが、コンビニではこれらを自分で事前に調べておく必要があります。もし宛先の書き方や追加サービス(配達証明など)について不安がある場合、郵便局の方が安心です。
ただし、郵便局が閉まっている時間帯に簡易書留を送りたいという場合、対応しているローソンが近くにあるならば、コンビニを活用するのも一つの手段です。その際は事前の準備と確認を怠らないようにしましょう。
このように、コンビニと郵便局では手続きの手軽さや対応力に違いがあり、どちらが良いかは「自分の状況」と「何を優先するか」によって変わってきます。信頼性やサポートを求めるなら郵便局、利便性を重視するならコンビニ、という選択が基本になります。
簡易書留用の封筒はコンビニで購入できる?サイズや選び方も解説

簡易書留で郵便物を送りたいと考えたとき、まず気になるのが「封筒はどこで手に入るのか」という点ではないでしょうか。特に、コンビニで準備できるのかどうかを知りたいという方は多いようです。
まず結論として、簡易書留専用の封筒というものは存在しません。つまり、特定の「簡易書留封筒」を探す必要はなく、自分で市販の封筒を用意すれば問題ありません。一般的に利用されているのは長形3号(A4の三つ折りが入るサイズ)や角形2号(A4がそのまま入るサイズ)などの封筒です。こうした封筒は、多くのコンビニで文房具コーナーに置かれており、1枚単位または少数パックで手軽に購入できます。
ただし、簡易書留で郵送する際には、内容物の重要性が高いケースが多いため、封筒選びには慎重さが求められます。例えば、機密文書や個人情報を含む書類を送る場合、厚手で丈夫な封筒を使うのが望ましいでしょう。中身が透けにくいクラフト封筒や、内側に透け防止加工がされているタイプであれば、より安心です。
また、封筒サイズによっては郵便料金も変わってくるため、事前に送りたい書類の厚さや重さを確認し、適切なサイズの封筒を選ぶことが大切です。特に厚さが2cmを超えるような場合は、定形外郵便扱いとなるため、封筒だけでなく切手料金にも注意が必要になります。
このように、コンビニで封筒を購入することは可能ですが、「簡易書留専用封筒」を探す必要はなく、用途や送付内容に合わせた適切な封筒を選ぶ意識が重要です。送るものの重要性に合わせて、素材や強度を確認しながら選んでいくようにしましょう。
簡易書留用の切手はコンビニで買える?料金と購入方法について
簡易書留を送る準備を進める中で、「切手はどこで買えばいいのか」「料金はいくらになるのか」といった疑問を持つ人は少なくありません。特に郵便局が閉まっている時間帯や休日などに投函を検討している場合、コンビニでの切手購入は大きな選択肢となります。
現在、多くのコンビニチェーン(ローソン、セブンイレブン、ファミリーマートなど)では、通常の郵便切手を販売しています。主にレジ横での取り扱いとなっており、希望の金額を伝えれば店員が在庫を確認して対応してくれます。ただし、販売しているのは主に82円や94円などの一般的な額面の切手が中心で、簡易書留に必要な正確な額面が揃っていないこともあります。
簡易書留の送料は、基本の郵便料金に加えて、書留料金(現在は350円)が上乗せされる仕組みです。例えば、50g以内の定形郵便であれば110円+350円=460円が必要になります。この場合、460円分の切手を用意する必要がありますが、コンビニでこのちょうどの額面が揃うとは限りません。複数の額面を組み合わせることで対応はできますが、やや手間がかかる点には注意が必要です。
また、コンビニで購入した切手は、基本的には返品・交換ができません。金額を間違えてしまった場合でも返金してもらえないため、購入前に正確な送料を把握しておくことが重要です。料金の詳細は日本郵便の公式サイトで確認できるほか、重さや封筒サイズに応じて窓口で見積もってもらうのが確実です。
このように、切手自体はコンビニで購入可能ですが、正確な料金計算や額面の組み合わせには細心の注意が必要です。不安がある場合は、郵便局でそのまま発送手続きと一緒に購入したほうが効率的で安心といえるでしょう。
ローソンで簡易書留を出す方法とは?受付時間や注意点も紹介
ローソンは郵便サービスとの連携が進んでいるコンビニであり、ゆうパックや切手の取り扱いのほか、一部店舗では簡易書留の発送も可能です。ただし、すべてのローソンで簡易書留を出せるわけではなく、対応しているのは限られた店舗に限られます。
簡易書留を出せるローソンの条件として、「ゆうパック取扱店」であり、かつ「ゆうゆう窓口機能」を備えている必要があります。このような店舗では、専用のカウンターが設けられていたり、郵便局と提携したバックヤードで郵便業務を行っていたりする場合があります。郵便局が閉まっている時間帯でも一部郵送サービスが利用できるため、仕事帰りや土日祝日にも活用しやすいのがメリットです。
ただし、ここで押さえておきたいのは、受付時間が店舗によって異なるという点です。ローソン自体は24時間営業が基本ですが、郵便受付の業務は時間が制限されていることがあります。例えば、平日は午前10時~午後6時まで、土日は受付不可といったケースもあり、事前確認が必須です。郵便サービスの取扱時間は、ローソン公式サイトや日本郵便の「郵便局・取扱店検索」で調べることができます。
さらに、ローソンで簡易書留を出す場合は、必要な切手や封筒を自分で事前に準備しておく必要があります。郵便局のように、その場で封筒のサイズや重さを計測してもらったり、不足料金を現金で支払ったりする柔軟な対応は期待できないケースが多いです。特に、受付を担当するのが郵便専門のスタッフではなく、一般の店舗スタッフである場合、郵便知識に差があることも理解しておくべきポイントです。
このように、ローソンで簡易書留を出すには、対応店舗の確認、受付時間の把握、そして事前準備が重要です。利便性は高いものの、郵便局ほどのサポート体制があるわけではないため、初めて利用する方は慎重に進めることをおすすめします。
簡易書留をコンビニで利用する前に知っておきたいQ&Aと活用法

- 簡易書留は土日や夜間にも出せるの?受付可能な時間帯とは
- 郵便窓口・ゆうゆう窓口とコンビニでの簡易書留の違いとは?
- 簡易書留の料金や切手代はいくら?封筒サイズ別に詳しく解説
- 簡易書留は速達にできるの?配達日数やオプションを比較
- レターパックと簡易書留はどっちがいい?用途別の使い分け
- 配達証明や郵便局留めを簡易書留で利用する方法とは?
簡易書留は土日や夜間にも出せるの?受付可能な時間帯とは
簡易書留を出すタイミングについて、土日や夜間にも対応しているのか気になる方は多いかと思います。特に平日は仕事で郵便局に行けないという方にとって、休日や遅い時間の対応可否は重要な情報です。
まず、通常の郵便局の窓口(いわゆる「一般窓口」)は、基本的に平日の9時〜17時ごろまでしか営業していません。このため、仕事終わりや土日に行っても、窓口での簡易書留の受付は原則できません。ただし、全国には「ゆうゆう窓口」と呼ばれる、営業時間が延長されている特別な窓口を備えた郵便局が存在します。このゆうゆう窓口であれば、平日は20時頃まで、土日祝日でも午前中から夕方まで営業しているところが多く、簡易書留の受付も可能です。
ゆうゆう窓口の有無や営業時間は、郵便局ごとに異なります。そのため、事前に日本郵便の公式サイトで検索して確認しておくことが重要です。特に大都市圏の主要郵便局では比較的遅くまで対応している傾向がある一方で、地方の小規模な郵便局ではゆうゆう窓口自体が存在しないこともあります。
一方で、コンビニ(特にローソン)などの民間店舗においても、ゆうパックや切手販売を行っているところがありますが、簡易書留の発送に対応しているのは一部の提携店舗に限られます。しかも、簡易書留の取り扱いができるとしても、郵便局と異なり、24時間いつでも受付可能というわけではありません。店舗内での受付時間は、たとえば「10:00〜18:00」のように限られている場合も多いため、夜間に出すには向いていないケースが多いのです。
このように、簡易書留を土日や夜間に出す場合は、近くにゆうゆう窓口のある郵便局があるかどうかが重要なポイントになります。コンビニは便利な一方で、店舗によって受付内容や時間が大きく異なるため、事前に確認をしておかなければ思わぬタイミングで受付を断られてしまうこともあるでしょう。
郵便窓口・ゆうゆう窓口とコンビニでの簡易書留の違いとは?
簡易書留を送る方法には複数の選択肢がありますが、よく比較されるのが「郵便窓口」「ゆうゆう窓口」「コンビニ」の3つです。それぞれにメリットと制約があり、用途や時間帯によって使い分ける必要があります。
まず、郵便窓口はもっとも一般的な手段です。全国の郵便局で平日の日中に利用でき、スタッフに質問をしながら手続きできる点が最大の利点です。たとえば、封筒のサイズが適切かどうか、料金はいくらか、必要な切手の組み合わせなど、分からないことがあればその場で聞いて解決できます。また、窓口では配達証明や速達などのオプションサービスも併用でき、柔軟な対応が可能です。
次に、ゆうゆう窓口は、通常の営業時間外でも郵便対応をしてくれる特別な窓口です。前述のとおり、夜間や休日にも営業しているため、忙しい人や急ぎで書類を送りたい人には非常に便利です。サービス内容は通常の郵便窓口とほぼ同じで、簡易書留の受付はもちろん、切手の販売や料金の計算も行ってくれます。ただし、すべての郵便局に設置されているわけではないため、あらかじめ設置有無と営業時間を確認しておく必要があります。
一方で、コンビニから簡易書留を送る場合は少し事情が異なります。まず対応しているのはローソンの一部店舗に限られており、セブンイレブンやファミリーマートでは原則取り扱っていません。そして、ローソンであってもすべての店舗が対応しているわけではなく、「ゆうパック取扱店」「郵便窓口併設型店舗」などの特定条件を満たしている必要があります。
また、コンビニでは基本的にその場での計測や料金案内は行われず、郵便に詳しいスタッフが常駐しているわけでもありません。切手の貼付や宛先の記載、封筒のサイズ確認など、すべて事前に自分で対応しておく必要があります。そのため、初めて簡易書留を利用する方には少しハードルが高いかもしれません。
このように、郵便窓口・ゆうゆう窓口・コンビニの違いは、主に「対応時間」「サポート体制」「受付サービスの柔軟性」にあります。利用者のニーズや状況に応じて、どの方法が最適かを選ぶことが、ストレスの少ない発送につながります。
簡易書留の料金や切手代はいくら?封筒サイズ別に詳しく解説
簡易書留を利用する際には、基本の郵便料金に加えて、簡易書留の加算料金が発生します。封筒のサイズや重さによって金額が変わるため、あらかじめ仕組みを理解しておくことが大切です。
まず、簡易書留の「追加料金」は全国一律で350円(2025年8月時点)です。この金額は、通常の郵便料金に上乗せされる形で請求されるため、合計の送料は封筒の種類や重量によって異なります。
例えば、定形郵便で最もよく利用される「長形3号封筒(A4の三つ折りが入るサイズ)」を使い、書類1枚(50g以内)を送る場合、基本料金は110円です。そこに簡易書留の350円が加わるので、合計で460円の切手が必要になります。
次に「角形2号封筒(A4書類を折らずに入れられるサイズ)」を使う場合、多くは25gを超えるため、50gまでの定形外郵便扱いになります。この場合の基本料金は140円で、合計は490円となります。さらに、封筒の中身が分厚くなり、100gや150gを超えると、基本料金がさらに上がっていく仕組みです。
郵便局では重さをその場で測って正確な料金を案内してくれますが、コンビニから送る場合は、あらかじめ自宅などで重さを量り、必要な切手の金額を計算しておかなければなりません。切手は複数枚を組み合わせることで対応できますが、細かい金額の切手が手に入りにくい場合もあるため、事前に郵便料金表を確認しておくことが安心です。
また、簡易書留を速達として送ることも可能です。この場合は、さらに速達料金(通常は300円)が加算されます。例えば、25g以内の定形郵便で簡易書留+速達とした場合、合計は110円+350円+300円=760円となります。重要書類を急ぎで届けたいときには有効な選択肢ですが、料金が高くなる点には注意が必要です。
このように、簡易書留の料金は「封筒のサイズ」と「中身の重さ」によって変動します。確実な配達を求めるからこそ、適切な料金計算と切手の用意が欠かせません。初めて利用する方は、できる限り郵便局での対応をおすすめしますが、慣れてくればコンビニでの利用も選択肢として検討できるでしょう。
簡易書留は速達にできるの?配達日数やオプションを比較

簡易書留は、重要書類などの大切な郵便物を安全に届けたいときに選ばれる方法ですが、急ぎで送りたい場合には「速達と併用できるのか?」という疑問を持つ方も多いようです。結論からいえば、簡易書留は速達と併用可能です。ただし、速達の利用には追加料金が必要であり、配達スピードや補償内容なども含めて理解しておくことが重要です。
まず、簡易書留とは「配達記録付き」の郵便サービスで、郵便物の配送過程を追跡できるほか、万が一の事故に備えて5万円までの損害補償が付いているのが特徴です。送付方法としては普通郵便に加算料金を上乗せする形で簡易書留のサービスを追加します。ここにさらに速達を組み合わせることで、「記録付きかつスピーディな郵送」が可能になります。
速達サービスを付けると、配達の優先順位が上がり、通常の郵便よりも早く届けられます。地域によって異なりますが、基本的には翌日配達が目安です。たとえば、関東から関西へ送る場合、通常の簡易書留では2日程度かかることが多いですが、速達を利用することで1日に短縮される可能性があります。特にビジネス文書や契約書など、納期が決まっているものには非常に有効です。
料金面で見ると、速達料金は通常の郵便料金+簡易書留料金に加えて、さらに300円(250g以内の場合)が必要になります。たとえば、50g以内の定形郵便を簡易書留+速達で送ると、基本料金110円+簡易書留350円+速達300円で、合計760円となります。料金はやや高めになりますが、そのぶんスピードと記録性を兼ね備えているため、安心して利用できる郵送手段といえます。
一方で、速達をつけたからといって「確実に翌日に届く」とは限らない点にも注意が必要です。たとえば、遠隔地への配送や天候の影響、年末年始などの繁忙期には、翌日配達が難しいこともあります。あくまで「早く届ける努力をするサービス」であり、保証ではないことを理解しておくと良いでしょう。
このように、簡易書留と速達は併用可能であり、状況に応じて柔軟に選ぶことができます。配達速度と安全性を両立したい場合には、有力な選択肢として検討する価値があるでしょう。
レターパックと簡易書留はどっちがいい?用途別の使い分け
郵便物を安全かつ確実に届けたいとき、「簡易書留とレターパックのどちらを選べばよいのか?」と迷う方は少なくありません。どちらも追跡機能を備えており、対面での配達も可能ですが、その特徴には明確な違いがあります。送る内容物や目的に応じて使い分けることが、トラブルを避けるための鍵になります。
簡易書留は、普通郵便に対して記録と補償を追加するサービスです。送る内容物に対して最大5万円までの損害補償が付き、配達過程の記録(追跡)も残ります。受取人に直接手渡しされるため、信書や重要な書類、個人情報を含む書類などには最適な方法といえます。特に企業間の契約書や税務関係書類、医療関連の個人情報など、万が一の事故が大きな問題につながるものには、簡易書留が強く推奨されます。
一方で、レターパックには「レターパックプラス」と「レターパックライト」の2種類があり、いずれも事前に専用封筒を購入して利用します。レターパックプラスは対面での配達、レターパックライトはポスト投函による配達で、どちらも追跡番号が付いています。最大のメリットは、全国一律料金で使える手軽さと速達並みの配達スピードです。たとえば、プラスは600円、ライトは430円で利用でき、どちらも通常1〜2日で配達されます。
ただし、レターパックには補償が付いていないという明確なデメリットがあります。万が一、紛失や破損があっても郵便局側からの補償は受けられません。そのため、内容物が高価であったり、紛失が致命的なトラブルになるような郵送には向きません。
用途別にまとめると、コストを抑えて書類や商品を素早く送りたい場合はレターパック、送付内容に万が一の保証を付けて安全性を高めたい場合は簡易書留がおすすめです。また、レターパックは専用封筒に収まるサイズに限られるため、厚さや形状によっては簡易書留しか選べないケースもあります。
このように、両者には明確な違いがあるため、送付するものの価値や重要度、配送スピード、コスト意識などを考慮して、適切な方法を選ぶことが大切です。
配達証明や郵便局留めを簡易書留で利用する方法とは?
簡易書留は追跡機能付きの郵便サービスとして多く利用されていますが、「配達証明」や「郵便局留め」といった追加オプションを組み合わせることで、さらに目的に沿った送り方が可能になります。これらのサービスを正しく活用するためには、仕組みや利用方法をしっかり理解しておくことが必要です。
まず、「配達証明」とは、郵便物が確実に相手に届いたことを、後日書面で証明してくれるサービスです。受取人が郵便物を受け取ると、その情報が記録され、差出人には「配達証明書」が発行されて郵送されてきます。法律関係やビジネス取引などで、書類の送付履歴を客観的に証明する必要がある場合には、非常に有効な手段です。簡易書留に配達証明を付けるには、郵便窓口で申告し、追加料金(2025年現在で350円)を支払うだけで手続きできます。
次に、「郵便局留め」は、受取人が自宅ではなく、あらかじめ指定した郵便局で郵便物を受け取れるサービスです。送り状に「〇〇郵便局留め」と明記し、受取人が本人確認書類を提示すれば受け取ることができます。この方法は、プライバシー保護や、不在がちな方が確実に受け取るための手段として活用されています。
簡易書留で郵便局留めを利用する際は、特別な申し込み手続きは必要ありません。ただし、宛名部分に「〇〇郵便局留め」と明記すること、受取人の名前と連絡先が明確であることが前提です。なお、郵便局留めは差出人側の都合だけではなく、受取人側が郵便局留めを希望している場合に使うのが原則とされているため、あらかじめ双方の合意を取っておくのが理想的です。
これらの追加サービスは、すべて郵便局の窓口で申し込むことができます。コンビニから簡易書留を送る場合は、こうしたオプションの受付ができない場合もあるため注意が必要です。なるべく手厚いサポートを受けたい場合には、郵便局の窓口を利用することをおすすめします。
このように、配達証明や郵便局留めといった機能を併用することで、簡易書留はより目的に合った郵送手段として活用できます。安全性と証明性を両立させたいときには、ぜひ活用してみてください。
簡易書留をコンビニで利用する際に押さえておくべきポイントまとめ

- 簡易書留は普通郵便に追跡と補償を加えた郵送方法である
- 損害補償は最大5万円までで高額品には不向き
- 郵便局の窓口ではスタッフのサポートを受けながら発送できる
- コンビニでは簡易書留を送れる店舗が限られている
- ローソンの一部店舗のみ簡易書留の発送に対応している
- 対応しているローソンは「ゆうパック取扱店」などの条件がある
- 店舗によって受付時間が異なり24時間対応ではない
- コンビニスタッフは郵便業務に詳しくない場合がある
- 簡易書留に専用封筒はなく市販の封筒で代用可能
- コンビニでも封筒は購入できるが内容に適した選定が必要
- 切手もコンビニで購入可能だが額面の組み合わせに注意が必要
- 重量やサイズによって料金が変わるため事前に確認すべき
- 簡易書留は速達オプションを付けて翌日配達を狙うことも可能
- レターパックとは補償や使い方に違いがあり用途に応じて選ぶ
- 配達証明や郵便局留めなど追加オプションも組み合わせ可能
関連記事