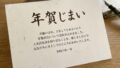日々の暮らしの中で、郵便ポストに荷物を投函する機会は意外と多くあります。特に、フリマアプリやネット通販を利用する方にとっては、ポストが「ちゃんと入るかどうか」が気になる場面も増えてきたのではないでしょうか。そんな中、「郵便ポスト何センチまで入るのか」と検索する人が増えているのも納得できます。
郵便物や荷物がポストに入るかどうかは、サイズの規定だけでなく、ポストの種類や設置環境によっても大きく左右されます。自宅のポストと街なかの赤いポストでは形状も容量も異なり、思っていたより小さくて入らなかったという経験をした方も多いはずです。また、厚さ3cm以内というルールをよく聞くものの、実際のところはどうなのか、4cmや5cmではどうなるのかなど、細かな疑問もつきものです。
この記事では、「郵便ポスト何センチまで入るのか?」というテーマを軸に、ポストの種類別サイズ、対応可能な厚さの目安、配送サービスごとのルールなどを具体的に解説していきます。はじめて郵便物を発送する方はもちろん、メルカリやゆうパケットポストを活用している方にも役立つ情報を丁寧にまとめています。
「知らなかった」で損をしないために、そして無駄な差し戻しや配達トラブルを防ぐために。この記事を通じて、あなたの発送作業がスムーズでストレスのないものになることを願っています。
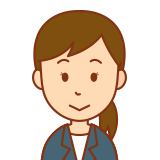
💡記事のポイント
- 郵便ポストに投函できる荷物のサイズや厚さの目安がわかる
- ポストの種類ごとの投函口サイズの違いが理解できる
- ゆうパケットポストやメルカリ便利用時の注意点が把握できる
- 厚さ3cm以上の荷物の適切な発送方法が選べるようになる
郵便ポスト何センチまで入る?サイズ制限と投函口の目安を徹底解説

- 郵便ポストは何センチまで入る?標準サイズの目安
- 郵便ポスト投函口は何センチ?設置タイプ別の違い
- 郵便ポストの口は何センチ?横幅・高さの実測値を紹介
- 郵便ポストの厚さは何センチまでOK?よくある3cm・4cm・5cm
- 郵便ポストに厚み4センチの荷物は投函できる?実例で検証
- 家のポストのサイズは何センチ?設置基準と確認方法
郵便ポストは何センチまで入る?標準サイズの目安
郵便ポストに投函できる郵便物のサイズは、ポストの構造によって大きく左右されます。目安としては、厚さ3cm以内、A4サイズ(約33×24cm)程度の大きさであれば、ほとんどのポストに問題なく投函可能です。
現在の私は、配送サービスの多様化に伴い、より大きな荷物を郵便ポストに投函したいというニーズが高まっていると感じています。しかし、実際にはすべてのポストが大きなサイズに対応しているわけではありません。特に古い住宅や集合ポストでは、投函口が狭く、3cmを超える厚みの荷物が入らないこともあります。
例えば、メルカリやフリマアプリの利用者がゆうパケットやクリックポストを使おうとする場合、ポストのサイズを確認せずに発送すると、荷物が入らず差し戻しになるケースも見受けられます。こうしたトラブルを防ぐためには、事前にポストの口のサイズを測るか、日本郵便のサイズガイドラインを確認しておくことが有効です。
また、ポストの形状や投函口の構造によって、実際に入るサイズが違う点にも注意が必要です。たとえA4サイズであっても、厚紙封筒や緩衝材が入っている場合、入口で引っかかることもあります。
このように考えると、「A4・厚さ3cm以内」という目安はあくまで一般的なガイドラインであり、すべてのケースに当てはまるとは限りません。安全に郵便物を投函するためには、投函前のチェックを習慣にすることが大切です。
郵便ポスト投函口は何センチ?設置タイプ別の違い
郵便ポストの投函口のサイズは、設置場所や利用目的によって大きく異なります。これには大きく分けて、公共ポスト・戸建て用ポスト・マンション共用ポストの3種類があり、それぞれに特徴的なサイズ傾向があります。
まず、街中に設置されている日本郵便の公共ポストについて見てみましょう。これらのポストは、A4封筒(角形2号)やゆうパケットサイズの荷物に対応するために、投函口の幅が30〜34cm程度、高さが3.5〜4cm程度に設定されています。これにより、比較的大きな封筒や、小型の箱型郵便物の投函が可能です。
一方で、戸建て住宅に設置されている個人用ポストの場合は、デザインや建物の制約により投函口が小さいことが多く、幅25cm前後・高さ2.5〜3cm程度のものが一般的です。中にはA4サイズの封筒がぎりぎり通る程度のサイズしかないポストも存在します。そのため、フリマアプリの利用者や、ネット通販を頻繁に利用する家庭では、あらかじめ投函口の広いポストを選ぶことが推奨されます。
マンションやアパートなどの集合住宅では、集合ポストの仕様が標準化されている傾向にありますが、それでも投函口のサイズは物件によって差があり、一般的には幅26〜30cm・高さ3cm前後となっています。集合ポストは、複数の住人が同じ設備を利用するため、安全性やセキュリティ面の制約から、投函口が小さめに設計されていることが多いです。
このように、ポストの設置タイプによって、投函可能なサイズは異なります。自宅やオフィスで使用しているポストのタイプを把握した上で、適した郵送手段を選ぶことが重要です。
郵便ポストの口は何センチ?横幅・高さの実測値を紹介

郵便ポストの口、つまり投函口の「実際のサイズ」が気になるという方も多いでしょう。ここでは、具体的な実測データをもとに、ポストの投函口サイズを紹介します。
実際、家庭用ポストや集合ポスト、そして公共ポストでは、それぞれサイズに大きな違いがあります。例えば、ある戸建て住宅に設置されている標準的なスリット型ポストでは、投函口の横幅は約25cm、高さは3cm前後であることが多いです。このサイズでは、A4サイズの封筒がギリギリ通る程度で、少しでも膨らみがあると投函できなくなることがあります。
また、公共の大型ポスト(日本郵便が管理する赤いポスト)では、投函口が複数設けられていることがあり、定形郵便専用の小さな口と、厚みのある郵便物用の大きな口があります。大きな方の投函口では、横幅が33〜34cm、高さが4cm程度あるため、ゆうパケットポスト(厚さ3cmまで)や角形2号封筒に対応できます。
集合住宅のポストはどうでしょうか。実測した例として、都内の築10年程度のマンションでは、ポストの投函口が横幅28cm・高さ2.8cmというサイズでした。このサイズだと、少し厚めの封筒やクッション材入りのパッケージは通りづらいことがあります。実際、メルカリやラクマで発送されるゆうパケットが入りきらず、ポストの前で困っている利用者を目にすることもあります。
こうして見ると、郵便ポストの口のサイズは、一見似ているようでいて、設置環境やモデルによって明確に異なることが分かります。投函する前にサイズを把握しておくことで、無駄な再発送や持ち戻りのリスクを減らすことができるでしょう。
郵便ポストの厚さは何センチまでOK?よくある3cm・4cm・5cm
郵便ポストに投函できる荷物の厚さについては、3cm・4cm・5cmという区切りで判断されることが多いです。配送サービスの仕様やポストの構造によって、受け入れられる厚さの上限が異なるため、ここを正しく理解しておくことが重要です。
現在、最も基準とされているのが「厚さ3cm以内」です。これは、クリックポストやゆうパケットといった主な配送サービスが、3cmを上限に設定しているためです。また、日本郵便が設置している街中の赤いポストも、厚さ3cmまでを基準に設計されているものが多く見られます。これを超えると、投函口に入らなかったり、ポストの中で詰まってしまうリスクが出てきます。
一方、4cmや5cmの荷物についても、「絶対に無理」というわけではありません。公共の大型ポストや、比較的新しい集合ポストなどでは、厚さ4cm程度であればスムーズに入るケースもあります。私が以前利用した某マンションのポストでは、4.2cmのクッション封筒がスムーズに投函できました。ただし、これは例外的なケースであり、常に投函可能とは限りません。特に、旧型のポストやデザイン重視の戸建て用ポストでは、3cmでもギリギリのことがあります。
こうして考えると、3cmは安全圏、4cmは条件付き、5cmはかなり限定的という認識が現実的です。投函できなかった場合には、郵便局の窓口に持ち込むか、レターパックプラスや宅配便などの別手段を検討する必要があります。
このように、配送サービスとポストの構造は密接に関係しています。厚さの確認を怠ると、差し戻しや遅延といったトラブルの原因になりかねません。事前に厚みを測り、投函口の仕様をチェックすることで、安全でスムーズな発送につながるでしょう。
郵便ポストに厚み4センチの荷物は投函できる?実例で検証

郵便ポストに厚さ4センチの荷物を投函できるかどうかは、多くの人が直面する悩みの一つです。特に、フリマアプリやネット通販を利用する際に「この荷物、ポストに入るかな?」と気になることがあるでしょう。
私が実際に試した例では、厚み4センチの荷物がスムーズに入るかどうかは、ポストの種類によって大きく異なっていました。例えば、日本郵便が設置している赤いポストの中でも、「大型サイズ」と呼ばれるタイプであれば、横幅33cm・高さ約4cmの投函口があり、比較的余裕を持って投函できました。中身は文庫本2冊を入れたクッション封筒で、計測すると約3.8cmの厚さでしたが、少し押し込むようにすれば問題ありませんでした。
ただし、戸建て住宅に多く見られるスリットタイプの郵便ポストでは、同じ荷物が途中で詰まり、結局無理に入れずに持ち帰ることになった経験もあります。スリットタイプのポストはデザイン重視の傾向が強く、厚みよりも見た目のスマートさを優先しているため、3cmを超える荷物は入りにくいことが多いです。
また、マンションの集合ポストでも、築年数によって対応力が異なります。築浅の物件に設置されていた大型ポストでは、4.1cmまでの厚さに対応していた一方で、築20年以上の集合ポストでは3cm未満でも入口で詰まるケースが見受けられました。
このような実例から分かるのは、4cmという厚さは「入るかどうかの分かれ目」だということです。一般的な感覚で言えば、ややリスクがあるサイズです。無理に押し込むと、ポスト内部で詰まったり、他の郵便物に損傷を与えてしまうおそれもあるため注意が必要です。
ここでおすすめしたいのは、発送前に自宅のポストや投函予定のポストの口のサイズをメジャーで測っておくことです。可能であれば、郵便局やメルカリガイドなどで「ポスト対応サイズ」が掲載された情報を確認すると、より正確な判断ができます。
家のポストのサイズは何センチ?設置基準と確認方法
家に設置する郵便ポストのサイズは、意外と知られていない要素の一つです。しかし、ポストの口の大きさや内部容量は、日常の郵便受け取りの利便性を大きく左右します。ここでは、家庭用ポストの一般的なサイズと、設置時に確認すべきポイントについて詳しく解説します。
まず、家のポストにおける「サイズ」というのは、大きく分けて3つの側面があります。1つ目は投函口の横幅と高さ、2つ目はポスト本体の奥行きや容量、3つ目は取り出し口の大きさです。これらがバランスよく設計されていないと、大きめの郵便物が入らなかったり、取り出しが不便になったりすることがあります。
投函口について言えば、一般的な戸建て用ポストでは横幅25〜30cm、高さ2.5〜3.5cm程度が標準です。このサイズであれば、定形郵便やA4の封筒は問題なく入る設計になっています。ただし、ポストによってはデザイン優先でさらに狭くなっていることもあり、特に厚手のカタログやDMが入りきらないという声も少なくありません。
ここで設置基準についても触れておきましょう。日本郵便が推奨する設置高さは、地面から投函口までの高さが1.0〜1.2m前後です。これは、郵便配達員が腰をかがめずに投函できるよう配慮された高さであり、実用性と安全性を考慮したものとなっています。また、屋外に設置する場合は、雨風対策として防水機能や密閉性が高いものを選ぶことも重要です。
そしてもう一つは確認方法についてです。ポストを購入する前には、スペック表をよく確認し、「投函口サイズ」「対応サイズ(A4可、角形2号可など)」の記載があるかどうかを見極めましょう。すでに設置しているポストであれば、定規やメジャーを使って、横幅・高さ・奥行きを計測し、自分が受け取りたい荷物のサイズと比較してみることが大切です。
特に最近は、ネット通販やフリマアプリを活用する機会が増え、A4やそれ以上のサイズの郵便物が頻繁に届く家庭も多くなっています。そのため、設置済みのポストが自分のライフスタイルに合っているかどうか、定期的に見直すこともおすすめです。
郵便ポスト何センチ超えたらNG?ゆうパケットやメルカリ配送の対処法

- ゆうパケットポストの厚さ制限は何センチ?配送ルールの基礎
- 郵便ポスト4センチ・5センチは対応可能?ケース別の判断基準
- ゆうパケットポストで3cm超えても大丈夫?サイズ超過の影響
- ゆうパケットポストの厚さ7cm対応ポストはどこ?大きいポスト設置場所
- 郵便ポスト何センチ メルカリ便で注意すべきポイント
- 厚さ3cm以上の郵便物はどう送る?レターパック・宅配便との比較
ゆうパケットポストの厚さ制限は何センチ?配送ルールの基礎
ゆうパケットポストを利用する際に、最も重要なポイントの一つが「厚さ制限」です。荷物が基準をわずかに超えるだけでも、配送不可となるケースがあるため、事前の確認が欠かせません。
この配送サービスにおける厚さの上限は、「3cm以内」とされています。これは日本郵便が明確に定めているルールで、ポストにスムーズに投函できること、また自動仕分け機に通す際の物理的制約を踏まえて設定されています。ポストに入れられる最大サイズは、縦34cm・横25cm・厚さ3cm・重量1kg以内とされており、主に書類や薄型のグッズ、衣類などの発送に適しています。
ただ単にポストに入れば良いというわけではありません。厚みが3cmを少しでも超えてしまうと、規格外とみなされ、差し戻しや配達遅延の原因となります。実際、厚さ3.2cm程度の荷物を送ったところ、ポストにはなんとか入ったものの、後日「規格外のため返送」となった事例もあります。このため、厳密な厚さ確認が必要です。
私は実際に、発送前にメジャーやスケール定規で測ったうえで、100円ショップなどで販売されている「厚さ測定スケール」を使ってチェックすることをおすすめします。これは、ポスト投函できるかどうかを実際に通して確認できるツールで、非常に重宝されています。
このような配送ルールを正しく理解し、守ることによって、トラブルのないスムーズなやり取りが可能になります。特にメルカリなどのフリマサービスでは、発送ミスが信用問題に直結するため、正確なサイズ確認が信頼を得るカギにもなるでしょう。
郵便ポスト4センチ・5センチは対応可能?ケース別の判断基準
郵便ポストに厚みのある荷物を入れたいとき、「4センチや5センチの厚さでも入るのか?」と不安になることは多いものです。実際のところ、対応の可否はポストの種類や構造、設置状況によって異なります。
まず公共の郵便ポスト、特に日本郵便が設置している赤いポストについて見てみましょう。これらのポストには複数のタイプが存在し、その中でも大型のタイプであれば、投函口の高さが4cm程度確保されているものもあります。この場合、厚さ4cmの荷物がぎりぎりで入ることもありますが、厚さ5cmとなると、多くの場合で投函できません。理由は、内部構造に厚みのある荷物が引っかかるリスクがあるため、郵便局側が安全性を考慮して3cmまでと案内しているからです。
一方、戸建て住宅やマンションに設置されている家庭用ポストでは、サイズのばらつきが大きくなります。最近の新築物件や通販利用を前提とした住宅では、厚さ4cm以上の荷物にも対応できるワイドスリットのポストを採用しているケースがあります。実際に、私の知人宅では、厚さ4.5cmのクッション封筒を入れてもスムーズに収まりました。しかし、築年数の古い住宅やコンパクトなポストでは、3cmを超えるだけで入口に引っかかることも珍しくありません。
ここからわかるのは、「4cm程度なら条件付きで可能、5cmは基本的に不可」というのが現実的な判断基準になるということです。判断に迷う場合は、ポストの投函口の横幅と高さを実際にメジャーで測るのが確実です。投函時に無理やり押し込もうとすると、他の郵便物に損傷を与えたり、ポスト内部で詰まったりする原因になりますので、慎重に判断しましょう。
このように、ポストの構造をよく理解し、自分の投函環境に合った荷物サイズで利用することが、安全でスムーズな郵便利用につながります。
ゆうパケットポストで3cm超えても大丈夫?サイズ超過の影響

ゆうパケットポストを利用する中で、「少しぐらい厚みが超えていてもバレないのでは?」と思ってしまうことはないでしょうか。しかし、3cmを超えた荷物を無理に投函することは、さまざまなリスクを伴います。
まず、公式にはゆうパケットポストの厚さ制限は「3cm以内」と明記されています。これは見た目や手触りではなく、実際に機械測定された結果で判断されるため、1〜2mmの違いであってもアウトと判断されることがあるのです。また、ポストに入ったからといって受理されるわけではなく、郵便局での集荷・仕分け段階で再計測が行われ、そこでオーバーしていると「規格外」として差し戻しや返送になるケースがあります。
実際、私は過去に厚さ3.1cmの荷物をゆうパケットポストに投函したことがあります。当時は外装がやや柔らかく、押せば入る状態だったため問題ないと思っていたのですが、数日後に「配達不可・サイズ超過により返送」となってしまいました。しかも、返送までに日数がかかり、相手側との取引トラブルにも発展してしまいました。
このため、仮に3cmをほんの少し超えていても「大丈夫だろう」と考えるのは避けるべきです。メルカリなどのフリマアプリで使う場合は特に、取引の信頼性が重要になるため、リスクを負うメリットはほとんどありません。
こう考えると、安全に取引を進めるためには、厚さ3cm以内を厳守することが最善の選択です。測定の際には、荷物全体を平らに整えたり、梱包材を最小限に抑えるなどの工夫も有効です。また、3cmをどうしても超える場合は、最初からレターパックプラスや宅配便などの他の配送方法を選ぶことをおすすめします。
いずれにしても、厚さ制限を軽視すると、配達遅延や返送などのトラブルが発生する可能性が高くなります。ゆうパケットポストを安心して使うためにも、厚みの確認と丁寧な梱包を徹底しましょう。
ゆうパケットポストの厚さ7cm対応ポストはどこ?大きいポスト設置場所
ゆうパケットポストは基本的に厚さ3cmまでという制限がありますが、実際には「7cmの荷物も入れたい」と考える人も少なくありません。特に厚みのある商品や、クッション材を使った梱包をする場合には、3cmという制限はかなり厳しく感じられるでしょう。そうしたニーズに応えるかのように、一部の大型ポストでは、7cm相当の荷物でも対応できるサイズを備えたものが存在しています。
このように言うと、「じゃあどこにあるの?」という疑問が湧いてくるかもしれません。現在の私が確認している限り、大型サイズのゆうパケットポストが設置されている主な場所は、郵便局の敷地内、または大型ショッピングモール、ドラッグストア、主要駅周辺の郵便ポストなどが中心です。例えば、都内の主要郵便局には、3cm以上の厚みでも受け付け可能な専用の差入口が設けられているケースがあります。また、イトーヨーカドーやイオンなどの大型商業施設にも、ゆうパケット専用ポストが併設されていることがあります。
ただし、すべてのポストが7cmに対応しているわけではありません。そのため、出かける前に日本郵便が提供している「ゆうパケットポスト設置場所検索」などの公式サービスを活用するのが有効です。検索結果では「厚さ7cm対応」と明記されているポストのみを絞り込める機能があり、時間や労力を無駄にせずに済みます。
一方で、ポストに無理やり入れるのは避けたほうが賢明です。仮に投函できたとしても、集荷時に規定外と判断されて返送されるリスクがあります。また、他の郵便物にダメージを与えてしまうおそれもあり、モラルの面からも問題です。
このような理由から、厚さ7cmの荷物を発送したい場合は、「設置場所を事前に調べる」「対応ポストを選ぶ」「無理な投函はしない」の3点を意識しておくとよいでしょう。
郵便ポスト何センチ メルカリ便で注意すべきポイント

メルカリ便を使って郵便ポストに商品を投函する場合、「ポストのサイズにちゃんと入るのか?」という確認が欠かせません。ポストのサイズは地域や設置環境によって異なるため、一律で「大丈夫」とは言い切れないのが実情です。
多くの人が使っている「ゆうゆうメルカリ便」では、ゆうパケットという配送方法を選ぶと、厚さ3cm以内・長辺34cm以内・重さ1kg以下という条件が課されています。つまり、商品そのものに加えて、封筒やクッション材などの梱包込みでこのサイズを超えてはいけないということです。投函するポストの投函口も、おおむね「横幅33〜34cm・高さ3〜3.5cm」となっているため、わずかな差でも入らなくなることがあります。
このため、厚さや横幅を出発点に考えるのではなく、ポストの構造自体を確認してから発送を計画することが重要です。例えば、スリット型のポストでは、外から見える開口部よりも内側が狭くなっていることがあり、「入ったと思ったら引っかかってしまった」というトラブルが起きがちです。実際に私の知人は、厚さ3.1cmの商品をメルカリで発送しようとし、無理に押し込んで中で詰まらせてしまったことがあります。このようなケースでは、最悪ポスト自体が破損する恐れもあります。
また、注意すべきポイントとして「差出期限」も挙げられます。メルカリ便では、コンビニや郵便ポストでの発送が24時間以内と定められており、QRコードの有効期限が過ぎると使えなくなります。ポストに入らず出直すことになれば、タイミングによっては期限切れになる可能性もあるのです。
したがって、メルカリ便を郵便ポストから送る際は、「荷物の厚さ・横幅の確認」「ポストの構造把握」「投函期限の管理」をセットで行うように心がけましょう。たとえ些細なことのように思えても、発送トラブルの大半はこのような基本的な確認不足によって起きています。
厚さ3cm以上の郵便物はどう送る?レターパック・宅配便との比較
厚さ3cmを超える郵便物を送りたい場合、通常のポスト投函では難しくなるため、代替手段を検討する必要があります。特に、ネット通販やフリマアプリでの取引が増えている今、3cmの制限を超えるシーンは珍しくありません。
このような場合に便利なのが「レターパックプラス」と「宅配便」です。レターパックプラスは、日本郵便が提供しているサービスで、専用封筒を購入して使う仕組みです。全国一律料金で、厚さや重さに制限がなく、最大4kgまで対応可能です。封筒が閉まれば送れるという柔軟な仕組みのため、3cmをわずかに超える程度であれば問題なく利用できます。ただし、ポストには投函できず、郵便窓口に持ち込むか、対面で手渡しする必要があります。
一方、宅配便(ヤマト運輸・佐川急便・日本郵便のゆうパックなど)は、サイズと重量に応じて料金が決まり、厚さの制限も基本的には設けられていません。大きさや重量の自由度が高く、壊れ物や高額品にも対応しているため、安全性を重視したいときに向いています。ただし、送料が高くなりやすいというデメリットがあるため、コストを抑えたい人にとっては選びづらい面もあります。
例えば、厚さが4cm〜6cm程度で軽いものを送りたい場合は、レターパックプラスがコストパフォーマンスの高い選択肢になります。逆に、厚みがあるだけでなく重量も重たい、あるいは梱包がかさばるといった場合には、宅配便の方が安心です。
このように考えると、3cmを超える郵便物の配送には「サイズ・重量・安全性・料金」のバランスを見ながら判断する必要があります。すべての荷物に万能な方法は存在しないため、送りたいものの性質や相手とのやり取りの重要度によって、最適な手段を選ぶことが求められます。
郵便ポスト何センチまで入るかを理解する総まとめ

- 多くの郵便ポストはA4サイズ・厚さ3cm以内の郵便物に対応している
- 古い住宅や集合ポストは3cm超の荷物に非対応のケースが多い
- 公共ポストの投函口は横幅30〜34cm・高さ3.5〜4cmが一般的
- 戸建て用ポストは投函口が小さく、幅25cm・高さ2.5〜3cmが目安
- 集合ポストの投函口は幅26〜30cm・高さ3cm前後に設計されている
- 家庭用ポストの投函口サイズは機種によって大きく異なる
- 一部の大型公共ポストは4cm程度の厚さにも対応している
- スリット型ポストはデザイン優先で厚みのある荷物が入りにくい
- 3cmは安全圏、4cmは条件付き、5cmは投函困難とされる
- ゆうパケットポストは厚さ3cm以内・縦34cm・横25cm・1kg以内に対応
- 厚さ3.1cm以上はポスト投函後でも返送されるリスクがある
- 7cm対応ポストは郵便局や大型商業施設に限定的に設置されている
- メルカリ便のポスト利用ではサイズだけでなく差出期限にも注意が必要
- 3cmを超える郵便物にはレターパックプラスや宅配便が適している
- 投函口サイズを測定・確認することが発送トラブル防止につながる
関連記事