「切手で支払いできるもの」と検索しているあなたは、きっと家に余っている切手を何とか有効活用できないかと考えているのではないでしょうか。あるいは、現金を使わずに済ませたい場面で、切手が使えるのかどうかを知りたいのかもしれません。
実は、切手は郵便関連の支払いを中心に、一部の場面で現金の代わりに使うことができます。しかし、どこでも自由に使えるわけではなく、利用できる範囲やルールには細かな制限があるため、正しい知識が欠かせません。知らずに使おうとすると、窓口で断られたり、せっかくの切手を無駄にしてしまうこともあるのです。
この記事では、切手で支払いが可能な商品やサービス、その具体的な使い方、注意点までを幅広く紹介します。郵便局での対応や通販・店舗での実例、さらには切手の換金方法や仕訳処理まで、初めての方にも分かりやすく丁寧に解説しています。
切手を賢く使い切るために、そしてちょっと得する知識としても役立てられる内容です。最後まで読めば、あなたの疑問がスッキリと解消されるはずです。ぜひ、読み進めてみてください。

💡記事のポイント
- 切手で支払いできる具体的な商品やサービスの種類
- 郵便局での切手使用に関するルールや注意点
- 切手が使える場所や使えない場面の違い
- 切手の換金や経理処理の方法とその限界
切手で支払いできるものとは?使い道・対象・最新情報まとめ

- 切手で支払いできるものは何ですか?
- 切手で買えるもの一覧|レターパック・年賀状など
- 郵便局窓口で切手が使えるサービス
- ゆうパックの切手払いは廃止?最新の対応状況
- 切手で支払いできる店|日常生活での実例紹介
- 切手はお金に変えられますか?換金・交換の方法と注意点
切手で支払いできるものは何ですか?
切手は郵便料金を前払いするための証書として古くから使われてきましたが、現在でも「一部の支払い手段」として活用することができます。つまり、切手は郵便関連サービスに限定されますが、現金の代替として使用可能な場面が確かに存在しています。
まず大前提として、切手は法律上の「通貨」ではないため、コンビニやスーパーといった一般の店舗での会計には使えません。また、電子マネーやクレジットカードと異なり、金融取引にも使えないという制約があります。そのため、何でもかんでも切手で支払えると考えてしまうと、期待外れになるケースもあるでしょう。
一方で、郵便局では特定のサービスや商品の購入時に、切手を代金の支払い手段として受け付けている場合があります。たとえば、レターパックや年賀状、はがき、封筒などがその対象です。また、郵便窓口で取り扱っている各種手数料や送料も、切手で支払うことができます。
とはいえ、すべての郵便局が同じ対応をしているとは限りません。実際、局ごとの対応に差があったり、特定のサービスでは「現金のみ可」と明記されていたりすることもあります。そのため、支払い前には確認を取るのが無難です。
このように考えると、切手はあくまでも「限定的な支払い手段」として位置付けられるものであり、日常的な買い物の手段とは一線を画しています。ただ、使い道を正しく理解していれば、無駄にせずに賢く活用することも可能です。
切手で買えるもの一覧|レターパック・年賀状など
切手で購入できるものには、主に郵便局で提供される商品やサービスが含まれます。ここでは代表的なものを具体的に紹介しながら、それぞれの特徴や注意点について解説します。
まず、もっとも代表的な例が「レターパック」です。レターパックは、全国一律料金で利用できる配送サービスであり、切手を使ってその料金を支払うことが可能です。レターパックライトやレターパックプラスなど種類が複数ありますが、基本的には郵便窓口で販売されており、切手による支払いが認められているケースが多く見られます。
次に、年末の風物詩である「年賀状」も、切手で購入できる商品のひとつです。特に大量に必要になる場合、不要な切手を活用すれば現金を使わずに済むというメリットがあります。さらに、通常の官製はがきや各種封筒、郵送用のラベル・シール類も対象となることが多いため、郵便関連の備品を一通り切手で揃えることが可能です。
ただし、近年では一部の商品について「現金のみの取り扱い」となっている場合もあるため、事前の確認は欠かせません。例えば、ゆうパックの専用箱や一部の記念商品は、切手での購入ができないことがあります。また、店舗によっては、釣銭対応が困難なことから高額な買い物への切手支払いを拒否されることもあります。
このように、切手で購入できる商品は意外と多いものの、利用できる範囲には制限があるため、実際の購入時には「何が対象か」「何枚まで使えるか」といった条件を確認しておくことが重要です。
郵便局窓口で切手が使えるサービス
郵便局の窓口では、いくつかのサービスにおいて「切手での支払い」が認められています。これは現金を使わずに、既に手元にある切手を有効活用できる方法として、知っておいて損はない情報です。
まず、最も一般的に利用されているのが、各種「郵便料金」の支払いです。具体的には、定形郵便・定形外郵便の送料、書留や速達といったオプションサービスの追加料金などが該当します。こうしたサービスを利用する際に、窓口で切手を提示すれば、そのまま料金として差し引いてもらえることが多いです。
また、各種発送サービスにかかる料金の支払いにも、切手が使えるケースがあります。レターパックの購入や、簡易書留・特定記録などのオプションを付けた郵便物の差し出しも含まれます。特に企業や団体などで大量の発送を行う場合、あらかじめ購入しておいた切手を使って一括で処理することで、支出を抑える効果も期待できます。
一方で、すべての郵便局窓口が同じ対応をしているわけではなく、切手による支払いに一部制限を設けているケースもあります。例えば、ゆうパックの料金については、以前は切手での支払いが認められていたものの、現在は多くの局で現金のみの取り扱いとなっています。このような変更は突然行われることもあるため、最新情報を確認する習慣が大切です。
なお、切手を使って支払う際には、額面の合計が不足しないように準備しておくこともポイントです。窓口では釣銭を出すことができないため、必要な金額ぴったりか、それを上回る切手を持参する必要があります。
このように考えると、郵便局窓口では切手を活用できる場面が多く存在しており、現金の持ち合わせがない場合や、余った切手の消化手段として有効に使うことができます。ただし、その場その場でのルールをしっかり確認し、無理のない範囲で活用することが肝心です。
ゆうパックの切手払いは廃止?最新の対応状況

かつては、ゆうパックの送料を切手で支払うことが一般的に認められていました。たとえば、贈り物やフリマサイトでの商品発送など、個人でも法人でもゆうパックを使う機会は多く、その際に「余った切手を使って送料を賄いたい」と考える人も少なくありませんでした。実際、郵便局の窓口で差し出す際に切手を貼って料金分を支払う方法が浸透していた時期もあります。
しかし、現在ではこの対応に変化が見られます。多くの郵便局では、ゆうパックの送料について「切手での支払いは不可」とする方針が取られるようになってきました。背景には、切手の再利用や換金性の問題、不正使用などのリスクがあると考えられており、日本郵便側でもその扱いを見直しているものと考えられます。特に高額な料金が発生する大型荷物や、頻繁に発送を行う事業者向けの発送では、現金またはキャッシュレス支払いを原則とする局が増えています。
これに加えて、現場の対応も一律ではなく、地域や郵便局によって多少の差がある点にも注意が必要です。ある局では「本来は不可だが、少額であれば便宜的に受け付けている」といった対応をしているケースもありますが、これはあくまで例外的な判断に過ぎません。特に2020年代以降、業務の標準化や不正防止の観点から、現金またはIC決済に一本化する動きが進んでいます。
このため、ゆうパックを発送する際に「切手で支払えるか」と考えたときは、まず事前にその郵便局へ直接確認することが重要です。公式サイトに記載がない場合でも、電話で聞けば最新の受付ルールを教えてもらえることが多いです。仮に支払いができないと分かった場合には、あらかじめ現金や電子マネーを用意しておく必要があります。
今後さらに切手による支払いの制限が強化される可能性もあるため、ゆうパックを頻繁に利用する人は、こうした変化を定期的にチェックしておくと安心です。
切手で支払いできる店|日常生活での実例紹介
切手は一般的に郵便局での利用を想定して発行されているものですが、実は一部の実店舗やサービスにおいても「支払い手段」として受け入れられることがあります。こうした場面では、現金の代わりに切手を使用することで、家に余っていた切手を活用できるというメリットがあります。
まず知られているのが、一部の個人経営の金券ショップや古物商です。こうした店舗では、切手をある程度の額面で「買い取り」してくれるだけでなく、商品の購入時に支払い手段として使えるケースもあります。もっとも、これは切手を「通貨」として受け取っているわけではなく、店側が独自に定めたルールのもとで「金券として扱っている」ことに由来します。実際、店舗によっては「80%の額面で換算して受け付けます」と明記されていることもあります。
また、対面ではなく郵送ベースの通販でも、まれに「切手支払いに対応」とうたう業者が存在します。主に地方の個人商店や、小規模のネットショップなどで見られる対応ですが、「代金相当額分の未使用切手を同封して郵送してほしい」といった形式が取られることが多いようです。こうした支払い方法は手間がかかるものの、現金を使わずに物品を入手したい人には便利です。
一方で、こういった店舗や業者は非常に限定的であり、大手チェーン店やコンビニ、スーパーなどで切手による支払いができることは基本的にありません。これは、会計システム上、金券での支払い処理が煩雑になることや、不正のリスク、監査対応の複雑さなどが要因です。したがって、日常的に切手を支払いに使うというのは、あくまで例外的な場面に限られると考えておいた方がよいでしょう。
これらを踏まえると、切手が使える店は存在するものの、どこでも使えるわけではないという現実があります。利用する際は、事前に店の公式情報を確認したり、問い合わせを行ったりすることが大切です。過去に使えたとしても、店舗ポリシーが変更されていることもあるため、最新の対応を確認してから利用するようにしましょう。
切手はお金に変えられますか?換金・交換の方法と注意点
切手はその性質上「金券」と似た扱いをされることがあり、「お金に変えられるのでは?」と考える方も少なくありません。確かに、現金に直接両替することはできませんが、一定の方法を取ることで、実質的にお金に近い価値に換えることは可能です。
まず最も一般的なのが、金券ショップやチケットショップでの「切手買取サービス」です。未使用の切手を額面の7割〜9割程度の金額で買い取ってもらうことができ、その場で現金を受け取ることができます。ただし、汚れや破れがあるもの、記念切手など一部のデザイン切手は買取対象外とされる場合があるため、状態や種類の確認が必要です。また、店舗によっては買取率が異なるため、複数の店で見積もりを取るのも一つの手です。
次に、郵便局での「交換制度」について触れておきます。切手やはがきは、所定の手数料を支払うことで、他の郵便商品に交換することが可能です。たとえば、古い切手を新しい額面の切手やレターパックに交換することができます。交換には1枚あたり5円の手数料がかかりますが、無駄なく使い切りたいときには有効な手段です。なお、現金への直接交換は郵便局では行っていないため、この方法は「実質的に金銭と同等の使い道に変える手段」として捉えるのが正確です。
一方で、ネットオークションやフリマアプリで切手を販売し、現金収入を得るという方法もあります。この場合、人気のある記念切手や、使い道の多い高額切手であれば、額面以上の価格で取引されることも珍しくありません。ただし、発送時のトラブルや送料の負担、手数料などを考慮する必要があります。出品者としてルールを守り、評価を下げないようにすることも重要なポイントです。
こうした選択肢を踏まえると、切手をお金に「直接変える」ことはできませんが、間接的に現金や現金同等物に変えることは十分に可能です。ただし、どの方法を選ぶにしても、それぞれの手間や手数料、換金率などをよく比較してから判断することが大切です。切手を無駄にせず、最大限に活用するためには、目的と状況に合った使い方を選ぶ工夫が求められます。
切手で支払いできるものの使い方と経理処理のポイント

- 切手で支払いのやり方|窓口・取引での流れ
- 切手で支払う際の仕訳処理|帳簿・会計での対応
- 切手で支払いできる通販サイト|活用できるシーンとは
- メルカリで切手払いは可能?出品者・購入者視点で解説
- 切手で購入できるものの具体例と注意点
- 現金の代わりに切手は使える?法律・慣習的な制約
切手で支払いのやり方|窓口・取引での流れ
切手を使って支払いをする際の方法は、想像以上に細かいルールが存在します。特に郵便局の窓口では、利用するサービスや商品の内容によって支払いの手順や注意点が異なってくるため、事前に手順を理解しておくことが重要です。
まず、切手による支払いが可能な場面は主に郵便関連サービスに限定されています。たとえば、定形・定形外郵便、書留、速達、レターパックの購入、年賀状やはがきの購入などが該当します。こういったサービスの利用時には、切手を料金分として窓口に提示することで、現金の代わりとして使用することができます。
実際の手続きでは、郵便局の窓口で「支払いに切手を使いたい」と伝えるだけで、特別な申請や書類提出は必要ありません。ただし、必要な料金と同額以上の切手を事前に用意しておくことがポイントになります。窓口では釣銭の返金対応が行われていないため、不足しないようにあらかじめ額面を揃えておくか、多めに持っていくと安心です。
さらに、貼ってある切手が複数種類・額面に分かれている場合でも、窓口で合算して処理してもらえることがほとんどです。とはいえ、あまりにも多くの枚数を持ち込むと対応に時間がかかるため、なるべく高額の切手を用意するなど、スムーズな支払いを心がけたいところです。
一方で、切手を商品購入の手段として使う場合、局によって対応が異なることがあります。特に地方の郵便局では「原則として現金のみ」としているケースや、「少額の場合に限り可」と制限を設けている場合もあります。そのため、支払い前に「この商品は切手で支払い可能か?」と確認することがトラブル防止につながります。
また、郵便局以外の場面で切手を使う場合、たとえば通販やフリマアプリなどでは、先方の指定に従って「封筒に必要分の切手を貼って送付」するなどの独自ルールがあることもあります。支払いに切手を使う際は、常に相手側のルールを優先する姿勢が求められます。
このように、切手による支払いは一見シンプルに見えますが、実際には場面や用途によって判断が分かれるため、丁寧な確認と準備が大切です。特に初めての方は、事前に郵便局に問い合わせたり、公式サイトで確認したりすることで、より安心して活用できるでしょう。
切手で支払う際の仕訳処理|帳簿・会計での対応
切手を使って料金の支払いを行った場合、その費用をどのように帳簿上で処理すればよいかは、特に個人事業主や小規模法人にとって関心の高いポイントです。切手は現金のように直接的な「通貨」ではありませんが、郵便料金や一部の商品購入に使えることから、会計上は特定の勘定科目で処理されることになります。
まず、事務的な支出に該当する郵便代や配送費に切手を使った場合、会計処理としては「通信費」として仕訳するのが一般的です。たとえば、郵便物を送るために100円分の切手を使った場合、以下のように帳簿に記載します。
通信費 100円/切手(または現金) 100円
この場合、「切手」という資産項目をあらかじめ管理している場合には、切手を減らす処理を行います。現金から直接購入して使ったのであれば「現金」として処理しても問題ありません。仕訳は企業ごとの会計方針や経理ソフトの設定によって若干異なるため、統一感を持って処理することが求められます。
一方、切手をあらかじめまとめて購入しておき、後日使用するようなケースでは「前払費用」や「貯蔵品」として一旦資産計上する方法もあります。たとえば、1,000円分の切手をまとめて購入した場合には、
貯蔵品(または前払費用) 1,000円/現金 1,000円
という形で記録し、実際に使用した際に「通信費」へ振り替える流れです。これにより、使った分だけを費用として計上することができ、帳簿上の正確性が保たれます。
ただし、切手の使用目的が通信費ではなく、たとえば商品や備品の購入などであった場合は、勘定科目もそれに合わせて変更する必要があります。誤ってすべて「通信費」として処理してしまうと、税務上の問題が生じる可能性もあるため注意が必要です。
さらに、記念切手や特殊な用途の切手を扱う場合には、単なる郵便料金以上の価値を持つこともあります。こういったケースでは、通常の切手とは異なる管理・評価が求められる場合があり、帳簿記載にも慎重さが求められます。
このように、切手で支払った際の仕訳は、一見すると単純に思えるかもしれませんが、実際には使用目的や取引形態によって適切な処理方法が変わってきます。正しく記録することで、経費の透明性が保たれ、確定申告や決算の場面でも安心です。迷った場合は、税理士や会計士に相談するのが確実です。
切手で支払いできる通販サイト|活用できるシーンとは
通常のネット通販では、クレジットカードやコンビニ払い、電子マネーなどが主な支払い手段となっていますが、中には「切手での支払い」を受け付けている通販サイトも存在します。特に、現金を使わずに商品を購入したい人や、手元に余った切手を活用したい人にとっては便利な選択肢となるでしょう。
まず最も多いのが、個人経営のネットショップや中小規模の通信販売事業者です。これらのショップでは、大手ショッピングモールに出店していない独自運営のサイトで、銀行振込や郵便振替と並んで「未使用切手での支払い可」と記載されていることがあります。このようなショップでは、商品代金相当の未使用切手を郵送し、それをもって支払い完了とするスタイルが一般的です。
たとえば、手作り雑貨や骨董品、地方の特産品などを取り扱うショップでは、「切手での支払いも対応可能」としているケースが見受けられます。特に、年配の方やネットバンキングを利用しない層にとっては、こうした柔軟な支払い方法が歓迎されているようです。
一方で、大手のECサイトや一般的なネットショップ(Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど)では、セキュリティや決済システムの関係から、切手による支払いは基本的に対応していません。そのため、こうした大手サイトでは、あくまで通常の電子決済手段を利用するのが前提となります。
このような切手支払い対応通販を利用する際には、いくつか注意点があります。まず、切手は原則「未使用」でなければなりません。また、額面の合計がぴったりでない場合は、過不足があっても返金されないことがあります。さらに、郵送による支払いのため、商品発送までに日数がかかることも念頭に置いておくべきです。
それでも、使い道に困っていた切手を有効活用できる点は大きな魅力です。支払い手段としての選択肢を広げたい方や、物々交換的な取引を楽しみたい方にとって、切手での通販購入は一つの手段として検討に値します。
以上のように、切手で支払いができる通販サイトは限定的ではありますが、探せば存在します。特にニッチな商品を取り扱うショップでは、柔軟な対応をしていることも多いため、気になる商品があれば「支払い方法に切手は可能か?」と問い合わせてみるのもよいでしょう。
メルカリで切手払いは可能?出品者・購入者視点で解説

フリマアプリ「メルカリ」は、多様な支払い方法に対応しており、利用者の利便性が非常に高いプラットフォームとして知られています。しかし、切手による支払いが可能かどうかは、ユーザーの間でも意外と誤解されやすいポイントです。
まず、公式にメルカリが提供している支払い方法には、「メルペイ」「クレジットカード」「コンビニ払い」「ポイント払い」「ATM支払い」などがありますが、「切手払い」はこの中に含まれていません。つまり、アプリ内で商品の購入をする際に、支払い手段として直接切手を使うことはできません。
しかし一方で、切手が全く使えないというわけではありません。購入者が出品者と事前に合意した場合に限り、「商品代金を切手で支払う」という取り決めを個別に交わすケースも存在します。たとえば、「メルカリではなく、個人間取引に切り替えて支払いたい」といった内容のやり取りがされることもあるようです。ただし、このようなやり取りはメルカリの利用規約に違反する可能性があり、推奨されていません。取引外での支払いはトラブルの元になりやすく、メルカリ事務局の補償対象外となるため、極力避けるべきです。
一方、出品者側として切手が関係してくるのは「発送コストの削減」という場面です。たとえば、商品発送時に日本郵便を使う場合、レターパックや定形外郵便の料金を「自分の持っている切手で支払う」という形で間接的に使うことができます。こうした使い方はルール違反ではなく、適切な方法であれば発送コストの節約手段になります。
このように考えると、切手はメルカリ内の「決済手段」としては使えないものの、出品者側の発送費として間接的に役立つ場面があります。ただし、利用者間での個別のやり取りで切手を送る・受け取るといった行為は、アカウント停止やトラブルのリスクがあるため、基本的には公式の支払い手段のみを使うことが安全です。
初心者であればあるほど、独自の支払い方法には手を出さず、ルールの範囲内で切手の活用方法を考えることが安心につながります。
切手で購入できるものの具体例と注意点
切手はあくまで郵便料金の前払い証書であるため、一般的な「お金」として広く使えるわけではありません。ただし、郵便局を中心に、切手を用いて購入できる商品やサービスは複数存在しており、正しく知っておけば無駄なく有効活用できます。
具体的な例として最も代表的なのが「レターパック」です。全国一律料金で送付できる便利な郵送パッケージで、切手を支払い手段として使用できます。次に挙げられるのが「はがき」「封筒」「年賀状」といった郵便用品です。これらは窓口で購入する際、必要な額面分の切手を提示すれば購入できるケースが多く見られます。
さらに、「簡易書留」「速達」「特定記録」といった郵便オプションも、切手での料金支払いが可能です。例えば、定形外郵便に簡易書留を付ける場合、合計金額を計算し、その分を切手で支払うことで発送できます。その他、収入印紙や、一部の郵便局で販売されている地域限定グッズ、記念切手などの購入にも使えることがあります。
ただし、こうした支払いにはいくつかの注意点も伴います。まず、切手での支払いが可能かどうかは、各郵便局の判断に委ねられる場合があるため、全ての商品やサービスが対象とは限りません。特に高額商品やゆうパック専用箱などは、現金のみとされることもあるため、事前確認が欠かせません。
また、切手での支払いは「釣銭が出ない」というルールがあるため、額面をぴったりにそろえるか、少し多めに持参しておくことが必要です。大量の低額切手を持ち込むと、処理に時間がかかったり、窓口対応を断られたりする場合もあるため、なるべく100円以上の切手を使うのが理想です。
このように、切手を使って購入できるものにはさまざまな種類がありますが、その活用にはルールとマナーが伴います。無駄にせず効率よく使うためにも、事前に対象商品と利用方法をしっかり確認することが、トラブル回避につながります。
現金の代わりに切手は使える?法律・慣習的な制約
切手は見た目や流通の仕組みから、一見すると「お金のように使えるのではないか」と考えてしまう人もいるかもしれません。しかし、実際には切手は日本国内において法定通貨としての地位を持っておらず、現金と同等に扱われるものではありません。
まず、法律上の立場から説明すると、切手は「通貨」ではなく「証紙」に分類されます。つまり、ある特定の用途、すなわち郵便料金の支払いに限定して使える“サービス利用券”のようなものです。したがって、切手を使ってスーパーやコンビニで商品を購入したり、飲食代金を支払ったりすることはできません。また、企業や自治体の会計でも、切手は現金と同列には扱われておらず、物品や役務の購入に直接使うことは制限されています。
一方で、慣習的には「金券」に近い形で流通している場面も見られます。たとえば、金券ショップでは切手を一定の買取価格で受け取り、現金化することができます。これにより、間接的に切手を現金に“換える”ことは可能です。ただし、額面そのままでの換金は難しく、買取価格は通常70〜90%程度に設定されているため、損をしないとは言い切れません。
さらに、個人間の取引においては、相手が同意すれば「代金を切手で支払う」という取り決めが成立することもあります。しかしこれは、あくまで双方の合意による“例外的な支払い手段”であり、一般に普及している手段ではありません。法人や商取引の現場では、こうした対応はまず行われませんし、税務的な裏付けをとるのも困難になります。
また、公共料金や税金、保険料といった公的な支払いにも切手は使用できません。これらはあくまで現金や指定された電子決済のみでの取り扱いとなっており、切手はそもそも受け付けられない対象です。
このように考えると、現金の代わりとして切手を用いることは、法律・制度・慣習いずれの観点から見ても非常に限定的です。日常生活の中で切手を現金のように使うのは現実的ではありませんが、郵便サービスの支払いなど適切な範囲で活用すれば、余った切手を無駄にせずに済ませることは可能です。
切手で支払いできるものを正しく理解するための総まとめ
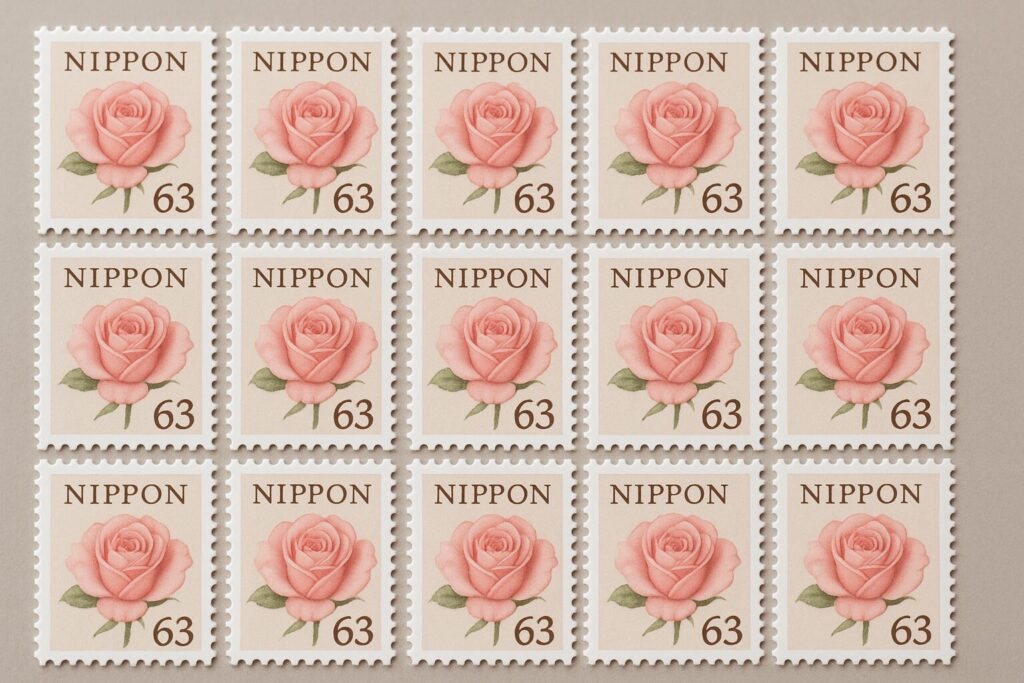
- 切手は郵便料金の支払いに使えるが、利用できる場面は主に郵便局内に限られる
- 郵便局ではレターパックやはがきなど、郵便商品を切手で購入することができる
- 年賀状や封筒、ラベル類といった郵便備品も、切手で支払える対象に含まれている
- 定形郵便や定形外郵便の送料も、窓口で切手を提示することで支払いが可能
- 書留や速達、特定記録などの追加サービス料金も、切手による支払いが認められている
- 郵便窓口で切手を使う場合は釣銭が出ないため、必要金額を正確に揃えて持参する必要がある
- 切手の取り扱い方は郵便局によって異なるため、事前に支払い可否を確認しておくと安心
- ゆうパックの送料を切手で支払う方法は、現在では多くの郵便局で廃止されている
- 金券ショップでは未使用の切手を額面の7〜9割程度で買い取ってもらうことができる
- 一部の小規模通販サイトでは、未使用切手の郵送による代金支払いを受け付けている場合がある
- メルカリでは公式に切手払いはできず、個別のやり取りによる支払いはルール違反となる
- 経理処理では、切手を使った支払いは主に通信費として仕訳されることが一般的
- 切手は通貨ではなく証紙扱いのため、法律上は買い物などの支払い手段として認められていない
- 一部の個人商店や古物商では、独自ルールにより切手を金券として受け取ることがある
- 切手の利用には使える場面と制限を理解し、目的に合った使い方を意識することが大切
関連記事


