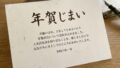荷物を送るときに「できるだけ安全に届けたい」と考える人は少なくありません。特に高額な品物や重要な書類を郵送する場合、通常の配送サービスだけでは不安を感じる方も多いでしょう。
そこで注目されているのがセキュリティゆうパックです。郵便局が提供するこの特別なサービスは、専用のラベルや伝票を用いて厳重に取り扱われ、通常のゆうパックとは異なる仕組みで荷物を守ります。そのため、安心感を重視する多くの利用者から選ばれています。
しかし、セキュリティゆうパックには料金体系や補償の上限、利用できるケースなど、事前に知っておくべきポイントがいくつもあります。実際に利用しようとしても「料金はいくらなのか」「どれくらいの日数で届くのか」「現金は送れるのか」といった疑問を持つ人は少なくありません。
本記事では、セキュリティゆうパックの特徴や仕組みをはじめ、料金や補償額、通常のゆうパックとの違いまでを分かりやすく解説します。最後まで読むことで、安心して利用するための判断材料が得られるはずです。
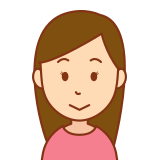
💡記事のポイント
- セキュリティゆうパックの料金と補償の仕組みと上限の考え方
- セキュリティゆうパックの元払いと着払いの使い分けとラベルの選び方
- セキュリティゆうパックの日数の目安と遅延を避けるための確認方法
- セキュリティゆうパックと通常のゆうパックとの違いと賢い使い分け
セキュリティゆうパックとは?安全性と料金の仕組み

- セキュリティゆうパックとは?サービス概要
- セキュリティゆうパックの料金はいくらですか?コストの比較
- セキュリティゆうパックはいくらまで保障されるのか?補償上限
- セキュリティゆうパックの元払いと支払い方法について
- セキュリティゆうパックは着払いで利用できるのか?
- セキュリティゆうパックの日数はどれくらいか?配送スピード
セキュリティゆうパックとは?サービス概要
セキュリティゆうパックは、日本郵便が提供するゆうパックに「セキュリティサービス(書留相当の取扱い)」を付加した特別な配送方法です。通常のゆうパックと比較して、より厳格な管理体制のもとで荷物を取り扱い、万が一の事故や紛失に備えた補償制度が強化されています。
具体的には、差し出しから配達までの全ての過程を郵便局側で記録する仕組みが導入されています。これにより、引受から到着までの経路追跡が一層厳密に行われ、配送の信頼性が大きく高まります。利用可能な窓口は郵便局または集荷サービスに限定され、コンビニからは差し出せません。これはセキュリティを担保するための重要な制約です。
対象となる荷物は高額品や重要な書類が中心で、例えば貴金属、美術品、重要契約書など「損害が発生した場合に高額な補償を要する品物」が典型例です。ただし、現金はゆうパック全般で禁止されており、送付できません。現金を郵送する必要がある場合は、現金書留を利用することになります(出典:日本郵便公式サイト https://www.post.japanpost.jp/service/security/
こうした背景から、セキュリティゆうパックは個人利用者よりも、金融機関や企業など高額商品を日常的に扱う法人での活用が多い傾向がありますが、個人でも安心を優先する際には有効な選択肢となります。
セキュリティゆうパックの料金はいくらですか?コストの比較
料金体系は、通常のゆうパック運賃に「セキュリティ加算料金420円(税込)」を上乗せする方式です。例えば、東京都から大阪府まで60サイズ・2kgの荷物を送る場合、通常ゆうパックの運賃はおよそ930円(2025年現在)。ここに420円を追加するため、セキュリティゆうパックの総額は1,350円前後となります(出典:日本郵便 料金表 https://www.post.japanpost.jp/service/you_pack/charge/ichiran.html
割引制度も通常のゆうパックとほぼ同様に適用されます。代表的なものは以下の通りです。
- 持込割引:郵便局窓口に直接持ち込むと1個につき120円割引
- 同一あて先割引:同じあて先に1年以内で繰り返し送ると60円割引
- 複数口割引:同一あて先へ一度に2個以上差し出すと60円割引(元払いのみ適用)
このため、大量発送や定期利用の場合、加算料金を含んでもある程度コストを抑えられる工夫が可能です。ただし、セキュリティゆうパックはコンビニから発送できないため、持込割引や複数口割引の適用は郵便局または集荷限定となる点に注意が必要です。
総じて、料金は通常のゆうパックより高くなるものの、補償や管理体制を考慮すると「追加コスト以上の安心を購入している」という位置づけが適切だといえます。
セキュリティゆうパックはいくらまで保障されるのか?補償上限
通常のゆうパックでは、損害補償の上限額は原則30万円です。これに対して、セキュリティゆうパックは補償額が引き上げられ、50万円までの実損額が賠償対象となります。発送時には、専用のラベルに「損害要償額」を明記する必要があります。
この金額は差出人の任意ではなく、荷物の内容品の「時価」や「購入価格」を上限に設定されます。つまり、10万円相当の商品を誤って50万円と記載しても、その金額が補償されるわけではなく、実際の価値に基づいて補償額が決まります。
補償対象となるのは、配送中の紛失や破損などの事故です。ただし、天災や差出人の不注意による破損、禁止物の送付などの場合は補償対象外となります。この点は、一般の保険契約と同様に免責事項として明確に規定されています(出典:日本郵便「セキュリティサービス規定」
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/security/index.html
特に高額品を送る際は、受取人が補償範囲や条件を十分に理解しているか確認しておくと安心です。法人利用では、契約先への納品トラブルを回避するため、補償内容を事前に取引契約に盛り込むケースも少なくありません。
セキュリティゆうパックの元払いと支払い方法について

セキュリティゆうパックを利用する際、最も一般的な支払い方法が元払いです。元払いとは、荷物を差し出す時点で差出人が送料を支払う方法で、郵便局窓口または集荷サービスの際に精算します。
元払いで利用する場合、セキュリティゆうパックの料金は通常のゆうパック基本運賃に420円のセキュリティ加算料金を上乗せした金額になります。例えば、80サイズの荷物を東京から福岡へ送る場合、通常の運賃が1,500円程度であれば、合計は1,920円前後となります(出典:日本郵便 料金表 https://www.post.japanpost.jp/service/you_pack/charge/ichiran.html
割引制度についても、元払いであれば適用範囲が広いのが特徴です。複数口割引は元払い限定で利用でき、同一あて先に複数個口を同時発送する際、1個あたり60円の割引が適用されます。また、持込割引や同一あて先割引も適用され、企業や小売業者がまとめて発送する場合には、実質的なコストを抑える効果が期待できます。
さらに、ビジネス利用者は郵便局との契約に基づく請求書払いを選択できる場合もあり、月末締めで支払う方式を導入する企業も少なくありません。これにより、大量発送を行う法人はキャッシュフローを安定させつつセキュリティゆうパックを効率的に利用することが可能です。
セキュリティゆうパックは着払いで利用できるのか?
セキュリティゆうパックは、元払いだけでなく着払いでも利用できます。着払いとは、荷物を受け取る側が配達時に送料を支払う仕組みで、特に法人間取引や返品対応で多く利用されます。
着払いで利用する場合は、通常のゆうパック着払い伝票を使用し、そこにセキュリティサービスを付加することになります。この際、セキュリティ専用の元払いラベルは使用せず、必ず「ゆうパック着払い専用伝票」を用いる点に注意が必要です。セキュリティサービスの加算料金420円は、元の送料と一緒に受取人が支払う形となります。
ただし、割引制度には制約があります。複数口割引は元払い限定のため、着払いには適用されません。持込割引や同一あて先割引も条件によっては利用できない場合があり、コスト面で元払いに比べて不利になるケースがあります。そのため、着払いを選ぶ際は、利便性を優先するのか、コストを重視するのかを事前に検討することが大切です。
また、代金引換サービスと併用する場合、引換金額が30万円を超えると自動的にセキュリティサービスを付けることが義務付けられています。このルールは、郵便局が配送の安全性を担保するために定めている規定です(出典:日本郵便「代金引換サービスのご案内」 https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/daibiki/
セキュリティゆうパックの日数はどれくらいか?配送スピード
セキュリティゆうパックの配送日数は、基本的に通常のゆうパックと同一です。つまり、東京都内から関西圏や九州の主要都市へは通常1~2日、北海道や沖縄県など遠隔地へは2~3日が目安です。
ただし、セキュリティサービスを付けた荷物は書留相当の取り扱いとなるため、通常よりも引受や配達時に確認作業が増えます。そのため、繁忙期や取扱量が多い時期には、まれに半日程度の遅延が生じることがあります。利用前に日本郵便が提供する「お届け日数を調べる」検索システム(https://www.post.japanpost.jp/deli_days/)で事前確認することが推奨されます。
また、航空輸送の制限にも注意が必要です。セキュリティゆうパックの対象品目に危険物や航空搭載不可の荷物が含まれる場合、陸送に切り替えられるため、配送日数が延びる可能性があります。特に沖縄や離島宛ての場合は、1~2日以上の遅れを見込んでおくことが現実的です。
さらに、天候や自然災害による影響も考慮が必要です。日本郵便は公式サイトで「遅延情報」を随時更新しており、台風や大雪の際には配達計画に影響が出ることがあります。高額品や納期厳守の荷物を送る際は、こうした外部要因も踏まえて発送計画を立てることが重要になります。
セキュリティゆうパックとゆうパックの違いと活用方法

- セキュリティゆうパックとゆうパックの違いについて
- ゆうパックのセキュリティラベルの役割
- ゆうパックのセキュリティ伝票の書き方
- 郵便局のセキュリティパックとの関係
- セキュリティゆうパックで現金は送れるのか?禁止物と注意点
- 利用者の体験談とおすすめの使い方
セキュリティゆうパックとゆうパックの違いについて
ゆうパックとセキュリティゆうパックは、基本的には同じ配送ネットワークを利用しています。しかし、その取扱い方法や補償制度には大きな違いがあります。
まず、補償額の上限が異なります。通常のゆうパックでは損害賠償の上限は30万円ですが、セキュリティゆうパックでは50万円まで補償されます。この違いは、高額品や壊れやすい品物を送る際に大きな安心材料になります。
さらに、取り扱い方法にも差があります。セキュリティゆうパックは書留郵便と同等の厳格な管理が行われ、差出から配達までの送達過程をすべて記録します。これにより、万が一事故が起きた場合でも、どの段階で問題が発生したのかを追跡しやすくなっています。
また、利用可能な場所も違います。通常のゆうパックは郵便局やコンビニから差し出すことができますが、セキュリティゆうパックは郵便局窓口と集荷に限定されます。これは、セキュリティ管理を徹底するために設けられた制約です。
最後に、料金体系にも違いがあります。通常のゆうパックに比べ、セキュリティゆうパックは加算料金420円が必ず必要となります。このため、コスト面では高くなりますが、安全性と信頼性を重視する利用者にとっては必要な投資だと考えられます。
(出典:日本郵便公式「ゆうパック」 https://www.post.japanpost.jp/service/you_pack/、
日本郵便公式「セキュリティサービス」https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/security/index.html
ゆうパックのセキュリティラベルの役割
セキュリティゆうパックを利用する際には、専用のセキュリティラベルを使用する必要があります。このラベルは単なる識別用のシールではなく、配送の安全性を担保するための重要な要素です。
ラベルには「セキュリティサービスを付加していること」が明示されており、郵便局員や配達員が通常のゆうパックとは異なる厳重な取り扱いを行うための目印となります。また、このラベルには差出時に記入する「損害要償額」の欄があり、ここに記入された金額が補償の上限額として扱われます。
加えて、ラベルには差出人や宛先、配達希望時間帯なども記載されるため、配送中の取り違えを防ぐ役割も果たします。特にセキュリティゆうパックは誤配や事故が許されない荷物が多いため、ラベルの管理は非常に重要です。
なお、着払いで利用する場合は通常のセキュリティラベルではなく、ゆうパック着払い専用伝票を使用します。ここで間違えると受付ができないため、発送前に確認することが求められます。
(出典:日本郵便公式「セキュリティサービス」
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/security/index.html
ゆうパックのセキュリティ伝票の書き方
セキュリティゆうパックを利用する場合、伝票の書き方にも通常のゆうパックとは異なる点があります。特に重要なのが、損害要償額の記入です。
損害要償額とは、万が一配送中に事故が発生した場合に補償を受けられる金額で、差出人が記入する必要があります。ただし、この金額は荷物の時価を超えて記入することはできません。たとえば、実際の価値が20万円の商品を50万円と記入しても、補償されるのは20万円までに制限されます。
伝票には、差出人と宛先の住所・氏名・電話番号のほか、配達希望時間帯や支払い方法(元払い・着払い)などを明確に記入します。これらの情報に不備があると、配達が遅れたり、補償を受けられない場合があります。
さらに、代金引換サービスと併用する場合には、代引伝票に引換金額や送金方法を正しく記入することも必要です。引換金額が30万円を超える場合、必ずセキュリティサービスを付ける決まりになっています。
伝票の書き方は郵便局の窓口で職員に確認でき、公式サイトでも記入例が公開されています。初めて利用する場合は、事前に日本郵便の公式サイトに掲載されている記入例(https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/security/index.html)を確認しておくと安心です。
郵便局のセキュリティパックとの関係

セキュリティゆうパックに関連して、しばしば「郵便局のセキュリティパック」という表現を目にすることがあります。しかし、この「セキュリティパック」という名称は正式なサービス名ではなく、利用者や一部業界で慣用的に使われている呼称にすぎません。正式名称は「セキュリティサービス」であり、ゆうパックに追加料金を支払うことで提供される特別取扱いです。
郵便局側が「セキュリティパック」という名称を公式に用いることはありませんが、利用者の間で定着しているため、窓口で「セキュリティパックをお願いします」と伝えても職員が理解して対応してくれるケースが多いのが実情です。ただし、公式な書類や伝票に記載されるのはあくまで「セキュリティゆうパック」という用語であるため、正確な名称を把握しておくことは誤解を避けるうえで大切です。
この誤解が生じやすい背景には、郵便局が提供する他のオプションサービス(簡易書留、一般書留、本人限定受取など)が「パック」という名称で宣伝されることがある点も挙げられます。利用者にとっては覚えやすい呼び方ですが、正式手続きでは正しい名称を使うことが必要です。
(出典:日本郵便公式「セキュリティサービス」
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/security/index.html
セキュリティゆうパックで現金を送れるのか?禁止物と注意点
セキュリティゆうパックで最も注意すべき点の一つが、現金の取り扱いです。結論から言えば、セキュリティゆうパックを含むゆうパックでは現金を送ることはできません。これは郵便法および日本郵便の規約により禁止されているためで、現金を送る場合は必ず「現金書留」を利用する必要があります。
禁止されているのは現金に限らず、金券、プリペイドカード、クレジットカード情報が記載された文書など、盗難や悪用リスクの高い物品も対象になります。セキュリティサービスを付けたからといって特例が認められるわけではなく、禁止物品の扱いは通常のゆうパックと同じです。
また、セキュリティゆうパックの補償対象は「適法に差し出された物品」に限られます。禁止物を誤って送付した場合、事故が起きても補償を受けることはできません。これは利用者の責任となるため、差し出し時に窓口で内容物の確認を受けることもあります。
現金をどうしても送る必要がある場合は、現金書留を利用することで10万円までの補償が受けられます。高額の場合は分割して送る方法が現実的です。高額商品や貴重品を送る際には、郵便局の規定をよく確認し、適切なサービスを選ぶことが安全確保につながります。
(出典:日本郵便公式「ゆうパックご利用上の注意」 https://www.post.japanpost.jp/service/you_pack/use.html
利用者の体験談とおすすめの使い方
セキュリティゆうパックは、特に法人や事業者の利用が多いサービスです。宝飾品やブランド品の店舗、オークション事業者、金融機関、さらには大学入試の答案用紙など、極めて重要かつ高額な物品を安全に輸送する際に広く利用されています。
利用の実態をみると、次のような活用法が挙げられます。
- 高額商品を顧客へ配送する小売業者が、通常のゆうパックでは不安な場合に利用
- ECサイトの返品対応で、商品価格が高額なときにセキュリティを付与
- 企業間の契約書類や重要文書のやり取りに利用
- 美術品や工芸品の展示会出品時の輸送手段として活用
このように、安心感が最優先される状況で選ばれるケースが多いのが特徴です。
おすすめの使い方としては、まず「損害要償額」を正しく設定することです。実際の価値に見合った金額を記載することで、万が一の際に適切な補償が受けられます。また、発送前に日本郵便が提供する配送日数検索を利用し、納期を正確に把握しておくことも重要です。
さらに、割引制度を活用することで、コストを最適化できます。法人利用の場合は複数口割引や契約による請求書払いを組み合わせることで、費用負担を軽減しながら高いセキュリティを確保することが可能です。
セキュリティゆうパックは追加料金が必要で手間も増えますが、その分安全性と信頼性を高められるサービスです。高額商品や大切な書類を安心して届けたい場合、積極的に検討する価値があるといえます。
(出典:日本郵便公式「セキュリティサービス」
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/security/index.html
セキュリティゆうパックの料金・補償・日数まとめ
- セキュリティゆうパックは、荷物の送達過程を記録し、書留相当の厳重な管理体制で取り扱われる
- 加算料金は通常のゆうパック基本運賃に対して420円を上乗せする仕組みになっている
- 補償額は通常のゆうパックが30万円までに対し、セキュリティサービスでは50万円まで拡大される
- 損害要償額の申告は必ず内容品の時価の範囲内で行い、それを超える設定はできない
- 差出方法は郵便局窓口または集荷に限られ、コンビニからの発送は利用できない
- 発送時は専用ラベルを使用し、着払いで利用する場合は着払い専用ラベルを必ず使用する
- 代金引換サービスで引換金額が30万円を超える場合は、セキュリティサービスの付加が義務付けられる
- 現金はゆうパックでは送れないため、送付が必要な場合は必ず現金書留を利用する必要がある
- 配送日数は基本的に通常のゆうパックと同じで、事前にお届け日数検索を活用すると確実である
- 元払いで発送する場合には、条件を満たせば複数口割引が適用できる場合がある
- 持込割引についても、条件を満たしていればセキュリティサービスを付加した場合でも適用可能である
- 伝票記入では損害要償額を明確に記入し、その金額の根拠となる資料を準備することが重要なポイントになる
- 法人や業務利用では、送り状印刷ソフト「ゆうパックプリントR」を使うと発行が効率的に行える
- 高額品や重要書類を確実かつ安全に輸送したい場合に特に適しているサービスである
- 利用にあたってはコストと安全性のバランスを考慮し、最終的にどのサービスを選ぶか判断することが鍵となる
関連記事