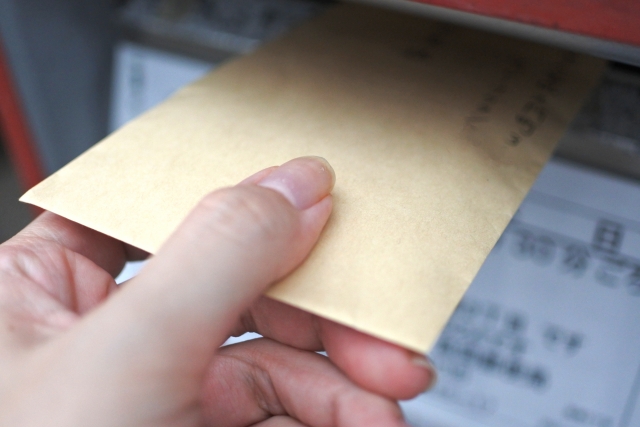郵便物を配達しないでほしいと依頼する方の多くは、自宅に届く郵便物に対して不安や不便を感じているかもしれません。たとえば、しつこいダイレクトメールをどうにかしたい、家族に知られたくない通知を避けたい、長期不在中の配達物をどうすればよいか分からない、といった悩みは非常に多く見られます。
この記事では、郵便物の配達を止める方法や、配達された郵便物の受取拒絶のやり方をはじめ、郵便局の「不在届」や「郵便局留め」の活用法、さらに私書箱の利用など、自宅への配達を回避するための具体的な手段を詳しく解説しています。また、郵便物が無くなるリスクを避けるための対策や、配達間違いが多い場合の対処、アパートの前の入居者宛の郵便が届くケースへの対応についても触れています。
配達が休止されることがある土日や、不在届がバレる可能性に関する注意点など、初めての方でも理解しやすいよう丁寧にまとめています。あなたの状況に合った適切な方法を見つけ、郵便に関する不安を解消しましょう。

💡記事のポイント
- 郵便物の配達を止める具体的な方法がわかる
- 不要な郵便物の受取拒否の手順が理解できる
- 家族に知られずに郵便を管理する方法が学べる
- 配達トラブルや長期不在時の対策が把握できる
郵便物の配達をしないでほしい時の対処法

- 配達止める方法は郵便局で手続き
- 受取拒絶の具体的なやり方
- 長期不在 郵便局留めの使い方
- 私書箱を利用して自宅配達を防ぐ
- 家族に知られたくない郵便の対策
- 迷惑な郵便をなくす工夫とは
配達止める方法は郵便局で手続き
郵便物の配達を一時的に止めたい場合には、「不在届」を郵便局に提出する必要があります。これは、旅行や出張、帰省などで長期間自宅を空ける際に便利な制度です。郵便物が自宅ポストに溜まってしまうと、防犯上のリスクも高まりますので、あらかじめ対策しておくことが重要です。
この制度を利用するには、まず自宅に郵便を配達している郵便局、または最寄りの郵便局の窓口に行き、「不在届」を提出します。手続きにあたっては、本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)が必要となります。また、不在届の用紙は郵便局で配布されているほか、公式サイトからダウンロードして事前に記入して持参することも可能です。
不在期間として指定できるのは最長で30日間です。この間に届いた郵便物は、配達されずに郵便局で一括保管され、不在期間終了後にまとめて配達されます。ただし、不在期間が30日を超える場合はこの制度を使えません。その場合は「転居届」を出して別住所への転送を依頼するか、民間の郵便物管理サービスや私書箱の利用を検討する必要があります。
なお、電話やメール、オンラインでは不在届の提出はできません。必ず窓口での手続きが求められる点には注意してください。また、不在届を出した際には、確認のための「不在届受付確認票」が自宅に届きます。家族に知られたくない場合は、この点も考慮しておく必要があります。
このように、郵便物の配達を一時的に止めたい場合は、事前の準備と窓口での手続きが求められますが、しっかりと制度を活用することで安心して外出や長期不在に対応できます。
受取拒絶の具体的なやり方

自宅に届いた不要な郵便物に対して「受取拒絶」を行うことで、その郵便を差出人に返送することができます。この制度は、しつこいダイレクトメールや心当たりのない郵便、または差出人不明の郵便物などに対応したい場合に有効です。開封前であれば、ほとんどの郵便に対して受取拒否が可能です。
手続きの手順は非常にシンプルです。まず、郵便物が届いた時点で開封せずにそのままにしておきます。そして、メモ用紙や付箋などの小さな紙を用意し、そこに「受取拒絶」と明記し、署名または押印をします。この紙を郵便物の表面に貼り付けて、郵便局の窓口に持参するか、郵便ポストに投函するだけで手続きは完了です。
この際の注意点として、すでに開封してしまった郵便物は受取拒否できないというルールがあります。さらに、サインをして受け取ったもの、料金を支払って受け取ったもの、圧着ハガキの接着部分を開いたものなども「開封済」とみなされるため、対象外となります。
また、郵便物の種類にも制限があります。日本郵便が取り扱っている郵便であれば、通常郵便やレターパック、ゆうパックなども受取拒否が可能です。一方で、クロネコDM便や佐川急便のメール便など、「郵便物ではない」と表示されているものに関しては、郵便局ではなく、それぞれの配送業者に直接連絡をとって対応を依頼する必要があります。
実際に拒絶した郵便物は、差出人が明記されている場合はそのまま返送されます。差出人不明の郵便については、郵便局で一定期間保管された後、破棄される流れとなります。
受取拒否という行為は、差出人に「この郵便はいらない」という意思表示を明確に伝える手段でもあります。そのため、何度も同じ相手から不要な郵便が届くようであれば、根本的な送付停止を依頼するための第一ステップとしても有効です。
長期不在 郵便局留めの使い方
長期間にわたり自宅を留守にする際、自宅ポストに郵便物が溜まってしまうことは、防犯上も非常にリスクが高まります。そんなときに便利なのが「郵便局留め」というサービスです。このサービスを利用すれば、自宅に配達されるはずだった郵便物を指定した郵便局で受け取ることができます。
まず、郵便局留めを利用するには、差出人に「〇〇郵便局留め」と明記してもらう必要があります。宛名欄には、自分の名前と連絡先(電話番号)に加え、受け取りたい郵便局の名前と住所を記入してもらいましょう。例えば、「東京都中央区銀座1-2-3 銀座郵便局留め 山田太郎様(電話番号)」のように記載します。郵便物には受取人の本人確認が必要となるため、記載される名前は身分証と一致する必要があります。
この制度の魅力は、手続きが不要で無料で利用できる点です。事前の申し込みも不要なため、突然の長期不在や緊急時でもすぐに活用できます。ゆうパックやレターパック、書留、通常の郵便物まで幅広く対応しているのもメリットの一つです。
ただし、郵便局での保管期間は最大で10日間となっています。それを過ぎると、差出人に返送されてしまうため、到着日を把握しておくことが重要です。荷物が届いたかどうかは、追跡番号があれば日本郵便の追跡サービスで確認できますが、通知は来ないため、受け取りのタイミングは自分で管理する必要があります。
このように、郵便局留めは長期不在時に自宅に郵便物を届けさせたくない場合に非常に便利な方法です。特に旅行や出張で一定期間家を空ける方にとって、安全かつ無料で利用できる手軽な選択肢といえるでしょう。
私書箱を利用して自宅配達を防ぐ

自宅への郵便配達を避けたい理由は人によってさまざまです。たとえば、プライバシーを重視したい場合や、家族に見られたくない郵便がある場合、あるいは長期的に不在にする可能性がある場合などが考えられます。そうしたニーズに応える手段の一つが「私書箱(ししょばこ)」の利用です。
私書箱とは、郵便物を受け取るために郵便局や民間サービスが提供する専用の保管スペースのことです。利用者はその住所を宛先として使うことで、自宅に郵便が届かないようにすることができます。郵便局が提供する「郵便私書箱」は無料ですが、利用には一定の条件(郵便物の受取数が多いなど)があり、審査を経てからの利用となります。
一方で、もっと手軽に利用できるのが民間の「私設私書箱サービス」です。これらのサービスでは、郵便物の受取・保管だけでなく、スキャンしてPDF化したり、Web上で中身を確認できたり、必要に応じて転送してくれるなど、機能が非常に充実しています。法人利用にも対応しているところが多く、ビジネスシーンでも重宝されています。
例えば、クラウド型の私書箱サービスであれば、スマートフォンやパソコンから郵便物を確認することができ、外出先でも対応が可能です。また、受け取った原本は一定期間保管してもらえ、後から必要になったときに指定先へ転送してもらえる点も安心材料となるでしょう。
ただし、私設私書箱は有料サービスであるため、料金体系は事前に確認しておく必要があります。月額費用やスキャン件数ごとの追加料金などが発生する場合もありますので、自分の使い方に合ったプランを選ぶことが大切です。
このように、私書箱を使えば自宅に郵便物を届けさせずに済むだけでなく、郵便物を効率的かつ安全に管理することも可能です。特にプライバシーを守りたい方や、仕事の郵便物を自宅と分けたい方にとって、非常に有効な手段となります。
家族に知られたくない郵便の対策
家族に見られたくない内容の郵便がある場合、自宅にそのまま届いてしまうとプライバシーの確保が難しくなります。たとえば、クレジットカードの明細、医療関係の通知、通販の注文履歴など、生活の中には知られたくない情報が含まれている郵便が少なくありません。このような場合には、いくつかの対策を講じることで、郵便物が家族に見られるリスクを大幅に減らすことが可能です。
もっとも確実なのは、自宅以外で郵便物を受け取る手段を用意することです。代表的な方法が「郵便局留め」や「私書箱」の利用です。郵便局留めであれば、宛先を郵便局に指定することで、自宅を経由せずに郵便を受け取ることができます。身分証を提示すれば本人が郵便局の窓口で直接受け取れるため、家族にバレる心配がありません。費用もかからず、手軽に利用できるのが魅力です。
一方、より継続的かつ多機能な受取方法を求める場合には、「私設私書箱」や「クラウド私書箱サービス」が便利です。これらのサービスでは、届いた郵便物を開封して中身をスキャンし、PDFでオンライン上に表示してくれるところもあります。外出先からスマホやパソコンで確認できるため、家族に見られる心配はなくなります。
ただし、注意点もあります。不在届を郵便局に提出することで一時的に郵便物の配達を止めることはできますが、この不在届を出すと「不在届受付確認票」が自宅に届くため、家族に不審に思われる可能性があります。誰にも知られずに郵便の受け取り方法を変更したい場合には、不在届よりも私書箱や郵便局留めのほうが適しています。
このように、家族に知られたくない郵便物を守るには、受取場所や手段を工夫することが鍵となります。日常的にプライバシーを守りたいと考えている方にとって、こうした方法をあらかじめ知っておくことが重要です。
迷惑な郵便をなくす工夫とは

毎日のように届く郵便物の中には、明らかに必要のないものや、受け取ること自体がストレスになるような内容も少なくありません。たとえば、しつこいダイレクトメール、差出人不明の郵便、あるいは過去に住んでいた人宛ての郵便など、「迷惑な郵便」は誰にでも起こり得る問題です。こうした郵便を少しでも減らすためには、いくつかの工夫が有効です。
最も基本的な対策は、「受取拒絶」の活用です。未開封の郵便物に「受取拒絶」と書いた紙を貼り、署名または押印した上でポストに投函することで、郵便局が差出人に返送してくれます。この方法は無料で手軽にでき、相手に「今後は送らないでほしい」という意思を明確に伝えることができます。何度か繰り返すことで、名簿から削除される可能性も高くなります。
さらに、郵便ポストに「チラシお断り」「DM不要」といったステッカーを貼ることも、投函物を減らす効果があります。特に集合住宅やマンションでは、業者が無作為に投函するケースが多いため、明示的に拒否の意思を示すだけでも変化が見られることがあります。
また、過去の住人宛ての郵便や、宛名が間違っている郵便については、郵便局に申し出て対応を依頼することができます。封筒に「この人は現在この住所に住んでいません」と記載し、ポストに再投函することで、配達が停止されるケースもあります。
もし迷惑な郵便が頻繁に届き、手間を感じるようであれば、クラウド私書箱サービスの利用を検討するのも一つの手です。物理的に自宅のポストに郵便が届かなくなるため、不必要な郵便物を開封する手間そのものをなくすことができます。
このように、受取拒否・表示による警告・サービスの利用といった複数の対策を組み合わせることで、迷惑な郵便を着実に減らすことが可能です。根本的な解決には時間がかかることもありますが、小さな工夫の積み重ねが大きな効果を生みます。
郵便物を配達しないでほしい理由と注意点

- 不在届 バレることはあるのか?
- 郵便物 無くなるリスクを防ぐ方法
- アパートの前の入居者宛の対処法
- 配達間違いが多い場合の対処法
- 郵便物は土日に配達されるのか?
- 受取拒否した郵便はどうなる?
不在届 バレることはあるのか?
郵便局に「不在届」を提出することで、一定期間自宅に郵便物を配達せず保管してもらうことができます。しかし、この便利な制度には「家族にバレたくない」という悩みが付きまとうこともあります。特に、一人で住んでいない場合や家族と同居している場合、周囲に知られずに不在届を出せるのかが気になるところです。
まず、結論から言うと「不在届がバレる可能性はあります」。その理由の一つが、日本郵便による「不在届受付確認票」の送付です。この確認票は、不正な手続きや郵便物の詐取を防ぐ目的で、自宅住所宛てに郵送される仕組みになっています。そのため、たとえ本人が正当に不在届を提出したとしても、この書類が家族に見つかることで、不在届の提出自体が知られてしまう可能性があります。
さらに、不在届を出した後は、自宅への郵便配達が一時的に止まるため、ポストが空になったことからも不審に思われることがあります。とくに日頃から頻繁に郵便が届くような環境にある方は、周囲の目が気になってしまうかもしれません。
このような事情を避けたい場合には、不在届ではなく「郵便局留め」や「私設私書箱」の活用が適しています。これらは配達を一時的に止めるのではなく、受け取り場所を自宅以外に変更する方法であり、手続きによって自宅宛に通知が届くこともありません。
また、郵便物が届かない理由について家族に問われた際のために、「旅行中に郵便物が盗まれるのが心配だったから」など、納得感のある説明を用意しておくと、さらに安心して対応できるでしょう。
このように、不在届は便利な反面、家族に知られてしまう可能性がある点を理解しておくことが大切です。状況に応じて、より適した方法を選ぶことがプライバシーを守るポイントとなります。
郵便物が無くなるリスクを防ぐ方法
郵便物が届かない、あるいはいつの間にか紛失していたという経験は、多くの人が一度はしているかもしれません。ポストからの盗難や配達ミス、さらには誤って捨てられてしまうなど、郵便物が無くなるリスクは意外と身近に存在しています。こうしたトラブルを未然に防ぐためには、日頃からいくつかの対策を講じておくことが重要です。
まず実行しやすいのが、ポストのセキュリティ強化です。鍵付きの郵便ポストに交換することで、第三者が郵便物に触れる機会を減らすことができます。また、投入口が広すぎると中の郵便物が手で抜き取られやすくなるため、狭めの投入口や内フラップ付きのタイプを選ぶのも効果的です。あわせて、郵便物が溜まりすぎないよう、こまめに取り出す習慣を持つことも忘れてはいけません。
加えて、配達ミスや誤投函を防ぐためには、ポストにしっかりと名前を表示することも大切です。特に集合住宅では、部屋番号だけで配達されることもあり、表札やステッカーで名前を記しておくことで、配達員が誤って投函するリスクを減らせます。
もし長期不在になる予定がある場合は、郵便局に不在届を出して郵便物を一時的に保管してもらう方法も有効です。前述の通り、不在届には通知が届くというデメリットがありますが、防犯の面では大きな安心材料となります。また、さらに安全性を求めるのであれば、「郵便局留め」や「私書箱」の利用も選択肢に入れるべきでしょう。
これに加えて、重要な書類や荷物については、追跡番号付きの配送方法を選ぶことも賢明です。ゆうパックやレターパックなどは配達状況をオンラインで確認できるため、紛失リスクを減らすことができます。
このように、郵便物が無くなるリスクは完全には避けられないものの、対策次第で限りなく小さく抑えることが可能です。日頃から「受け取る環境」と「配達方法」の両面に注意を払うことが、トラブルの予防につながります。
アパートの前の入居者宛の対処法

アパートに引っ越してきた後も、前の住人宛ての郵便物が届き続けるというケースは珍しくありません。これは、前の入居者が郵便局に転居届を出していない、または転送期間(通常1年)が過ぎてしまっていることなどが主な原因です。このまま放置してしまうと、自分の郵便物と混ざったり、重要な通知を見逃したりする恐れがあります。そこで、正しい対処を知っておくことが大切です。
まず、前の住人宛の郵便物を受け取ってしまった場合、開封せずに対応することが基本です。郵便物の宛名が自分以外であることに気づいた時点で、封を切らないように注意しましょう。次に、封筒の表面に「この人はこの住所に住んでいません」「宛先不明のため返送願います」などのメッセージを明記し、そのままポストに投函します。郵便局側で差出人に返送される仕組みです。
ただし、何度返送しても同じ宛先の郵便が届く場合には、郵便局の窓口で直接相談することも選択肢です。その際、何通も届いて困っている旨を伝えると、局側で差出人に対して発送停止を促す対応をとってくれる場合もあります。
さらに、アパートのポストに前の住人の名前が表記されたままだと、配達員が混乱する原因になります。表札やポストに現住人の名前だけを明確に表示し、余計な名前を一切残さないことも、誤配防止の一助となります。
また、民間から送られてくるダイレクトメールやカタログ類は、郵便ではなく宅配便や独自のDM便で届くこともあります。これらの場合は、それぞれの配送業者に連絡し、送付停止を依頼する必要があります。送り元の企業の連絡先が記載されていれば、そこへ事情を説明することで、今後の送付を止めてもらえる可能性が高くなります。
このように、前の入居者宛ての郵便物が届くのはよくあることですが、適切に対応すれば煩わしさを軽減できます。放置せず、早めに対処することで、スムーズな郵便環境を整えることができるでしょう。
配達間違いが多い場合の対処法
自宅に届く郵便物の中に、明らかに他人宛のものが混ざっていたり、別の部屋の郵便が誤って投函されていたりするケースは、特に集合住宅などでよく見られます。こうした配達間違いが繰り返されると、自分の重要な郵便が他人の手に渡ってしまうリスクもあるため、早めに対応することが重要です。
まずできる対策として、ポストや表札にしっかりと自分のフルネームを掲示しておくことが挙げられます。特にマンションやアパートでは、部屋番号だけで配達されていることもあるため、表記が不明確だと配達員が間違えてしまう可能性が高くなります。名前の表示があれば、少なくとも誰が住んでいるかの判断材料になり、誤配を防ぐ助けになります。
また、誤って届いた郵便物については、開封せずに対応しましょう。自分宛でないと気づいたら、そのまま封筒に「配達先間違い」と書き、再度ポストに戻すことで、郵便局が回収・再配達してくれます。ポストに戻す際は、目立つようにメモ書きを貼ると確実です。
もし配達ミスが頻繁に起こるようであれば、郵便局に直接相談するのが最も効果的です。居住している住所、部屋番号、名前を伝えたうえで、何度も配達ミスが起こっていることを報告すると、配達担当者への注意喚起や配達体制の見直しを行ってもらえることがあります。
さらに、民間配送業者による配達間違いの場合は、送り主に連絡するか、誤って配達された荷物に記載されている配送会社へ問い合わせましょう。誤配の内容を伝えると、営業所から回収に来てもらえるケースもあります。
なお、配達ミスによって他人の郵便物を開封してしまった場合には、刑法に抵触する可能性があるため注意が必要です。意図せずとも、中身を見てしまう前に「誤配」と気づいた段階で返送・報告するのが適切な対応です。
このように、配達間違いへの対処には、「明確な表示」「迅速な対応」「正しい報告」がカギとなります。繰り返しのミスが防げるよう、自分の住環境に合わせた対策を心がけましょう。
郵便物は土日に配達されるのか?

土日に郵便物が配達されるのかどうかは、郵便の種類によって異なります。一般的に「普通郵便(定形・定形外)」については、2021年10月以降、土曜日の配達が廃止されており、日曜日や祝日も含めて配達は行われていません。そのため、たとえば金曜日に投函された普通郵便は、土日を挟んで翌週の月曜日以降の配達となることがあります。
ただし、すべての郵便物が土日に届かないわけではありません。速達、書留、ゆうパック、レターパックプラスなどの「特殊取扱郵便」や「宅配便に近いサービス」に関しては、土曜日・日曜日・祝日を問わず配達されます。たとえば、ネット通販で注文した商品がゆうパックやレターパックで発送されている場合、土日でも自宅に届く可能性があります。
この違いは、日本郵便の業務負担軽減やコスト削減を背景に導入されたものであり、日常的な手紙や請求書などの普通郵便に関しては、平日のみの配達体制が基本となっています。
また、速達や書留は追加料金が発生するため、土日にも確実に届けたい郵便物がある場合は、これらのオプションを活用するのが確実です。郵便局窓口で相談すれば、適切な方法を案内してもらえるでしょう。
このように、土日の郵便配達は一部に限られており、すべての郵便物が対象ではありません。特に急ぎの書類や重要な通知がある場合は、発送方法に注意を払い、必要に応じて速達などを利用するようにしましょう。
受取拒否した郵便はどうなる?

郵便物を受け取りたくない場合、「受取拒否」という方法で差出人に返送することが可能です。これは主にダイレクトメールや差出人不明の郵便、さらには心当たりのない通知などに対して用いられます。開封前であれば、受取拒否の手続きを取ることで、郵便物は配達されずに差出人のもとへ返送される仕組みになっています。
具体的には、受取を拒否したい郵便物の封筒やパッケージに「受取拒絶」と書かれた紙を貼り付け、署名または押印を加えてポストに投函するか、郵便局の窓口に提出します。これにより、その郵便物は郵便局を経由して、差出人に返送される流れとなります。
差出人の情報が明記されている場合は、郵便局がその住所宛に返送処理を行います。一方で、差出人が不明な郵便物については、まず郵便局内で開封され、差出人が特定できるかが確認されます。もし差出人が判明すれば返送されますが、特定できない場合は、郵便局にて3か月間保管された後、破棄されます。
このとき注意しておきたいのは、「開封済み」の郵便物や、一度署名・料金支払いを行ったものに関しては、受取拒否の対象外となる点です。また、裁判所などから届く「特別送達」のような重要文書も受取拒否はできません。拒否したことで不利になる可能性があるため、内容を確認したうえで対応する必要があります。
さらに、受取拒否を行った郵便には「受取拒絶」の文字と署名がそのまま残された状態で差出人に返送されます。そのため、誰が拒否したかは明確に相手に伝わります。相手との関係性を考慮したうえで実行することが望ましいでしょう。
このように、受取拒否された郵便は一定の手続きを経て処理されるため、差出人に対して明確な意思表示を行いたい場合に有効です。ただし、対象となる条件や注意点もあるため、状況に応じた判断が求められます。
郵便物を配達しないでほしい時の対処法まとめ
- 郵便物の配達を止めたい場合は、郵便局で「不在届」を提出する必要がある
- 不在届の手続きは、郵便局窓口でのみ受け付けており、電話やメールでは申請できない
- 不在届で指定できる配達停止期間は最長30日間で、それを超える場合は別の対応が必要になる
- 手続きには運転免許証や健康保険証などの本人確認書類を持参することが求められる
- 不在届を出すと「受付確認票」が自宅に届くため、家族に知られたくない場合は注意が必要
- 30日を超える不在には「転居届」や私書箱、郵便物管理サービスなどの代替手段が有効になる
- 自宅に届いた不要な郵便物は、開封前であれば「受取拒否」の対応ができる
- 「受取拒絶」と記載した紙を郵便物に貼り付け、署名または押印してポストへ投函すれば返送される
- 差出人が不明な郵便物は郵便局で一時保管され、一定期間後に処分される流れになる
- 裁判関連などの特別送達郵便は受取拒否の対象外で、拒否すると不利益になることもある
- 郵便局留めを使えば、自宅を通さず指定した郵便局で直接郵便物を受け取ることができる
- 郵便局の私書箱や民間の私設私書箱を利用すれば、自宅住所に郵便が届くのを避けられる
- クラウド型私書箱サービスでは、郵便物の内容をスキャンしてWEB上で確認できる便利な機能がある
- 配達間違いを防ぐには、ポストや表札にフルネームを明記し、郵便局に繰り返し相談するのが効果的
- 郵便物の紛失や盗難リスクを下げるには、鍵付きポストの設置や追跡可能な配送方法の利用が有効
関連記事