「クッション封筒郵便局」と検索している方の多くは、「この封筒って郵便局で使えるの?」「送料はいくらかかる?」「どこで買えるの?」といった、発送前の不安や疑問を抱えているのではないでしょうか。特にフリマアプリや個人取引が一般化した今、壊れやすい小物を安全かつスムーズに送る手段として、クッション封筒の活用ニーズは高まっています。
とはいえ、郵便局での取り扱いルールや料金体系、切手の貼り方など、細かい部分でつまずいてしまうことも少なくありません。また、封筒選びや購入場所に悩む人も多いはずです。この記事では、そんな不安を解消するために、クッション封筒を郵便局でどう使うのか、その基本から応用までをわかりやすくまとめました。
実際に送れるものの種類、送料の目安、送り方の手順、さらには最安で封筒を手に入れる方法まで、初めての方にも実践しやすい内容で構成しています。この記事を読み終える頃には、安心してクッション封筒を使った発送ができるようになっているはずです。どうぞ最後までお付き合いください。

💡記事のポイント
- 郵便局でクッション封筒を使って送れるものと利用できるサービス
- クッション封筒の送料とサイズ・重さによる料金の違い
- 郵便局から発送する際の梱包手順と宛名の書き方
- クッション封筒の購入場所や選び方のポイント
クッション封筒は郵便局でどう使う?送り方・料金・購入方法

- クッション封筒は郵便局で何が送れる?利用ルールと対応サービス
- クッション封筒の郵便局での送料はいくら?サイズ・重さ別に解説
- クッション封筒を郵便局から送る方法とは?梱包と発送の手順
- クッション封筒に貼る切手の料金は?郵便局での購入方法も紹介
- クッション封筒の宛名はどう書く?郵便局での正しい記載方法
- クッション封筒は郵便局で買える?購入場所・種類・価格の比較
クッション封筒は郵便局で何が送れる?利用ルールと対応サービス
クッション封筒を使って郵便局から荷物を送る場面は、フリマアプリや個人取引が一般化してきた現在ではよく見られるようになりました。封筒の内側に緩衝材が付いているため、壊れやすいものを安心して送る手段として活用されています。ただし、郵便局でクッション封筒を使用する際には、どのような荷物が送れるのか、どのサービスが使えるのかについて、いくつかのルールを知っておく必要があります。
まず、クッション封筒で送ることができる代表的なアイテムとしては、小型の電子機器、アクセサリー、文具類、書類、CD・DVDなどがあります。これらは、通常の封筒では破損のリスクがあるものの、クッション封筒を使うことである程度の衝撃から保護できるため、実用的な選択肢といえます。
ただし、内容物によっては郵便局のサービスでは送れないものもあります。例えば、現金、危険物、液体、冷蔵・冷凍が必要なものなどは、封筒の種類に関係なく郵送できません。また、医薬品や化粧品の一部も制限の対象となるため、個人輸送であっても十分に注意する必要があります。
対応している郵便サービスとしては、主に「定形外郵便」「ゆうパケット」「ゆうメール」「レターパック」「ゆうパック」などがあります。送るもののサイズや重さ、追跡や補償の有無などによって使い分けるのが基本です。たとえば、小さな雑貨であれば定形外郵便が手軽ですが、追跡や補償が必要な場合はレターパックやゆうパックの利用が向いています。
このように、郵便局でクッション封筒を使用する際は、荷物の内容とサイズに応じて最適なサービスを選ぶことが大切です。送りたいものが送付可能かどうか不安なときは、事前に郵便局の公式サイトで確認したり、窓口で直接相談するのが安心です。
クッション封筒の郵便局での送料はいくら?サイズ・重さ別に解説
クッション封筒を使って郵便局から荷物を送る場合、気になるのが送料です。送料は封筒のサイズや重さによって細かく変わるため、送る前にある程度の目安を知っておくと、予期せぬ出費を防げます。特に、クッション封筒は中に緩衝材が入っている分だけ厚みが出やすく、これが送料に直接影響するため注意が必要です。
まず、最も利用されることが多いのが「定形外郵便」です。このサービスは「規格内」と「規格外」に分かれており、サイズと重さによって料金が段階的に設定されています。規格内の条件は、長辺34cm以内・短辺25cm以内・厚さ3cm以内・重さ1kg以内とされており、この範囲に収まれば比較的安価に送ることが可能です。たとえば、100g以内であれば140円、250g以内で210円、500g以内なら390円というように料金が設定されています。
一方で、厚さが3cmを超える、あるいは形状が特殊で機械での処理が難しい場合は「規格外」となり、送料は一段階高くなります。例えば250g以内であれば350円、500g以内では510円というように、重くなるほど料金が上がっていきます。このため、クッション封筒に厚みのあるものを詰め込んだ場合、見た目以上に送料が高くなるケースもあります。
さらに、追跡サービスや速達を希望する場合には、レターパック(ライト:370円、プラス:520円)やゆうパックなど、他のサービスを選ぶ必要があります。これらのサービスは送料がやや高くなるものの、配達状況の追跡や対面配達が含まれているため、大切な荷物を送る際には検討する価値があります。
いずれのサービスを使う場合でも、事前に封筒に中身を入れた状態で、サイズと重さを測っておくのが賢明です。特に自宅で切手を貼ってポスト投函する場合には、送料不足による返送や追加料金の請求を避けるためにも、慎重な確認が必要です。
クッション封筒を郵便局から送る方法とは?梱包と発送の手順
クッション封筒を使って郵便局から荷物を送る際には、ただ封筒に物を入れて投函するだけではなく、いくつかの手順を正しく踏む必要があります。特に初めて利用する場合は、送り方や梱包方法を誤ることで配達が遅れたり、内容物が破損したりするリスクがあるため、しっかりと確認しておきましょう。
まずは、送る物に合ったサイズと厚みのクッション封筒を選ぶところから始めます。中身が厚すぎると郵便局での取り扱いに制限が出る可能性があるため、封筒のサイズ選びは非常に重要です。あらかじめ送る物の寸法を測り、厚み3cm以下であれば「定形外郵便(規格内)」として扱える可能性が高くなります。
次に、封筒に中身を丁寧に入れます。封筒の中にはすでにプチプチなどの緩衝材がついていますが、割れ物や精密機器を送る場合には、さらにプチプチを重ねるなどして補強することをおすすめします。封の部分もしっかりと閉じましょう。粘着テープが弱いと感じた場合は、追加でガムテープやOPPテープなどで封を補強すると安心です。
宛名と差出人の情報は、封筒の表面にしっかりと記載します。文字は読みやすく、郵便番号は7桁すべてを正確に記入します。受取人情報は封筒の中央に、差出人情報は左上か裏面に記入するのが一般的です。また、荷物の内容に応じて「折曲厳禁」「ワレモノ」などの表示を添えることで、郵送中のトラブルを防ぐことができます。
封筒の準備が整ったら、発送方法を選びます。ポスト投函が可能なサイズと重さであれば、必要な金額の切手を貼って投函することができます。一方で、重さやサイズが不明な場合、あるいは追跡や補償をつけたい場合は、郵便局の窓口で発送するのが確実です。窓口では職員がその場でサイズ・重量を測り、最適な発送方法と料金を案内してくれます。
こうして見てみると、クッション封筒での発送はそこまで難しいものではありませんが、サイズや重さに関するルール、宛名の記入、封の補強といった基本を押さえておくことで、安全かつ確実に荷物を届けることができます。最初は面倒に感じるかもしれませんが、慣れてしまえばスムーズに対応できるようになるでしょう。
クッション封筒に貼る切手の料金は?郵便局での購入方法も紹介

クッション封筒で荷物を郵送する際、最も基本的な準備の一つが「切手の貼付」です。適正な料金の切手を貼らなければ、荷物が配達されなかったり、受取人に不足分の料金を請求されたりすることがあります。このようなトラブルを避けるためにも、発送前に正しい切手の金額を把握し、適切な場所に貼り付けることが大切です。
まず、クッション封筒に貼る切手の料金は、中身の重さと封筒のサイズによって変わります。特に多く使われるのが「定形外郵便」で、さらに「規格内」と「規格外」に分類されます。例えば、規格内(厚さ3cm以内・1kg以内)の場合、50g以内であれば140円、100g以内では180円、250g以内では270円などの料金がかかります。一方で、規格外になると、同じ重さでも料金は大きく異なり、例えば250g以内だと450円になります。封筒自体に厚みがあるため、実際には中身が軽くても「規格外」に該当することが多い点には注意が必要です。
切手の購入については、郵便局の窓口が最も確実です。職員が封筒を測ってくれるため、間違いのない料金で切手を購入できます。また、郵便局内にはセルフで使える郵便料金表も掲示されており、重さを量るスケールが設置されていることもあります。ただし、切手は郵便局だけでなく、一部のコンビニやスーパー、ネット通販でも購入可能です。ただし、これらの場所では封筒の測定や料金案内が受けられないため、発送初心者にはあまりおすすめできません。
切手は封筒の右上にまっすぐ貼るのが基本です。シワがあったり斜めになっていたりすると、読み取り機器がエラーを起こす場合もあるため、できるだけ丁寧に貼りましょう。また、複数枚の切手を組み合わせる場合は、重ねたりしないように注意が必要です。
このように、クッション封筒に貼る切手は「重さ・サイズ・サービス内容」によって変わるため、事前の確認が重要です。可能であれば郵便局の窓口で確認・購入をすることで、より確実に発送できるでしょう。
クッション封筒の宛名はどう書く?郵便局での正しい記載方法
郵便物の中でも、特にクッション封筒は厚みがあるため、宛名の書き方に少し工夫が必要です。配送トラブルを防ぐには、郵便局が定める記載ルールを理解し、正しく宛名を書くことが基本となります。ここでは、誰でも実践できる具体的な手順を詳しくご紹介します。
まず、宛名は封筒の表面に、受取人の情報を「中央やや右寄り」に配置します。文字は縦書きでも横書きでも構いませんが、日本郵便では横書きが推奨されている傾向があります。書く内容としては、郵便番号、住所、氏名をこの順に記載します。郵便番号は必ず7桁すべてを記入し、できれば赤枠付きの「〒」マークも添えると認識されやすくなります。
次に、差出人情報は「表面の左上」または「封筒の裏面」に記載するのが一般的です。万が一、宛先不明で配達できなかった場合には差出人に返送されるため、こちらも省略せずに書いておきましょう。特にオークションやフリマアプリなどで商品を送る場合、返送が必要なケースもあるため、記載は必須と考えてください。
宛名を書くときに気をつけたいポイントは、まず文字を「濃く・はっきり・大きく」書くことです。印刷されたラベルでも問題ありませんが、インクがにじむ紙質の封筒や、手書きで薄いペンを使うと、読み取り機械で正しく認識されない可能性があります。特にマンション名や部屋番号、建物名などは略さずに書くようにしましょう。書き忘れがあると配達できないこともあります。
加えて、内容物が壊れやすいものや精密機器である場合、「ワレモノ注意」や「天地無用」などの表示を添えると、取り扱いが丁寧になります。必要であれば「折曲厳禁」と記載することも有効です。郵便局の窓口では専用のシールをもらえることもあるため、受付時に確認してみると良いでしょう。
こうして正しく宛名を書くことで、配達ミスやトラブルのリスクを大きく減らせます。慣れていないうちは簡単なチェックリストを用意して、記載漏れがないか出す前に確認するのがおすすめです。
クッション封筒は郵便局で買える?購入場所・種類・価格の比較
クッション封筒は文房具店や100円ショップなどでも購入できますが、郵便局で手に入るということをご存知でしょうか。郵送用に最適化された封筒をその場で購入できるため、急ぎで荷物を送りたいときや、発送に不慣れな人にとっては便利な選択肢となります。
郵便局で販売されているクッション封筒は、基本的に「スマートレター」や「レターパック」などの専用封筒とは異なり、緩衝材入りの汎用封筒として提供されています。封筒のサイズは主にB5やA4、角形サイズなどが中心で、外装はシンプルなクラフト紙や白地のものが多く、特に小物や雑貨、書類の郵送に適しています。
価格帯としては、1枚あたり100円〜200円前後が一般的です。もちろんサイズや厚みによって異なりますが、郵便局の窓口では商品ごとの詳細な説明を受けられるため、自分の荷物に適した封筒を選びやすくなっています。発送サービスと組み合わせて購入すれば、サイズの適合性もその場で確認できるため、手間が省けるのもメリットです。
ただし、郵便局の店舗によっては取り扱いがない場合もあります。特に小規模な郵便局では在庫が限られていることがあるため、事前に電話などで確認しておくと安心です。なお、最近では日本郵便の公式オンラインストアや一部ECサイトでも、郵便局仕様のクッション封筒が販売されており、自宅でまとめて購入することも可能です。
一方で、価格を重視する場合は、100円ショップやコンビニの文具コーナーでの購入も候補に入ります。クオリティに若干の違いがあるものの、コストを抑えたい場合には十分実用的です。用途や発送方法によって、郵便局の封筒が最適な場合と、他店の商品で十分な場合を見極めることが大切です。
このように、郵便局では実用性の高いクッション封筒を取り扱っており、その場で購入できる利便性や安心感があります。発送初心者や荷物の扱いに慎重になりたい方には、窓口での購入が特におすすめです。
クッション封筒は郵便局以外でも買える?コンビニ・100均

- クッション封筒はどこに売ってる?購入できる場所を徹底調査
- クッション封筒はダイソーで買える?種類・サイズ・価格をチェック
- クッション封筒はコンビニ(ローソン・ファミマ)で買える?在庫と特徴
- クッション封筒はヤマト運輸やネコポスでも使える?対応可否と注意点
- クッション封筒を最安で手に入れるには?価格比較とおすすめ店
- 発送用のクッション封筒を選ぶコツとは?用途別の選び方ガイド
クッション封筒はどこに売ってる?購入できる場所を徹底調査
クッション封筒は、日常生活やビジネスシーンで意外と活躍するアイテムです。壊れやすいものを送る際の必需品であるにもかかわらず、「いざ使いたいときに、どこで買えばよいのかわからない」という声は少なくありません。そこでここでは、クッション封筒を購入できる主な場所を具体的に紹介し、それぞれの特徴やメリット・デメリットについて解説していきます。
まず、最も手軽に入手できるのが100円ショップです。ダイソー、セリア、キャンドゥといった大手チェーンでは、文具コーナーや梱包資材の棚に置かれていることが多く、1枚入りや2枚入りのパッケージで販売されています。価格の安さが最大の魅力ですが、サイズやクッションの厚みに限りがあるため、送りたい物の形状に合うかどうかを事前に確認しておく必要があります。
次に、コンビニも有力な購入先です。ローソン、ファミリーマート、セブン-イレブンなどでは、店舗によってはレターパックや宅急便用の資材と一緒にクッション封筒が並んでいることがあります。ただし、取り扱いがない店舗も多く、売り場が目立たないため、見つけにくいこともあります。あらかじめ在庫の有無を確認したい場合は、電話で問い合わせると確実です。
さらに、文房具店やホームセンターでも取り扱いがあります。こちらは種類が豊富で、サイズ展開も幅広いため、大きめの荷物や特定の用途に合ったものを選びたいときに便利です。特に、大型店舗では法人向けの業務用商品も置かれているため、まとめ買いをしたい場合にも向いています。
また、郵便局の窓口でも簡易的なクッション封筒が販売されています。発送のついでに購入できるため効率的ではありますが、品ぞろえは限られており、価格もやや高めです。一方で、サイズが郵送サービスに適合している点や、窓口でスタッフに相談できる点は安心材料になるでしょう。
最後に、最も確実なのがインターネット通販です。Amazonや楽天市場、モノタロウなどでは、種類やサイズ、材質などを細かく選べ、価格も比較的安価です。特に大量購入や法人利用を想定している場合にはコストパフォーマンスに優れています。ただし、送料がかかる場合や、すぐに使いたいときには不向きです。
このように、クッション封筒は意外と多くの場所で販売されています。それぞれの特徴を踏まえて、自分の目的やタイミングに合った購入方法を選ぶことが大切です。
クッション封筒はダイソーで買える?種類・サイズ・価格をチェック
ダイソーは、手軽に必要なアイテムをそろえることができる100円ショップの代表格です。クッション封筒も例外ではなく、全国の多くのダイソー店舗で取り扱われています。ここでは、ダイソーで買えるクッション封筒の種類やサイズ、そして価格について詳しく見ていきます。
まず、ダイソーのクッション封筒は、「エアクッション封筒」や「緩衝材付き封筒」という名称で売られていることが多く、主に文具コーナーや梱包用品の棚に並んでいます。封筒の外側はクラフト紙や白いコート紙で、中にはプチプチ状の緩衝材が貼り付けられており、CD、アクセサリー、スマホアクセサリーなど小さなものを安全に送るのに適しています。
サイズについては、A5・B5・角形2号(A4対応)といったバリエーションがあり、それぞれのサイズに対応した中身の大きさに合わせて選ぶことが可能です。ただし、厚みは限定されており、あまり分厚いものや重量のある品物を送るには不向きな場合があります。そのため、あらかじめ送るもののサイズや厚みを測っておくと安心です。
価格は基本的に1枚入りまたは2枚入りで110円(税込)というシンプルな設定です。一般の文具店などと比較してもかなりリーズナブルであるため、コストを抑えたい場合には大きなメリットがあります。一方で、安価な分だけ材質はやや薄く、封の粘着力もそれほど強くないものがあるため、発送の際にはテープで補強するなどの対策が必要になることもあります。
なお、取り扱い商品は店舗によって異なり、すべてのダイソーで在庫があるとは限りません。特に小規模な店舗では取り扱いがないこともあるため、確実に購入したい場合は大型店やダイソーの公式通販サイトを利用する方法もあります。
このように、ダイソーのクッション封筒はコスパに優れ、ライトユーザーには非常に便利なアイテムです。ただし、サイズや耐久性には限りがあるため、内容物に応じて他の選択肢も検討すると良いでしょう。
クッション封筒はコンビニ(ローソン・ファミマ)で買える?在庫と特徴
コンビニは日用品や文房具が手軽に購入できる便利な場所ですが、「クッション封筒も置いてあるのか?」という点については意外と知られていません。ここでは、ローソンやファミリーマートなどの大手コンビニでのクッション封筒の取り扱い状況と、購入時の注意点について紹介します。
まず、ローソンでは店舗によっては「クッション封筒」や「緩衝材付き封筒」が販売されています。封筒のサイズは小型〜中型程度が中心で、スマートレターやレターパックと並んで置かれているケースが多いです。ただし、文具や梱包資材の棚が設けられていない小規模店舗では、取り扱いがないことも珍しくありません。そのため、実際に買いに行く前に在庫状況を確認しておくと無駄足を防げます。
一方、ファミリーマートでも同様に、店舗によってクッション封筒の取り扱いがあります。とくに、大型店やオフィス街にある店舗では、書類用封筒や小包用の梱包資材が揃っていることがあり、そこにクッション封筒も置かれていることがあります。価格帯は1枚あたり150円前後が多く、100円ショップに比べるとやや高めですが、すぐに必要なときには非常に便利です。
どちらのコンビニでも、クッション封筒は「急な発送ニーズ」に対応するための商品として位置づけられているため、品ぞろえは限定的です。サイズも1〜2種類に絞られており、大きな荷物や複数の商品を送りたい場合には不向きです。さらに、売り場が分かりづらいことも多く、店員に尋ねなければ見つからないケースもあります。
もう一つの特徴は、宅配便と連携している点です。例えばローソンではヤマト運輸、ファミリーマートでは日本郵便(ゆうパック)と提携しており、店頭で梱包資材と送り状を一緒に準備できるのは利便性の面で優れています。ただし、封筒のサイズや重さがサービスの規定に合っているかは、自分で判断する必要があります。
このように、コンビニでクッション封筒を購入することは可能ですが、在庫やサイズに限りがあるため、あくまで「緊急時」や「一時的な利用」に向いています。頻繁に使用する場合やこだわりのある商品を送りたい場合は、文具店やネット通販を併用するのが賢明です。
クッション封筒はヤマト運輸やネコポスでも使える?対応可否と注意点

クッション封筒は、割れ物や精密機器を送る際に便利な梱包資材ですが、どの配送サービスにも使えるわけではありません。特にヤマト運輸やその提供する「ネコポス」で使用できるのかどうかは、利用前に確認しておく必要があります。
まず、ヤマト運輸では基本的にクッション封筒を使用して荷物を送ることが可能です。宅急便コンパクトや宅急便では、封筒や箱などに関する明確な制限は少なく、中身がしっかり保護されていて、外形寸法や重量が規定内であれば問題なく利用できます。したがって、たとえばスマートフォンのアクセサリーやガジェット関連の製品、小型の書籍などをクッション封筒に入れて送るのは、実務上もよく行われている手法です。
一方で、ネコポスに関しては、対応サイズが非常に厳密に定められているため注意が必要です。ネコポスの最大サイズは「縦31.2cm以内×横22.8cm以内×厚さ2.5cm以内、重さ1kg以内」とされています。ここでポイントになるのが「厚さ」と「封筒の柔軟性」です。クッション封筒そのものに厚みがあるため、薄い内容物を入れても厚さ制限の2.5cmを超えてしまうケースがよくあります。また、柔らかい素材の封筒だとしても、サイズオーバーになると機械処理ができず、受付拒否される可能性があります。
さらに、ネコポスを利用する際は、送り状の発行方法や集荷方法にも決まりがあります。主にヤマトの「らくらくメルカリ便」や「クロネコメンバーズ」などの提携サービスを通じて利用されることが多く、事前の登録やアプリの使用が前提になることもあります。このため、個人での発送を想定している場合は、ネコポスの詳細な運用ルールを事前に確認することが欠かせません。
こう考えると、ヤマト運輸の通常の宅急便では自由度が高く使いやすい反面、ネコポスでのクッション封筒使用はサイズ制限との戦いになるとも言えます。クッション封筒を使いたい場合は、必ず実物を測り、厚さが基準を超えていないかを確認しましょう。少しでも不安がある場合は、店舗に持ち込んでスタッフに見てもらうと安心です。
クッション封筒を最安で手に入れるには?価格比較とおすすめ店
クッション封筒は頻繁に使うものではないかもしれませんが、まとめて送る機会がある人にとっては、できるだけ安く手に入れたいと考えるのが自然です。ここでは、クッション封筒の価格帯を比較しながら、コストを抑えて入手するための具体的な方法とおすすめの購入先をご紹介します。
まず、100円ショップはもっとも身近で低価格な選択肢です。ダイソーやセリア、キャンドゥといった店舗では、1枚入りまたは2枚入りで税込110円という価格で販売されています。シンプルなデザインで、サイズもA5やB5程度が主流です。コストパフォーマンスの良さでは群を抜いていますが、その分、材質や封の粘着力には若干の不安があるため、重要なものや壊れやすい物を送る際には追加でテープ補強を行うのが無難です。
次に注目すべきは、ネット通販サイトです。Amazonや楽天市場では、クッション封筒を10枚・20枚単位で販売している業者が多数存在し、単価に換算すると1枚あたり30円〜80円程度で購入可能です。特にまとめ買いを考えている方には圧倒的なコストメリットがあります。加えて、サイズやカラー、素材(クラフト紙・白紙・防水タイプなど)も選べるため、用途に応じた商品を見つけやすいのが特徴です。ただし、送料が別途かかる場合や、到着までに日数がかかる点には注意が必要です。
一方、コンビニや郵便局では利便性は高いものの、価格面では割高になる傾向があります。たとえば、ファミリーマートでは1枚150円前後、郵便局ではサイズによって200円を超える場合もあり、頻繁に使う方にとってはコストが気になるかもしれません。ただ、必要なときにすぐ手に入るという利点は見逃せません。
価格だけに注目するとネット購入が最安ですが、実際には「使う頻度」「必要なサイズ」「今すぐ必要かどうか」などによって、最適な購入先は変わってきます。たとえば、フリマアプリで定期的に商品を発送している人であれば、ネットでまとめ買いするのが経済的です。逆に、「明日中に送りたい」という状況であれば、多少高くてもコンビニや郵便局で買う方が現実的です。
このように、価格だけでなく目的やタイミングに合わせて購入先を使い分けることで、コストを最小限に抑えつつ、必要なときに必要な枚数だけを無駄なく確保できます。
発送用のクッション封筒を選ぶコツとは?用途別の選び方ガイド
発送用のクッション封筒を選ぶ際には、ただ「サイズが合えばいい」という考え方では不十分です。用途や内容物の性質によって最適な封筒は異なり、誤った選択をしてしまうと、配送中の破損や受け取り側の印象低下といったリスクにつながる可能性もあります。ここでは、用途ごとに適したクッション封筒の選び方を具体的に解説していきます。
まず、最も基本的な選び方として重視すべきなのが「サイズ」と「厚み」です。例えば、スマートフォンケースやアクセサリーなどの小物を送る場合、A5サイズのクッション封筒で十分対応できます。一方で、書類やノートなどを送るのであれば、A4対応の角形2号サイズが望ましいです。厚みに関しては、配送サービスによって制限があるため、特にポスト投函型(クリックポストやネコポス)を利用する場合は、封筒の厚みが3cm以内になるよう計算しておく必要があります。
次に注目したいのが「封筒の素材」と「クッション性能」です。外側がクラフト紙でできているものはコストが安く、書き込みやすいというメリットがありますが、見た目がやや無骨です。反対に、白いコート紙や防水加工のある封筒は、見た目がきれいで雨にも強く、贈り物やビジネス用途には適しています。中のクッションについても、厚みや柔らかさに差があるため、壊れやすい物を送る場合はクッション性が高いものを選ぶと安心です。
また、封の閉じ方も見落としがちなポイントです。テープ付きタイプは手間がかからず便利ですが、粘着力が弱いものもあり、心配なときは追加のテープで補強した方が良いでしょう。再利用を考える場合は、チャック付きやフラップ付きのものを選ぶのも一つの方法です。
このように発送用のクッション封筒は、用途や送り先、配送手段によって選ぶべきポイントが異なります。単純に「安いもの」「適当なサイズ」で選ぶのではなく、「何をどのように送るか」を基準に、自分に合った封筒を選ぶことが、スムーズで安心な発送につながります。
クッション封筒郵便局での使い方と購入・発送のポイントまとめ
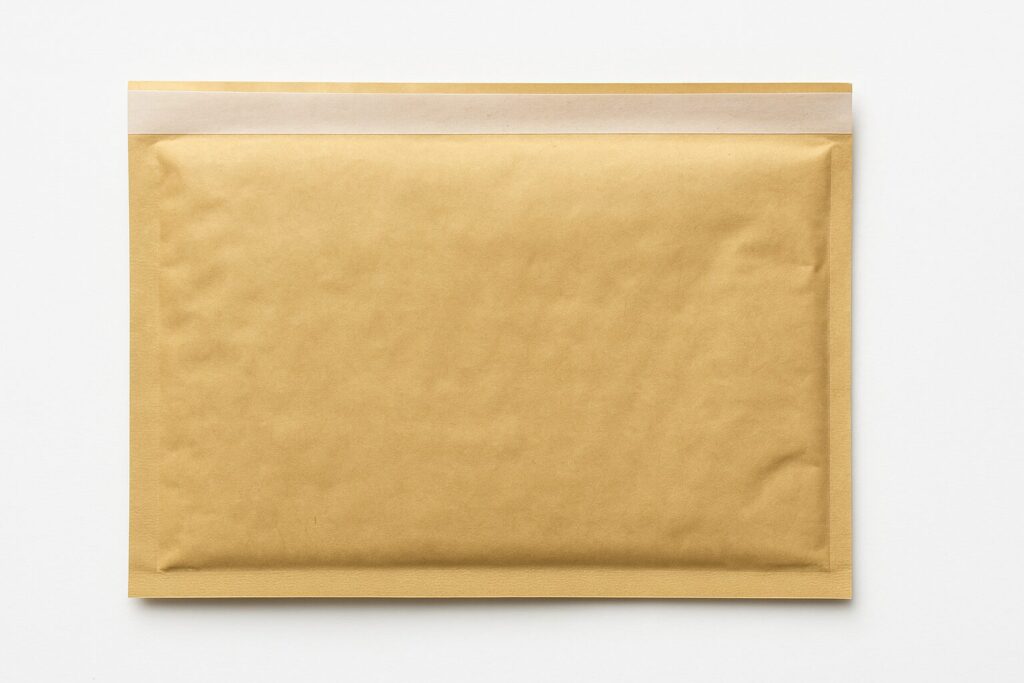
- クッション封筒は郵便局で小型の壊れやすい物の発送に適している
- 郵便局で使えるサービスには定形外郵便、ゆうパック、レターパックなどがある
- 定形外郵便は厚さと重さで規格内と規格外に分かれ料金が異なる
- クッション封筒の厚みで規格外になるケースが多く送料が上がりやすい
- 送料を抑えるには中身を詰め込みすぎない工夫が必要
- 切手の料金は重さとサイズによって変動するため事前に測るのが望ましい
- 切手は郵便局で購入すれば適正料金を案内してもらえる
- クッション封筒の宛名は読みやすく大きめの字で書くことが推奨されている
- 差出人情報の記載は返送対策として必須とされている
- 郵便局では封筒のサイズに合った発送サービスをその場で選べる
- クッション封筒は郵便局の窓口でも購入できるが取り扱いは店舗により異なる
- ダイソーでは低価格で複数サイズのクッション封筒を取り扱っている
- コンビニでは在庫にばらつきがあるが緊急時の購入には便利
- ネコポスは厚さ2.5cm以内の制限がありクッション封筒は適さない場合がある
- 発送内容に応じて封筒の材質やサイズを選ぶことが配送トラブル防止につながる
関連記事


