「郵便局配達何時まで」と検索しているあなたは、荷物や郵便物がいつ届くのか、あるいは再配達が何時まで可能なのか知りたい状況ではないでしょうか。特に仕事や外出の予定があると、配達時間を正しく把握しておくことはとても重要です。
夜なのにまだ届かない、土日でも配達してくれるのか、翌日届かせたい場合は何時までに出せばいいのかなど、タイミングを見誤ると受け取れないだけでなく、必要な書類や荷物が間に合わないこともあります。
この記事では、郵便局の配達は何時までか、最新の配達時間の目安から再配達の受付時間、土日の配達状況、さらに翌日に届けたい場合の出し方まで、必要な情報をまとめています。生活やビジネスに役立つ実用的な内容だけを、わかりやすく整理しました。
配達時間の仕組みを知ることで、荷物の受け取りがスムーズになり、不安やストレスも軽減できます。遅い時間帯の配達状況や、21時を過ぎても届かないときの対処法についても触れていきますので、ぜひ最後まで読み進めて、安心して郵便を利用できる知識を身につけてください。
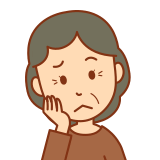
💡記事のポイント
- 郵便配達終了の目安と夜間の上限
- 郵便の再配達の当日締め切りと申し込み方法
- 郵便の土日配達の可否と時間帯指定の最新ルール
- 郵便を翌日に届けるための差出しタイミング
郵便局の配達は何時まで?最新の配達時間と配達状況まとめ

- 郵便局の配達は何時までか詳しく解説
- 郵便の配達は夜何時まで行われるのか
- 郵便で一番遅い時間の配達事例と実情
- 郵便局の配達は何時から始まるのか
- 郵便局の午前中の配達は何時から届くのか
- 郵便配達は1日に2回あるのか最新情報
郵便局の配達は何時までか詳しく解説
郵便局の配達時間は、郵便物の種類や地域ごとの配達体制によって異なります。特に、普通郵便とゆうパックなどの荷物系サービスでは、運用ルールが大きく異なる点に注目する必要があります。
まず、普通郵便の配達は日中が中心です。現在の制度では、普通郵便は原則として夜間に配達されません。これは、郵便法に基づく業務効率化や人員配置の見直しにより、従来のような夕方以降の配達が縮小されているためです。配達は午後の早い時間帯に集中することが多く、夕方以降は配達量が少なくなる傾向があります。
一方、ゆうパックをはじめとする荷物配達サービスでは、夜間帯まで対応しています。指定できる配達時間帯は、午前中、12時〜14時、14時〜16時、16時〜18時、18時〜20時、19時〜21時の6区分で運用されています。このうち、19時〜21時が最も遅い配送枠であり、利用者の生活スタイルに合わせた幅広い選択肢が提供されています。
ただし、時間帯指定はあくまで範囲を示すものであり、確実な時間ではない点に注意が必要です。交通状況、天候、繁忙期(特に年末や通販セール時期)などによって遅延が発生する可能性があり、実際には20時台後半に配達されるケースもあります。
普通郵便は「夕方まで」、荷物は「夜間21時頃まで届く可能性がある」という理解が現実的です。また、確実に夜間に受け取りたい場合は、ゆうパックなどの時間帯指定サービスを利用するのが最も確実な方法です。
信頼性の高い情報を確認したい場合には、日本郵便の公式案内が基準となります。
(出典:日本郵便公式サイト https://www.post.japanpost.jp)
郵便の配達は夜何時まで行われるのか
夜間の配達が何時まで可能かは、多くの利用者にとって重要なポイントです。特に「21時を過ぎても届かない」という不安を抱く人も少なくありません。夜間の配達時間帯の上限は、ゆうパックの時間帯指定サービスが基準となります。
現在、日本郵便では最も遅い配達枠が「19時〜21時」です。従来は「20時〜21時」という専用枠が存在しましたが、2024年10月に廃止され、現在の運用に統一されています。これにより、夜間の対応は以前と比べてやや前倒しされた形です。
つまり、夜間配達の上限は「21時頃」が目安ということになります。ただし、実際の配達は地域や日によって前後します。都市部では交通渋滞や荷物量、ビルのセキュリティ対応が影響することがあり、地方ではルートの合理化により配達時間帯が限定される場合があります。
また、繁忙期(年末年始、Amazonセール期間など)には、配達量が急増し、時間帯指定が遅れるケースも見られます。日本郵便も繁忙期の遅延について注意喚起を行っており、夜間の最終枠において実際に20時50分頃に届いたという利用ケースも報告されています。
一方、普通郵便は夜間配達を行いません。夜遅くに手紙が届くことを期待して待ち続けるのではなく、翌日以降の配達に回ると考えた方が現実的です。夜間の受取を確実にしたい場合は、ゆうパックやレターパックプラスなどのサービスを活用することが推奨されます。
郵便で一番遅い時間の配達事例と実情
郵便物が届く最も遅い時間帯に関する実情は、荷物と普通郵便で大きく異なります。荷物が最も遅く届く可能性があるのは「19時〜21時」の時間帯です。この枠内であれば、配達ルートの最終順や地域の状況によって20時後半に到着することもあります。
なお、例外的に21時を少し過ぎて到着するケースがSNSなどで話題になることがありますが、これはあくまで例外的な状況であり、通常運用ではありません。配達員の勤務時間管理や労働環境の保護の観点からも、21時以降の配達は制度上避けられる運用となっています。
また、普通郵便は夜間配達を行わないため、夕方以降に届かない場合は通常翌配達日に持ち越されます。特に、土日祝日については普通郵便の配達は原則休止されており、金曜日の夕方以降に差し出した普通郵便は、最短でも月曜日以降の配達になる可能性があります。
このため、急ぎの郵便物を確実に夜間帯に届けたい場合は、速達やゆうパックといった追加サービスの利用が必須です。また、再配達の受付締切にも注意が必要で、当日中に再配達を希望する場合は、担当郵便局の受付時間内に手続きを行う必要があります。
利用者としては、「普通郵便は日中」「荷物は21時まで」という基本理解を持ちつつ、繁忙期や天候などの外部要因による遅延の可能性も見込んでおくと安心です。遅延が続く場合は、追跡システムや最寄り郵便局への問い合わせを活用することで状況を把握できます。
郵便局の配達は何時から始まるのか

郵便局の配達が始まる時間は、全国で統一されているわけではありません。地域の配達センター規模、担当エリアの広さ、当日の郵便物の量、天候・交通事情などによって幅が出るのが実情です。都市部と地方でも差があり、人口密集地では早朝から大量の仕分け作業が行われます。
一般的な流れとしては、早朝から郵便物の仕分け作業が行われ、その後、配達担当者が順次出発します。多くの地域では午前9時頃から配達がスタートするケースが多いとされています。ただし、ゆうパックに午前中指定があることから、午前中の早い時間帯を目指して動く配達体制が組まれていることが一般的です。
一方、普通郵便については時間帯指定がありません。郵便物は各集配営業所のルートに従って巡回順に配達されるため、同じ地域でも日によって到着時刻が前後することがあります。平日でも繁忙期には午前中の配達が遅れ、午後にかかることも想定されます。
また、大型物流拠点の新設や郵便法改正による業務最適化の影響で、地域ごとの配達体制は年々改善されています。正確な時間を確保したい場合や、重要な書類を午前中早めに受け取りたい場合には、ゆうパックや速達を検討することで予見性が高まります。
(出典:日本郵便株式会社公式サイト https://www.post.japanpost.jp)
郵便局の午前中の配達は何時から届くのか
午前中の配達についても、明確な時刻が制度として決まっているわけではありません。ゆうパックなどの荷物の場合、「午前中」という配達希望枠が設定されており、一般的には8時〜12時の間とされています。ただし、これは配達完了目標時間帯であり、必ずしも指定時刻きっかりに届くことが保証されるものではありません。
郵便局では、配達希望時間帯に合わせて配達ルートを調整していますが、交通渋滞、天候不良、大型団地・ビルのセキュリティ対応などにより、午前中枠の終盤にずれ込むことも見られます。
普通郵便の場合、時間帯指定がないため、午前に届く日もあれば午後に回る日もあります。特に繁忙期や年末年始は郵便量が大幅に増加するため、午前中の配達期待値は相対的に下がる傾向があります。
重要書類や契約に関わる資料など、午前中必着が求められる場合は、配達時間帯指定郵便や速達を利用することで確実性が向上します。速達の場合は通常よりも優先的に処理され、都市部であれば朝早い段階での配達にも対応するケースがあります。
確実性を重視する場合は、郵便追跡サービスを活用し、リアルタイムで状況を確認することもおすすめです。
郵便配達は1日に2回あるのか最新情報
かつては一部地域で午前便・午後便といった形で複数回配達が行われていました。しかし、近年の郵便法改正や業務効率化、郵便物量の減少、人員体制の見直しにより、現在では原則一日一回の配達が標準となっています。
特に普通郵便については、2021年の制度改正で土曜日配達が休止され、平日のみの配達が基本となりました。また、郵便物到着までの日数が見直され、一部地域で配達日数が繰り下げられています。これにより、従来感じられていた「午前中に来なかったから午後に来る」という期待は、現在の運用では当てはまらなくなっています。
一方、荷物は別系統で運用されており、ゆうパックなどの宅配便サービスは土日祝日も配達されます。時間帯指定も可能で、生活スタイルに合わせて受取時間が調整できる仕組みです。
複数回配達制度の廃止は効率化が目的であり、人員不足対策や物流全体の最適化という背景があります。郵便サービスをより確実に利用するには、配達物の種類に応じて適切なサービスを選ぶことが重要になります。
参考表:荷物と普通郵便の配達の目安
| 区分 | 配達日 | 配達時間帯の目安 | 夜間帯 |
|---|---|---|---|
| ゆうパック等の荷物 | 平日・土日祝 | 午前中、12-14、14-16、16-18、18-20、19-21 | あり |
| 普通郵便 | 平日のみ(原則) | 日中中心で巡回順に到着 | なし |
郵便局の再配達や時間指定は何時まで?土日や当日扱いの受付時間ガイド

- 郵便局の再配達受付は何時まで可能か
- 郵便局で指定できる配達時間帯と注意点
- 郵便局の配達は土日に何時まで対応しているのか
- 郵便物は何時までに出せば翌日に届くのか
- 郵便局の当日配達は何時まで受付しているのか
- 郵便局の配達時間は後から変更できるのか方法と注意点
郵便局の再配達受付は何時まで可能か
再配達を依頼できる時間は、配達を担当する郵便局ごとに受付締切時刻が設定されており、全国で完全に統一されているわけではありません。これは、各配達エリアの業務量や担当人員、交通事情、配達ルートの構成などが異なるためです。
一般的な目安として、日本郵便が案内しているところでは、当日中の再配達を申し込む場合、夕方頃までの手続きが必要になるケースが多く、17時前後を目安として案内されることがあります。しかし、地域によっては16時や18時など異なる締切時間が設定されているため、必ずしも全国共通ではありません。
再配達の申し込み方法は複数用意されており、不在票に記載された番号を使って、電話・公式Webサイト・LINE公式アカウント・ゆうびんIDアプリから手続きができます。特にWebやアプリ経由は24時間受け付けており、締切時間に間に合えば当日配達を手配できます。締切後の場合は翌日の再配達指定となります。
なお、どうしても当日中に荷物を受け取りたい場合、郵便局の窓口で「窓口受取(持ち戻り郵便物の受取)」が可能な時間帯が設定されているケースもあります。夕方以降でも、郵便局の集配営業所に直接受け取りに行ける場合があるため、急ぎの場合は担当局への電話確認が最も確実です。
(出典:日本郵便公式「再配達の申込」 https://www.post.japanpost.jp)
郵便局で指定できる配達時間帯と注意点
荷物を確実に受け取りたい場合、時間帯指定サービスの活用が非常に有効です。郵便局では、ゆうパックなどの荷物について、以下6つの時間帯指定枠が提供されています。
- 午前中
- 12時〜14時
- 14時〜16時
- 16時〜18時
- 18時〜20時
- 19時〜21時
これらの枠は時間帯「帯」であり、例として「14時〜16時」を選択しても、必ず14時ちょうどに配達されるわけではなく、帯の中で最適なルートに応じて配達が行われます。
また、かつては20時〜21時のみを指定できる独立枠が存在しましたが、2024年に廃止され、現在は19時〜21時枠が最遅帯となっています。この変更は、物流業界全体での働き方改革や人員配置最適化の流れの一環として行われました。
集合住宅やオフィスビルなど、セキュリティ設備や入館手続きが必要な物件では、配達効率上、枠の後半に配達される傾向があります。早い時間帯の受取を希望する場合、午前中または12時〜14時の早い枠を選択することで、スムーズに受け取れる可能性が高まります。
参考表:ゆうパックの指定可能時間帯
| 指定枠 | 内容 |
|---|---|
| 午前中 | 午前中の範囲で配達 |
| 12-14 | 昼過ぎの時間帯 |
| 14-16 | 午後前半 |
| 16-18 | 夕方 |
| 18-20 | 夜間前半 |
| 19-21 | 夜間後半の最遅枠 |
郵便局の配達は土日に何時まで対応しているのか
土日祝における郵便配達の対応状況は、郵便物の種類やサービス形態によって変わります。
まず、普通郵便(はがき・手紙など)は、2021年以降の制度変更により、土曜日配達が廃止されています。そのため、基本的に平日のみの配達です。ただし、祝日を含むカレンダー状況によっては、郵便受けに届く時刻がずれ込むことがあります。
一方で、ゆうパック・レターパック・速達などの「荷物系サービス」「特別扱い郵便物」は、土日祝も配達されます。また、ゆうパックは時間帯指定が可能なため、土日でも19時〜21時枠での配達が行われるケースがあります。つまり、荷物については休日でも夜間帯までの配達が期待できます。
荷物を確実に受け取りたい休日がある場合、荷物系サービスを利用するか、配達時間帯指定郵便や速達を選択することで到着時間の予見性が高まります。また、不在の場合には翌日以降の再配達手続きが必要なため、受取予定が分かっている場合は事前に配達希望時間帯を指定しておくと安心です。
郵便物は何時までに出せば翌日に届くのか

郵便物を翌日に届けたい場合、差し出した時間と取扱局の処理スケジュールが大きく影響します。とくに、郵便局窓口とポスト投かんでは扱いタイミングが異なるため、注意が必要です。
まず、窓口で当日扱いになる締切時刻は局ごとに異なります。一般的な案内では、午前差出の場合はおおむね正午頃、午後差出であれば17時前後が、当日受付のひとつの目安とされています。都市型の集配局や主要拠点では遅め、地方の小規模局では早めに設定されていることもあります。
次に、ポスト投かんの場合は、最終取り集め時刻が重要になります。ポストの表示に記載された回収時間を過ぎると、翌日分扱いに回されるため、翌日に届けることは難しくなります。住宅街のポストは夕方前に最終回収となるケースが多く、オフィス街や駅前のポストでは夜間の回収が設定されている例もあります。
なお、普通郵便は制度改正により翌日配達範囲が大幅に縮小されています。現在では、近距離であっても翌々日配達が一般化しつつあり、地域によってはさらに日数を要する場合があります。とくに、金曜日の発送は週末の通常郵便停止の影響で到着が遅れやすいため、業務用文書や契約書などの重要書類を取り扱う際には、計画的な差出が求められます。
確実に翌日に届けたい場合、速達やゆうパックなどの荷物系サービスを選択するのが現実的です。速達は通常郵便より優先で処理され、都市部では午前中差出で翌日午前に届くケースもあります。荷物サービスの場合は追跡も可能で、到着見込みも案内されるため安心感があります。
(出典:日本郵便公式「手紙・はがきの送付」 https://www.post.japanpost.jp)
郵便局の当日配達は何時まで受付しているのか
当日配達に関しては、二つの観点で理解すると整理しやすくなります。
1つ目は「差し出しを当日扱いとする時間」、
2つ目は「再配達を当日中に受け取れる申し込み時間」です。
まず、差出しについては、郵便窓口や取扱所ごとに設定されている当日処理の締切時刻に間に合う必要があります。一般的には夕方頃が目安とされますが、主要集配局であれば17時以降も受付できる場合があります。一方、小規模局や簡易郵便局では締切が早めに設定されることもあるため、最寄り局の営業時間と締切時刻を事前に確認すると安心です。
次に、再配達の当日受付についてです。こちらも担当局の体制により異なりますが、最終受付は原則として夕方までと案内されています。Webや自動電話での受付は24時間対応していますが、当日実行できるかどうかは、締切時刻に間に合うかで決まります。
荷物をその日のうちに受け取りたい場合、なるべく午前中〜早い午後の時間帯で依頼するのが現実的です。また、夜間帯の受け取りを希望する場合は「19時〜21時」枠を選択することで、当日中の受取期待値が高まります。
業務や契約タイミングが絡む場合には、速達や時間帯指定郵便を利用し、さらに追跡サービス確認を併用することで、受取リスクを減らすことができます。
郵便局の配達時間は後から変更できるのか方法と注意点
郵便物の配達時間帯は、基本的に後から変更することが可能です。不在票に記載された「お問い合わせ番号」を利用し、Webサイト、音声自動対応、オペレーター対応、またはLINE公式アカウントから受付できます。再配達申し込みと同様の手続きで、柔軟に変更を行える点が利便性の特徴です。
ただし、希望の時間帯にすでに配達枠が埋まっている場合、当日の別時間帯や翌日以降の時間帯を提案されることがあります。とくに、夜間帯(19時〜21時)は人気枠で、仕事帰りの受取を希望する利用者が多いため、繁忙期には集中しやすい傾向にあります。
配達条件によっても調整が左右される点に注意が必要です。マンションのオートロックや法人オフィスの入館ルールがある場合、配達効率上、希望帯の後半になることがあります。また、宅配ボックスが設置されている場合は、その情報を事前に登録しておくと、配達がスムーズになり再訪リスクを減らせます。
配達時間変更を行う際は、配送ステータスの確認も重要です。すでに配達担当者がトラックに積み込み出発している場合、当日中の変更受付ができないこともあります。したがって、受取時間の調整が必要な場合は、なるべく早いタイミングで手続きすることが推奨されます。
郵便局の配達は何時まで?最新配達時間と再配達の受付時間まとめ

- 配達終了の目安は、普通郵便は日中が中心で、ゆうパックなどの荷物は夜間帯まで対応される傾向がある
- 夜間配達の最遅時間帯は、荷物の19時から21時の配達帯が上限の実質的な目安となっている
- かつて選択できた20時から21時の時間指定枠は廃止され、現在は19時から21時の枠のみとなっている
- 普通郵便は制度変更により土曜日配達が休止され、日曜・祝日も原則として配達されない運用となっている
- ゆうパックやレターパック、速達などの荷物系や特殊扱い郵便は、土日祝でも通常どおり配達が行われる
- 再配達の当日受付時間は地域差があり、一般的には夕方頃までの申し込みが当日再配達に間に合う目安とされる
- 郵便物を当日扱いにするかどうかは、郵便局窓口の受付締切時刻とポストの最終取り集め時刻に左右される
- 翌日に必ず届けたい場合は、普通郵便よりも速達やゆうパックなどの荷物系サービスを利用するのが堅実で確実
- 午前中配達の指定は「午前中」という帯での目安であり、分単位での到着時間の確約はできない仕組みになっている
- 配達は午前の早い時間帯から順次開始されるが、当日の物量や配達ルートによって出発時刻が前後することがある
- 普通郵便は原則として一日一回の配達体制となっており、夜間帯の配達は制度上想定されていない
- 配達時間帯指定は、午前中から19時〜21時までの六つの区分から選択する形式になっている
- 夜間帯は利用希望が集中しやすく、特に19時〜21時枠は需要が高く予約枠が埋まりやすい傾向がある
- 受け取り条件やマンション・ビルの入館ルールなどを事前に登録しておくと、スムーズな配達につながる
- 荷物が届かない、遅延の可能性があると感じたときは、追跡サービスの確認に加えて担当局に直接問い合わせるのが最短で確実な手段となる
関連記事







