郵便物を送るとき、切手の料金が足りているか不安になった経験はありませんか?特に、返信用封筒を送る場面や、やや厚めの資料を封入するような場面では、うっかり郵送料が不足してしまうことがあります。そんなときに便利なのが「不足分受取人払い」という制度です。
この仕組みをうまく活用すれば、差出人側が切手を貼り忘れても、受取人が料金を支払うことで郵便が無事に届けられます。ただし、やみくもに使ってよい制度ではなく、いくつかのルールや注意点を理解しておく必要があります。正しい書き方を知らずに送ってしまうと、郵便局で処理されず返送されたり、相手に迷惑をかけてしまうこともあるため注意が必要です。
この記事では、「不足分受取人払いとは何か?」という基本から、実際の使い方、書き方のポイント、さらには利用する際の注意点までを丁寧に解説します。受取人が本当に支払ってくれるのか、手書きでも大丈夫なのか、切手を貼らずにポスト投函していいのか…そんな疑問を一つひとつ解消できるよう構成しています。
この記事を読むことで、制度の仕組みを理解するだけでなく、現場でのトラブルを避けるための実践的な知識も身につけられます。これから不足分受取人払いを使おうと考えている方はもちろん、すでに利用したことがある方にも役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
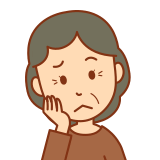
💡記事のポイント
- 不足分受取人払いがどのような制度か、その基本的な仕組みを理解できる
- 封筒への具体的な書き方や記載位置などの実務的な方法がわかる
- 使えないケースや受取人が拒否した場合の注意点を把握できる
- 着払いとの違いや、制度を誤用した際に起こり得るトラブルを知ることができる
不足分受取人払いとは?郵便料金不足時の正しい対応方法

- 不足分受取人払いとはどういう意味か?
- 不足分受取人払いはできない場合もある?注意点を解説
- 郵便料金不足は差出人が払う?受取人が払う?
- 不足料金受取人払いの正しい書き方とは?
- 切手の不足分を支払う方法|現金・切手の取り扱いも
- 郵便料金不足の郵便物はどうなるの?配達・返送の流れ
不足分受取人払いとはどういう意味か?
不足分受取人払いとは、郵便物の送料が不足していた場合に、その差額分の料金を郵便物の「受取人側が支払う」制度のことを指します。差出人のミスや確認不足により、正しい郵便料金が貼られていなかった場合、本来は差出人が責任を持って対応すべきところですが、あらかじめ「不足分を受取人が払ってもよい」といった意思表示があることで、この制度が適用されます。
この方法が利用される代表的なケースとして、返信用封筒を送る場面があります。例えば企業や役所が、問い合わせや申請に対する返信用封筒を用意する際、そこに切手を貼らずに「不足分受取人払い」と明記しておくことで、切手がなくても受取人側で料金の支払いを行うことが可能になります。これにより、依頼者側が自分で切手を用意する手間を省けるメリットがあります。
ただし、不足分受取人払いを成立させるためには、郵便物の表面にその旨をはっきり記載しておく必要があります。具体的には、「不足料金受取人払い」や「不足分受取人払い」といった文言を記し、場合によってはスタンプやゴム印を使って強調することもあります。記載が不明瞭だと、郵便局側で処理できないケースもあるため、正確な表記と位置づけが重要になります。
こうして見ると、不足分受取人払いは便利な制度ではあるものの、その使い方にはルールや前提条件があるため、郵便物を送る前にきちんと理解しておくことが大切です。
不足分受取人払いはできない場合もある?注意点を解説
不足分受取人払いは万能な制度ではなく、状況によっては適用できないことがあります。制度上は確かに便利ではありますが、適切に処理されなければ受取人に郵便物が届かない、あるいは差出人に返送されるといったトラブルの原因にもなりかねません。
まず注意すべきなのは、すべての郵便物で不足分受取人払いが使えるわけではないという点です。たとえば、通常郵便で明確な意思表示がなく、勝手に切手が足りない状態で送っただけでは、受取人払いにはなりません。明確に「不足分を受取人が負担する」ことを記載していなければ、郵便局側では処理されず、差出人に返送される可能性があります。
また、受取人が料金の支払いを拒否した場合にも、この方法は使えません。つまり、受取人払いで発送された郵便物を、受取人側が「料金を払いたくない」「そんな物は頼んでいない」といった理由で拒否すれば、その郵便物は差出人に戻されます。受取人の了承が前提になるため、事前の説明や合意が不可欠です。
さらに、「料金不足」と「着払い」の違いについて混同しがちな点も注意が必要です。不足分受取人払いは、あくまで郵便料金の差額の話であり、宅配便などで使われる「着払い」とはまったく異なる扱いです。そのため、郵便局員や利用者自身が誤って処理を行うと、トラブルにつながる恐れもあります。
このように、不足分受取人払いには便利な側面がある一方で、制度を正しく理解していなければ思わぬミスが起きる可能性があります。送り手としては、ルールや手順をよく確認したうえで活用することが求められます。
郵便料金不足は差出人が払う?受取人が払う?
郵便料金が不足している場合、その支払い義務が誰にあるのかという点は、状況によって異なります。原則として、郵便料金の支払い責任は「差出人側」にあります。つまり、切手を貼った人が適正な料金を確認せずに郵便物を差し出した場合、不足があれば差出人に返送され、再送が必要になるのが一般的な流れです。
しかしながら、あらかじめ郵便物に「不足料金受取人払い」と明記されている場合に限っては、受取人がその不足分を支払うことが可能になります。これは、受取人側の了承を前提とした制度であり、差出人が郵送ミスをした場合の救済策ではありません。事前に取り決めがなされていない状態で不足料金が発生した場合、郵便局は原則として受取人に支払いを求めることはありません。
例えば、企業が送付する返信用封筒において、「切手を貼らずに返送してください。不足分は弊社で負担いたします」と書かれているケースがあります。こういった場面では、受取人(企業)が不足分の支払いを了承しているため、料金不足が発生しても問題なく処理されます。
一方で、個人間のやり取りや非公式な文書のやり取りで、こうした記載がなかった場合、郵便局側で受取人への請求は行われません。このときは、料金不足の郵便物は差出人に返送され、再送の手間が生じてしまいます。
このため、郵便料金不足を防ぐ最も確実な方法は、差出人が事前に重さやサイズを正確に確認し、適切な切手を貼ることです。受取人払いの制度に頼るのではなく、基本的な郵便ルールを守ることで、トラブルのリスクを最小限に抑えることができます。
不足料金受取人払いの正しい書き方とは?
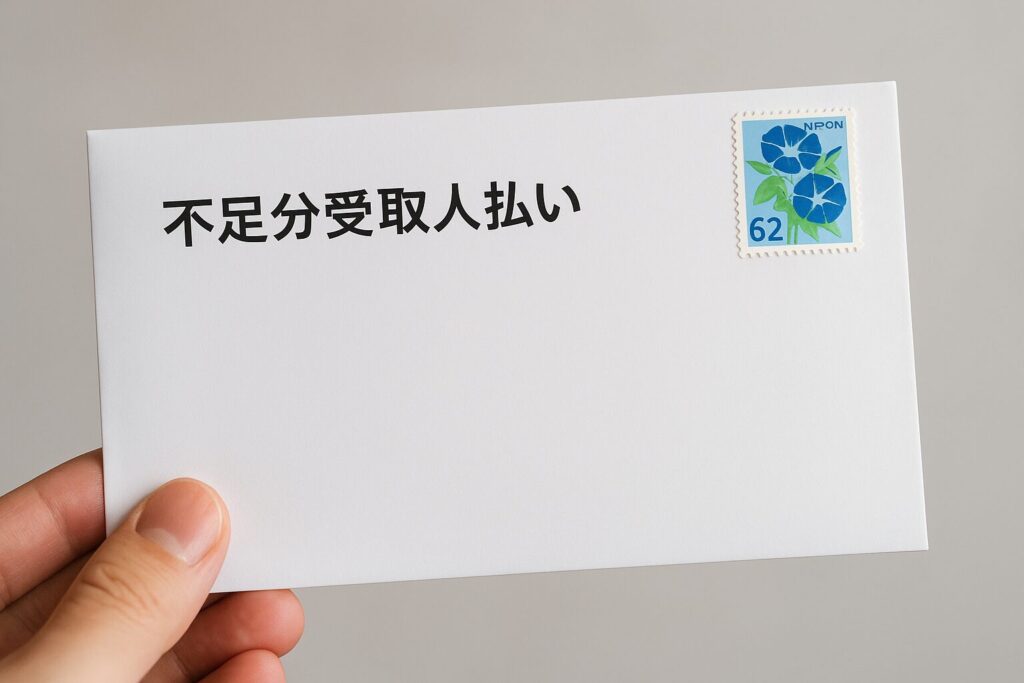
郵便物を送る際に、あらかじめ受取人に不足料金の支払いをお願いする場合は、郵便物の表面に「不足料金受取人払い」であることを明示しておく必要があります。この記載がなければ、郵便局側で処理できず、通常通り差出人に返送されてしまいます。つまり、適切な書き方をしなければ制度そのものが活用できないということです。
まず、最も基本的なのは、封筒の左下か中央付近に「不足料金受取人払い」と明記することです。記載する文字は手書きでも構いませんが、見えにくかったり読みにくかったりすることを避けるため、できるだけハッキリと書く必要があります。実務ではゴム印やスタンプを使うことも一般的です。視認性が高まり、処理ミスを防ぐ効果が期待できます。
また、企業や団体がこの方式を使用する場合には、あらかじめ「郵便局との契約(受取人払い契約)」が必要になるケースがあります。この契約を結んだ上で、専用の表示やコードを用いることで、受取人払いが正式に認められる仕組みになっています。個人間のやりとりではそこまでの手続きは不要ですが、ビジネス用途では確認が必要です。
さらに、記載ミスを防ぐためには、テンプレート化された封筒を使用する方法も有効です。たとえば、あらかじめ「不足分受取人払い」と印刷された返信用封筒を用意しておけば、毎回手書きしたりスタンプを押したりする手間が省けます。こうした事前準備ができていれば、郵便局とのやり取りもスムーズです。
ただし、誤解を防ぐために、受取人が支払いに同意しているかどうかの確認を取ることも重要です。とくに個人宛ての郵便物で、受取人に何の説明もないまま料金を請求する形になると、トラブルに発展する可能性があります。これを避けるためには、郵送前に口頭や文面で一言断りを入れるなどの配慮も必要でしょう。
このように、書き方は単に文字を記すだけではなく、郵便局や受取人への配慮も含めた全体設計が求められます。ルールを理解して丁寧に対応することが、正しくスムーズな郵送につながります。
切手の不足分を支払う方法|現金・切手の取り扱いも
郵便料金が不足していると判明した場合、どのようにその差額分を支払えば良いのかを理解しておくことは、日常的に郵便物をやり取りする人にとって重要です。特に、封筒に貼った切手の金額が規定の料金に満たなかったとき、その不足分をどのように補えばよいのかは、意外と知られていない部分です。
一般的に、切手の不足が発覚するのは、郵便局の仕分け段階においてです。その際、不足金額は差出人または受取人が負担することになります。どちらが支払うかは、郵便物に記載された内容によって判断されます。たとえば、「不足料金受取人払い」と明記されていれば、受取人がその差額を支払うことになります。そうでない場合、基本的には差出人に返送されます。
不足分の支払い方法には主に2つあります。ひとつは現金による支払いです。郵便局の窓口で直接、不足分を現金で支払うことができます。ただし、これは郵便物が差出人に返送された後の対応となるため、再送の手間や時間がかかります。
もうひとつは、追加の切手を貼って補う方法です。たとえば、84円切手を貼ったものの、実際には94円必要だった場合、不足分の10円分を追加の切手で補うことが可能です。この際、差出人に返送されてから追加で貼り直す必要があるため、やはり一度は配達が中断されます。郵便局員によっては、不足金額の通知とともに「差出人払いにて返送されました」と明記して戻してくることもあります。
一方で、受取人が不足料金を支払うケースでは、配達時に郵便局員が直接料金を請求することがあります。その際、受取人は現金で支払うか、後日窓口で精算することになりますが、基本的には配達時に支払いが求められると考えておいた方がよいでしょう。まれに、小銭の持ち合わせがないなどの事情で受け取りを拒否され、郵便局に持ち帰られるケースもあるため注意が必要です。
こうした不便やトラブルを防ぐためには、最初から適正な料金を確認して送付することが最善です。特に重さやサイズで金額が変わる定形外郵便や特殊取扱いの郵便物では、ポスト投函ではなく、窓口で重さを量ってもらってから差し出すことが望ましいと言えます。
郵便料金不足の郵便物はどうなるの?配達・返送の流れ
郵便物の料金が不足していた場合、それがどのような処理をされ、最終的にどうなるのかを正しく理解しておくことで、無用なトラブルや再送の手間を避けることができます。郵便局では日々多くの郵便物を取り扱っており、料金不足に対するフローもある程度マニュアル化されていますが、そこにはいくつかのパターンがあります。
まず、郵便物が料金不足であると判断された場合、郵便局は差出人または受取人のどちらがその費用を負担するのかを確認します。「不足料金受取人払い」と明記されていれば、受取人に配達され、配達時に不足分の支払いを求められるのが基本的な流れです。受取人が料金を支払えば、そのまま郵便物は受け取られ、やりとりが成立します。
一方で、そのような明記がない郵便物に関しては、原則として「差出人に返送」されます。このとき、封筒の裏面に記載された差出人の住所に向けて郵便物は戻され、料金不足の旨が記されたシールや紙片が添付されて返ってくるのが一般的です。差出人はその不足金額を確認し、追加で切手を貼り直した上で再度差し出す必要があります。
なお、差出人の情報が封筒に書かれていない、または不明瞭な場合には、郵便物は配達不能郵便物として一定期間、郵便局で保管されることがあります。その後、所定の保存期間が過ぎると処分対象になる可能性もあるため、差出人情報の記載は非常に重要です。
また、受取人払いが指定されていたとしても、受取人がその支払いを拒否した場合には、郵便物は差出人に返送されます。これもまた、やりとりが成立しない原因となります。事前に受取人と料金負担について合意が取れていない場合、せっかくの郵送が無駄になってしまう恐れがあります。
このように、郵便料金が不足していると、さまざまなパターンで遅延や返送が発生します。これを避けるためには、発送前にサイズや重さを確認する習慣をつけることが何よりも大切です。特に複数ページの書類を同封する際や、封筒の素材が重い場合には、少しでも不安があれば窓口での計量を依頼すると安心です。
不足分受取人払いの記載方法と便利なツールの活用

- 不足料金受取人払いの書き方|手書きで対応する方法
- 不足分受取人払いを手書きで行う際の注意点と例文
- 不足分受取人払い用のゴム印・スタンプ・ハンコの使い方
- 切手なしの返信用封筒に不足分受取人払いを適用するには?
- 不足分着払いと受取人払いの違い|間違いやすいポイント
- 受取人払いの期限切れとは?有効期間と対処方法を確認
不足料金受取人払いの書き方|手書きで対応する方法
郵便料金が不足した場合に、その差額を受取人が支払う「不足料金受取人払い」という制度は、実務の現場でもよく利用される方法です。とくに、返信用封筒や社内申請書類のやりとりで用いられるケースが多く、わざわざ切手を貼る手間が省けることから、業務効率化にもつながります。この方法を採用するには、郵便物に「その旨を明記する」ことが絶対条件です。
特別な契約がなくても、簡易的な形で利用するのであれば、封筒の表面に**「不足料金受取人払い」または「不足分受取人払い」などの文言を手書きで記載するだけでも機能します**。この際、書く位置は封筒の左下、または住所の下あたりが適切とされています。郵便局の仕分け担当者が一目で確認できるよう、できるだけ大きめの文字で、はっきりと記載しましょう。
書体について厳格なルールはありませんが、読みやすさは重視すべきポイントです。たとえば、崩した文字や極端に装飾された文字だと、処理ミスの原因になります。手書きで対応するからこそ、丁寧な記載が求められるのです。
加えて、郵便物が業務用であれば、記載内容に「御中」や「担当者名」なども含めておくと、受取人側での処理がスムーズになります。また、受取人にとっても「差額を自分で支払う」という負担が発生するため、事前にその了承を得ておくことが理想的です。とくに個人間でのやり取りでは、こうした配慮が信頼関係を保つうえで重要になります。
このように、特別な道具や印刷技術がなくても、手書きだけで不足料金受取人払いを成立させることは十分可能です。ただし、それを確実に成立させるには、読みやすい文字、正しい記載位置、そして事前説明といった「丁寧さ」が前提になります。
不足分受取人払いを手書きで行う際の注意点と例文
不足分受取人払いを手書きで行う場合、ただ文字を書くだけでは意図が正しく伝わらないことがあります。郵便局の仕分け作業は膨大な量の郵便物を高速で処理する現場で行われており、そこでは「見やすさ」と「明確さ」が最優先されます。つまり、手書きで記載する際には、いくつかの大切な注意点を意識しなければなりません。
まず、記載する内容としては「不足料金受取人払い」や「不足分受取人払い」のどちらかを明確に書くことが基本です。どちらも意味としては大きな違いはありませんが、表記の統一性や明瞭さの面で、「郵便局が理解しやすい表現」を選ぶのが無難です。文字数が少ないほうが視認性は上がるため、「不足料金受取人払い」という表現が一般的に用いられることが多いようです。
次に、書く場所にも注意が必要です。住所のすぐ下や封筒の左下など、郵便番号や宛名と混在しない場所に書くのが適切です。誤解を避けるため、赤ペンや目立つ色のペンを使うという方法もありますが、派手すぎる装飾は逆に処理の妨げになる可能性もあるため、色の使い方にも節度が求められます。
ここで、実際に使える例文をいくつか紹介します。
- 「※本封筒は不足分受取人払いにてご返送ください」
- 「この郵便物は不足料金を受取人払いで処理をお願いします」
- 「返信時は切手不要。不足料金は受取人が負担します」
こうした文言を封筒の空きスペースに手書きするだけでも、郵便局側に意図が伝わります。ただし、これらの文言があっても、郵便局員の判断やその時の対応状況によっては、手続きがスムーズに進まないこともあります。そのため、念のために窓口で内容を確認しておくと安心です。
特に注意したいのは、「手書きで対応するからこそミスが起こりやすい」という点です。字がかすれていたり、位置がずれていたりすると、郵便局で見落とされてしまい、本来受取人払いにしたかった郵便物が差出人に返送されてしまう可能性があります。こうした事態を防ぐためにも、できるだけ明確で簡潔な記載を心がけましょう。
不足分受取人払い用のゴム印・スタンプ・ハンコの使い方
手書きでの記載が面倒だったり、郵便物の量が多い業務用途の場合には、「不足分受取人払い」の文言をゴム印やスタンプ、ハンコで対応するという方法が非常に有効です。これにより作業の効率化が図れるだけでなく、記載ミスのリスクも大幅に低減されます。
まず、ゴム印やスタンプで対応する際には、文言が明確かつ郵便局で一般的に認識されている形式であることが重要です。例えば、「不足料金受取人払い」「不足分受取人払い」などが代表的な表記です。どちらを選んでも差し支えはありませんが、可能であれば郵便局の窓口で使用可能かどうかを事前に確認しておくと安心です。
スタンプを押す位置は、封筒の左下が一般的です。宛名や郵便番号にかぶらないよう、他の情報と混同されない場所に押すことで、郵便局の仕分け担当者にも正確に伝わります。作業を行う際は、封筒の素材やインクの乾きやすさなども考慮し、スタンプがにじんだり擦れたりしないよう注意する必要があります。
また、押し方そのものにも気を配るべきです。印字が薄い、斜めになって見づらい、といった押し方では、逆にトラブルの原因になります。業務で大量に処理する場合は、スタンプ専用の補助器具を使うと、毎回均等な押印ができるため便利です。
このようなツールは、文房具店やネットショップで比較的安価に手に入れることができます。中には、企業ロゴと併記されたスタンプや、住所と一体化したタイプなどもあり、用途に応じて選ぶことが可能です。頻繁に郵便物を発送する企業であれば、こうした専用のスタンプを作成しておくことで、手間とミスの両方を削減できるでしょう。
ただし、ゴム印を使ったからといって、受取人払いが必ず適用されるわけではありません。受取人が支払いを拒否したり、郵便局が処理基準に合わないと判断したりした場合には、郵便物が差出人に返送されてしまうこともあります。そのため、文言の明確さに加えて、受取人との事前合意やルールの確認も欠かせません。
このように、ゴム印やスタンプは非常に便利な道具ですが、正しい使い方とルールへの理解がセットになってはじめて、その効果を発揮するものです。手書き対応と比べて効率が高い分、より責任を持って運用する意識も求められます。
切手なしの返信用封筒に不足分受取人払いを適用するには?

企業や官公庁から届く書類の中には、返信用封筒が同封されているケースがあります。このとき、封筒に切手が貼られておらず、代わりに「不足料金受取人払い」と記載されていることに気づいた方もいるのではないでしょうか。これは、切手を貼らずにそのままポスト投函しても、料金が不足していれば受取人側で支払ってくれる、という仕組みを活用したものです。
返信用封筒に不足分受取人払いを適用するには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。まず前提として、「差出人ではなく受取人が不足料金を負担する」という意思表示が封筒に明確に記載されていなければなりません。この記載がない場合、たとえ意図があっても郵便局側では通常どおり「差出人負担」として処理され、料金不足が発生すると差出人に返送されてしまいます。
記載方法としては、封筒の左下あたりに「この封筒は不足料金受取人払いで郵送できます」や「返信時は切手不要です。不足料金は当方が負担いたします」といった文言を記すのが一般的です。ゴム印や印刷された案内文があるとより明確ですが、手書きでも対応は可能です。
一方で、郵便局と正式に「受取人払い契約」を結んでいる企業や団体は、専用の表示スタンプや番号を封筒に記載することで正式な受取人払いを成立させることができます。この契約があることで、大量の返信郵便にも効率的に対応できるメリットが生まれます。
注意点としては、郵便物の重さや内容によって実際の送料が変動することです。たとえば、用紙を多く入れすぎて定形外郵便に該当すると、料金が大きく変わってしまいます。すると、想定より高額な負担が受取人に発生し、トラブルにつながる恐れがあります。そのため、送付物の重さが想定範囲内に収まるよう、封入物の枚数を制限したり、案内文で「○g以内を目安にしてください」といった注意書きを加えることが望ましいでしょう。
このように、切手なしの返信用封筒に不足分受取人払いを適用するには、単に「貼らない」という判断だけでなく、郵便局のルールに従った適切な表示や想定される使用方法への配慮が不可欠です。受け取る側との信頼関係を損なわないためにも、事前準備を怠らないようにしましょう。
不足分着払いと受取人払いの違い|間違いやすいポイント
郵送や配送の現場でよく耳にする「着払い」と「受取人払い」という言葉は、一見すると同じ意味に感じられるかもしれません。しかし、両者は運用されるシーンも、手続きも、扱う機関も異なります。そのため、誤って使い分けると、配送がスムーズに進まなかったり、想定外の費用が発生したりするリスクがあります。
まず、「着払い」とは宅配便やゆうパックなど、主に民間配送業者や日本郵便の宅配サービスで使われる支払い方法を指します。差出人が送料を払わずに荷物を出し、受取人が荷物の受け取り時にその送料を支払う仕組みです。ヤマト運輸や佐川急便、日本郵便のゆうパックなどで広く利用されており、個人利用にも非常に馴染みがあります。
一方で、「受取人払い」とは郵便制度、特に定形郵便や定形外郵便といった郵便物に対して適用される制度であり、送料が不足していた場合に、その差額を受取人が支払うという仕組みです。この方法は、郵便局の通常郵便でのみ運用されており、宅配便とは全く別の制度として扱われます。
間違いやすいポイントの一つは、「不足分」という言葉の使い方です。郵便物で料金が不足していた際に「着払いで送ればいい」と誤解してしまうことがありますが、これは正確ではありません。着払いは最初から送料を全額受取人に請求する形で、料金不足の補填ではなく「料金支払いそのものを受取人に委ねる」配送手段です。一方で、受取人払いは基本的に差出人が支払うことを前提としつつ、特定の場合に限り差額を受取人が負担するという制度です。
さらに、着払いはラベルに「着払い」の印字が必要であり、受取人が支払いに同意していないと受け取りを拒否されるケースもあります。一方、受取人払いの郵便物も同様に、受取人が料金支払いを拒否すれば配達はされず、差出人に返送されます。どちらの方法でも、「受取人が料金負担を了承している」という前提が成立していなければトラブルの元になります。
このように、「着払い」と「受取人払い」はまったく異なる制度であり、それぞれの特徴や使いどころを理解しておくことが大切です。用語を混同しないよう、利用する配送手段や郵便の種類によって適切に判断することが求められます。
受取人払いの期限切れとは?有効期間と対処方法を確認
郵便物を送る際に「受取人払い」を指定することは、差出人の手間やコストを軽減する便利な手段です。しかし、この制度にも有効期間、いわゆる「期限」があることをご存じでしょうか。正しく運用するためには、この期限切れのリスクや対応方法についても理解しておく必要があります。
まず、受取人払いには明確な「制度的な有効期限」が設けられているわけではありません。ただし、郵便局が実際にその郵便物を処理するタイミングや、受取人側での受け取り可否などによって、実質的に「期限切れ」と同様の扱いが生じることがあるのが実情です。
例えば、受取人払いの契約を結んでいる企業が、内部での処理フローの都合により、一定期間が過ぎた郵便物を受け取らないと決めているケースがあります。受取人側が明確に「この日以降の郵便物には対応しない」としていれば、それは事実上の期限切れとして扱われ、受け取りを拒否される可能性が出てきます。
また、郵便局で保管される期間にも注意が必要です。郵便物が配達されても受取人がその場で料金を支払えなかった場合、一時的に郵便局で留め置かれることがあります。しかし、この留め置きには期限があり、原則として7日以内に引き取りや料金の支払いが行われないと、郵便物は差出人に返送されてしまうことになります。これがいわゆる「受取人払いの期限切れ」として扱われる事例です。
このようなトラブルを防ぐには、いくつかの対処法があります。まず、受取人と事前に合意を取っておくことは必須です。とくに法人あてに送る場合には、「○月○日までに投函ください」といった明確な期限を案内文に記載すると、受取側でも対応がしやすくなります。
さらに、可能であれば差出人情報も封筒に明記しておくことが望ましいです。期限切れによって返送される際、差出人が明確でない場合には郵便局での保管や廃棄の対象になってしまいます。こうした事態を回避するためにも、発送前の準備と確認を怠らないことが重要です。
このように、制度上は明示されていなくても、「受取人払いには期限の概念が存在する」と捉えて対応することが、スムーズな郵送業務につながります。
不足分受取人払いの仕組みと利用時の注意点まとめ
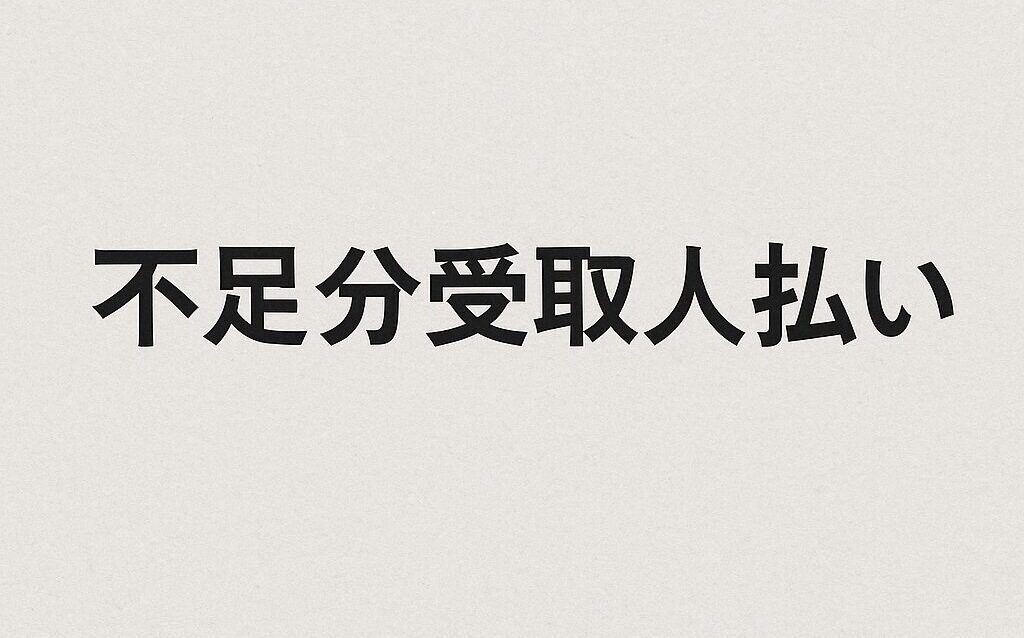
- 不足分受取人払いは、郵便料金が不足していた際に、その差額を受取人が支払うことを前提とした郵便制度である
- 差出人が料金不足に気づかず投函した場合でも、受取人が了承していれば不足分を代わりに支払うことができる
- この制度を利用するには、封筒の表面に「不足料金受取人払い」といった文言を明確に記載しておく必要がある
- 企業や団体が業務用として正式に使用するには、郵便局と受取人払い契約を結んでおくことが求められる場合がある
- 手書きで対応する際は、文字が見やすいように大きめの字ではっきりと記載し、郵便局の誤認を防ぐことが大切である
- ゴム印やスタンプを利用すれば、記載の手間を軽減でき、表記の統一や処理ミスの予防にもつながる
- 「不足料金受取人払い」の表示が封筒にない場合、郵便局は差出人に郵便物を返送するため、事前の記載は必須である
- たとえ表示があっても、受取人が料金支払いを拒否した場合、その郵便物は差出人に返送されてしまうことになる
- 宅配便の着払いとは制度の性質が異なり、郵便局の扱いとしては不足分を補う目的でしか利用されない
- 主に返信用封筒で使用されるケースが多く、あらかじめ「料金は当方が負担します」と記載された案内とセットで使われる
- 切手が不足していた場合は、差出人が現金で支払うか、追加の切手を貼って再送することで対処が可能である
- 郵便局の仕分け作業で料金不足が発覚した場合、郵便物は一旦止まり、差出人または受取人への対応が取られる
- 差出人情報が封筒に記載されていない場合、配達不能郵便として一定期間保管後に廃棄される恐れがある
- 万一返送が必要になった場合に備えて、封筒には差出人の氏名・住所を明記しておくのが望ましい
- 企業などの受取人によっては、一定期間が経過した郵便物を受け取らない運用をしていることがあり、事前確認が重要である
関連記事


