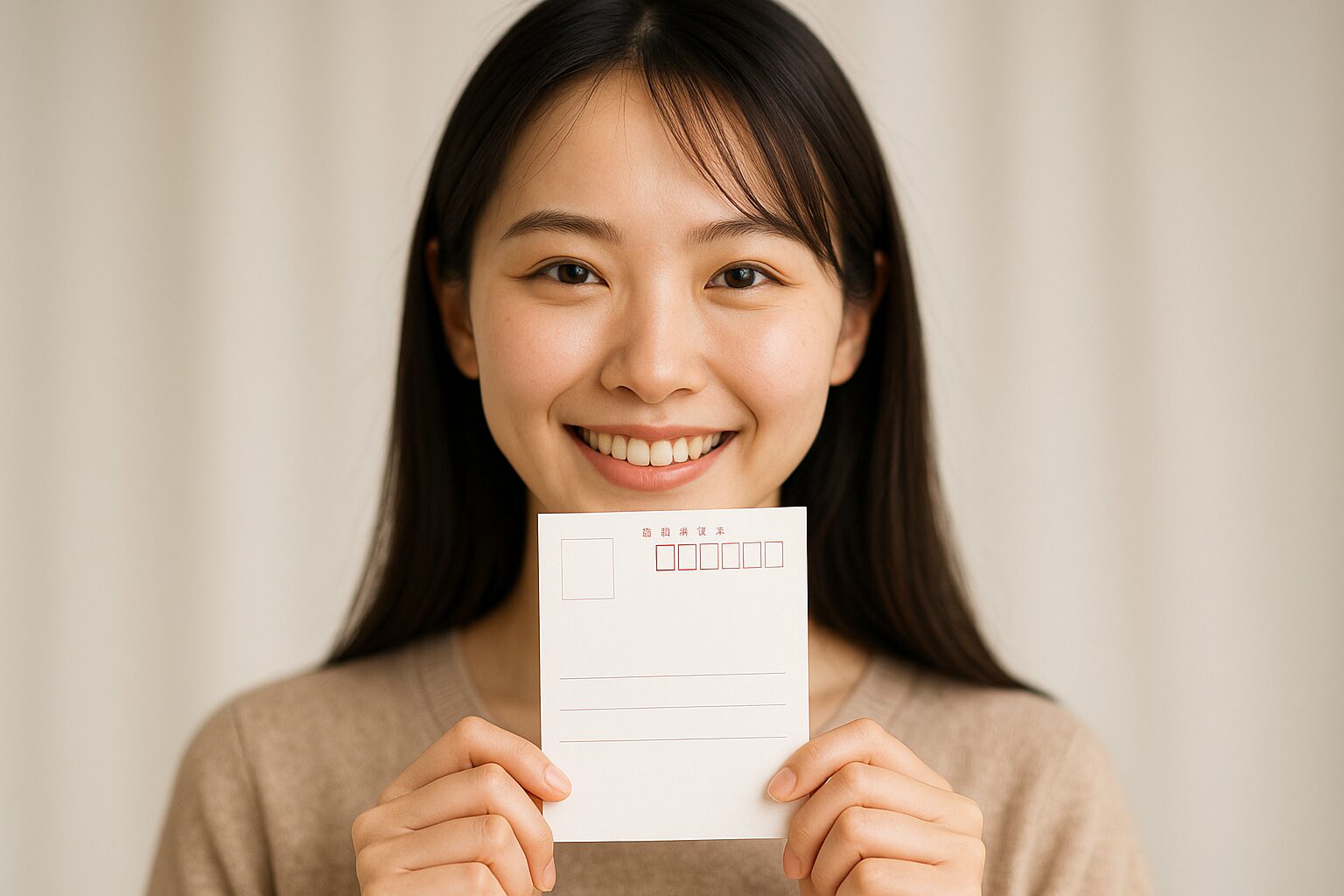「コンビニで往復ハガキ」と検索しているあなたは、おそらく今すぐに往復ハガキを用意したい、あるいはどこで手に入るのかを知りたい状況ではないでしょうか。郵便局まで行く時間がなかったり、できれば通勤途中や自宅近くのコンビニでサッと手に入れたいと考えるのは、ごく自然なことです。
しかし、実際にはコンビニで往復ハガキを買えるのかどうか、印刷できるのか、店舗ごとに違いがあるのかといった情報は、調べてみると意外と断片的で分かりづらいのが現実です。また、必要な場面になって初めて「そもそも往復ハガキってどうやって書けばいいの?」と悩む方も少なくありません。
この記事では、そんな疑問や不安を解消すべく、「コンビニで往復ハガキは買えるのか?」という基本的な問いから、取り扱いのあるコンビニチェーン、印刷の方法や注意点、さらには正しい書き方や料金についてまで、幅広く丁寧に解説しています。
読み進めるうちに、あなたが今知りたかったことが自然とつながって理解できるよう構成していますので、ぜひ最後までご覧ください。コンビニで往復ハガキを使いこなすための実践的なヒントがきっと見つかるはずです。
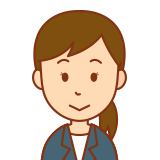
💡記事のポイント
- コンビニで往復ハガキが購入できるかどうか
- どのコンビニで往復ハガキが取り扱われているか
- コンビニで往復ハガキを印刷する方法と注意点
- 往復ハガキの正しい書き方や料金の知識
コンビニで往復ハガキは買える?購入・印刷・取扱店舗のまとめ

- コンビニで往復ハガキは買えるのか?購入可否の確認
- 「往復はがきがコンビニにない」と言われる理由とは?
- コンビニでの往復ハガキ販売の実情と店舗ごとの違い
- 往復ハガキのセブンイレブン・ファミリーマートでの取り扱い状況
- コンビニでの往復ハガキ印刷の方法と注意点
- コンビニで印刷済みの喪中はがきは買えるのか?
コンビニで往復ハガキは買えるのか?購入可否の確認
コンビニで往復ハガキが買えるのかどうかについては、多くの人が混乱しやすいポイントです。結論から言えば、「一部の店舗では購入可能だが、すべてのコンビニで常時手に入るとは限らない」というのが実情です。これは、往復ハガキの需要がそれほど高くないため、コンビニ各社が全店舗で取り扱う必要性を感じていないことに起因しています。
現在、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンといった大手コンビニチェーンでは、通常の官製ハガキは比較的多くの店舗で販売されています。しかし、往復ハガキは特殊な用途に使われることが多いため、需要が限定的であり、取り扱いをしていない店舗も珍しくありません。特に、地域密着型の小規模な店舗やフランチャイズ店では、在庫コストや販売効率の観点から、あえて取り扱いを避けているケースもあります。
実際、店舗に足を運んだものの「往復ハガキは置いていません」と言われて困惑するケースもあるでしょう。そのような場合は、まず最寄りのコンビニに事前に電話で問い合わせることが確実です。また、郵便局では常に販売されていますし、オンラインでの注文やAmazonなどのECサイトでも取り扱いがありますので、確実性を求めるならそちらを利用する方法もおすすめです。
さらに、最近ではコンビニ内に設置されているマルチコピー機で、往復ハガキサイズの印刷が可能なサービスも登場しています。ただし、この場合はあくまで印刷機能の提供であって、往復ハガキそのものの販売ではないため、用紙の持参が必要になることが多いです。
このように考えると、コンビニで往復ハガキを購入できる可能性はあるものの、必ずしも頼れる入手ルートではないことを理解しておく必要があります。確実性・利便性・価格を総合的に考慮し、目的に合った入手方法を選ぶことが重要です。
「往復はがきがコンビニにない」と言われる理由とは?
往復はがきがコンビニにないとされる背景には、いくつかの現実的な理由が存在します。その最も大きな要因は、「需要の少なさ」です。往復はがきは通常のハガキと異なり、使用場面が非常に限定されています。例えば、出欠確認、講習会やイベントの申し込み、公的な手続きなど、特定の状況下でのみ利用されることがほとんどです。そのため、年間を通して安定した販売が見込める商品とは言えず、コンビニとしても在庫を持つメリットが薄いのです。
また、コンビニの店舗スペースは限られており、商品構成にも戦略が求められます。限られたスペースの中で売れ筋の商品を優先して陳列するのは当然の方針であり、あまり動かない往復はがきを常設商品として置くことは合理的ではありません。特に地方やフランチャイズ型のコンビニでは、本部からの商品供給が限られており、地域ニーズに応じて売場構成が異なることもあります。
さらに、消費者の側にも「往復はがき=郵便局で買うもの」という意識が根強く残っているため、コンビニで探すという行動自体が一般的ではないという現実もあります。こうした需要と供給のギャップが、結果として「コンビニにない」と感じさせる原因になっているのです。
一方で、取り扱いをしているコンビニがまったく存在しないわけではありません。実際には、大型店や駅近の店舗などでは、往復はがきを置いているところもあります。こうした店舗では、ビジネス利用や急な対応が求められる顧客層が多いため、ニーズを見越して商品を揃えている場合があります。
このように、往復はがきが「ない」と言われてしまうのは、物理的に売っていないというよりも、「売っている店舗が極めて少ない」ことが理由です。そのことを理解しておけば、あらかじめ郵便局や通販を活用するという合理的な選択も取りやすくなるでしょう。
コンビニでの往復ハガキ販売の実情と店舗ごとの違い
コンビニでの往復ハガキ販売は、思っている以上に店舗ごとの差が大きいというのが実情です。多くの人は、全国どこに行っても同じ商品が買えると考えがちですが、実際にはそうではありません。特に往復ハガキのようなニッチな商品は、その店舗の立地や客層によって取り扱いが大きく異なる傾向があります。
例えば、駅構内やオフィス街にあるセブンイレブンやファミリーマートなどでは、ビジネス用途を意識して往復ハガキを置いている店舗もあります。こうした場所では、急ぎの郵便対応を求める利用者も多く、一定の需要が見込まれるからです。一方で、住宅街の中にある小規模店舗や、フランチャイズ形式の店舗では、売上効率が優先されるため、販売していないことのほうが多いのが現実です。
また、同じチェーン店であっても、本部が一律に商品を供給するのではなく、店舗側で仕入れの裁量を持っていることもあります。そのため、あるエリアのローソンでは取り扱っているのに、少し離れた店舗ではまったく在庫がないということも珍しくありません。これは、コンビニが地域密着型の商売をしている証拠とも言えます。
このような事情を知らずに「コンビニに行けば買えるはず」と思ってしまうと、実際に店舗を訪れて落胆することにもなりかねません。だからこそ、往復ハガキをコンビニで確実に手に入れたいと考えているのであれば、事前に電話などで在庫を確認することが重要になります。
なお、近年では一部のコンビニで、マルチコピー機を利用した往復ハガキの印刷が可能になってきています。ただし、これはあくまで印刷サービスであって、往復ハガキという形式の郵便物が購入できるわけではありません。ハガキ用紙の持ち込みが必要だったり、用紙サイズの制限があったりと、利用には一定の条件が伴うため注意が必要です。
こうして見ると、コンビニでの往復ハガキ販売は「可能性はあるが確実ではない」と言えます。郵便局であれば確実に入手できますし、ネット通販での購入も手軽です。自分のスケジュールや使用目的に応じて、最適な購入手段を選ぶことが大切です。
往復ハガキのセブンイレブン・ファミリーマートでの取り扱い状況

セブンイレブンやファミリーマートといった大手コンビニチェーンでは、はがき類の販売をしている店舗が多くありますが、往復ハガキに関しては事情が少し異なります。というのも、通常の官製はがきや年賀はがきと比べて、往復ハガキは特定の用途にしか使用されないため、取り扱っていない店舗も少なくないのが現状です。
まず、セブンイレブンについてですが、全国展開しているものの、往復ハガキの在庫があるかどうかは各店舗の判断に委ねられています。特に、オフィス街や大学の近く、官公庁のそばにある店舗では、ビジネス用途や事務手続き向けのニーズがあるため、取り扱っている可能性が高い傾向にあります。ただし、すべての店舗に共通して置いてあるわけではなく、都市部であっても在庫を持たないところも存在します。そのため、セブンイレブンで確実に往復ハガキを手に入れたい場合には、事前に電話などで在庫確認をすることが現実的です。
一方、ファミリーマートにおいても同様で、はがき類の取り扱いは店舗の規模や立地、オーナーの方針により異なります。実際に、ファミリーマート公式サイト上では、往復ハガキの取り扱いについて明記されていないケースが多く、購入を検討している人にとってはやや不親切な印象を受けるかもしれません。ただ、実際には取り扱いのある店舗も存在し、とくに交通量の多いエリアや公共施設の近くでは、在庫を確保している例も見られます。
このように、両チェーンに共通する特徴は、「全国共通の商品ラインナップではなく、店舗ごとに異なる判断がなされている」という点です。したがって、公式情報やネット検索だけに頼るのではなく、実際に利用を予定している店舗へ直接問い合わせることで、スムーズな購入が可能になります。
往復ハガキが必要な場面は、期日が決まっていることが多いため、「近所のコンビニにあるだろう」と思い込まず、早めに確保しておくことが安心につながります。万が一店舗で見つからなかった場合でも、郵便局やオンラインショップを活用すれば代替手段はありますので、柔軟に対応することが大切です。
コンビニでの往復ハガキ印刷の方法と注意点
往復ハガキを印刷したいというニーズは、公的な申請や返信用書類、案内状などに利用するため、特にビジネスや行政手続きの場面で一定数存在します。現在、多くのコンビニにはマルチコピー機が設置されており、文書データや画像ファイルをその場でプリントできる便利な環境が整っています。ただし、「往復ハガキの印刷」に関しては、いくつかの制約や注意点があるため、事前に把握しておくことが重要です。
まず前提として、ほとんどのコンビニのコピー機は「往復ハガキそのもの」を用意しているわけではありません。印刷に使うはがき用紙は、基本的に利用者が持ち込むか、通常サイズのはがきを店舗で購入して印刷に使うことになります。しかし往復ハガキは、はがきを二つ折りにしたような特殊な形状をしており、普通紙とは印刷サイズや給紙の仕方が異なります。そのため、マルチコピー機で正確に印刷するためには、原稿サイズの設定や印刷位置の調整が必要になることがあります。
次に、印刷可能なファイル形式や保存方法にも注意が必要です。多くのマルチコピー機では、PDF形式やJPEG形式のデータを印刷できますが、USBメモリやスマートフォンとの接続設定に時間がかかることもあります。特に、両面印刷や片面にだけ印字したい場合など、細かいレイアウト調整が求められるシチュエーションでは、操作ミスによる印刷失敗のリスクも考慮すべきです。
さらに、印刷コストについても留意する必要があります。白黒で1枚数十円、カラー印刷では100円前後かかるケースが一般的です。枚数が多くなるとコストがかさむため、用途と必要数に応じた使い分けが必要です。どうしても自宅にプリンターがなく、コンビニで済ませたいという場合には、事前に印刷物のプレビュー確認をしておくことで、無駄な失敗を減らすことができます。
このように、コンビニで往復ハガキを印刷することは不可能ではありませんが、紙の持ち込み、印刷設定、レイアウト調整といった注意点が多く、初心者にとってはハードルがやや高い作業です。印刷内容にミスが許されない書類の場合は、パソコンで原稿を作成し、自宅のプリンターや専門の印刷業者に依頼するという選択肢も検討すべきです。
コンビニで印刷済みの喪中はがきは買えるのか?
年末が近づくと、喪中はがきの準備が必要になる方も増えてきます。その際、「印刷済みの喪中はがきをコンビニで手軽に買えたら便利なのに」と考える人も多いのではないでしょうか。結論から言えば、印刷済みの喪中はがきをコンビニで購入できるケースは非常に限られており、ほとんどの店舗では取り扱っていません。
多くのコンビニでは、年賀はがきのシーズンになると、店頭で年賀状用の印刷受付や予約販売を行う特設コーナーが設置されます。しかし、喪中はがきに関しては事情が異なり、あらかじめ印刷された商品をレジ横に陳列している例はほとんどありません。これは、喪中はがきが個別の事情に合わせた内容で印刷されることが多く、宛名や文面が固定された既製品では対応しきれないことが理由の一つです。
一方で、セブンイレブンなど一部のコンビニでは、マルチコピー機を活用して、喪中はがきのテンプレートを選んでその場で印刷できる「ネットプリント」サービスを提供していることがあります。このサービスでは、あらかじめ用意された文例を選択し、差出人情報を入力するだけで印刷が可能なため、ある程度の柔軟性とスピード感を持って対応することができます。ただし、この方法も利用者自身が印刷を行うスタイルであり、「印刷済みのはがき」を購入するという形ではない点に注意が必要です。
また、喪中はがきの印刷は、通常はがきと違い、レイアウトや表現に気を遣う場面が多く、フォーマルな文面が求められることもあります。そのため、印刷の質や文例の正確さに不安がある場合は、文具店や印刷業者、郵便局のサービスなど、より専門的な対応が可能なルートを選ぶことも一つの方法です。
このように考えると、喪中はがきの準備をコンビニだけで完結させるのは現実的ではなく、必要に応じて他の方法も併用することが求められます。急ぎで用意したい場合には、オンライン注文+店頭受け取りが可能なサービスを活用することで、スピードと品質のバランスを取ることができるでしょう。
コンビニで買える?往復ハガキの基礎知識と正しい使い方

- 往復はがきの書き方|返信部分と往信部分の正しい記入例
- 往復はがきに必要な切手の種類と料金ガイド
- 往復はがきに切手がいらないケースはあるのか?
- 往復はがきの値段はいくら?2025年版の最新料金
- 往復はがきを郵便局で購入する方法とサービス内容
- 往復ハガキの出し方|ポスト投函と郵便窓口の違いとは?
往復はがきの書き方|返信部分と往信部分の正しい記入例
往復はがきの正しい書き方を理解していないと、相手に届かなかったり、返信がスムーズに返ってこなかったりする可能性があります。特に、公的機関や団体への申込み、イベントの出欠確認などで使用する際は、形式に従って丁寧に記入することが求められます。そこでまず、往復はがきの構成から説明します。
往復はがきは、その名の通り「往信(送る)部分」と「返信(戻る)部分」が一体となっており、中央で折りたたむ仕様です。使用前は1枚の紙として扱いますが、投函時は折り目を付けて二つ折りにします。表側には送り先の宛名、裏側には本文やメッセージを記入します。返信側には、返信が返ってくる相手の名前や住所をあらかじめ記入しておくのがマナーです。
往信部分の表面には、相手の郵便番号・住所・名前を丁寧に書きましょう。団体宛であれば「○○係」や「御中」を忘れずに記載します。裏面には本文や申込み内容を記入しますが、何についての連絡なのか、誰からの連絡なのかがすぐにわかるように、見出しやタイトルを書くと親切です。たとえば、「○○イベント参加申込書」「○○に関するお問い合わせ」などのように記載すれば、相手側も対応しやすくなります。
次に返信部分ですが、ここがミスの多い箇所です。表面には、自分の郵便番号・住所・氏名をあらかじめ記入しておきます。返信してもらいたい内容がある場合は、裏面に記入欄を設けたり、選択肢を提示しておいたりすることが効果的です。例えば「ご参加されますか? ○出席 ○欠席」などの形式でチェックを入れてもらう方法が一般的です。
このように、往復はがきは一枚で送受信の両方が行える便利なツールですが、書き方を誤ると本来の目的を果たせません。折り目の向きや記入欄の配置にも気を配り、受け取った相手が迷わず返信できるように心がけることが重要です。
往復はがきに必要な切手の種類と料金ガイド
往復はがきを使う際にまず確認すべきことの一つが、正しい料金で切手が貼られているかどうかです。往復はがきは、片道のはがきが2枚分連結された郵便物なので、通常のはがきよりも高い料金が設定されています。間違った料金で送ってしまうと、受取人に迷惑がかかったり、戻ってきたりすることがあるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
往復はがきの通常料金は170円です。これは、片道の通常はがきの料金が85円であることから、往信と返信の合計で170円となっています。この料金には、往信と返信の両方に切手が貼られていることが前提です。市販の往復はがきを購入する場合は、あらかじめこの金額の切手が印刷されているものが販売されており、追加で貼る必要はありません。
ただし、自作で往復はがきを作成する場合や、返信用部分だけ別途用意するようなケースでは、それぞれに適切な切手を貼る必要があります。往信部分に85円、返信部分にも85円の切手を貼るのが基本となります。ここで注意すべきなのは、返信部分に切手が貼られていないと、相手が返信時に送料を負担しなければならなくなってしまう点です。これは非常に失礼にあたるため、必ず自分で切手を用意して貼り付けておくべきです。
また、特殊な用途で往復はがきを使用する際や、封入物を貼り付ける場合には、重さが変わってくることもあります。その場合、料金が変動する可能性があるため、郵便局で確認してから投函することをおすすめします。特に厚紙やシールなどを使ってデザインを工夫するような場合は、定形外郵便に該当してしまうこともあるため注意が必要です。
このように、往復はがきに使用する切手の種類と金額は基本的に決まっていますが、使い方によっては例外もあります。あらかじめルールを理解し、ミスのないよう準備をすることが、円滑なやりとりにつながります。
往復はがきに切手がいらないケースはあるのか?
「往復はがきに切手はいらないのでは?」と疑問に思う方もいるかもしれません。確かに、郵便局などで販売されている往復はがきには、すでに切手相当の郵便料金が印刷されているため、追加で切手を貼る必要はありません。このため、一部のケースでは「切手不要」という考え方が成立しますが、状況によっては例外もあるため、少し詳しく解説しておきましょう。
まず、市販の往復はがきを購入した場合についてです。このタイプには、往信と返信の両方に必要な切手代があらかじめ印刷されているため、購入後に追加の切手を貼る必要は基本的にありません。このような「郵便料金込み」のはがきは、もっとも一般的な形式であり、郵便局や一部の文具店などで手軽に購入できます。何も貼らずに、そのまま内容を書いて投函すれば問題ありません。
一方で、自作の往復はがきを使う場合や、印刷会社に依頼してオリジナルの往復はがきを作成する場合には、郵便料金が含まれていないことがあります。このような場合には、自分で往信・返信それぞれに切手を貼る必要があります。特に、返信側の切手を忘れてしまうと、受け取った相手が自分で送料を負担しなければならなくなるため、非常に失礼な印象を与えてしまいます。
また、まれに企業や自治体から送られてくる往復はがきの中には、「返信不要」や「料金受取人払い」と記載されているものがあります。このような場合は、あらかじめ返信料金を差出人側が負担する契約になっており、受取人が切手を貼る必要はありません。ただし、これは特別な契約や事前の手続きが必要な方法であり、個人が日常的に使う場面では該当しません。
このように、「切手がいらないケース」は主に(1)料金込みの市販はがきを使用する場合、(2)返信側の料金を差出人が負担する契約がある場合に限られます。それ以外のケースでは、原則として切手を貼る必要があるため、「自分が貼るべきなのか」を用途に応じて見極めることが大切です。間違った理解で投函してしまうと、郵便物が相手に届かない、あるいは戻ってくる可能性があるため、注意しましょう。
往復はがきの値段はいくら?2025年版の最新料金

往復はがきの価格は、片道分のはがきが2枚つながった仕様であるため、通常のはがきよりも高く設定されています。2025年8月現在、往復はがき1枚あたりの料金は170円です。この金額は、往信(行き)と返信(戻り)それぞれの郵送料が円であることをもとに算出されています。郵便料金は時折改定されるため、購入や発送前には必ず最新の料金を確認することが大切です。
この126円には、往復分の郵便料金がすでに含まれており、郵便局で購入する往復はがきにはあらかじめ切手相当の料金が印刷されています。したがって、通常の使い方であれば、追加で切手を貼る必要はありません。ただし、後述するように自作の往復はがきを使う場合や、重量オーバーなど特別な条件がある場合は別途料金が必要になる可能性もあります。
また、官製往復はがき(郵便局で販売されている公的なはがき)以外に、印刷業者やネットショップなどでオリジナルの往復はがきを作成するケースもあります。その際、郵送料は印刷料金には含まれていないことが多く、自分で切手を貼る必要があります。こうした場合でも、85円分を2面に貼ることで同じ料金体系になります。
さらに、料金が変更されるタイミングにも注意が必要です。物価変動や郵便事業の見直しにより、郵便料金は数年に一度見直される傾向があります。2024年にも一部の郵便サービスで値上げがありましたが、今後もその傾向が続く可能性があります。特にビジネスや学校行事などで大量に往復はがきを使用する場合には、事前に最新料金を確認して、余計な費用や手間が発生しないよう備えておくと安心です。
このように、2025年の現時点では往復はがきの料金は170円が基本ですが、購入場所や使い方によっては追加費用がかかることもあります。正確な知識をもって運用することで、無駄なトラブルを防ぐことができます。
往復はがきを郵便局で購入する方法とサービス内容
往復はがきを確実に手に入れたいと考えたとき、もっとも信頼できるのが郵便局での購入です。郵便局では通常の官製はがきと同様に、往復はがきも常備されており、必要な枚数を窓口で購入することができます。特に、コンビニや文具店では在庫が不安定だったり、取り扱いがないケースも多いため、確実性を重視するなら郵便局の利用が最適です。
購入方法はとてもシンプルです。近隣の郵便局窓口へ行き、「往復はがきをください」と伝えるだけで、現在の販売価格(2025年時点では1枚170円)で購入できます。必要な枚数をまとめて買いたい場合や、特殊なサイズの用紙を希望する場合は、事前に在庫確認や取り寄せが必要になることもあるため、余裕を持って訪問することをおすすめします。
また、郵便局では購入だけでなく、さまざまなサポートサービスも提供されています。例えば、往復はがきの記入方法がわからない人には、記載例を提示してもらえることがありますし、窓口での相談にも丁寧に対応してもらえるのが魅力です。特に、高齢者や郵便に不慣れな人にとっては、こうした人的サポートの存在が安心材料になります。
さらに、ビジネスや団体向けに大量の往復はがきを使用する場合には、郵便局によっては事前注文や見積対応をしてくれるケースもあります。また、郵便局のオンラインストアを活用すれば、自宅にいながら往復はがきを注文し、配送してもらうことも可能です。これにより、近くに郵便局がない人や、忙しくて来局できない人でも安心して入手できます。
このように、郵便局での購入は信頼性が高く、サービスも充実しており、往復はがきを利用する際の最も基本的な手段と言えるでしょう。特に、初めて往復はがきを使用する場合や、確実な発送・返信を必要とする用途では、郵便局を利用することがもっとも安全で確実な方法です。
往復ハガキの出し方|ポスト投函と郵便窓口の違いとは?
往復ハガキを正しく送りたいと思ったとき、「ポストに入れればいいのか?」「郵便局の窓口から出すべきか?」といった疑問を持つ人は少なくありません。実際、往復ハガキは通常の郵便はがきと同様に、どちらの方法でも送付できますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。用途や状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。
まず、もっとも手軽なのはポスト投函です。往復ハガキも普通のはがきと同じく、料金さえ正しく支払われていれば、ポストにそのまま投函して問題ありません。特別な手続きは不要で、宛先や差出人情報を記入し、折り目をしっかりとつけて二つ折りにして投函するだけでOKです。近所のポストにすぐに投函できるのは、日常的に郵便物を扱う人にとっては非常に便利な手段でしょう。
一方で、郵便局の窓口から出すという方法にも、明確な利点があります。たとえば、往復はがきの形状や内容に不安がある場合、窓口で確認してもらうことで、「料金不足」「誤投函」といったトラブルを未然に防ぐことができます。また、往復はがきの返信部分に不備があると、相手に返信してもらうことができないため、事前に専門の職員にチェックしてもらえるのは安心感につながります。
さらに、ビジネス用途や重要な書類のやりとりで往復はがきを使用する場合、証拠が残る形で出したいという人もいるでしょう。この場合、普通郵便ではなく「簡易書留」や「特定記録郵便」として出すことも可能です。ただし、これらのオプションはポスト投函では利用できないため、必ず郵便窓口での手続きが必要になります。
このように、ポスト投函と窓口発送のどちらにもメリットはあります。普段使いであればポスト投函でもまったく問題ありませんが、内容が重要だったり、確実に届いてほしい場合には、郵便局の窓口を利用するほうが安全です。また、返信を求める往復はがきは、記入や折り方、切手の貼り方まで細かいルールが関係するため、不安がある場合はプロに確認してもらうことをおすすめします。
コンビニで往復ハガキを取り扱う現状と活用ポイントのまとめ

- コンビニでは往復ハガキを一部の店舗で購入できるが、全店での取扱いは保証されていない
- 往復ハガキの需要が限られるため、コンビニ各社は常時の取り扱いをしていないことが多い
- 店舗によって往復ハガキの在庫状況は異なり、同じ系列でも扱っていない場合がある
- セブンイレブンやファミリーマートでは、地域や立地によって往復ハガキを置いている店舗もある
- 駅や役所の近くなどでは、ビジネスニーズに対応するために往復ハガキを置いている可能性が高い
- 住宅街や地方の小型店舗では、需要が少ないため取り扱いが省かれているケースが多い
- 確実に入手したい場合は、訪問前に電話で店舗に在庫確認をしておくのが安全
- 往復ハガキは主に申込書・出欠確認・公的手続きなど限られた目的で使用される郵便物である
- コンビニのマルチコピー機では往復ハガキサイズへの印刷が可能な機種も増えている
- 印刷を行うには、自分で往復ハガキ用の用紙を持参し、給紙やレイアウト設定に注意が必要
- 使用できるファイル形式(PDFやJPEGなど)や保存媒体(USB、スマホ)を事前に確認すべき
- 印刷済みの喪中はがきは、ほとんどのコンビニでは市販されておらず、取り扱いも限定的
- 一部コンビニではマルチコピー機を使った喪中はがき印刷サービスに対応している場合がある
- 郵便局で販売されている往復ハガキは、切手込みで安心して購入できる最も確実な入手方法
- コンビニでの往復ハガキ活用は、あくまで緊急時や他の手段が使えないときの補完的な選択肢となる
関連記事