郵便をもっと手軽に、もっと安く送りたいと考えている人にとって、ミニレターは非常に魅力的な選択肢です。しかし、その使い方にはいくつかのルールがあり、特に気をつけなければならないのがミニレターの厚みです。
ミニレターは、全国一律料金で利用できる便利な郵便サービスですが、封を閉じた最終的な状態で厚みが1センチ以内に収まっていなければなりません。この厚さの制限を超えてしまうと、思わぬトラブルや追加料金が発生する原因になります。せっかく手軽なつもりで利用しても、ルールを知らなかったばかりに返送されたり、受取人に負担をかけてしまうこともあるのです。
この記事では、ミニレターの厚み制限を正しく理解し、トラブルなく安全に郵送するためのポイントを丁寧に解説します。加えて、実際に送れるサイズや重量、入れてよいもの・いけないもの、購入場所や注意点、さらには廃止の噂や料金不足の対応まで、幅広く網羅しています。
これからミニレターを使ってみたい方や、久しぶりに利用する予定の方も、この記事を最後まで読むことで、不安なく活用できる確かな知識が身につくはずです。

💡記事のポイント
- ミニレターの厚みとサイズの基準、厚みオーバー時の選択肢
- ミニレターの料金の考え方と料金不足を避ける具体策
- ミニレターに入れていいもの・送ってはいけないものの判断軸
- ミニレターはどこで買えるか、買い方、よくあるデメリットへの対処
ミニレターの厚みとサイズ規定の基礎知識

- ミニレターの厚み制限|送れる厚さの上限について解説
- ミニレターの厚みオーバー時の対処法と追加料金が発生するケース
- ミニレターのサイズの正式規格と重量制限について
- ミニレターに入れていいものと入れてはいけないものの違い
- ミニレターはどこで買えるのか?郵便局以外の購入場所も紹介
- ミニレターの買い方|初心者でもわかる購入手順と注意点
ミニレターの厚み制限|送れる厚さの上限について解説
ミニレターは、全国一律料金で利用できる日本郵便の「郵便書簡」という郵送手段のひとつで、主に軽量の書類やカードなどを安価に送りたいときに活用されます。ただし、誰でも気軽に使える反面、利用にあたっては明確なサイズと重量の制限があり、とくに「厚み」に関しては厳密な基準が設けられています。
ミニレターとして受け付けてもらうには、最終的な状態――つまり封かん済みの状態で、厚さが1センチメートル以内である必要があります。加えて、重量も25グラム以内に収めなければなりません。この2つの条件を満たさなければ、ミニレターとして引き受けてもらえず、別の郵便サービスの適用対象となります。
この1センチという厚み制限は、郵便物を仕分けるための自動区分機に対応させるために設定されています。自動処理で支障なく流通させるには、封筒が一定の薄さ・平坦さを保っていることが不可欠であり、基準を超えると機械に詰まる・破損するなどのトラブルを招く恐れがあります。したがって、この規定は安全な輸送と効率的な運用を両立させるための合理的な措置といえます。
厚さの判定は、差し出し時点での状態に基づいて行われるため、たとえ封入時に薄く見えても、封をした際に角が浮いていたり、部分的に膨らんでいたりすると基準を超えてしまう可能性があります。これは、カード類や複数枚の紙を封入したときなどに起こりやすく、均等に重ねていないと厚みの偏りが出やすくなります。
対策としては、封入物を平らに整えることが基本です。たとえば、写真やメッセージカードを入れる場合は、厚みの異なる素材を重ねすぎないよう注意する必要があります。厚手の台紙を使う場合も、可能な限り薄くて軽量なものを選び、封筒全体の厚みに配慮してください。
なお、郵便局の窓口では、専用のスリットゲージを用いて厚さをその場で計測します。このゲージに通れば厚さ1センチ以内と認定されますが、自宅で準備する段階からその目安を知っておくと安心です。10mm幅のカードやノギス、スケールなどを使えば、おおまかなチェックは十分に可能です。微妙な場合には窓口に持ち込んで確認してもらうのが最も確実な方法といえるでしょう。
(出典:日本郵便「郵便書簡(ミニレター)」https://www.post.japanpost.jp/service/standard/one_price.html
ミニレターの厚みオーバー時の対処法と追加料金が発生するケース
ミニレターを利用する上で特に注意すべきなのが、厚みや重量の制限を超えてしまった場合の対応です。封入物が多かったり、素材が厚手だったりすると、意図せず「厚さ1センチ」「重量25グラム」のいずれか、あるいは両方を超えてしまうことがあります。こうなった場合、ミニレターとしては受け付けてもらえません。
このようなケースでは、選択肢として以下の3つの対応策が現実的です。
- 封入物を減らして再調整する
余計な紙類や厚みのある台紙などを取り除くことで、条件内に収め直す方法です。特に複数枚のカードや写真を入れた場合は、1〜2枚削るだけで厚さが大きく変わることもあります。 - 別の郵便サービスへ変更する
たとえば、定形郵便は厚さ1センチ以内であれば50gまで送れますし、定形外郵便であればさらに厚みがあるものにも対応可能です。また、スマートレター(180円〜210円)はA5サイズ・厚さ2センチ以内・1kgまでの条件で送付可能です。レターパックライト(370円〜430円)に切り替えれば厚さ3センチ以内・4kgまでに対応し、追跡番号も付与されます。 - 封筒や梱包方法を見直す
封筒そのものが厚すぎる場合や、折り方にムダがある場合は、薄手の封筒や別の折り方で厚みを抑えることも検討できます。
これらのサービスへの切り替えは、当然ながら料金も上がります。仮に厚みが1.5センチで重量が50g以内であれば、定形外郵便の規格内として扱われ、料金は120円または140円となるケースが多いです。
特に注意が必要なのは、ポスト投かん後に厚みオーバーが発覚した場合です。日本郵便では、引受時にサイズや重量を再確認しており、規格外と判断されれば、差出人に返送されたり、受取人が不足分の料金を支払わなければならない事態も起こり得ます。
このようなトラブルを避けるためには、事前に厚さと重量の確認を丁寧に行うことが最も効果的です。少しでも不安がある場合は、ポストではなく郵便窓口での差し出しを選ぶことで、受付時点でのアドバイスや代替手段の提案を受けることができます。
ミニレターのサイズの正式規格と重量制限について
ミニレターには、郵便法および日本郵便の規定に基づいた明確なサイズと重量の制限があります。この条件を満たさなければ、ミニレターとしての扱いは受けられず、料金体系や取り扱いが自動的に変わるため、送付前の確認は非常に重要です。
ミニレターの展開時のサイズはおおよそ縦27.9センチ×横16.5センチで、この用紙を三つ折りにして封筒型にすることで、封かん後の仕上がりサイズは「長辺約16.4センチ」「短辺約9.2センチ」程度になります。これは、日本郵便の「定形郵便物」の規格に該当しており、長辺14〜23.5センチ、短辺9〜12センチ以内である必要があります。
重量に関しては、ミニレターとして送るには25グラム以内でなければなりません。ここで注意すべきなのは、この重量が「封筒自体+封入物の合計」であるという点です。ミニレターの本体(封筒兼便せん)は約2〜3グラムあるため、実質的に封入できる物の重量は22グラム程度と考えるのが現実的です。
このわずかな数グラムの差が、大きな違いを生みます。たとえば、写真を数枚封入しただけでも簡単に25グラムを超えてしまうため、家庭用の1グラム単位で測定できるデジタルスケールを活用して事前に計測しておくことが望まれます。重量オーバーで差し戻された場合、再送にかかる時間や料金の負担は決して小さくありません。
また、仕上がりサイズの確認も見落とされがちです。用紙の折り方が雑だったり、封入物の角が飛び出していたりすると、仕上がりが規格を超えてしまう可能性があります。この場合もミニレターとしては扱われず、通常の定形郵便または定形外郵便への変更が必要になります。
このように、サイズと重量の両面からの確認が欠かせません。差し出す前に、定規とスケールを使っての最終チェックを行うことで、不意のトラブルを未然に防ぐことができます。
(出典:日本郵便「郵便のサイズと重量制限」https://www.post.japanpost.jp/service/standard/one_size.html
ミニレターに入れていいものと入れてはいけないものの違い

ミニレターは、便せんと封筒が一体化している特殊な郵便物で、文書や軽量な物品の郵送に利用されますが、封入できる内容物には厳密な制限があります。これは、郵便法や日本郵便の内規によって定められており、すべてのものを自由に送れるわけではありません。
まず、入れても問題ないものとして代表的なのは、次のような軽くて平らなアイテムです。
- 手紙やメモ用紙などの文書類
- ポストカードやショップカード
- 写真(枚数を抑えることが前提)
- チケット、クーポン、領収証などの紙類
- トレーディングカード(1〜2枚程度)
これらは、厚さ1センチ以内・重量25グラム以内に収まるものであれば、原則として封入可能です。ただし、折れやすいものやインクがこすれやすいものについては、薄い台紙を添えるなどの補強が推奨されます。
一方で、ミニレターで送ってはいけないものは明確に定められており、違反した場合には郵便物の差し戻しや廃棄、最悪の場合は法的措置を受ける可能性もあります。禁止されている主な物品は以下の通りです。
- 現金、小切手、有価証券などの金銭的価値のあるもの
- 貴金属、宝石類などの高価な品物
- 爆発物、引火性液体、毒物などの危険物
- 食品や植物、生き物などの腐敗・変質の恐れがあるもの
- 刃物や鋭利な器具など、安全性を損なう物品
- 磁気カード、ICチップ付きカード(破損リスクが高いため非推奨)
とくに誤解されがちなのが、商品券やギフトカードなどの高額な金券類です。たとえ薄くても金銭的価値があるものは原則として送付不可です。また、磁気カードなどは輸送中の影響で読み取り不能になるリスクがあるため、万が一の補償がないミニレターでは送付に向いていません。
安全に利用するためには、内容物がミニレターの特性に合致しているかを冷静に見極める必要があります。迷った場合は郵便局窓口に相談し、誤送によるトラブルを未然に防ぐ姿勢が求められます。
ミニレターはどこで買えるのか?郵便局以外の購入場所も紹介
ミニレター(郵便書簡)は、郵便局が発行・販売している特殊な郵便物であるため、購入場所がやや限られています。最も確実な入手先は、全国の郵便局窓口です。平日の営業時間内であれば、1枚単位から購入が可能で、在庫も安定しています。
郵便局では、切手類や封筒類と同じコーナーで取り扱っており、窓口で「ミニレターをください」と伝えるだけで簡単に購入できます。また、郵便局の一部では、平日夜間や休日に営業している「ゆうゆう窓口」でも取り扱っている場合があります。ただし、すべての郵便局がゆうゆう窓口を設けているわけではないため、事前に郵便局公式サイトで対応状況を確認するのが安全です。
郵便局以外では、以下のようなルートでも販売されていることがあります。
- 一部の文具店やローカル商店での郵便用品取り扱いコーナー
- 金券ショップ(額面より安く入手できる可能性あり)
- フリマアプリ・ネットオークション(未使用品に限る)
- 日本郵便の公式オンラインショップ(https://www.shop.post.japanpost.jp/
ただし、郵便局以外で購入する際には注意点があります。特に、旧額面(例:63円、80円)のミニレターが出回っていることがあり、これらを使用する場合は現行料金との差額分の切手を追加で貼る必要があります。また、非公式ルートで購入したものには折れや汚れがある場合もあるため、状態をよく確認した上で使用すべきです。
郵便局で購入する場合と比べて、価格や信頼性の面でばらつきがあるため、急ぎの用途や確実性を重視する場合には、郵便局窓口での購入が最も安心です。
ミニレターの買い方|初心者でもわかる購入手順と注意点
ミニレターの購入方法は非常にシンプルです。郵便局の窓口で「郵便書簡を○枚ください」と伝えれば、必要な枚数をすぐに購入できます。窓口での購入には、現金に加えて電子マネーやキャッシュレス決済が使える局も増えており、利便性も高まっています。
ミニレターは通常、1枚単位で購入できるほか、10枚や50枚といった単位でのまとめ買いも可能です。法人や大量発送を予定している場合には、事前に在庫状況を問い合わせておくとスムーズです。郵便局の公式オンラインショップでも購入できますが、発送までに数日かかるため、即日入手したい場合には店舗での購入が適しています。
購入時に注意すべき点は以下の通りです。
- 旧料金のミニレター:過去に販売されていた額面(63円、80円など)のものを使う場合は、現行の85円との差額分の切手を追加で貼る必要があります。差額不足の場合、郵便物は返送されたり、追加料金を受取人が支払うケースもあるため要注意です。
- 書き損じ対応:ミニレターは切手と同様に、書き損じた場合には5円の手数料で他の郵便切手やはがきと交換できます。ただし、破れや汚れがあると交換対象外となることもあるため、取り扱いは丁寧に行う必要があります。
- 保管方法:湿気や折れに弱いため、未使用のミニレターはクリアファイルなどで平らに保管し、折れや変形を防ぎましょう。
さらに、ミニレターは封筒と便せんが一体化しているため、構造上「切って使う」「折り曲げる」といった加工ができません。誤って封筒部分を切り取ったり、糊付け箇所を破ったりすると無効になってしまいます。封入する内容や記入する文字の配置にも注意を払い、正しい形式での使用が求められます。
ミニレターの厚みと料金・利用制限・最新動向

- ミニレターの料金はいくら?最新の送料と改定履歴
- ミニレターの送料の仕組みと計算方法について
- ミニレターの料金不足にならないためのチェックポイント
- ミニレターのデメリットと他サービスとの比較
- ミニレター 廃止の噂と日本郵便の公式見解
- ミニレターで送ってはいけないものとは?違反時のリスク
ミニレターの料金はいくら?最新の送料と改定履歴
ミニレターの料金は、2025年8月現在で全国一律「85円」に設定されています。これは、日本郵便が提供する郵便書簡としての料金であり、重量や配達距離にかかわらず、厚さ1センチ以内・重量25グラム以内という条件を満たしていれば、全国どこへでも同一料金で送ることができます。
この料金には、便せんと封筒が一体となった用紙の価格と郵送費が含まれています。つまり、切手を別途用意する必要がなく、ミニレターをそのまま記入して封かんすれば、ポストに投かんするだけで発送できるという点が特徴です。
ミニレターの料金は過去にも複数回改定されています。主な改定履歴は以下の通りです。
| 改定年 | 旧料金 | 新料金 | 主な改定理由 |
|---|---|---|---|
| 2014年 | 80円 | 82円 | 消費税率5%→8%への変更 |
| 2019年 | 82円 | 84円 | 消費税率8%→10%への変更 |
| 2023年 | 84円 | 85円 | 郵便事業の収益構造見直し |
このように、主に税制改正や郵便事業の採算性の観点から料金が調整されており、今後も経済情勢や物流コストの上昇に応じて見直される可能性があります。
また、旧料金のミニレター(例えば、63円や80円券面のもの)を使用する場合は、現行料金との差額分の切手を追加で貼らなければなりません。差額が不足すると、郵便物は差し戻されるか、受取人が追加料金を支払う必要があるため、使用する際には額面の確認を徹底する必要があります。
(出典:日本郵便「郵便料金表」https://www.post.japanpost.jp/send/fee/kokunai/
ミニレターの送料の仕組みと計算方法について
ミニレターの送料は、他の郵便サービスと異なり「全国一律85円」の定額制が採用されています。このため、差し出す地域や配達先の距離によって料金が変わることはありません。ただし、この送料が適用されるのは、あくまで「ミニレターの定義に完全に合致した郵便物」である場合に限られます。
ミニレターとしての条件は以下の通りです。
- 厚さ:1センチメートル以内
- 重量:25グラム以内(封筒部分の重量を含む)
- サイズ:長辺14〜23.5センチ、短辺9〜12センチの定形サイズ内
これらの条件を少しでも超えると、ミニレターとしては取り扱ってもらえず、通常の定形郵便、定形外郵便、あるいはスマートレター・レターパックなどへの変更が必要となります。その際は重量やサイズに応じた別料金が適用され、85円よりも高くなるのが一般的です。
料金の計算方法に迷う方も多いですが、ミニレターの場合は非常にシンプルです。基準内であれば一律85円、超えた場合は以下のような別料金体系になります。
| 種別 | 厚さの上限 | 重量の上限 | 料金(目安) |
|---|---|---|---|
| 定形郵便(25g以内) | 1cm | 25g | 84円〜110円 |
| 定形外(規格内) | 3cm | 50g〜1kg | 120円〜350円 |
| スマートレター | 2cm | 1kg | 180円〜210円 |
| レターパックライト | 3cm | 4kg | 370円〜430円 |
このように、条件を満たしていれば最も安価に利用できるのがミニレターですが、少しでもオーバーした場合は、別サービスへの切り替えが必要となり、送料も一段高くなります。事前の計測と確認が重要になる理由はここにあります。
ミニレターの料金不足にならないためのチェックポイント
料金不足は、郵便物が差し戻されたり、受取人に不足分の支払いを求められたりする原因となります。特にミニレターは、制限が厳格に定められているため、わずかなオーバーでも料金不足扱いになる可能性が高く、注意が必要です。
ミニレターを利用する際に、料金不足を防ぐためのチェックポイントは以下の通りです。
- 封かん後の再測定を必ず行う
封入後に厚みや重量が変わるケースは少なくありません。封筒にのりを塗ることで重量が増したり、封入物の端が重なって厚くなることがあります。封を閉じた最終状態で測定し直すことが大切です。 - 厚さの最大部分を確認する
郵便局では、最も厚い部分を基準に測定します。カードや写真が重なっている部分が1センチを超えていると、他の部分が薄くても引き受け不可となることがあります。 - 旧額面のミニレターには追加切手を貼る
例えば、63円の旧額面ミニレターを使用する場合、22円分の切手を追加で貼らなければなりません。この差額の確認を怠ると、確実に料金不足になります。 - 窓口から差し出す
不安がある場合は、ポスト投かんではなく、郵便局の窓口で厚み・重量を測ってもらいましょう。その場で不足があれば、適切な案内を受けることができます。
料金不足によって返送されると、再送の手間や時間、さらなる送料負担が発生します。とくにイベントチケットや期日指定のある書類などを送る場合には、1回の失敗が大きなトラブルに発展する可能性もあるため、計測・確認は必ず行うべきです。
承知しました。
以下に、最後の3つのセクションを強化・詳細化してご提供いたします。
ミニレターのデメリットと他サービスとの比較
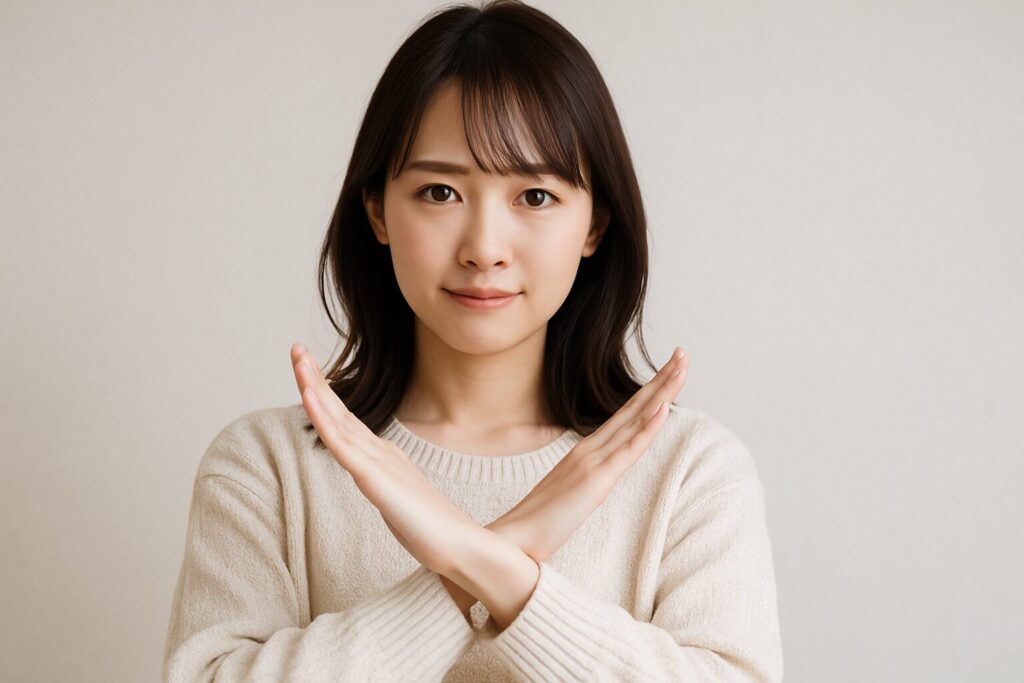
ミニレターはコストパフォーマンスに優れた郵送手段として人気がありますが、すべての郵送ニーズに対応できるわけではありません。利用前に理解しておくべき明確なデメリットがいくつか存在します。
主なデメリットは次のとおりです。
- 厚み・重量の制限が厳しい
1センチ以内・25グラム以内という条件をわずかでも超えると、ミニレターとしては取り扱ってもらえません。封入物の量や形状に柔軟性がないため、やや扱いにくいと感じる利用者も少なくありません。 - 追跡・補償機能が一切ない
ミニレターは普通郵便と同様、発送後の追跡番号が付与されません。また、紛失や破損が起きた場合も、補償の対象外です。高価なものや重要書類の送付には適していないという点に注意が必要です。 - 書き損じや封かんのやり直しが難しい
ミニレターは封筒と便せんが一体化しているため、内容の修正や封かんの再開封が困難です。訂正が必要になった場合には、新たに書き直すことが求められることもあります。
一方で、こうした制限やリスクを回避したい場合には、以下のような代替サービスとの比較が有効です。
| サービス名 | 厚さ制限 | 料金(全国一律) | 追跡 | 補償 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミニレター | 1cm以内 | 85円 | × | × | 最安・軽量物向け |
| 定形郵便 | 1cm以内 | 84〜110円 | × | × | 封筒自由・重量50gまで対応 |
| スマートレター | 2cm以内 | 180〜210円 | × | × | 厚みある書類向け |
| レターパックライト | 3cm以内 | 370〜430円 | ○ | × | 追跡あり・速達相当 |
| レターパックプラス | 制限なし | 520〜600円 | ○ | × | 手渡し配達・厚物送付向け |
このように、用途や優先事項(コスト、安心感、容量など)に応じてサービスを適切に使い分けることで、無駄なトラブルや不安を回避できます。ミニレターは確かに経済的ですが、それだけで選ぶのではなく、内容物の性質と重要度に合わせて判断することが賢明です。
ミニレター 廃止の噂と日本郵便の公式見解
インターネット上では定期的に「ミニレターが廃止されるのではないか」という噂が広まることがあります。背景には、郵便物全体の取扱量減少や、郵便サービスの構造改革に対する一般的な不安がありますが、2025年8月現在、日本郵便が公式に「ミニレターの廃止」を発表した事実は一切ありません。
むしろ、日本郵便の公式ウェブサイトでは、ミニレターの利用案内や販売ページが引き続き掲載されており、現在も全国の郵便局やオンラインショップを通じて購入・利用が可能です。
これまでに廃止ではなく「料金改定」や「取り扱い条件の見直し」が行われてきた経緯はあります。たとえば、消費税の変更やコスト見直しに伴い、料金が80円から85円へ段階的に変更されるなど、制度的なアップデートが実施されています。
しかし、ミニレター自体は、軽量な書面を手軽に送付できる郵便手段として根強い需要があり、簡易な連絡文書や業務連絡、カードなどの送付手段として今なお利用されています。
このように、根拠のない廃止の噂に惑わされることなく、日本郵便の公式情報を確認する習慣を持つことが大切です。新たな料金改定や制度変更の可能性はゼロではありませんが、廃止の判断はサービス全体に大きな影響を与えるため、事前に十分な告知がなされると考えられます。
(参考:日本郵便「お知らせ・報道発表資料」https://www.post.japanpost.jp/notification/index.html
ミニレターで送ってはいけないものとは?違反時のリスク
ミニレターは日常的な書面のやり取りに便利な手段ですが、その内容物には厳しい制限が設けられています。送ってはいけないものを封入した場合、差し戻しや廃棄、さらには法的措置の対象になることもあります。利用前に、何が禁止されているのかをしっかり確認しておくことが重要です。
ミニレターで送付が禁止されている主な内容物は、以下の通りです。
- 現金(紙幣・硬貨いずれも不可)
- 有価証券類(商品券、株券、小切手、ギフトカードなど)
- 貴金属・宝石類(金・銀・プラチナ、ダイヤモンド等)
- 刃物や危険物(ハサミ、カッター、スプレー缶、花火など)
- 生ものや腐敗の恐れがあるもの(食品、植物、昆虫など)
- 違法物・薬物・禁制品(麻薬、銃火器、毒物等)
また、以下のような物品も、送ること自体は可能であっても、ミニレターという形式では避けるべきものに含まれます。
- 磁気カード、ICカード、電子チケット(輸送中に磁気エラーが発生するリスク)
- 厚みや重量のギリギリを攻めた内容物(配送中に膨らんだり変形する可能性)
- 水濡れや折れに弱い書類(封筒の紙質が薄いため、防護力が弱い)
これらの物をミニレターで送ると、郵便物が途中で開封・返送されたり、受取人が損害を被ったりする可能性があります。場合によっては、郵便法違反として罰金刑や懲役刑に処されることもあります。
とくに、現金や金券類の送付に関しては、金銭的価値があることから盗難や紛失のリスクも高く、郵便局では絶対にミニレターでの送付を推奨していません。高価な物や重要書類を送る際は、補償や追跡が付帯する書留郵便やレターパックプラスなど、別の手段を選ぶべきです。
日本郵便が定める「禁制品」の最新情報は、以下の公式ページから確認できます。
(出典:日本郵便「禁制品・送れないものについて」https://www.post.japanpost.jp/int/use/restriction/mail_method.html
ミニレターの厚みとサイズと料金まとめ

- ミニレターの厚みは、封かんを終えた最終状態で1センチ以内に収めることが必要です
- 重量は封筒本体の重みを含めて25グラム以内に抑えるよう注意が必要です
- 料金は全国一律85円で、旧額面の用紙は差額分の切手で調整します
- 厚みや重量をオーバーした場合は、定形外や他の郵便サービスへ切り替える必要があります
- サイズは封入後の仕上がりが定形郵便の規格内に収まるよう調整することが大切です
- 入れていいものは薄い紙片やカード程度で、台紙の使いすぎは厚み超過につながります
- 現金や危険物など、郵便法で送付が禁止されているものは封入してはいけません
- ミニレターには追跡や補償が付かないため、高価品や一点物の送付には不向きです
- 封かん時ののり付けは薄く均一に行い、自動仕分け機での詰まりを防止します
- 重量や厚みは封かん後にも必ず再計測し、誤差を吸収できるようにしておきましょう
- ミニレターの購入は郵便局が確実で、夜間はゆうゆう窓口を活用すると便利です
- 料金が不足していると返戻や遅延の原因になるため、事前にしっかり計測しましょう
- デメリットが目立つ場合は、スマートレターやレターパックなど他の手段を検討しましょう
- 廃止の噂に惑わされず、日本郵便の公式サイトで最新の案内を必ず確認してください
- トレカや写真を送る際は、角をそろえて薄紙で平らに補強して封入すると安全です
関連記事







