現金書留を利用したいけれど、郵便局での受付時間が何時までなのか、土日や夜間にも対応しているのか、気になる方は多いのではないでしょうか。特に大切なお金を送る場合、受付可能な時間を逃してしまうと、相手に届く日数や料金にも影響してしまいます。
この記事では、郵便局の現金書留受付時間を中心に、料金の仕組み、配達にかかる日数、追跡方法、さらに速達やゆうゆう窓口の活用までをわかりやすくまとめました。初めて利用する方はもちろん、久しぶりに現金書留を使う方にも役立つ内容になっています。
最後まで読んでいただければ、郵便局で現金書留を送る際の不安を解消し、スムーズに手続きができるようになるはずです。
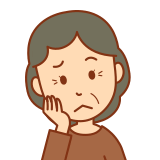
💡記事のポイント
- 窓口別の現金書留の受付時間と何時まで出せるかの考え方
- 現金書留の料金の内訳や速達指定などオプションの整理
- 現金書留の到着までの日数の目安と遅延を避けるコツ
- 現金書留の差し出し後の追跡と郵便局留めの使い方
郵便局での現金書留の受付時間と基本ルール

- 郵便局での現金書留の受付時間は土日も対応している?
- 現金書留は郵便局で何時まで受付してもらえるのか
- 現金書留をゆうゆう窓口で出すときの注意点
- 郵便局の営業時間と現金書留の受付可能な時間帯
- 郵便局で現金書留を送る方法と手続きの流れ
- 郵便局で現金書留を送る際のサイズや規定について
郵便局での現金書留の受付時間は土日も対応している?
土日の現金書留の受付可否は、郵便局ごとの営業形態に大きく依存します。多くの郵便局では、平日のみ通常窓口を開設しており、土日は閉局しているケースが少なくありません。しかし、主要都市部や駅周辺の大型郵便局を中心に、ゆうゆう窓口を併設している郵便局が存在しており、そこでは土日や祝日、早朝や夜間にも現金書留の差し出しが可能な場合があります。
ゆうゆう窓口は、通常の窓口が閉まっている時間帯に利用できるサービスで、郵便物の差し出しや受け取り、再配達受付などに対応しています。現金書留もこの対象に含まれますが、窓口担当者による封かん確認が必要なため、設置局であっても一部の時間帯で取り扱いを制限していることがあります。差し出し予定の郵便局が土日に現金書留を取り扱っているかどうかは、日本郵便の公式サイトの「郵便局・ATMをさがす」ページで個別に確認することが推奨されます(出典:日本郵便「郵便局・ATMをさがす」)。
また、土日の集荷タイミングは平日と異なる場合があり、差し出し時間によっては配達までの日数に影響することがあります。土日に差し出しても、集荷の都合で実質的な処理が週明けになる可能性があるため、日数に余裕を持った発送計画が重要です。急ぎの書類や支払いを現金書留で送付する場合は、可能な限り平日の早い時間帯に手続きするのが理想ですが、どうしても土日しか時間が取れないという場合は、事前に利用予定の郵便局が土日の現金書留に対応しているか、締切時間はいつかなどを詳細に確認することが求められます。
来局時には、混雑時間帯を避けることも有効です。特に月初・月末、祝日前後の午前中などは利用者が集中しやすく、受付までに時間がかかる可能性があります。封筒の準備や宛名の記入はあらかじめ済ませておくことで、待ち時間のストレスを軽減できます。
現金書留は郵便局で何時まで受付してもらえるのか
現金書留の差し出し可能な時間は、単に郵便局の営業時間と一致するわけではありません。多くの郵便局では、現金書留の受付に関して「当日扱いの締切時間」を設けており、たとえば「平日は17時まで」「土曜は15時まで」などと、普通郵便や荷物の受付より早めに設定されていることがあるため注意が必要です。
この締切時間を過ぎて現金書留を差し出した場合、翌日扱いとなり、配達予定日が1日遅れることがあります。とくに公共料金や重要な支払い、契約書類の送付などで期日に制約がある場合は、差し出し時刻に細心の注意を払わなければなりません。
現金書留は、封かん確認や現金金額の申告、追跡番号の発行など、通常郵便と比べて手続きに時間を要します。そのため、閉局間際に駆け込んでも「受付をお断りされる」「翌日扱いになる」といったケースが現実に起こり得ます。特に月末や年末年始などの繁忙期は、窓口が非常に混雑するため、受付処理に時間がかかることも想定してスケジュールを組むべきです。
また、ゆうゆう窓口を利用する場合も、夜間であればスタッフが少人数体制で運営されており、現金書留のような特殊な取扱を断られることもあるため、事前確認が不可欠です。対応しているかどうか、また当日扱いにしてもらえるかは、郵便局ごとの運用に左右されるため、できるだけ公式情報や電話問い合わせで情報を収集しておくと安心です。
時間に余裕をもって来局し、封入や宛名記入、封かんの準備もすべて整えた状態で差し出すことで、受付担当者の負担を減らすと同時に、スムーズな手続きが可能になります。送り先の相手にも確実な配達日を伝えることができ、信頼を損なうリスクを避けられます。
現金書留をゆうゆう窓口で出すときの注意点
ゆうゆう窓口は、通常の郵便窓口が閉まった時間帯にも利用できる、時間外対応の郵便受付窓口です。全国すべての郵便局に設置されているわけではありませんが、中央郵便局や大規模な拠点局では、多くの場合に併設されています。このゆうゆう窓口では、通常郵便や書留、ゆうパックの差し出しだけでなく、現金書留の受付にも対応していることがあります。
しかし、現金書留は封かん確認を伴う特殊な郵便物であるため、対応には限りがあります。夜間や深夜帯の時間帯では、ゆうゆう窓口が営業していても「現金書留の受付は取り扱っていない」とする局もあります。特に深夜帯(22時以降など)では、現金の取扱を避ける安全上の理由や、人員体制の制約から断られることがあるため、事前の確認が非常に重要です。
また、混雑状況によっては、通常窓口と比較して受付までの待ち時間が長くなる傾向があります。夜間や週末は仕事終わりの利用者が集中しやすく、待機時間が30分以上に及ぶこともあるため、余裕をもったスケジューリングが求められます。
専用袋や封筒が手元にない場合でも、多くのゆうゆう窓口では現地で購入または入手することが可能です。ただし、数量に限りがあるため、確実に準備したい場合は事前に郵便局で購入しておくと安心です。封かんや宛名記入などの手続きも、通常窓口と同様に行われるため、以下のような準備をしておくとスムーズに進行します。
- 宛先住所と受取人氏名の正確なメモ
- 差出人情報(名前、住所、連絡先)
- 封入する現金の金額と内容の確認
- ペン、印鑑、のり等の持参(局内で借りられない場合もある)
なお、ゆうゆう窓口で受付を行った場合でも、翌日扱いになる可能性がある点には注意が必要です。特にその日の集荷時間を過ぎている場合、実際の配達開始は翌営業日以降となることがあります。これを避けたい場合は、可能な限り日中の通常窓口を利用することが望ましい選択と言えるでしょう。
郵便局の営業時間と現金書留の受付可能な時間帯

郵便局の営業時間は局ごとに異なりますが、一般的に通常窓口は平日の9時から17時ごろに集中しており、土日祝日は休業、または大幅に短縮されることが多い傾向にあります。そのため、現金書留を確実に差し出すには、平日の営業時間に合わせて計画することが基本といえます。
一方、大型の郵便局や主要拠点では「ゆうゆう窓口」が設置されており、平日の夜間や土日祝日も受付可能な時間帯が用意されています。このゆうゆう窓口は、通常窓口の閉局後も対応しているため、仕事や学業で日中に時間が取れない人にとって大変便利です。ただし、すべての局に設置されているわけではなく、地域差が大きいため、利用予定の郵便局にゆうゆう窓口があるかどうかを事前に確認することが欠かせません。
また、現金書留は安全性を担保するために通常の郵便物とは異なる特別取扱となっており、当日扱いの締切時刻が局ごとに設定されています。この時刻を過ぎて差し出した場合、翌日扱いとなり配達日数が延びる可能性があります。急ぎの送付を希望する際には、当日扱いの締切を把握し、その時間より前に手続きすることが重要です。
受付可能な時間帯を判断する際には、以下の観点が参考になります。
- 利用するのが通常窓口か、ゆうゆう窓口か
- 当日扱いの締切が何時に設定されているか
- 翌日扱いとなった場合、到着日がどの程度延びるか
- 休日や祝日の集荷スケジュールに影響が出るか
これらを意識して来局時間を選べば、郵便局 現金書留 受付時間の理解が単なる知識にとどまらず、確実な行動計画に結びつきます。より詳細な営業時間情報は、日本郵便の公式検索サービスから確認することが可能です(出典:日本郵便「郵便局・ATMをさがす」)。
受付窓口の比較(概要)
| 窓口タイプ | 受付時間帯の目安 | 当日扱いの締切 | 特徴 | 休日対応の有無 |
|---|---|---|---|---|
| 通常窓口 | 各局の営業時間内 | 局ごとに設定 | 手続きが落ち着いて行える | 局によって休業や短縮あり |
| ゆうゆう窓口 | 夜間や休日に対応する場合あり | 局ごとに設定 | 営業時間外でも差し出し可能 | 設置局のみ利用可 |
郵便局で現金書留を送る方法と手続きの流れ
現金書留を送るには、通常の郵便物とは異なる専用の手順が必要です。現金を安全に届けるための特別取扱郵便であるため、準備段階から差し出しまでの流れを正しく理解しておくことが欠かせません。
まず、専用の現金書留用封筒や袋を準備します。これは郵便局の窓口で購入でき、サイズは複数用意されています。封筒には内袋と外封筒があり、現金を封入した後は二重に包む形で安全性を高めます。
次に宛先住所と氏名、差出人情報を丁寧に記入します。特に金融機関や公的機関への送付では、誤記入が配達遅延につながる恐れがあるため、記載内容を再確認することが大切です。現金を入れたら、のり付けやテープで厳重に封かんします。この際、局員が中身を確認する手続きが義務付けられているため、勝手に封をしてはいけません。窓口での確認後に封を閉じるのが正しい流れです。
その後、窓口で差し出しを行い、料金を支払います。料金は、基本の郵便料金に現金書留の加算料金が上乗せされる仕組みで、金額や重さ、オプション(速達など)によって変動します。最後に局員から受領証が渡されるため、配達完了を確認するまで大切に保管してください。
早く届けたい場合は、当日扱いの締切時刻前に差し出す、速達を追加して配達時間を短縮する、または夜間にゆうゆう窓口を利用することで処理を前倒しする方法があります。どの手段を選ぶかは、送付先や金額、期日までの余裕などに応じて検討すると良いでしょう。
郵便局で現金書留を送る際のサイズや規定について
現金書留には、郵便物の安全性を確保するためのサイズや重量に関する規定があります。専用封筒は複数のサイズが用意されており、小さな金額からまとまった金額まで対応できるようになっています。封筒は内袋と外封筒の二重構造となっており、内容物が透けて見えたり、破損したりしないように工夫されています。
現金を封入する際には、紙幣の折り方に厳密な決まりはありませんが、封筒内で動かないように工夫することが推奨されます。台紙を添えたり、複数枚の紙幣を内袋にまとめて収めたりすると、配送中の偏りや破損を防げます。
厚みが出てしまう場合は、無理に小さい封筒へ詰め込むのではなく、ワンサイズ大きな封筒へ切り替えると、封かん確認がスムーズになります。無理な封入は破損や料金計算上のトラブルにつながるため避けるべきです。
また、重量が規定を超える場合には追加料金が発生します。料金体系は重量区分によって細かく設定されているため、差し出す前に封筒の重さを確認しておくと安心です。もし重量やサイズが基準を超えてしまった場合、現金書留として取り扱えないケースもあるため注意が必要です。
送付前に郵便局で封筒を購入し、その場で記入・封入することで、局員による確認も同時に進められます。こうした準備を適切に行えば、受付から発送までの流れが滞りなく進み、安心して現金を届けることができます。
郵便局での現金書留の受付時間と料金・日数・便利なサービス

- 郵便局で現金書留を送った場合にかかる日数
- 現金書留の料金と追加費用の仕組み
- 郵便局で現金書留に使う袋の入手方法
- 郵便局で現金書留を送った後の追跡サービスの利用方法
- 郵便局で現金書留を速達として送る方法とメリット
- 現金書留を郵便局留めにする際の注意点
郵便局で現金書留を送った場合にかかる日数
現金書留を差し出してから到着までにかかる日数は、郵便局に持ち込む時間帯、差し出し先との距離、祝日や休日の有無、配送ルートの混雑状況など複数の要因で変動します。一般的に、同一県内や近隣地域への差し出しであれば1〜2日程度で届くケースが多いですが、遠方や離島宛ての場合は中継局の経由が増えるため、3日以上かかることもあります。
特に注意すべきは、当日扱いの締切時刻です。この時刻を過ぎて受付した現金書留は翌日扱いとなり、配達予定が1日遅れることになります。早く届けたい場合は、必ず締切前に受付を済ませるとともに、必要に応じて速達を付与すると、配達スピードが大幅に向上します。
また、天候不良や交通事情による遅延も想定しなければなりません。大雨や台風、年末年始などの繁忙期には、通常より1日以上遅れることが実際にあります。そのため、重要な支払いや期限が決まっている送付では、余裕を持った日程で差し出すことが安心につながります。
現金書留には追跡番号が付与されるため、差し出し後は日本郵便の公式追跡サービスを利用して処理状況を確認できます。これにより、配達の進捗を把握しつつ、受取人へ到着予定を伝えることが可能となり、双方にとって安心感が高まります(出典:日本郵便「郵便追跡サービス」)。
現金書留の料金と追加費用の仕組み
現金書留の料金は、通常の郵便物と同じく重量とサイズで決まる基本料金に、現金書留専用の加算料金を組み合わせて算出されます。さらに、速達や配達日指定といったオプションを追加すると、その分が上乗せされます。
現金書留特有の加算料金は、補償額に連動して設定されています。つまり、送付する現金の金額が大きくなるほど、補償の範囲が広がり、それに応じて料金も高くなる仕組みです。これは、現金という高リスクな内容物を安全に取り扱うための制度であり、一般の書留郵便とは異なる点です。
窓口では、封筒の重量やサイズ、オプションの有無をその場で確認し、最終的な合計金額を提示してもらえます。複数の現金書留をまとめて差し出す場合も、それぞれの封筒ごとに料金が異なる可能性があるため、事前に概算を把握しておくと安心です。特に速達を付ける場合は追加料金がかかるため、緊急性の有無に応じて賢く選択すると良いでしょう。
料金の考え方(内訳イメージ)
| 項目 | 内容 | 代表的なポイント |
|---|---|---|
| 基本料金 | 重量とサイズで決定 | 定形・定形外など区分で変動 |
| 現金書留加算 | 補償と取扱手数に相当 | 現金送付の特別取扱 |
| オプション | 速達や配達日指定など | 必要に応じて追加 |
| 合計 | 上記の合算 | 窓口で最終確定 |
郵便局で現金書留に使う袋の入手方法
現金書留は、必ず専用の袋や封筒を使用することが義務付けられています。この専用袋は、郵便局の窓口で購入できるほか、一部の取扱店舗やオンラインショップでも入手可能です。封筒は内袋と外封筒の二重構造になっており、中身が透けたり破損したりしないよう工夫されています。
差し出す前に、宛名や差出人の記入欄、封かん部分を確認し、必要に応じて署名や押印を行います。記入に不備があると受付に時間がかかるため、事前に準備しておくとスムーズです。
封入時には、内容物が偏らないように平らに整え、封筒の角が破けないよう台紙を添えるとさらに安全性が高まります。現金を入れた後は局員による封かん確認が行われるため、自分で完全に封をしてしまわず、窓口で指示に従ってのり付けを行うのが正しい手順です。
また、利用する金額や厚みに応じて封筒のサイズを選ぶ必要があります。無理に小さいサイズを使用すると破損や受付拒否の原因になり得るため、適切なサイズの封筒を用意することが大切です。こうした専用袋の使用は、日本郵便が定める安全基準に基づくものであり、現金を確実に届けるための必須ルールといえます。
郵便局で現金書留を送った後の追跡サービスの利用方法

現金書留は、他の特殊取扱郵便と同様に追跡サービスに対応しています。差し出し時に渡される受領証には13桁の追跡番号が記載されており、この番号を使って郵便物の処理状況を確認できます。日本郵便の公式サイトにある郵便追跡サービスや専用アプリを利用することで、差し出しから配達完了までの主要な工程がステータスとして反映されます。
更新されるステータスは、例えば「引受」「通過」「到着」「お届け先にお届け済み」などで、どの局で処理されているかが表示されるため、配達の進捗を把握しやすくなっています。配達予定がタイトな場合には、この情報を活用して受取人に到着見込みを共有すれば、行き違いや不安を避けられます。
また、まれに天候不良や交通事情で配送が遅延することもあり、その際にはステータス更新が停滞することがあります。数日間動きがない場合や、配達完了予定日を過ぎても更新がない場合は、差し出し局へ問い合わせを行うと、より詳細な状況を確認できます。万一の事故や紛失に備えても、追跡番号は到着確認が済むまで大切に保管しておくことが望ましいといえます(出典:日本郵便「郵便追跡サービス」)。
郵便局で現金書留を速達として送る方法とメリット
現金書留は、もともと現金を安全に送るために特別な手続きを設けている郵便サービスであり、通常の郵便物よりも慎重に取り扱われます。しかし、安全性に加えて「スピード」も求められる場合には、速達を付与することで配達時間を短縮することができます。
速達を指定した現金書留は、通常郵便と異なり優先的に仕分け・輸送され、専用のルートに組み込まれるため、都市部であれば最短で翌日午前中、地方宛てでも通常より早い時間帯に届けられる可能性が高まります。たとえば同一県内であれば、午前中の早い時間に差し出すことで当日中の配達に間に合うケースもあるなど、速達の効果は非常に大きいといえます。
料金面では、基本料金と現金書留加算額に加え、速達料金が上乗せされます。速達料金は重量に応じて設定され、例えば250gまでであれば数百円程度の追加で利用できます。このコストはかかるものの、入学金や授業料の納付、契約金の送付、公共料金の支払いなど、支払期日に遅れることが許されないケースでは、保険のような意味合いを持ちます。万一遅れてしまうことで発生するリスクや不利益を考えれば、速達の追加料金は十分に価値のある投資といえるでしょう。
速達を利用する際に意識すべきポイントとしては、差し出す時刻です。郵便局では「当日扱いの締切時刻」が設けられており、この時間を過ぎると速達を付けても翌日扱いになってしまいます。特に夕方以降の持ち込みでは、想定した効果が得られない可能性があるため、できるだけ午前中、遅くとも昼過ぎまでに差し出すことが理想です。
ただし、速達であっても天候不良や自然災害、大規模イベントによる交通規制などの外的要因までは完全に回避できません。台風や大雪の際には航空便や陸送が遅延する可能性が高まるため、確実に届けたい場合には、差し出しのタイミングを天候と照らし合わせて調整することが望ましいです。また、受取人に事前連絡をしておくことで、万が一の遅延時にも柔軟に対応できる体制を整えることができます。
速達付きの現金書留は、安全性と迅速性を兼ね備えた手段であり、特に期限厳守が求められる用途では非常に有効です。差し出す局や時間、料金を正しく理解し、状況に応じて最適な方法を選択することで、安心かつスムーズな送付が実現できます。
現金書留を郵便局留めにする際の注意点
現金書留は、受取人の都合に合わせて郵便局で直接受け取れる「郵便局留め」のサービスを利用することができます。この方法では、自宅や勤務先に配達してもらう代わりに、指定した郵便局で受け取る形となります。セキュリティを重視したい場合や、確実に本人が受け取りたい場合に有効です。
受取人が郵便局で現金書留を受け取る際には、本人確認書類の提示が必須です。運転免許証やマイナンバーカードなど、公的に認められた身分証明書を持参しなければ受け取ることができません。差出人はあらかじめ、利用する郵便局の名称、到着見込み日、必要書類を受取人に伝えておくと、受け取り手続きが円滑になります。
さらに、郵便局留めには保管期限が設けられており、通常は到着日から10日程度とされています。期限を過ぎると差出人に返送されるため、長期放置は避けなければなりません。確実に受け取れるよう、到着したら速やかに受取人が局へ出向くことが大切です。
差し出し側は宛名の記載に注意が必要です。受取人の氏名に加えて「○○郵便局留め」と明記し、郵便局の正確な住所と局名を記載する必要があります。これを誤ると誤配や返送の原因になるため、公式サイトで受取局の正式名称を確認してから記入するのが望ましいでしょう。到着後の連絡方法を事前に決めておけば、受け取り忘れを防ぎ、スムーズな受け渡しが可能となります。
現金書留は郵便局で何時まで?受付時間と料金まとめ

- 郵便局の現金書留受付時間は、通常窓口とゆうゆう窓口など窓口の種類によって異なる
- 当日扱いの締切前に差し出すことで、配達開始が早まり到着を短縮できる
- 土日に差し出す場合は、ゆうゆう窓口を設置している郵便局の利用を検討すると便利
- 料金は基本料金に現金書留加算が組み合わされ、さらに速達などのオプションを付けると追加される
- 速達を追加することで優先的に処理され、通常よりも配達日数を短縮できる可能性が高まる
- 追跡番号を利用すれば、差し出しから配達完了までの進捗状況を随時確認できる
- 専用袋と二重封かんを利用することで、安全性が強化され、紛失や破損のリスクを減らせる
- サイズや重量が規定を超過すると、追加料金が発生したり、現金書留として取り扱えなくなる場合がある
- 郵便局の営業時間や現金書留の受付可能時間を事前に確認しておくと安心して差し出せる
- 締切時刻を過ぎてしまうと翌日扱いとなり、配達が遅れる可能性があるため注意が必要
- 郵便局留めを利用する場合は、本人確認書類の提示や保管期限に気を付けて受け取る必要がある
- 到着日が重要な場合は、余裕を持って早めに手続きすることが安全につながる
- 受け取った控えと追跡番号は、配達完了を確認できるまで必ず保管しておくことが大切
- 混雑を避けて来局すれば、封かん確認や差し出しの手続きもスムーズに進められる
- 天候や交通事情による遅延の可能性を踏まえて、余裕を持った計画を立てて差し出すことが望ましい
関連記事







