切手を封筒に入れて郵送しても大丈夫なのか――ふとした場面で、そんな疑問を抱いたことはありませんか?たとえば「お礼に切手を送りたい」「返信用に切手を同封したい」など、ちょっとしたやりとりの中で切手を送る必要が出てくることは意外と多いものです。
しかし、切手は金券類に分類されるため、「本当に送ってもいいの?」「違法にはならない?」「マナーとして問題ない?」といった不安を感じる人も少なくありません。ましてや、郵便物としての扱いやルール、さらには相手に対する印象まで考えると、正しい知識がないまま送るのは少し心配になります。
そこで本記事では、「切手は郵送していいか」というキーワードで情報を探している方に向けて、法律上の取り扱いやマナー、梱包の仕方、封筒の選び方、郵便料金の目安などをわかりやすくまとめました。個人でもビジネスでも役立つよう、よくある疑問や失敗しやすいポイントにも触れながら丁寧に解説しています。
最後まで読んでいただければ、もう「送っていいかどうか」で迷うことはなくなるはずです。安心して切手を郵送するために、ぜひ参考にしてみてください。

💡記事のポイント
- 切手を郵送しても違法にならない条件と注意点
- 安全かつ丁寧に切手を送るための梱包や封筒の選び方
- 普通郵便や追跡付き郵便など発送方法の使い分け
- 郵送時のマナーや相手に配慮した送付のコツ
切手を郵送していいか?法律・マナー・正しい送り方を徹底解説

- 切手を郵送するのは違法なのか?気になる法的ルール
- 切手を普通郵便で送ってもいいですか?安全な発送方法とは
- 切手を封筒に入れて送るのはOK?封入時の注意点と例外
- 封筒に小物や切手を同封して郵送するときの正しい手順
- 切手なしで郵送するとどうなる?郵便事故を防ぐために
- 郵送で送ってはいけないもの一覧|切手は大丈夫?
切手を郵送するのは違法なのか?気になる法的ルール
切手を郵送すること自体は、原則として違法ではありません。実際、多くの人が記念切手の交換や、郵送料金として使う切手を誰かに送る目的で日常的に郵送しています。ですが、ここで注意すべきは「どのように」「どんな目的で」送るのかという点です。
切手は日本郵便が発行する「金券類」に該当します。現金と同じように価値のあるものと見なされるため、たとえば営利目的で不正に流通させたり、郵便制度を悪用した場合には違法となる可能性があります。特に、未使用の切手を販売目的で送る場合や、換金性の高いものと合わせて送るケースでは、法的な扱いが変わってくるため注意が必要です。
ただし、通常の個人間でのやりとり、たとえば「お礼として数枚の切手を送る」「仕事のやり取りで必要な切手を同封する」といった用途であれば、まったく問題ありません。また、日本郵便の公式ガイドでも、封筒に切手を入れて送ることを禁止している記述はなく、一定のマナーや条件を守っていれば安全に送ることができます。
つまり、送る目的や内容が常識の範囲内であれば、切手の郵送に違法性はありません。とはいえ、金券としての扱いを理解し、必要以上に大量の切手を送る場合や、営利的な取り扱いをする際には一度、郵便局や法的専門機関に確認を取ることをおすすめします。誤解やトラブルを避けるためにも、基本ルールは押さえておくと安心です。
切手を普通郵便で送ってもいいですか?安全な発送方法とは
切手を普通郵便で送ることは可能です。ただし、送る方法や状態によっては、紛失やトラブルのリスクもあるため、慎重に判断する必要があります。
普通郵便とは、日本郵便が提供する最も一般的な郵送方法で、手軽に送れる反面、補償がありません。そのため、切手のように小さくて軽く、紛失しやすいものを送る場合、梱包や封入の工夫がとても重要になります。例えば、封筒に直接切手を入れるのではなく、台紙に貼り付けてから封筒に入れることで、封の中で動かず、折れたり破れたりするのを防ぐことができます。
また、郵送中に封筒の中身が透けて見えると、盗難のリスクも高まります。できるだけ厚手の封筒を使用する、または中に薄紙を一枚重ねるなどの対策をすると安全性が高まります。さらに、外から見て「金券が入っている」とわかるような書き方は避けましょう。切手は換金性があるため、注意が必要です。
もし送る切手の価値が高い場合や、相手に確実に届けたい場合は、普通郵便ではなく、書留や特定記録郵便といった追跡機能付きの方法を検討すると良いでしょう。これらのサービスを使えば、配達記録が残るため、万が一の紛失時にも対応が可能になります。
つまり、普通郵便でも切手は送れますが、安全性を高めるための工夫は必須です。送り方を工夫することで、相手にも安心して受け取ってもらえるでしょう。
切手を封筒に入れて送るのはOK?封入時の注意点と例外
切手を封筒に入れて送ることは可能です。多くの人が仕事のやり取りやプレゼント、お礼の品として切手を封入していますが、正しく封入しないと破損や紛失のリスクがあるため、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。
まず大切なのは、切手をそのまま封筒に入れないことです。封筒の中で折れ曲がったり、濡れたりすると、使用できなくなってしまいます。このような事態を防ぐためには、台紙などの厚紙に切手を固定し、そのうえで封筒に入れると良いでしょう。マスキングテープや軽い糊で台紙に仮留めすると、移動中のズレも防げます。
また、封筒に入れる際はサイズにも注意が必要です。定形郵便のサイズを超えると送料が変わるため、封筒と切手の厚み・重さを事前に計量しておくと安心です。郵便局の窓口で確認するのも一つの方法です。
例外として、業務利用や商用利用で大量の未使用切手を封筒に入れて送る場合には、内容物の確認や税務上の扱いが必要になるケースがあります。この場合は、事前に送付先や関係部署と確認を取ることをおすすめします。
また、相手に切手を送る際には、何の目的で送っているのかを簡単にメモ書きしておくと親切です。突然切手だけが届くと、受け取った側が戸惑うこともあります。手書きの一言を添えるだけで印象は大きく変わるものです。
このように、封筒に切手を入れて送ること自体は問題ありませんが、安全に、そして失礼のないように送るためには、細かな配慮が求められます。送り方次第で、相手に対する信頼感も伝わるものです。
封筒に小物や切手を同封して郵送するときの正しい手順

封筒に小物や切手を同封して郵送する場合には、内容物の性質や形状に合わせた梱包と郵送方法を選ぶことが大切です。郵便事故や破損を防ぐためにも、最低限のルールとマナーを守る必要があります。
まず、同封する小物が何であるかを明確にし、それに応じて封筒のサイズと材質を選びましょう。例えば、薄いキーホルダーや金属製のピンバッジなどを送る場合、普通の紙封筒だと破れたり、封筒の角から突き出てしまうリスクがあります。こうした場合には、厚手のクラフト封筒やクッション封筒を使うのが安心です。
次に、切手や小物が封筒の中で動かないように固定する工夫も必要です。切手であれば厚紙に仮止めし、さらにビニール袋などに入れて水濡れ対策をすると良いでしょう。小物についても、プチプチや薄い布などで包み、できれば透明な袋に入れてから封筒に封入することで、より安全に届けることができます。
封筒のサイズや厚みにも注意しましょう。郵便には「定形郵便」と「定形外郵便」があり、それぞれサイズと重さの基準が決まっています。例えば、厚みが1cmを超える場合は定形外郵便扱いとなり、送料も変わってきます。郵便局ではその場で重さとサイズを測ってもらえるので、不安な場合は窓口に持ち込むのがおすすめです。
さらに、封筒に「折り曲げ厳禁」「取扱注意」などの注意書きを明記することで、配達時のトラブルを防ぎやすくなります。郵便局によっては、シールを貼ってくれるサービスもあるため、依頼してみてもよいでしょう。
このように、小物や切手を封筒で安全に送るには、単に「封をして投函する」だけでなく、中身の保護、郵便区分の確認、相手への配慮まで含めて考える必要があります。ひと手間かけることで、安心して郵送でき、受け取る側にも丁寧さが伝わります。
切手なしで郵送するとどうなる?郵便事故を防ぐために
郵便物に切手を貼らずに投函してしまった場合、ほとんどの場合、正常に相手へ届けられることはありません。料金不足として扱われ、返送や追加料金の請求が発生する可能性があります。これは個人の郵送でもビジネスシーンでも大きなトラブルに発展しかねないため、切手の貼り忘れには細心の注意が必要です。
日本郵便では、切手のない郵便物を発見した場合、まず送り主の情報が記載されていれば、その住所に返送されます。しかし、差出人が書かれていない場合や、住所が不完全な場合には、郵便局で一定期間保管されたのちに廃棄されるか、場合によっては受取人に料金の請求がいくことになります。
また、切手を貼ったつもりで金額が不足していた場合も、同様に「料金不足」として扱われます。郵便局は郵便物の重さやサイズ、配送先などから正確な料金を判定しているため、たった10円や20円の不足でも対象になります。これにより、受取人に迷惑をかけたり、信用を失うリスクが生まれてしまうのです。
さらに、切手が途中で剥がれてしまうケースもあります。これは、古い切手や湿気のある場所に保管していた切手に多く見られる現象です。剥がれた切手は無効と見なされ、料金不足扱いになるため、しっかりと貼付されているかどうかを投函前に必ず確認しましょう。
郵便事故を防ぐためには、まず郵便物のサイズと重さを正確に測定し、それに応じた切手を正しく貼ることが大前提です。そして、差出人情報を必ず記載し、剥がれにくい位置にしっかりと貼付する工夫が求められます。とくに、ビジネス文書や大切な書類を送る場合には、切手貼付のミスが相手との関係性に影響を与えることもあるため、確認作業を怠らないようにしましょう。
郵送で送ってはいけないもの一覧|切手は大丈夫?
郵便を利用する際には、法律や郵便局の規定により、送ってはいけないものがいくつか存在します。これらは、事故やトラブルの原因になるだけでなく、最悪の場合は法的責任を問われるケースもあるため、送る前に必ず確認しておくべきです。
代表的な「送ってはいけないもの」には、現金や危険物、爆発物、毒物、腐敗しやすい食品、動植物、違法薬物などが挙げられます。たとえば、現金は現金書留でなければ送ることができません。封筒にお札を直接入れて普通郵便で送る行為は郵便法違反に該当する可能性があり、非常に危険です。
一方で、切手については一般的に送付が認められています。未使用の切手であれば、金券の一種ではありますが、日本郵便のサービスに利用されることを前提としたものであり、通常の封筒に入れて郵送することに問題はありません。ただし、前述の通り、営利目的での大量送付や、換金性のある物品と一緒に送る場合には注意が必要です。
また、香水やリチウム電池など、一見無害に思えるものでも航空便として扱う場合には制限があります。国際郵便ではさらに規制が厳しくなるため、送付前に必ず日本郵便の公式サイトか窓口で確認することが推奨されます。
ちなみに、日常的に誤って送られてしまうものの一つに「生もの」があります。例えば、チョコレートや果物などを封筒に入れて送る人もいますが、温度や配送環境によって傷む恐れがあるため、郵送には不向きです。これらはクール便などの別の配送手段を検討すべきでしょう。
このように、郵便には明確なルールと安全性確保のための規定があり、それに沿って利用することが必要です。切手は基本的には送っても問題ありませんが、他の内容物との組み合わせや送り方によっては、ルール違反になることもあるため、慎重な判断が求められます。
切手を郵送していいか迷ったら|正しい送り方とマナーまとめ

- 切手を郵送する方法|封筒のサイズや貼り方のポイント
- 切手を送るときのマナーとは?ビジネス・個人での違い
- 切手を封筒に入れて送る際の丁寧な梱包とメモの書き方
- 郵送時の切手代はいくら?重さ・サイズ別料金早見表
- 切手はコンビニでも買える?手軽に入手する方法
- 郵送に使える切手の種類とは?記念切手・通常切手の違い
切手を郵送する方法|封筒のサイズや貼り方のポイント
切手を郵送する方法は、思ったよりも奥が深く、封筒の選び方や切手の貼り方ひとつで、郵送の安全性や相手への印象が大きく変わります。何気なく行っている作業かもしれませんが、正しく送るためには基本をしっかり押さえることが大切です。
まず、封筒のサイズ選びから考えてみましょう。日本郵便では、郵便物を「定形」「定形外」「大型」の3つに分類しており、それぞれにサイズと重さの上限が定められています。一般的な切手のやりとりで使われるのは「定形郵便」で、長形3号(120mm × 235mm)が最もポピュラーです。これにより、A4用紙を三つ折りにしてちょうど入るサイズで、多くのビジネス文書やちょっとした贈り物にも対応できます。
封筒を選んだら、切手をどこに貼るかも重要なポイントになります。通常、封筒の表面、右上の角に貼るのが正式なルールです。貼る位置がずれていると、機械による仕分けで読み取れなかったり、郵便局員の手間が増えることがあります。さらに、切手が斜めになっていたり、折れていたりすると、相手に雑な印象を与える可能性もあります。見た目の美しさと機能性の両方を意識しましょう。
また、切手の金額も正確に把握しておく必要があります。封筒に何かを同封する場合、重さが25gを超えると送料が変わってきます。たった数グラムの違いでも料金が変動するため、郵便物の重さを量り、必要な金額分の切手を用意するようにしましょう。万が一、金額が不足していると「料金不足」として戻される、または受取人に不足分の請求が行くことがあります。
最後に、封を閉じる際はしっかりとのり付けすることも忘れてはいけません。封筒の口が開いていたり、粘着が弱かったりすると、中身が飛び出して紛失する可能性もあります。とくに湿気の多い季節や、紙質によってはのりがうまく接着しないこともあるため、テープで補強すると安心です。
このように、切手を郵送するためには、サイズ、貼り方、重さ、そして封の仕方まで、細かい点に配慮することが求められます。相手にきちんと届くように、ひとつずつ丁寧に確認する習慣をつけておきましょう。
切手を送るときのマナーとは?ビジネス・個人での違い
切手を人に送る機会は意外と多くあります。仕事で「返信用切手」を送ったり、個人のやりとりで「ちょっとしたお礼」として送ったりするケースが考えられます。こうした場面では、単に切手を封筒に入れるだけでなく、相手との関係性に応じたマナーを意識することが大切です。
まず、ビジネスで切手を送る場合には、基本的に「返信用」として同封するケースが多いでしょう。例えば、履歴書の返送をお願いする場合や、書類のやりとりで相手に返信を依頼する場合です。このときのマナーとしては、未使用の切手を新品の状態で送るのが原則です。角が折れていたり、粘着面が汚れている切手は、相手に不快感を与える可能性があるため避けましょう。
さらに、ビジネスのやりとりでは、切手をむき出しで封筒に入れるのではなく、台紙に貼ってから透明な袋などに包み、さらに簡単なメモを添えることが望ましいです。これにより、丁寧な印象を与えると同時に、受け取った側も扱いやすくなります。メモには「返信用切手を同封いたします。よろしくお願いいたします」といった一文を添えるだけでも、相手の印象が良くなるでしょう。
一方、個人のやりとりでは、もう少しカジュアルな対応も可能です。例えば、手紙の中に切手を入れて「余っていたので、よければ使ってください」といった形で送ることもあります。この場合は、形式ばったマナーよりも、気持ちが伝わるような工夫が重視されます。ただし、やはり切手が破損しないようにする配慮は必要です。
どちらの場合にも共通するのは、「相手の立場に立って送る」という意識です。切手は小さな紙片ではありますが、郵送や通信の助けになる大切な物です。相手が安心して使えるように、送る側の誠意と丁寧さが伝わる工夫を忘れないようにしましょう。
切手を封筒に入れて送る際の丁寧な梱包とメモの書き方
切手を封筒に入れて送る場合、最も重要なのは「相手の元に確実に、そして丁寧に届くように工夫すること」です。ただ封筒に入れるだけでは、配送中に折れたり、濡れたり、場合によっては紛失してしまうリスクがあります。そのため、梱包の仕方にはしっかりと気を配る必要があります。
まず、切手はとても薄く軽いため、封筒の中で動きやすく、破損しやすい特徴があります。そのまま入れるのではなく、厚紙や名刺サイズのカードなどに軽く貼り付け、切手が曲がったり折れたりしないように固定するのが基本です。貼り付けにはマスキングテープなど、簡単にはがせる素材を使用すると、受け取った側がスムーズに取り出せます。
次に、雨や湿気による水濡れ対策も必要です。切手は水に弱いため、ビニール袋や透明な封筒に入れると安心です。封筒の外から見えないように気を配ることも忘れずに。万が一にも中身が透けて見えると、郵送中に盗難に遭うリスクもあるため、外装には厚紙を一枚挟んだり、色付き封筒を使うなどの対策が有効です。
また、メモを同封することも大切なマナーのひとつです。いきなり切手だけが送られてきた場合、受け取った側は驚いてしまうことがあります。簡単な内容でもかまわないので、「いつもお世話になっております。ご利用いただければ幸いです」など、一言メッセージを添えると丁寧な印象になります。ビジネスであれば社名や氏名を明記したメモを入れ、個人間なら手書きのメッセージが温かみを感じさせてくれます。
なお、封筒に入れた切手の重さとサイズによって、必要な郵送料が変わる場合があります。とくに複数枚の切手や、カードなどを同封する場合は、合計の重さが25gを超えることもあります。正確な料金がわからない場合は、郵便局の窓口で計測してもらうことをおすすめします。
このように、切手を封筒で送る際は、「保護」「気遣い」「丁寧さ」の3点を意識して梱包することが重要です。たとえ小さなものでも、そこに込められた配慮が、相手の心に届くことにつながります。
郵送時の切手代はいくら?重さ・サイズ別料金早見表

郵送にかかる切手代は、封筒の「サイズ」と「重さ」によって細かく分類されており、事前に確認しておかないと、料金不足で郵便物が返送されたり、受取人に迷惑をかけてしまうことがあります。日本郵便では、郵便物を「定形郵便物」「定形外郵便物(規格内・規格外)」の3つに分けており、それぞれに対応する料金体系が決まっています。
まず最もよく使われる「定形郵便物」について解説します。これは、封筒のサイズが長辺14cm〜23.5cm、短辺9cm〜12cm、厚さ1cm以内、重さ50g以内の郵便物です。通常の手紙や履歴書などが該当します。料金は50g以内であれば110円です。これを超えると「定形外」となり、料金が変わります。
次に「定形外郵便物」の中でも「規格内」のものについてですが、これは長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内、重さ1kg以内の郵便物が対象です。小型のカタログや薄手の雑誌、グッズなどが当てはまります。料金は、重さに応じて140円(50g以内)、180円(100g以内)、270円(150g以内)、320円(250g以内)と段階的に上がっていきます。500g、1kgと重くなるほど料金も上がる仕組みになっています。
一方で「定形外郵便物(規格外)」は、上記のサイズを少しでも超えた場合に該当します。たとえば、厚さが3cmを超えたり、長さが34cmをわずかに超えただけでもこの扱いになります。料金はさらに高くなり、50g以内であっても260円からスタートし、以降500g以内で660円、1kg以内で920円など、かなりの差が生じます。特に、商品や小物を送る際に意識しておかないと、無駄な送料が発生する可能性があるため注意が必要です。
また、速達や書留などのオプションサービスを追加する場合は、基本料金にそれぞれの追加料金が上乗せされます。速達は300円が基本で、これに通常の郵便料金を加えた額が必要になります。
こうした情報は郵便局の公式サイトでも確認できますが、目安として手元に早見表を用意しておくと非常に便利です。郵便を頻繁に利用する方であれば、封筒サイズのテンプレートや計量器を用意しておくと、正確に切手代を計算できます。
送料の計算ミスは、小さな手間のようでいて、送り手と受け取り手の双方に負担をかけることになります。しっかりと規格を把握したうえで、余計なトラブルを防ぎたいところです。
切手はコンビニでも買える?手軽に入手する方法
切手は郵便局だけでなく、コンビニでも購入できることをご存じでしょうか。特に平日の日中に郵便局へ行くのが難しい人にとって、コンビニで切手を手軽に入手できるのは非常に便利な選択肢です。ただし、どのコンビニでも同じように取り扱っているわけではない点には注意が必要です。
現在、切手の取り扱いがある代表的なコンビニチェーンには、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなどが挙げられます。これらの店舗では、レジで店員に声をかけることで、所定の額面の切手を購入できます。陳列棚に置いてあるわけではないため、まずは「84円切手を◯枚ください」といった形で伝える必要があります。
販売されている切手の種類は、通常は「84円」「94円」「63円」など、需要の高い額面に限られている場合がほとんどです。特殊な額面の切手や、記念切手、シール式切手などは基本的に置かれていません。もし複数の額面の切手を組み合わせて送料を支払いたい場合や、コレクション性のある切手を探している場合には、郵便局を利用する必要があります。
また、コンビニでは現金での支払いが基本で、クレジットカードや電子マネーに対応していない場合もあります。各店舗の方針によって異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。さらに、レジが混雑している時間帯などは、切手の取り扱いに時間がかかることもあるため、余裕をもって購入するよう心がけると安心です。
一部のローソンでは、郵便ポストやレターパック、スマートレターの販売も行っており、郵便に関する手続きをほぼ店内で完結できるケースもあります。ただし、これらのサービスの有無も店舗ごとに異なるため、いつも利用する店舗で取り扱いがあるかどうかを確認しておくと便利です。
日常的に郵便を利用する人にとって、切手を必要なときにすぐ手に入れられる手段を確保しておくことは、ちょっとしたストレスの回避につながります。コンビニを上手に活用すれば、郵便局の営業時間外でも柔軟に対応できるので、ぜひ選択肢のひとつとして考えてみてください。
郵送に使える切手の種類とは?記念切手・通常切手の違い
切手とひとことで言っても、実はさまざまな種類が存在します。郵便料金を支払うための「通常切手」だけでなく、特別なデザインが施された「記念切手」も広く流通しており、用途によって使い分けることが可能です。ただし、それぞれの特徴や使い方を正しく理解しておかないと、思わぬトラブルにつながることもあります。
まず、もっとも一般的に使われるのが「通常切手」です。これは郵便局が常時販売しているもので、84円や63円など、現在の郵便料金に対応する額面が設定されています。デザインはシンプルで、自然・文化・伝統工芸などがモチーフになることが多く、業務用やビジネスでのやり取りにも違和感がありません。サイズも小さく、紙質や印刷のクオリティも安定しているため、大量に使う際に向いています。
一方で、「記念切手」は特定のイベントやテーマにちなんで発行される限定デザインの切手です。アニメや歴史的な出来事、スポーツ大会など、話題性の高い題材を採用することでコレクターにも人気があります。これらの切手も郵便料金の支払いに使用することができ、通常の切手とまったく同じ効力を持ちます。
ただし、記念切手にはいくつかの注意点があります。まず、額面が特殊な数字になっている場合があるため、目的の送料と一致しない場合は他の切手と組み合わせて貼る必要があります。さらに、デザインが華やかすぎる場合、ビジネス用途では不適切に感じられることもあるため、TPOに応じた使い分けが求められます。
また、最近では「シール式切手」という便利な形状の切手も登場しています。従来の水で濡らして貼るタイプではなく、シールのように剥がしてすぐ貼れるため、手紙を書く習慣がある人や高齢者の方にも人気です。ただし、こちらも郵便局や一部のコンビニでしか手に入らない場合があるため、必要なときにすぐ入手できるとは限りません。
こうした切手の種類を理解しておくことで、用途に応じた選択ができるようになります。見た目の印象も郵便物の一部と考え、相手や場面にふさわしい切手を選ぶことが、丁寧なコミュニケーションにつながるのではないでしょうか。
承知しました。以下に、先ほどの箇条書きをやや長めの文に整えて再構成しました。重複を避けつつ、「だ・である調」で統一しています。
切手は郵送していいか迷ったときに押さえておきたい15のポイント
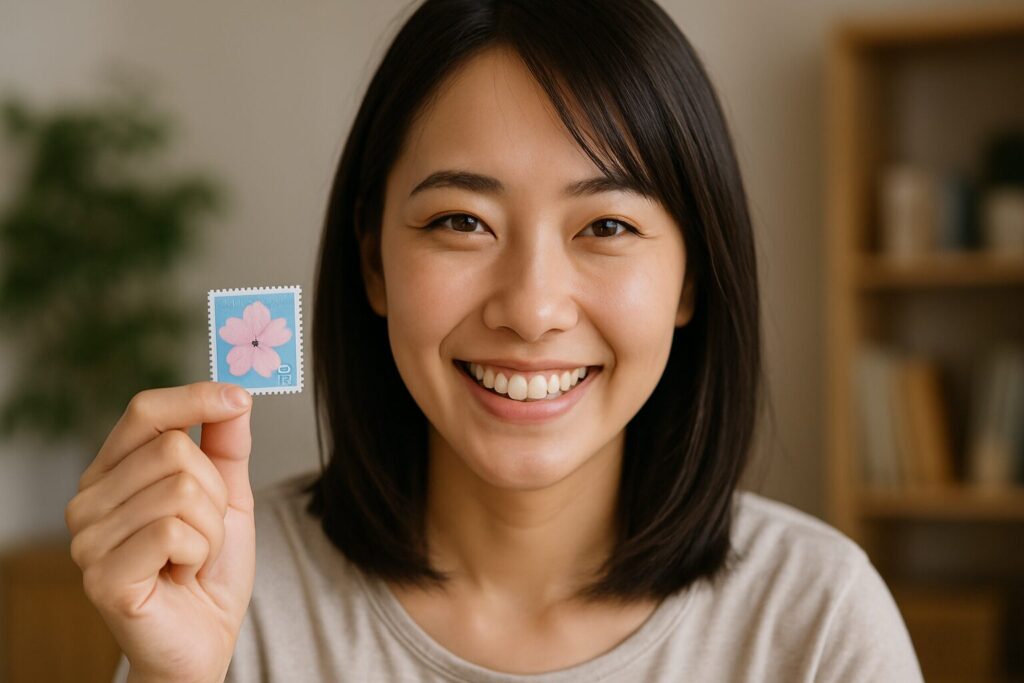
- 切手を封筒に入れて郵送する行為そのものは違法ではなく、個人間のやりとりであれば広く認められている
- 営利目的で大量の未使用切手を郵送する場合には、税務上や法律上の制約が生じる可能性があるため事前確認が必要
- 普通郵便でも切手は送れるが、追跡や補償がないため大切な内容であれば配送手段の再検討をおすすめする
- 封筒の中身が透けて見えると盗難のリスクが高まるため、厚手の封筒や内側に紙を重ねるなどの対策が効果的
- 切手はそのまま封筒に入れるのではなく、台紙などに仮止めして折れや紛失を防ぐようにするとよい
- 同封物の厚みや重さによって郵便区分が変わるため、送付前に料金とサイズを確認しておくことが重要
- 切手だけを送る場合でも「返信用です」「ご利用ください」などのメモを添えることで相手への配慮が伝わる
- 小物を一緒に送る際は、封筒が破れないようにクッション封筒や厚紙を使用して丁寧に梱包するのが安全
- 定形郵便と定形外郵便では送料が大きく異なるため、サイズと重量を正確に把握して適切な料金を選ぶべき
- 切手の貼り忘れや料金不足は「料金不足郵便物」として処理され、返送や受取人への請求につながるリスクがある
- 記念切手も通常の郵送に使用可能だが、ビジネス用途には不向きなデザインもあるためTPOを考慮して選ぶことが望ましい
- セブンイレブンやローソンなど一部のコンビニでも主要額面の切手が購入できるため、急ぎの場合に便利である
- 切手には通常切手・記念切手・シール式切手などがあり、目的や相手によって使い分けることで印象が良くなる
- ビジネスで送る切手は、汚れや折れがない状態のものを使い、台紙と透明袋で丁寧に梱包するのが基本的なマナー
- 書類や高価な切手など確実に届けたい場合には、書留や特定記録などの追跡サービス付き郵便を選ぶのが安心
関連記事


