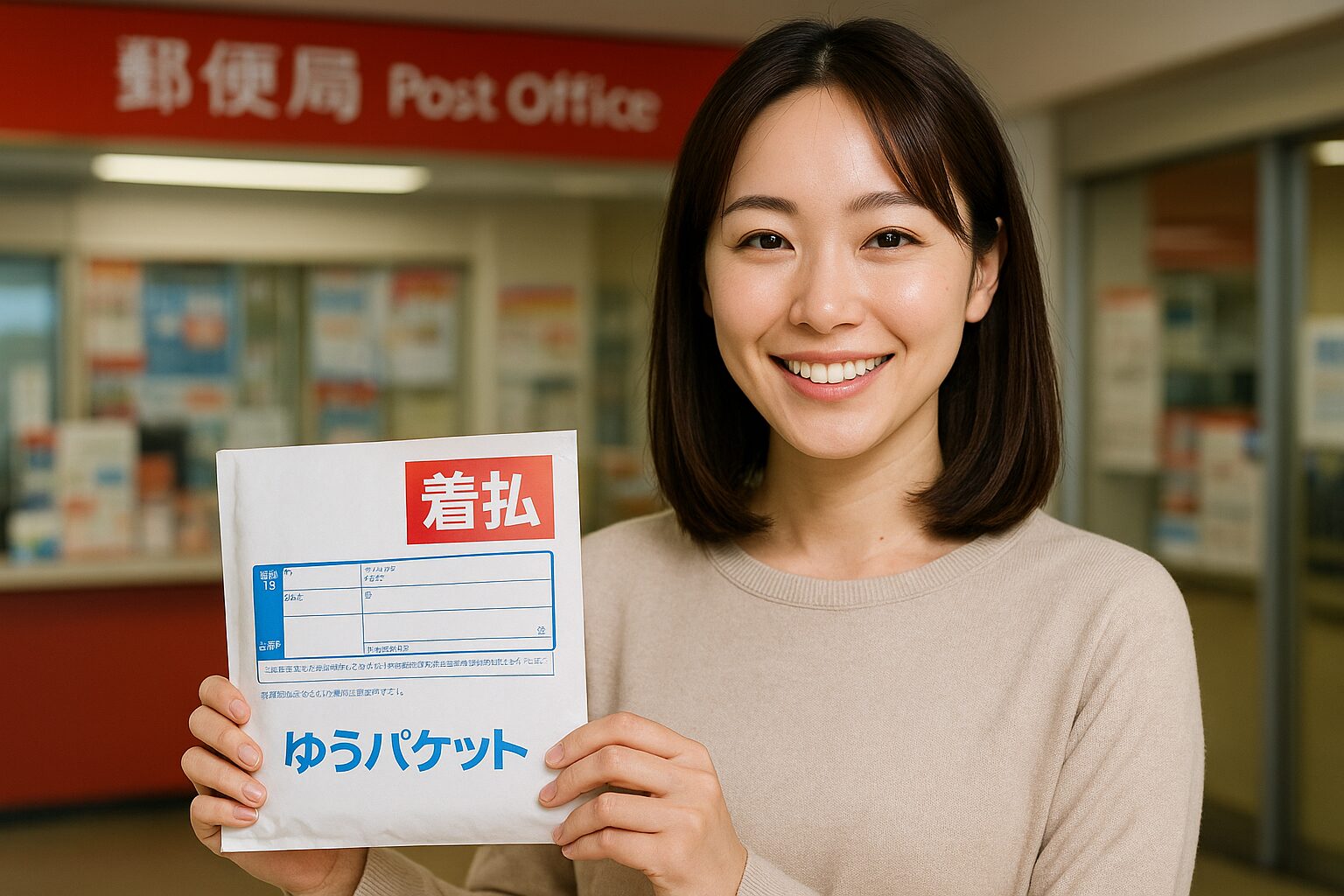「ゆうパケット着払いのやり方」と検索してこのページにたどり着いた方は、おそらく「送り方がよくわからない」「コンビニからでも出せるのか」「料金はいくらかかるのか」など、実際に送る前に不安や疑問を感じているのではないでしょうか。ゆうパケットは日本郵便が提供する便利な配送サービスですが、着払いで利用する際にはいくつか特有のルールや注意点があります。何も知らずに発送しようとすると、郵便局で断られたり、相手に迷惑をかけてしまうこともあるため、事前の正しい理解がとても大切です。
この記事では、ゆうパケットを着払いで送るための基本的な流れから、必要な準備、専用ラベルの入手方法、注意点、よくある勘違いまで、初めての方でもわかりやすいように詳しく解説しています。さらに、料金の目安や追跡の仕方、利用できる場所・できない場所までカバーしているので、読み終わる頃には自信を持って手続きできるようになるはずです。
大切な荷物をスムーズに、トラブルなく届けるために、まずは正しいやり方をしっかり確認しておきましょう。この記事が、あなたの不安を解消し、確実な発送の手助けとなれば幸いです。

💡記事のポイント
- ゆうパケット着払いの正しい発送手順と必要な準備
- 着払い用ラベルの入手方法と記入・貼付のコツ
- コンビニやゆうパケットプラスでの利用可否
- 着払い時の料金や追跡方法の仕組み
ゆうパケット着払いのやり方を完全解説|準備から発送までの手順

- ゆうパケットで着払いを送る方法とは?
- ゆうパケットを着払いで送るにはどうすればいい?
- ゆうパケット着払いの伝票はどこでもらえる?
- ゆうパケット着払いの送り方と必要な準備
- ゆうパケット着払いの追跡方法について
- ゆうパケットの着払い料金はいくらかかる?
ゆうパケットで着払いを送る方法とは?
ゆうパケットで着払いを利用するには、通常の発送方法とは異なる手順が必要です。日本郵便の「ゆうパケット」は、もともと元払いが基本のサービスであるため、着払いにするためには専用の伝票と対応した手続きを行う必要があります。誤解されがちですが、普通にコンビニや郵便ポストに投函するだけでは着払いにはなりません。事前の準備と正しい窓口での発送が求められます。
具体的には、ゆうパケットの着払いは郵便局の窓口でのみ対応しています。コンビニやポストでは着払い発送はできないため注意が必要です。発送時には、着払い専用の伝票(ゆうパケットのラベル)が必要となり、それを商品に貼付したうえで窓口に持ち込むことで、発送手続きが完了します。
また、着払いとはいえ、送り主が送料を支払わないだけで、受け取り側に送料が加算される仕組みです。つまり、相手が受け取り時に送料を支払う必要があります。このため、事前に受取人の了承を得ておくことがトラブル防止につながります。送る側としては便利に感じられますが、相手の負担を伴う行為であることを理解しておきましょう。
このように、ゆうパケットで着払いを送るには、決まった条件と正確な手続きが不可欠です。正しい手順を知っていれば、無駄なトラブルや再発送を避けることができるでしょう。
ゆうパケットを着払いで送るにはどうすればいい?
ゆうパケットを着払いで送るには、いくつかの明確な手順とルールを理解しておく必要があります。前述の通り、ゆうパケットは本来「元払い(送り主が送料を負担)」のサービスですが、条件を満たせば着払いでの利用も可能です。ただし、それには適切な伝票の準備や郵便局窓口での手続きが求められます。
まず、着払いで送るためには、ゆうパケット着払い専用の「ラベル付き伝票」を入手する必要があります。この伝票は通常の郵便局の窓口で配布されており、在庫がない場合もあるため、事前に電話などで問い合わせると安心です。伝票を手に入れたら、宛名や差出人情報、品名、料金負担の区分(着払い)を記入し、荷物にしっかりと貼付します。
そして重要なのが、発送方法です。着払いゆうパケットは、必ず郵便局の窓口から差し出す必要があり、コンビニやポスト投函では受け付けてもらえません。これは着払いサービスに対応できる設備や確認手順が、窓口に限られているためです。
また、発送前に受取人へ「着払いで荷物を送ること」を明確に伝えておきましょう。いきなり着払いで届くと、驚かれたり、受取拒否される可能性もあるからです。相手との信頼関係や確認は、円滑な取引や郵送において非常に重要です。
このように、単に「着払いで送る」といっても、専用伝票の準備、発送方法の制限、受取人との事前連絡など、複数のポイントを押さえる必要があります。ゆうパケットを着払いで利用する際は、こうした点を一つひとつ丁寧に確認してから発送手続きを行いましょう。
ゆうパケット着払いの伝票はどこでもらえる?
ゆうパケットの着払い伝票は、通常の郵便局の窓口で無料でもらうことができます。ただし、すべての郵便局が常に在庫を持っているわけではないため、事前に電話で取り扱い状況を確認しておくと安心です。伝票の正式名称は「ゆうパケット専用 着払伝票」や「ゆうパケット着払いシール」などと呼ばれることが多く、一般的なゆうパックやレターパックの伝票とは異なる専用品です。
この伝票は、ゆうパケット専用の小型ラベルと、着払い区分を示す表示がセットになっており、宛名や差出人、品名、配達希望日などを記入するスペースがあります。なお、印字済みのバーコードなどが含まれているため、ネットから自分で印刷することはできません。必ず郵便局で配布されている実物を使用する必要があります。
さらに注意点として、着払い伝票を取得しただけでは、すぐに発送できるわけではありません。伝票を正しく記入し、荷物にしっかり貼り付けたうえで、郵便局窓口へ持ち込むことが必要です。伝票を貼った状態でポストに投函したり、コンビニに持ち込んだりしても、着払いとしては受け付けてもらえません。これは、着払いの受付処理には専用の確認手続きが必要だからです。
このような理由から、着払い伝票を入手した際には、同時にその利用方法やルールについてもしっかり確認しておくとよいでしょう。職員に簡単な説明を受けておくことで、記入ミスや発送トラブルを防ぐことができます。伝票の取得と使い方は、ゆうパケットの着払いをスムーズに利用するための第一歩です。
ゆうパケット着払いの送り方と必要な準備

ゆうパケット着払いで荷物を送りたい場合、発送手順と準備すべきものを正確に理解しておくことが重要です。通常のゆうパケットとは異なり、着払いにはいくつかの制限があり、対応する手続きも異なります。これを知らずに手続きを進めてしまうと、郵便局で受付を断られたり、相手に負担を強いることになりかねません。
まず準備すべきものは大きく分けて4つあります。「ゆうパケット対応の梱包資材」「着払い専用の伝票」「宛先と差出人情報」「商品そのもの」です。梱包については、ゆうパケットのサイズ制限(縦・横・厚さの合計が60cm以内、かつ厚さ3cm以内、重さ1kgまで)に収まるように工夫が必要です。箱で送る場合は、ゆうパケット専用箱やクッション封筒が便利ですが、厚みには特に注意が必要です。
次に必要なのが、着払い専用の伝票です。これは前述の通り郵便局の窓口で無料でもらうことができ、インターネットからは入手できません。宛名や差出人欄、品名、注意事項などを記入し、間違いのないよう貼り付けてください。万一、記入ミスや貼り付けミスがあると、受付時に差し戻される可能性があります。
発送は必ず郵便局の窓口から行いましょう。コンビニやポストでは着払い対応ができないため、持ち込んでも受け付けてもらえません。窓口では、伝票に不備がないか確認した上で受付が行われます。担当者が着払いであることを確認し、システムに情報を登録します。この処理があるため、ポスト投函では完結しないのです。
また、相手が送料を支払うことになるため、事前に着払いで発送する旨を相手に伝える配慮も必要です。特に取引先や初めての相手であれば、事前連絡はトラブル回避につながります。
このように、ゆうパケット着払いの発送には事前準備と手順の正確な理解が求められます。一つでも抜けがあるとスムーズに送ることができないため、準備段階からしっかりチェックしておくことが重要です。
ゆうパケット着払いの追跡方法について
ゆうパケット着払いで荷物を送った場合でも、元払いと同様に配送状況を追跡することが可能です。発送後の不安やトラブルを防ぐうえで、追跡機能を利用することは非常に重要です。特に着払いの場合、受取人が料金支払いを伴うため、相手から「まだ届かない」などの問い合わせを受ける可能性もあります。その際に、追跡番号が役立ちます。
追跡の方法は非常にシンプルです。郵便局で着払い発送を行うと、伝票に記載されている**お問い合わせ番号(追跡番号)**が発行されます。この番号は、差出人用の控えに明記されているため、絶対に紛失しないように保管しておきましょう。この番号を日本郵便の公式サイトにある「郵便追跡サービス」へ入力することで、荷物の現在位置や配達状況が確認できます。
配送ステータスは「引受」「到着」「配達中」「配達完了」などの段階に分かれており、それぞれの時間や地域が表示されるため、配送の進行状況がひと目でわかります。また、万一配達が遅延した場合でも、どこで止まっているのかが確認できるため、差出人としても冷静に対応しやすくなります。
一方で、注意すべき点もあります。例えば、伝票に記載された番号が不鮮明だったり、インクのにじみで読み取れなかったりすると、正しく追跡できないことがあります。また、追跡情報が反映されるまでにタイムラグがあるため、発送直後に検索しても「情報が登録されていません」と表示されることもあります。このような場合でも、数時間~1日程度で情報が反映されるのが一般的です。
このように、ゆうパケット着払いにおいても追跡は問題なく利用できます。発送後は追跡番号をしっかり管理し、必要に応じて受取人にも番号を伝えておくと、安心感のあるやり取りが可能になります。
ゆうパケットの着払い料金はいくらかかる?
ゆうパケットを着払いで利用する際にもっとも気になるのが、送料の金額ではないでしょうか。基本的に着払いでも料金体系そのものは元払いと変わらず、ゆうパケットの重量別料金が適用されます。ただし、着払い手数料などはかかりませんが、支払いは受取人に発生するため、事前説明が不可欠です。
現在(2025年時点)のゆうパケットの送料は、以下の3段階に分かれています。
- 厚さ1cm以内 = 250円
- 厚さ2cm以内 = 310円
- 厚さ3cm以内 = 360円
これらの料金は全国一律であり、配送距離による加算はありません。また、料金は差出人ではなく受取人が支払う形式となるため、相手がこれらの金額を受け取り時に負担することになります。例えば、厚さ1cm以内の小型商品を送る場合は、250円+26円(着払い手数料)=276円を相手が支払って荷物を受け取る、という流れになります。
ただし、実際には受取人がその金額を「現金」で支払うことが前提になります。クレジットカードやキャッシュレス決済には対応していないため、事前に現金の用意を促しておくとトラブルを防ぎやすくなります。また、荷物を受け取られずに差し戻されると、返送料も差出人の負担となる場合があります。
加えて、発送時には上記料金に基づいた適切な重さであることを郵便局窓口で計量されます。重さオーバーが発覚した場合は、その場で指摘され、料金が自動的に高くなります。発送前に自宅で事前に重さを測っておくと、予想外の請求を回避できます。
このように、ゆうパケット着払いの料金はシンプルで全国共通ですが、支払い方法や重さ、受取拒否のリスクなど、把握すべき点も多くあります。適切な情報をもとに発送を行うことで、無駄な手間や費用を避けることができるでしょう。
ゆうパケット着払いのやり方を使いこなすコツと注意点

- ゆうパケット着払いはコンビニでも利用できる?
- ゆうパケットプラスで着払いはできるのか?
- ゆうパケット着払い用ラベルの書き方と貼り方
- ゆうパックの着払いで現金以外の支払いは可能?
- ゆうメールや普通の封筒でも着払いはできる?
- ゆうパケットの通常料金と着払い料金の違いを比較
ゆうパケット着払いはコンビニでも利用できる?
ゆうパケットの着払いサービスを利用する際に、コンビニから発送できるのかという点は、多くの人が疑問に感じる部分です。結論から言えば、ゆうパケットの着払いはコンビニでは利用できません。これは、着払いという形式が郵便局の専用システムを使った手続きになるためであり、コンビニのレジ端末では対応できないからです。
現在、ローソンやミニストップなど一部のコンビニでは日本郵便のサービスが取り扱われていますが、これはあくまでも「元払い」で発送する場合に限られます。着払いに関しては、受取人が配送料を負担するため、荷物ごとに確認や登録作業が必要であり、それを処理するための端末やオペレーションが整っているのは郵便局だけです。そのため、コンビニで「ゆうパケットを着払いで送りたい」と申し出ても、受付を断られてしまうのが実情です。
さらに注意が必要なのは、伝票の扱いです。コンビニでは「元払い用」の伝票しか設置されていないため、着払い専用の伝票をもらうこともできません。伝票の有無にかかわらず、コンビニから着払いで発送することは原則不可と覚えておいた方が良いでしょう。誤って持ち込んだ場合、手間だけでなく時間も無駄になります。
このように考えると、ゆうパケットの着払いを利用する際には、初めから郵便局の窓口を利用するつもりで準備を整える方が効率的です。コンビニ発送ができると思い込んでいる方も多いため、あらかじめ正しい知識を持っておくことで、手続きがスムーズになります。
ゆうパケットプラスで着払いはできるのか?
ゆうパケットには通常版の他に「ゆうパケットプラス」というサービスがありますが、このゆうパケットプラスで着払い発送が可能かどうかを疑問に思う方も多いようです。結論から言えば、ゆうパケットプラスでは着払いに対応していません。この点は通常のゆうパケットとは異なり、明確に制限されています。
ゆうパケットプラスは、厚さ7cmまで、重さ2kgまで対応しており、専用の箱を使用するという点で通常のゆうパケットよりも大きな荷物に対応できるサービスです。料金は出品者負担の場合は380円、落札者負担の場合は410円となっており、手軽さとコストパフォーマンスの良さから人気のある発送方法です。しかし、システム上の都合からか、このサービスに着払いのオプションは設けられていないため、送り主が必ず元払いで送料を負担する必要があります。
では、なぜゆうパケットプラスでは着払いが利用できないのでしょうか。一つの要因として、ゆうパケットプラスがヤフオクやメルカリといった個人間取引の利用を前提としている点が挙げられます。これらのサービスでは、送料込みの価格設定が一般的であり、着払いを前提とした取引は少ないため、郵便局側としても着払い対応の必要性が低いと判断していると考えられます。
このため、ゆうパケットプラスを使って着払いで送りたいと考えている場合は、他の発送方法を検討する必要があります。例えば「ゆうパック」や「宅急便(着払い対応)」など、より自由度の高いサービスを利用するのが現実的です。
このような制限があることを事前に理解していないと、箱の準備や梱包が無駄になってしまう可能性があります。ゆうパケットプラスを選ぶ際は、着払いの可否に注意して計画的に準備しましょう。
ゆうパケット着払い用ラベルの書き方と貼り方
ゆうパケット着払いを正しく発送するためには、専用ラベル(伝票)の書き方と貼り方が非常に重要です。発送そのものは郵便局の窓口で行いますが、事前にラベルを正確に記入し、適切な位置に貼付しておかないと、受付で差し戻されることもあります。ここでは、初めて着払いを利用する方でも迷わず作業できるよう、具体的な手順を紹介します。
まず、ラベルは郵便局の窓口で無料でもらうことができます。伝票は通常、3枚複写になっており、1枚目が郵便局用、2枚目が配達員用、3枚目が差出人控えとなっています。ラベルの上部には「着払い」と明記されているので、元払い用と混同しないよう注意しましょう。
書き方としては、まず宛先(受取人)の郵便番号・住所・氏名・電話番号を記入します。次に、差出人(あなた)の情報として、同様に郵便番号・住所・氏名・電話番号を記入します。品名欄には「衣類」「雑貨」「書類」など、具体的な内容を簡潔に書くと良いでしょう。なお、配達希望日や時間帯の指定は、ゆうパケットでは対応していないため、記入は不要です。
書き終えたラベルは、荷物の表面にまっすぐ貼り付けます。貼る位置はできるだけ中央または右下を避け、左上〜中央付近に配置するのが一般的です。また、テープで貼る場合はバーコード部分を隠さないように注意し、はがれにくいように四隅をしっかりと留めてください。
貼り方を間違えると、バーコードが読み取れず追跡機能が使えなかったり、荷物の取り扱いに支障が出たりすることがあります。さらに、伝票がずれていると荷物が機械で処理されず、配送が遅れる可能性もあるため、貼付位置と固定方法は非常に重要です。
このように、ゆうパケット着払いをスムーズに利用するには、ラベルの記入内容と貼付方法の正確さがカギとなります。初めての方は、郵便局の職員に確認してもらいながら作業を進めると安心です。
ゆうパックの着払いで現金以外の支払いは可能?

ゆうパックの着払いサービスを利用する際に、「現金以外でも支払いができるのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。特にキャッシュレス化が進んだ現在では、クレジットカードや電子マネー、スマホ決済など、さまざまな支払い方法が普及しており、郵便局でも対応していてほしいと感じるのは自然なことです。
しかし、ゆうパックの着払いについては、支払い方法が「現金のみ」に限定されているのが現状です。配達員が荷物を届ける際、受取人はその場で送料を現金で支払う必要があり、キャッシュレス決済には対応していません。これは郵便局の業務体制が関係しており、配達員が持ち歩く端末ではカードの読み取りやQRコード決済を行う機能が備わっていないためです。
さらに、郵便局の窓口であっても「着払いで届いたゆうパックの受け取り時」の支払いは現金に限定されます。ゆうパックを送るときには、窓口によってはクレジットカードや電子マネーでの支払いが可能な場合もありますが、着払いに限って言えば、いずれの方法も利用不可となっている点に注意が必要です。
このため、着払いのゆうパックを受け取る予定がある方は、事前に必要な金額を確認し、現金を準備しておくことをおすすめします。特に配達時間帯が不在になりがちな方や、キャッシュレス派の方にとっては、不便に感じることもあるかもしれません。もし受け取り時に現金がない場合、荷物の受け取りができず再配達となるケースもあるため、注意が必要です。
今後キャッシュレス対応が進む可能性もありますが、現時点では現金払いが唯一の方法であるため、あらかじめ理解しておくと安心です。送り手も、受取人に「着払い・現金のみ」と伝えておくことで、無用なトラブルを避けることができるでしょう。
ゆうメールや普通の封筒でも着払いはできる?
ゆうメールや普通の封筒を使って郵便物を送る場合でも、着払いができるのかという質問を受けることがあります。一見すると簡単に実現できそうに思えますが、実際にはいくつかの制限があるため、注意が必要です。
まず、ゆうメールは書籍・CD・DVDなどを低価格で送れる郵便サービスとして広く利用されています。送料が安く、追跡サービスも一部対応しているため、個人取引やフリマアプリでも人気ですが、ゆうメール自体には着払いの制度がありません。ただし、「料金受取人払」という形式であれば、ゆうメールでも似たような運用が可能になる場合があります。
この「料金受取人払」は、事前に郵便局との契約が必要な法人向けサービスであり、個人では基本的に利用できません。契約を交わした上で、専用の承認印を得て、所定のラベルを貼る必要があります。つまり、一般的な個人利用者が、封筒に「着払い」と書いてポストに投函しても、それは正式な着払いとしては扱われず、郵便物は返送されてしまう可能性が高いということです。
次に、「普通の封筒」に関してですが、これも着払いには対応していません。通常郵便である定形・定形外郵便には着払いの制度そのものが存在せず、封筒を使って着払いにしたい場合は、ゆうパックやゆうパケットなど、着払いが可能な配送サービスを利用して封筒に入れる必要があります。
このように、ゆうメールや普通郵便では、着払いをそのまま利用することはできません。もしどうしても封筒で着払いをしたい場合には、封筒を利用しつつも、その中身とサイズ・重さに応じて、着払い可能なサービスを選ぶ必要があります。事前に郵便局の窓口で相談してみるのが、安全かつ確実な方法です。
ゆうパケットの通常料金と着払い料金の違いを比較
ゆうパケットには「元払い(通常の料金支払い方法)」と「着払い」という2つの発送方法がありますが、それぞれの料金に違いがあるのか、または仕組みそのものに差があるのかについて気になる方も多いはずです。ここでは、料金体系だけでなく、利用の際の心理的・実務的な違いについても比較しながら解説します。
まず、料金面について結論を述べると、ゆうパケットの通常料金と着払い料金の金額そのものはまったく同じです。これは、ゆうパケットが全国一律の重量別料金を採用しているためです。2025年現在の料金は以下の通りです。
- 厚さ1cm以内 = 250円
- 厚さ2cm以内 = 310円
- 厚さ3cm以内 = 360円
この料金は、元払いであっても着払いであっても変わりません。着払いは特別な割増料金26円が請求されるのが特徴です。
では、どこに違いがあるのでしょうか。最も大きな違いは、「送料を誰が支払うか」という点にあります。元払いでは送り主が支払うのに対し、着払いでは受け取り側が支払います。この点が、利用目的や受け取る側の印象に大きく影響することがあります。
例えば、ネットオークションやフリマアプリなどでは、送料をどちらが負担するかは非常に重要な交渉ポイントになります。送料込みであれば購入者に安心感を与えられますが、着払いになると「追加でお金がかかる」「送料を知らないまま注文した」といった不満が生じやすくなります。特に着払いは、配達時に現金での支払いが求められるため、利便性よりも手間が増えると感じる人も少なくありません。
さらに、発送方法にも違いがあります。元払いであればコンビニやポストから気軽に出せますが、着払いの場合は郵便局窓口での対応が必須となります。この点も、送り手にとっては手続きの煩雑さにつながるため、状況に応じてどちらを選ぶべきか考える必要があります。
このように、ゆうパケットの通常料金と着払い料金は数値上は同一であっても、実際の運用や相手への配慮、発送の利便性においては大きな違いがあると言えます。どちらを選ぶかは、送る相手との関係性や用途に応じて検討することが重要です。
ゆうパケット着払いのやり方の総まとめポイント

- ゆうパケットの着払いは、全国の郵便局窓口からのみ発送手続きが可能となっている
- コンビニやポストへの投函では、着払い発送が受け付けられないため注意が必要
- 着払い専用の伝票(ラベル)は、郵便局の窓口で無料でもらうことができる
- この伝票はオンラインやコンビニには置かれていないため、必ず郵便局で入手する必要がある
- ラベルには宛先や差出人の情報に加え、品名や着払いの区分なども正しく記入する必要がある
- ラベルを荷物に貼る際は、バーコードが見えるようにしっかり固定しなければならない
- 荷物の追跡は、お問い合わせ番号を使って日本郵便の公式サイトで確認できる仕組みになっている
- お問い合わせ番号は伝票の控えに書かれているため、発送後も必ず保管しておくことが重要
- 送料は全国一律で、厚さや重さによって3段階に分かれており、着払いでも金額は変わらない
- 着払いには26円程度の手数料が加算されるため、実際の支払いはその分だけ高くなる
- 受取人は荷物の受け取り時に、送料を現金で支払う必要があり、カードなどは使えない
- 発送前には、着払いで送る旨を必ず受取人に伝えておくことで、受け取り拒否のリスクを避けられる
- ゆうパケットプラスは着払いに対応しておらず、元払いでしか利用できない点に注意が必要
- ゆうメールや普通郵便は基本的に着払いには非対応で、料金受取人払などの例外対応も限定的である
- ゆうパケットのサイズや重量制限(厚さ3cm以内・重さ1kg以内)を超えると着払いでも発送できない
関連記事