「郵便料金不足を払わなかったら、いったいどうなるのか?」と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、もしかすると、突然届いた料金不足の通知に驚いたり、支払いをするべきか迷っていたりしているのではないでしょうか。あるいは、メルカリなどで取引中の荷物が届かず、原因を調べているのかもしれません。
郵便料金の不足というと、一見些細なミスのようにも思えますが、実際には思わぬトラブルや信用問題に発展することがあります。料金を払わなかったことで郵便物が届かなくなるだけでなく、取引相手との関係が悪化したり、再配達や返送に時間がかかったりすることも少なくありません。場合によっては、法的なトラブルにつながることさえあります。
この記事では、「郵便料金不足を払わなかったら」どうなるのかという疑問に対して、実際の郵便局での取り扱いや利用者の口コミ、遅延の仕組み、受取人払いの理由などを網羅的に解説していきます。よくある誤解や見落としがちな注意点についても丁寧に説明していますので、同じような状況に置かれた方にとって参考になるはずです。
郵便という身近なサービスだからこそ、ルールや仕組みを正しく知っておくことが大切です。最後まで読むことで、無用なトラブルを防ぎ、よりスムーズに郵便を利用できるようになるはずです。
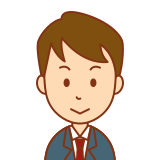
💡記事のポイント
- 郵便料金不足の郵便物が届くかどうかの仕組み
- 払わなかった場合に起こる具体的なトラブルや影響
- 受取人払いの理由と郵便局の対応方法
- 実際の体験談や知恵袋での口コミ事例
郵便料金不足を払わなかったらどうなる?トラブル事例とリスク

- 郵便料金不足を払わなかったら郵便は届くのか?
- 郵便料金の不足を無視すると違法になるのか?
- 郵便料金不足を払わなかった人の口コミを紹介(知恵袋など)
- 郵便料金が不足して10日過ぎたら届く?配達遅延の実態
- 郵便料金の不足分を受取人払いにするのはなぜ?
- 郵便料金不足金を受取人が払う仕組みと注意点
郵便料金不足を払わなかったら郵便は届くのか?
郵便料金が不足している郵便物が、本当に届くのかどうかは、多くの人が疑問に思う点です。とくに、「たった数円の差だから、無視してもそのまま届くのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、実際の運用はそのように単純ではありません。
郵便局では、投函された郵便物のサイズ・重さ・形状などをもとに、貼付されている切手の金額が適正かどうかを確認しています。もしその金額が不足していた場合、該当の郵便物は「不足料金扱い」として特別な処理に切り替わります。基本的にはそのまま配達されることはなく、一時的に保留となったうえで、受取人に不足料金を支払うよう通知が送られます。
受取人がその通知をもとに料金を支払えば、郵便物は正式に配達されますが、逆に支払いを拒否したり、通知に気づかないまま放置した場合は、差出人に返送される流れとなります。このように、受取人または差出人のどちらかが不足料金を負担しなければ、原則として郵便物は最終的に宛先へ届くことがありません。
また、郵便局の判断によっては、不足料金が極めて少額な場合や、差出人・受取人の情報が不明確な場合には、配達を見送るだけでなく、郵便物を一定期間保管したのち廃棄されることもあります。こうした措置は、郵便物の公正な取り扱いとサービスの安定性を保つために必要なルールとして設けられています。
さらに、メルカリやネット通販などで購入した商品がこのような料金不足により届かないとなると、トラブルの原因にもなり得ます。買い手にしてみれば、送料込みと記載されていたにもかかわらず、自分が不足料金を支払わされる状況は不満を招きやすいからです。
このように、郵便料金不足を放置したままにしておくと、郵便物が届かないだけでなく、相手との信頼関係に影響を及ぼす可能性があります。正しく届くためには、発送時点での料金確認が何より重要なのです。
郵便料金の不足を無視すると違法になるのか?
郵便料金が不足していたとき、そのまま放置してしまうことに法的な問題があるのかどうかは、気になるところです。特に、故意ではなくうっかりミスで起こった場合、「違法になるのでは?」と不安になる方もいるかもしれません。ここでは、料金不足を放置することがどのような立場に置かれるのかについて整理しておきます。
まず、郵便料金の不足そのものがただちに刑事罰や行政罰につながるわけではありません。単発的なミスであれば、郵便局も柔軟に対応してくれることが多く、たとえば差出人に返送されたり、受取人に通知が送られるといった通常の流れに沿って処理されます。つまり、1回の料金不足が重大な法律違反として扱われることはまずありません。
しかし、だからといって繰り返し無視しても構わないというわけではありません。郵便は日本郵便という公的な業務を担う企業によって運用されており、そのサービスには一定の利用規約が存在しています。たとえば、料金不足であることを知りながら繰り返し同様の行為を行った場合、意図的な不正行為として郵便法やその他の規則に抵触する恐れがあります。
また、仮に受取人が不足料金の支払いを無視し続けた場合、その郵便物は届かず、差出人に返送されるか廃棄されることになります。この対応は法律ではなく、あくまで運用ルールに基づくものですが、差出人とのトラブルに発展する可能性も十分にあります。とくにメルカリなどのフリマ取引においては、評価や取引履歴に悪影響を与える結果になりかねません。
他方で、悪質なケース、たとえば料金を故意に少なく貼ってコストを節約しようとするなどの行為は、郵便法第4条の「不正行為の禁止」に抵触する可能性があります。こうした場合、損害賠償を請求されるリスクや、業務妨害として問題視される可能性も否定できません。
このように、郵便料金の不足を無視してもすぐに違法とは言えないものの、その行為が継続的または悪意を伴っている場合には、法的なリスクを生むことになります。利用者としては、正しい金額での利用を心がけ、信頼される送り手・受け手であることが求められます。
郵便料金不足を払わなかった人の口コミを紹介(知恵袋など)
実際に郵便料金不足を払わなかった人たちの声は、インターネット上に数多く投稿されています。特に「Yahoo!知恵袋」などのQ&Aサイトには、現実的で参考になる体験談が多く見られます。こうした口コミを通じて、料金不足に対する受け取り方やその後の流れがどのように処理されるのかを知ることができます。
たとえば、「届いた郵便に不足料金のハガキが同封されていたけど、面倒だったので支払わなかった。そしたら何も届かず、そのまま音沙汰なしだった」という体験談があります。このケースでは、郵便局からの通知を無視したことで郵便物が返送された可能性が高く、送った側と受け取る側の間で不信感が残ってしまうようです。
また別の例では、「メルカリで購入した商品が料金不足で届いた。受け取りの際に100円請求されたが、そんなこと聞いていなかったので腹が立った」という声もあります。こうした事例では、購入者が納得していなかったことで悪い評価をつける原因となり、出品者にとってもマイナスになってしまいます。
一方で、受取人がやむを得ず払ったものの、出品者に連絡しても何の謝罪もなかったという投稿も見られました。このような事態では、取引自体は完了していても、心情的には不満が残りやすく、リピーターになってもらえない可能性が高くなります。
こうした口コミに共通しているのは、「料金不足の通知はあっても、対応が遅れたり面倒に感じたりすることで、結果的にトラブルになる」という点です。少額であっても、相手に追加の手間を強いることは、信頼を損ねる要因になり得るのです。
口コミの中には、「局に連絡したらすぐに再配達してくれた」「料金を後から支払って問題なく届いた」というポジティブな体験もありますが、それは例外的な対応であり、すべてのケースに当てはまるわけではありません。
このように、郵便料金不足に関する実際の体験談は、さまざまな立場やケースを通じて、対応の重要性を教えてくれます。少しの気配りや手間を惜しまないことで、大きな信頼の差につながることがよくわかります。
郵便料金が不足して10日過ぎたら届く?配達遅延の実態

郵便物の料金が不足している場合、その郵便物がいつ届くのかは多くの人にとって気になるところです。特に、発送から10日以上経っても届かない場合、何か問題が発生しているのではないかと不安になる方も少なくありません。ここでは、料金不足による配達遅延の実態について詳しく見ていきます。
まず、郵便物に貼られている切手の金額が不足していると、郵便局はその時点で「不足料金が発生している郵便物」として特別な処理を行います。通常の郵便物とは異なり、一時的に保留扱いとなり、受取人に不足料金の支払いを求める形で対応することが多くなります。支払いの方法は、原則として「受取人払い」で通知が届き、その通知をもとに受取人が料金を支払うことで、ようやく配達が再開されます。
この手続きが入るため、郵便物が通常の配達スケジュールから大きく外れてしまうことがあります。具体的には、通常であれば2~3日で届くはずの郵便が、料金不足の確認や通知発送、受取人からの支払いを経る過程を含めることで、10日以上かかってしまうことも珍しくありません。加えて、受取人が通知にすぐに気づかなかったり、対応が遅れたりすれば、その分だけさらに日数が延びてしまいます。
また、料金不足が確認されてから差出人への返送が決定されるまでにも一定の保留期間が設けられるため、差出人にも状況がわからないまま時間が過ぎてしまうケースがあります。実際、知恵袋やSNS上でも「10日以上経っても届かない」「追跡できない郵便が止まっている」といった声が多数見られます。
このように、郵便料金が不足していた場合、単に遅れるだけでなく、再配達や返送といった対応が必要になることがあり、想定以上に時間がかかってしまうことがあるのです。重要な書類や期限のある郵便物を送る際には、料金の確認を徹底することが非常に大切です。
郵便料金の不足分を受取人払いにするのはなぜ?
郵便料金が不足していた場合、ほとんどのケースで「受取人払い」という形で不足分の請求が行われます。差出人が明確であっても、なぜあえて受取人に負担を求めるのか疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。実は、この制度には郵便サービスの円滑な運用や公正性を保つための意図が含まれています。
まず、郵便局が郵便物を扱う際には、郵便物の中身や差出人の意図に立ち入らず、機械的かつ中立的に取り扱うことが基本とされています。たとえ料金が不足していても、内容や重要度に応じて判断を変えるようなことは原則として行いません。そこで設けられているのが「受取人払い」という選択肢です。
この方法を採用することで、郵便局は郵便物の配達を止めずに済みます。つまり、差出人に確認を取る手間を省きながら、受取人の意思によって最終的な配達の有無を決めてもらうことができるのです。受取人が料金を支払えば配達され、支払わなければ差出人に戻る。こうしたシンプルなフローが、現場の効率性を支えています。
また、差出人が不明、あるいは連絡が取れない場合には、受取人払いという制度がなければ郵便物の行き先を決められず、宛先不明として廃棄されてしまう可能性もあります。そうした無用な廃棄を防ぐうえでも、受取人に確認を取るという仕組みは理にかなっているのです。
もちろん、受取人側からすれば、差出人のミスによって料金を負担するのは納得できないと感じることもあるでしょう。ビジネスの場面では、そうした料金不足が原因で信頼を失うこともあります。そのため、差出人としては、相手に余計な負担や誤解を与えないように、適切な料金での発送を心がけることが求められます。
このように、郵便料金の不足分を受取人払いとするのは、郵便システム全体の公平性と効率性を保つための工夫であることがわかります。
郵便料金不足金を受取人が払う仕組みと注意点
郵便料金が不足していた際に、受取人がその不足分を負担する「受取人払い」の仕組みは、郵便の利用に慣れていない方にとっては少しわかりにくいものかもしれません。しかし、この仕組みには明確なルールと流れがあり、対応を誤るとトラブルにつながることもあります。ここでは、その仕組みと注意点をわかりやすく説明します。
まず、郵便物に貼られた切手が実際の重量やサイズに対して不足している場合、郵便局側がその郵便物を一時的に保留扱いとし、「不足料金通知」を作成します。この通知は、通常であれば受取人の住所にハガキまたは封書で届きます。その内容には、不足金額・支払い方法・対応期限などが記載されており、受取人がこれに応じて支払うことで配達が再開される仕組みです。
受取人が支払いを完了すると、郵便物は通常通り配達されますが、支払わなかった場合は差出人に返送されるか、宛名や差出人が不明な場合は郵便局で保管または廃棄処理となることがあります。この過程には一定の猶予期間があるため、数日〜10日程度のタイムラグが生じることになります。
ここで注意しておきたいのは、通知の見逃しや、期限切れによる未対応です。例えば、不足料金通知がポストに埋もれて気づかないまま放置してしまった場合、郵便局側は「受取辞退」と判断して処理を進めることがあります。その結果、差出人とのやりとりに支障が出たり、大切な書類や荷物が届かないといった問題が発生することもあるのです。
また、メルカリやフリマアプリなどでの個人間取引では、料金不足の郵便が届くことでトラブルに発展することもあります。購入者が不快に思い、取引に悪影響を及ぼす可能性があるため、こうした場面では特に注意が必要です。
このように、郵便料金不足に対して受取人が支払う仕組みは明確に整備されていますが、その運用には注意すべきポイントも多く含まれています。郵便をやりとりする際には、こうしたルールを正しく理解したうえで、相手に迷惑をかけないような発送方法を選ぶことが求められます。
郵便料金不足を払わなかったら困る?正しい対応とよくある誤解

- 郵便料金不足のお知らせが届いたらまず確認すべきこと
- 郵便料金不足を払わなかったらハガキなしでも届くのか?
- 郵便料金不足の通知にハンコだけが押されていた場合の意味
- 郵便料金不足について問い合わせるときの窓口と流れ
- 普通郵便の料金が不足した場合にとるべき正しい手続き
- 郵便料金不足を払わなかったらメルカリなどの取引に与える影響
郵便料金不足のお知らせが届いたらまず確認すべきこと
郵便料金不足のお知らせが届いた場合、多くの人は「これは何の通知なのか?」と戸惑ってしまうことがあるようです。特に日常的に郵便を使っていない方にとっては、突然の料金請求に不安を覚えるかもしれません。そこで、こうした通知が届いたときに確認すべきポイントを順を追って整理しておきます。
最初に確認すべきなのは、どの郵便物に対する通知なのかという点です。不足料金のお知らせには、多くの場合「郵便物の差出人」「送付先」「不足金額」「問い合わせ番号」などが記載されています。ただし、まれに差出人が記載されていなかったり、内容が簡略化されている場合もあるため、記載情報は慎重に確認しましょう。たとえば、送付物の追跡番号や受付局のスタンプがあれば、どこから発送されたものかを推測できることがあります。
次に、不足金額が適切かどうかも見ておきたいところです。特に封筒や荷物のサイズ・重さによっては、わずか数円の差で不足扱いになることがあります。自分が心当たりのある受取物であれば納得できるかもしれませんが、身に覚えがない場合は、誤配送や迷惑郵便の可能性も考慮しなければなりません。そのような場合には、通知に記載されている郵便局に直接問い合わせることで、詳細な内容や対応方法を教えてもらうことができます。
さらに、通知に記載された支払い方法と期限をチェックすることも重要です。期限を過ぎてしまうと郵便物は差出人に返送されてしまうことが多いため、急ぎで確認・対応を行いましょう。支払い方法は、窓口支払いや現金書留、QRコードによるスマホ決済など、地域や局によって異なることがあります。
このように、郵便料金不足のお知らせが届いたときは、単なる請求通知と捉えるのではなく、内容の正確性と支払い手続きの必要性を丁寧に確認することが大切です。内容を把握せずに放置してしまうと、大切な郵便物を受け取れないばかりか、差出人にも迷惑がかかる可能性があるため注意が必要です。
郵便料金不足を払わなかったらハガキなしでも届くのか?
郵便物の料金が不足していた場合、通常は郵便局から「不足料金の通知ハガキ」が届き、それを受け取ったうえで料金を支払うことで郵便物を受け取る仕組みになっています。しかし、この通知ハガキが届かないまま、郵便物が配達された、あるいは届かなかったといったケースも時折見られます。こうした状況では、「ハガキがなくても届くのか?」「通知が来ていないだけでは?」といった疑問が生じるのも無理はありません。
まず、原則としては「通知なしに不足料金の郵便物が配達されることはない」と考えておくと良いでしょう。郵便局側は、不足料金が発生した時点でその郵便物を一時保留とし、受取人に対して通知を出すことで受領の意思確認と支払いの案内を行います。この通知がなければ、受取人は料金不足に気づかないままとなり、意図しない料金支払いが発生してしまう可能性があるため、通知は重要な手続きの一つなのです。
ただし、現場の処理によっては例外が発生することもあります。例えば、郵便局員の判断で不足料金が極めて少額である場合や、配達地域での運用ルールに従って「そのまま配達」されるケースもないわけではありません。また、郵便局の混雑や人為的なミスにより、通知ハガキの送付が遅れたり、そもそも発送されていなかったという事例もあるようです。
実際にネット上では、「通知がなかったのにいきなり受け取りに来いと電話があった」「料金不足と書かれたスタンプだけ押されて郵便が届いた」といった報告も見受けられます。これらのケースは例外的ではあるものの、システムの運用や地域差によって取り扱いにバラつきがあることを示しています。
このため、料金不足に関する通知が届かず郵便物も来ない場合は、最寄りの郵便局に直接問い合わせることをおすすめします。特に急ぎの書類や心当たりのある郵便物を待っているときは、少しでも不審に思った時点で行動することが重要です。
郵便料金不足の通知にハンコだけが押されていた場合の意味
郵便料金不足の通知や、料金不足で届いた郵便物に「ハンコだけ」が押されていることがあります。このスタンプが具体的に何を意味するのか、またそれに対してどう対応すべきなのかは、初めて目にする方にはわかりにくいものかもしれません。しかし、こうした表示には、郵便局の内部処理に関する一定の意味が込められています。
まず、「ハンコだけ」が押されている場合、それは「この郵便物には料金が不足しています」という郵便局側からの簡易的な通知であることがほとんどです。たとえば、「料金不足」「受取人払い」「不足◯円」などと書かれたゴム印が封筒の表面に押されている場合、それが不足料金の有無を知らせる唯一の手がかりになることがあります。このスタンプがあるということは、郵便局が不足を確認したが、通常の通知ハガキの発送や詳細な案内までは行われていないということもあり得ます。
一方で、単にスタンプだけで詳細が何も書かれていない場合、受取人は混乱することが多いでしょう。このようなケースでは、通知ハガキの発送が手違いで漏れてしまった、あるいは差出人のミスを郵便局が黙認して配達した可能性も考えられます。さらに言えば、一部の郵便局では、特に少額の不足であれば受取人に負担を求めずそのまま配達する運用をしていることもあるようです。その際、処理の記録としてハンコだけを残すという対応が行われるのです。
こうした状況に遭遇した場合、まずは郵便物の内容と差出人を確認し、自身が料金を支払う必要があるのかを判断しましょう。不明な点があれば、封筒に押された局名や消印から担当局を特定し、電話で問い合わせることで詳細を確認できます。特にビジネスのやり取りやメルカリなどでの個人取引では、たとえ自分が受取人であっても相手側の信頼に関わる問題となるため、事実関係の把握は不可欠です。
このように、「ハンコだけ」が押されていた場合でも、そこには何らかの意味が含まれています。何気なく見過ごさず、しっかり確認・対応することで、トラブルや誤解を未然に防ぐことができるのです。
郵便料金不足について問い合わせるときの窓口と流れ

郵便料金不足に関する通知を受け取ったものの、「これは何の郵便に対するものなのか」「どうやって確認すればいいのか」といった疑問を持つ人は少なくありません。とくに差出人が明記されていなかったり、心当たりのない場合は、不審に思ってしまうのも当然です。そこで、郵便料金不足に関して問い合わせる際の基本的な窓口とその流れについて説明します。
まず、問い合わせをする前に確認すべき情報があります。通知書や不足料金が貼られた郵便物には、どの郵便局で処理されたのかを示す局名スタンプや、不足料金の金額、そしてまれに郵便物の種別(定形郵便・定形外郵便など)が書かれている場合があります。これらの情報は、どの局に、どの郵便物の件で問い合わせるべきかを判断する手がかりになります。
実際に問い合わせる場合は、通知に記載された郵便局に電話をかけるのが基本です。もし通知に電話番号が書かれていない場合は、日本郵便の公式サイトにある「郵便局検索」から該当する郵便局の電話番号を調べることができます。また、全国共通のお客様サービス相談センター(0120-232886)にかけて、どの局に連絡すべきかを相談するのも一つの方法です。
電話をかける際には、通知に記載されている整理番号や金額、局名などを手元に準備しておくと、対応がスムーズになります。窓口担当者に対しては、「〇〇郵便局から郵便料金不足の通知が届いたが、内容に心当たりがないので確認したい」と伝えると、丁寧に対応してもらえるケースが多いです。
一方、郵便局によっては来局による窓口対応を案内されることもあります。その際は通知ハガキや該当の郵便物、本人確認書類を持参するようにしましょう。
このように、問い合わせの際は慌てずに情報を整理し、落ち着いて行動することが大切です。初めてでも対応しやすい体制が整っているため、不安を感じたときには積極的に相談してみてください。
普通郵便の料金が不足した場合にとるべき正しい手続き
普通郵便を出した後に料金が不足していたことが判明した場合、どのような手続きが必要になるのかを知っておくと、相手に迷惑をかけることなくスムーズに対応できます。これは個人の手紙であっても、ビジネスやフリマアプリなどの取引に関係する郵便であっても同じです。ここでは、差出人として取るべき具体的な手順を整理しておきます。
まず、郵便料金が不足していた郵便物は、配達途中で郵便局により発見され、一時的に配達保留となります。その後、原則として受取人に「不足料金通知」が届き、不足分を支払うかどうかの判断を委ねる形になります。受取人が支払いを拒否または放置した場合、その郵便物は差出人に返送されることになります。
ここで差出人にできる対応としては、まず郵便局に連絡し、該当の郵便物がどこにあるのかを確認することです。特に重要書類や期日のある書類を送った場合は、一刻も早く対応を取る必要があります。返送された場合には、手元に戻った郵便物を開封して内容を確認し、必要があれば正しい料金で再送します。このとき、差出人が追加で不足分の切手を貼って再投函すれば、再び受取人へ送ることができます。
また、まれに受取人から「料金不足で届いた」と連絡が入ることもあります。その場合には、受取人の手間を考慮して、謝罪とともに不足分を現金書留や振込などで補填することも一つの誠意ある対応です。フリマアプリなどの取引であれば、取引メッセージを通じて状況を説明し、評価に影響しないよう努めましょう。
こうした対応を避けるためには、発送前に郵便物の重さやサイズを正確に測ることが基本です。家庭用のキッチンスケールでも概ね対応できますし、心配な場合は郵便局窓口で重さを測ってもらうことが確実です。
このように、普通郵便の料金不足が発覚した場合には、郵便局や相手方と丁寧にやり取りを行い、できるだけ早く正しい手続きをとることが信頼維持にもつながります。
郵便料金不足を払わなかったらメルカリなどの取引に与える影響
フリマアプリのメルカリやラクマなどで商品を発送する際、郵便料金のミスは思わぬトラブルの原因になります。中でも、料金が不足したまま発送してしまい、それに気づかず放置した場合、取引相手との信頼関係に大きな影響を与えることがあります。ここでは、郵便料金不足を払わなかったときにメルカリなどの取引でどのような問題が生じるのかを解説します。
まず、料金が不足した郵便物は、原則として受取人に不足分の支払いを求める通知が届きます。相手がこの通知に基づいて支払いを行えば配達されますが、「なぜ自分が払わなければならないのか」と不快に思う方も少なくありません。これは、取引上の信頼に直結する問題であり、受取人が評価に「悪い」「非常に悪い」をつけるきっかけにもなり得ます。
また、通知に気づかない、もしくは支払いを拒否した場合、商品は差出人に返送されてしまいます。この過程で時間がかかるため、購入者としては「いつまでも届かない」「取引メッセージの返答がない」といった不満を抱きやすくなります。メルカリでは、取引がスムーズに行われなかった場合、キャンセルや事務局対応となる可能性もあります。
このようなトラブルを回避するためには、発送前の準備が重要です。商品を梱包したら、そのままポストに投函せず、重さとサイズを必ず確認しましょう。特に「定形外郵便」は、数十グラムの違いで料金が大きく変わるため注意が必要です。局員に確認してもらうのが最も確実ですし、匿名配送サービス(らくらくメルカリ便・ゆうゆうメルカリ便など)を使えば、料金不足の心配を回避できます。
いくら商品や対応が丁寧でも、配送ミスひとつで信頼は簡単に失われます。郵便料金不足を「たった数十円の問題」と軽く考えず、取引全体の印象を左右する重要な要素としてしっかり対応していくことが大切です。
郵便料金不足を払わなかったらどうなるのかを総まとめ

- 郵便料金が不足している郵便物は、通常の配達ルートから外れ、一時的に郵便局で保留扱いとなる
- 不足している金額の支払いが確認されるまで、郵便物は宛先に届けられることはない
- 受取人が不足料金の支払いを拒否した場合、その郵便物は差出人へ返送される流れになる
- 料金不足の通知を受け取ったにもかかわらず放置していると、一定期間後に郵便物が廃棄処分されることがある
- 同じ差出人から繰り返し料金不足の郵便が出された場合、故意の不正とみなされ郵便法違反に問われる可能性がある
- 通常は不足料金の通知がハガキで届くが、処理の簡略化により封筒やスタンプのみの場合もある
- 郵便物に「料金不足」「受取人払い」などのスタンプが押されているだけで、通知ハガキが届かないケースも見られる
- メルカリなどフリマアプリで料金不足が発生すると、受取人が不快に感じ、評価や今後の取引に悪影響を及ぼすことがある
- 通常2〜3日で届く郵便が、料金不足の対応により10日以上かかるケースも珍しくない
- 数十円の不足であっても、郵便局や相手側に手間や不信感を与えるため、想像以上にトラブルになりやすい
- 差出人が不明な場合や連絡がつかない場合には、受取人払い制度が活用され、受取人の判断に委ねられる
- 郵便局では郵便物の内容を判断せず中立的に処理するため、受取人の支払い意思によって配達の可否が決まる
- 不足料金に関する問い合わせは、通知に記載された郵便局か、日本郵便のサービスセンターを通じて行う
- 通知書が届いたら、内容や記載された期限、支払い方法を必ず確認し、できるだけ早く対応することが望ましい
- 郵便料金のトラブルを未然に防ぐには、発送前にサイズと重量を確認し、正確な料金を貼って送ることが基本である
関連記事







